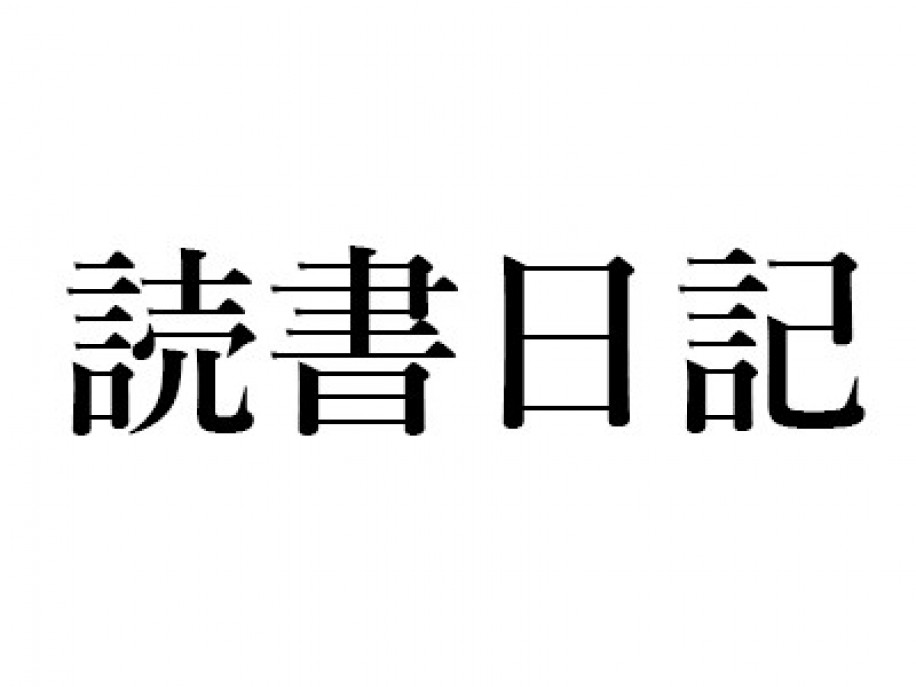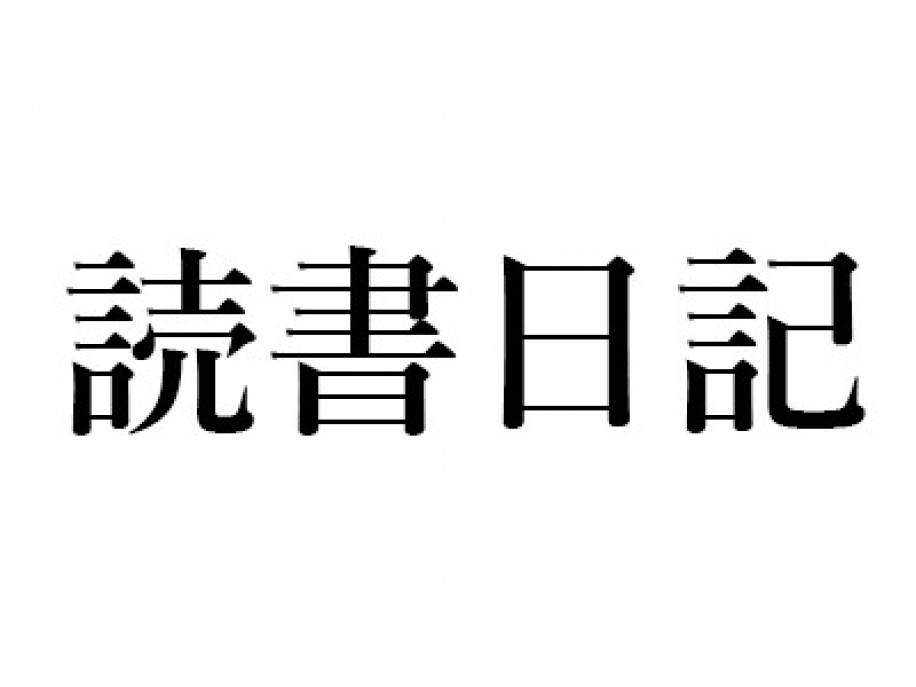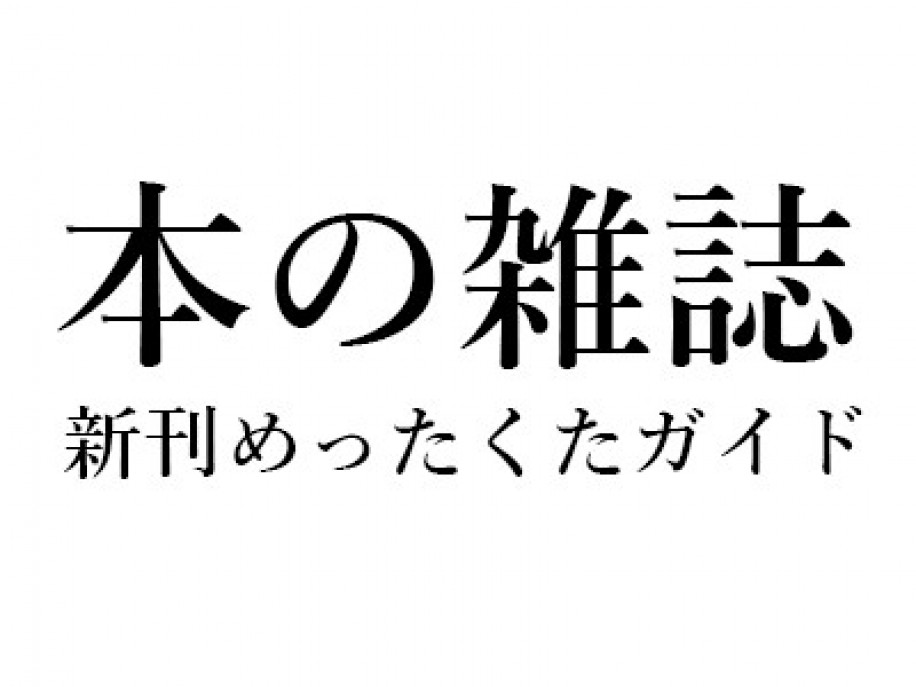読書日記
柴田元幸「読書日記」- プレイボーイ日本版 - ニコルソン・ベイカー『中二階』『U&I』(白水社)、都築響一『東京スタイル』(筑摩書房)、赤塚不二夫『天才バカボン』(竹書房)
人生の大問題と取り組まない文学について
文学というと、何となく、人生の大問題と取り組むものみたいに思える。たとえば、個人と社会の対立とか、芸術と実人生の乖離とか、最近じゃ現実と虚構の錯綜とか、もちろん、そういう高尚な問題を扱う文学もあっていい。でもわれわれはべつに、四六時中人生の大問題とがっちり四つに組んでいるわけではない。むしろ、人生の大問題と取り組んでいるふりをしつつ、眼前の小問題を相手に右往左往している、というのがたいていの場合実情ではないだろうか。だったら、そういういろんな小問題と取り組む文学もあっていいはずだ。ニコルソン・ベイカーの『中二階』のすごさは、いままでの文学ではおよそ扱うに値しないと思われてきた、というかあまりにも瑣末なので文学で扱うに値するかどうかさえも考えられてこなかった、きわめて非芸術的な諸問題をめぐる考察だけで、とても面白い小説を作り上げてしまっていることである。日本では、テレフォン・セックスの会話だけでできた、これはこれで十分秀逸な小説『もしもし』が一足先に訳されたベイカーだが、この本国でのデビュー作はもっといい。
プラスチック・ストローの問題点とその対策。レコードプレーヤーのトーンアームと機関車とホチキスの形の変遷の歴史的並行性。トーストは四角に切るべきか三角に切るべきか。ミシン目の偉大さ。男子トイレで隣に他人に立たれて放尿しにくいときの対策。ペーパータオルと熱風乾燥機の比較……などなど、昼休みを終えた一人のサラリーマンが、自分のオフィスのある中二階へ向かうエスカレーターに乗って、降りるまでの数十秒間に頭に浮かぶろんな問題が、無数の「注」を付した文章を通して、きわめて綿密かつ情熱的に考察される。「注」をひとつ引用すると――、
「(1)[私は]今ではもう、靴下をはく際の“あらかじめじゃばら寄せ方式”、すなわち靴下の内側に両手の親指を入れてくしゃくしゃに縮め、出来上がったドーナツの環の中に爪先を差し込むやり方を採用していない。幼稚園のころ、教育熱心な新米先生たちから教わって以来長いあいだ、これを素晴らしいテクニックであると信じきっていて、靴下のゴムの部分を持って足を突っ込み、踵の位置をちゃんと収めるためにくるぶしのあたりを何度ももぞもぞさせるようなやり方は、怠慢で計画性のない人間のすることだと思っていた。では、なぜやめてしまったか? “あらかじめじゃばら寄せ方式”は確かにスマートなやり方ではあるが、これだと、朝シャワーを浴びてから部屋に戻るまでの間に、掃除の行き届かない床を歩いて足の裏にくっついた細かいゴミが、そのまま足の裏に残ってしまうのだ。もう一方のより素朴なやり方は、スマートさの点では劣るうえに、古い靴下だと破れてしまうという危険性も孕んでいるのだが、足を奥に滑り込ませる過程で足の裏に付着したゴミが落ちるので、家を出て地下鉄の駅に向かう道すがら、土踏まずの下あたりで細かい粒がコロコロするというような不快な事態は、めったに起こらずにすむ。」
この引用からもある程度伝わると思うけれど、ニコルソン・ベイカーという人はどうやら、ストローやホチキスや靴下のはき方をめぐる諸問題が本当に好きなのであり、それらと本気で対峙して人生を送っているのだ。この手の小説は、作家がアイデアを利用している感じが鼻につき出したらおしまいだが、この人の場合は心配無用、そして訳文も作者のそういう世界観にしっかり共鳴している。
『中二階』に刺激されて、同じベイカーの未訳作品『U&I』も読んだ。タイトルを声に出してみるとユー・アンド・アイ、すなわちアナタとワタシ。これは小説ではなく長篇エッセイで、Uは大物作家ジョン・アップダイク、Iはベイカー本人のこと。要するに、新進作家が大先輩作家に対して感じる尊敬、羨望、嫉妬、その他もろもろの感情が書いてあるのだが、かつ、そうやって尊敬とか羨望とか嫉妬とかをあからさまに書いてしまうことの嫌らしさを自覚していることも書いてあり、かつそういう嫌らしさを自覚していることを書いてしまうことの嫌らしさも書いてあり……と、メタレベル、メタメタレベル、メタメタメタ……のあいだを考察は行き来する。でもこの行き来の仕方が、案外しっくり来るのだ。実際、たいていの人は、ひとりでぼんやりモノを考えるとき、まさにこんな感じに、いくつもの論理階梯のあいだをいい加減に行ったり来たりしているんじゃなかろうか。『中二階』と同じで、一見変な本だが、実は相当リアルに現実を写しとっている気がする。
都築響一の『東京スタイル』から得られるのは、『中二階』そっくりの楽しさだ。四百ページ近いこの写真集の被写体になっているのは、よく雑誌に載っているようなリッチでシックでエレガントなインテリアなんかではない。現実に東京で生きている人たちが住んでいる、たいていはモノでびっしり埋めつくされたゴッチャゴチャの空間である。本や服やAV機器がびっしり並び、安物のカラーボックスとかプラスチック製収納用品とか何の変哲もない灰皿や薬ビンやティッシュの箱とかがそこらじゅうに転がっている室内に注がれたカメラの視線には、悪意も皮肉もいっさい感じられない。読むほうも、パラパラめくっているうちに、あっこのカネゴン人形オレも持ってた、とか、あっこの本大学のとき読んだ、とか、そうそう中野のアパートにいたときこんなテレビ拾ったっけな、とか自分の東京生活としっかり重ねあわせながら、夢中になって眺めている。人間そのものは写真にいっさい出てこない(一枚だけ鏡に手と足が映っているが)のに、生活の手ごたえが見事に伝わってくる。これはまさに、二十世紀末の東京生活に関する貴重な資料だ。
これより一時代前の、昭和三十~四十年代の東京の雰囲気を伝える一級の資料が、『おそ松くん』『天才バカボン』など、一連の赤塚不二夫の漫画だと僕は思っている。かつて東京じゅうにあった、空き地に土管が転がり、白熱電球の街灯の下には黄色っぽい光の水たまりが浮かび、道路にまだガードレールがなかった町。ほとんどの子供にとっては、それが全宇宙だった。そういう小宇宙としての「下町」の感じを、赤塚不二夫は生き生きと記録している。今回竹書房から出た『天才バカボン』七巻セットを読んで、改めてそう思った。
『天才バカボン』のストーリー展開は、『おそ松くん』とだいたい同じである。バカボン一家の住んでいる町に、泥棒とか気の触れた科学者とかいった「異人」が現われて、おまわりさんやらお掃除おじさんやらを巻き込んだすったもんだがあった末に、「異人」が排除され、町に秩序が戻る、というのが基本的パターン。ほぼ毎回、最後の方で出てくる、寝静まった町を月が照らしている(そしてネコが一匹だけ起きている)一コマがとても好きだ。
『おそ松くん』のころの赤塚不二夫はけっこう感傷的なところがあって、ギャグで笑わせておいて、最後にホロリと泣かせることもよくあった(実際、感傷小説の王者O・ヘンリーの短篇「最後の一葉」や「警官と賛美歌」も『おそ松くん』で漫画化している)。ところが『天才バカボン』の途中から、そういうチャップリン的ペーソスを赤塚不二夫は自分に禁じるようになって、純粋にドタバタ・ナンセンスだけで勝負するようになり、その姿勢が『レッツラ・ゴン』で完成するのである。
でも実をいうと、初期の、泣かせる赤塚も僕は十分好きだ。「愛と笑いと涙」とかいったキャッチフレーズの新作映画なんか金をもらっても見たくないが、こと赤塚不二夫に関しては、小学生のころ、『おそ松くん』が連載されていた少年サンデーを買いに、まさに赤塚的な町を歩いていった日々を思うと、センチメンタルで何が悪い、と臆面もなく開き直ってしまうのである。
【この読書日記が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする
初出メディア