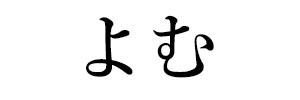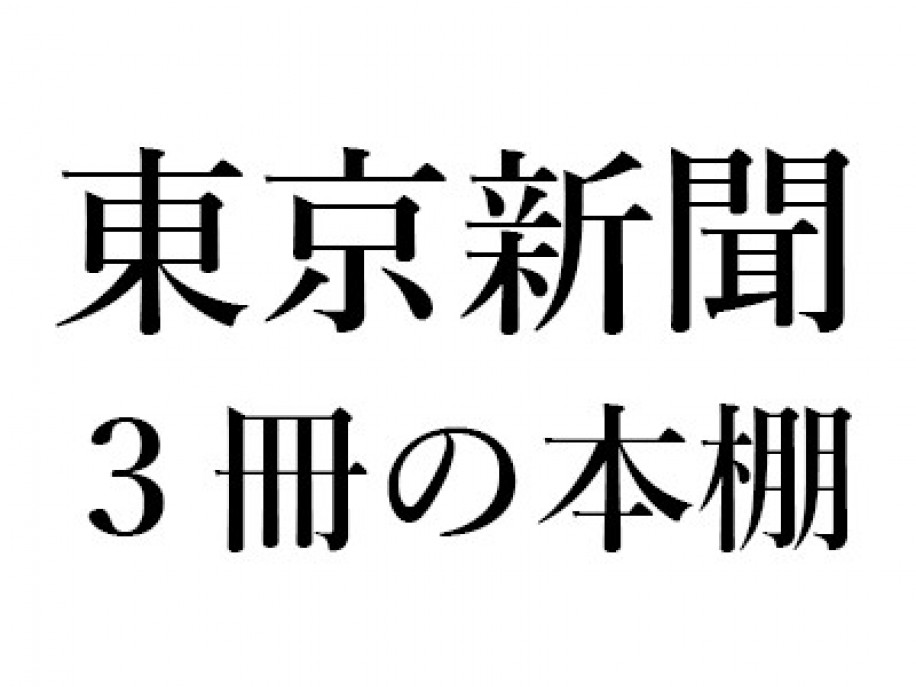コラム
瀬戸内晴美『美は乱調にあり』(角川文庫)、井手文子『青鞜の女たち』(筑摩書房)、堀場清子『青鞜の時代――平塚らいてうと新しい女たち』(岩波書店)ほか
『青鞜』再発見
一九九一年五月で平塚らいてう没後二十年になる(ALL REVIEWS事務局注:本書評執筆時期は1991年頃)。二昔半前、本郷誠之小学校の郷土史クラブにいた私は、薄暗く、整理のあともない資料室の卒業生資料に平塚明(らいてう)の名前を見つけた。NHKの「風雪」という番組が雪の塩原心中や『青鞜』発刊を取り上げたのを見たばかりだった。それから瀬戸内晴美『美は乱調にあり』(角川文庫)、井手文子『青鞜の女たち』『自由それは私自身』(筑摩書房)、小林登美枝編『元始、女性は太陽であった――らいてう自伝』(大月書店)、香内信子編『母性保護論争』などを読みふけってきた。
堀場清子『青鞜の時代――平塚らいてうと新しい女たち』(岩波新書)のあとがきに「少女のころから『青鞜』は輝かしい伝説として私の天空にかかっていました」とあるのは世代こそ違うが私の思いでもある。人間として十全に生きようと願う多くの女性が、青春期に『青鞜』と出会い、らいてうの毅然とした、また野枝の激しい生き方に魅かれるだろう。
ところでその『青鞜』の活動は私の住む本郷、下谷あたりが舞台なのだ。らいてうの家が曙町、発刊を相談した生田長江邸が根津西須賀町。事務所は初め千駄木林町の物集(もずめ)邸におかれ、のち蓬来町の万年山勝林寺に移った。田村俊子は谷中天王寺町に住み、らいてうの通学路、座禅へ通う道、森田草平や奥村博とのデートコースもほぼ私の町の範囲に納まってしまう。
昨年四月、小林登美枝さんや望月百合子さんとこの『青鞜』のあとを一日歩き、俄然、興味が再燃した。それから『自伝』や『青鞜』復刻版(全五十二冊、不二出版)を読み返しながら、何度となく谷中や千駄木を歩いた。らいてうの通った禅道場両忘庵は谷中天王寺脇に移って現存し、谷中墓地には南湖院の高田畊安、らいてうを吉原へ連れていった尾竹竹坡、同人の江木欣々の墓も見つけた。青鞜社の建てた遠藤清子の墓は了俒寺の草むらに隠れ、訪ねる人もないとのことだった。料亭伊香保跡や浅草海禅寺も足で確かめた。らいてうは何と「歩く人」だったことだろう。
そのうちなんだか『青鞜』の人々が身近に思えてきた。これまではなにしろ「大空の星」だからつい神格化したり、その華やかな恋に憧れたり、らいてうや野枝の思想的根拠は何かなどに興味があった。が自分も同じ千駄木の山で、二十代の女性だけで地域雑誌『谷根千』を始めた共通性もあって、だんだん編集集団としての『青鞜』に興味を引かれていった。
『青鞜』の後記を読んでいると「青鞜」編集室が目に浮ぶ。静かな編集室で煙草を吹かしながら後記を書く。皆で汗だくになって校正をしたり、研究会の看板をらいてうがヤセ腕で書き上げる。小林哥津、尾竹紅吉、伊藤野枝の十代三羽ガラスがふざけ合う。事務所を貸した万年山勝林寺(現在は染井にある)を訪ねると、「前住職が少年のころよく『青鞜』のお姉様方に焼き芋を買いにやらされたそうです」と話して下さった。ふうん、「青鞜」ってイモねえちゃんの集りだったのかァ。出版には素人の若い女性たちが、ともかくもひたむきに小さな雑誌を編集していた様子が伝わってくる。
そう、ミニコミなのだ。女性史上での輝きから誤りやすいが、『青鞜』は初版千部、最盛期で三千部。足かけ六年、五十冊ほど出ただけなのである。
いや自主出版を五年つづけるのは大変なことだ。内省的ならいてうが、読者への対応、書店との交渉などの事務に体の芯から疲れ切って『青鞜』を手放すのもよくわかる。たった千部、たいしたものだ。昔の千部はいまの千部とはちがうだろう。そして、いまは千部の雑誌の版元を引き受けてくれる出版社はまずないだろう。しかし、本当に伝えたいことを共有し発信していくメディアはそんなに大きくなれるはずはないのだ。何十万部となると
双方向性、批判的公共性は失われ、雑誌は操作・洗脳のためのもの、たとえばいまあるおおかたの商業誌のような「大企業の共同PR誌」になりやすい。
このたび最も教わるところの多かった本は、冒頭にあげた堀場清子氏の『青鞜の時代』である。ハンディで読みやすく、同人一人一人にも光をあてながら、鮮やかに活動集団としての『青鞜』を時代の中に位置づけている。
小さなことでは、らいてうがモデルとなっているヒロインが「一枚置きに義歯を入れ、物を言ふたびに煌々(きらきら)と人の眼を射」ていたのは森田草平『煤煙』の創作なのか気にかかっていた。が前掲書で『女学世界』の杉浦翠のらいてうインタビューにも「蕋とも見るや金義歯(きんいれば)のちらちらと」とあるではないか。これは要吉(草平)が「何か知ら終始思ひ切ったことをしなけりゃ、一日も居られない女だ」と、このしとやかで不敵な女性を、当時、男性の側からは理解不可能だったことを示す大事なモチーフである。
またらいてうが『青鞜』三巻一号の「新しい女」特集に執筆せず、『中央公論』の「閨秀十五名家一人一題」に「新しい女」を寄せたことについて堀場氏は、「彼女の歴史的発声は“名流夫人”らの愚文に混じって『中央公論』を飾るより、あくまで『青鞜』それ自身の旗幟として、寡兵の陣頭に翻えるべきだった」と批判しておられる。まことに同感だ。それでこそ『青鞜』復刻版も輝きを増しただろうと惜しまれる。
それにしてもこの復刻版は異例の安価であるのに、お茶の水女子大の女性資料センター、文京区の婦人センターでも鍵付の書棚にしまってあった。『青鞜』復刻版くらい開架式で読めるのがまともな「女性資料室」といえるのではないか。
【このコラムが収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする
初出メディア