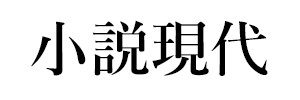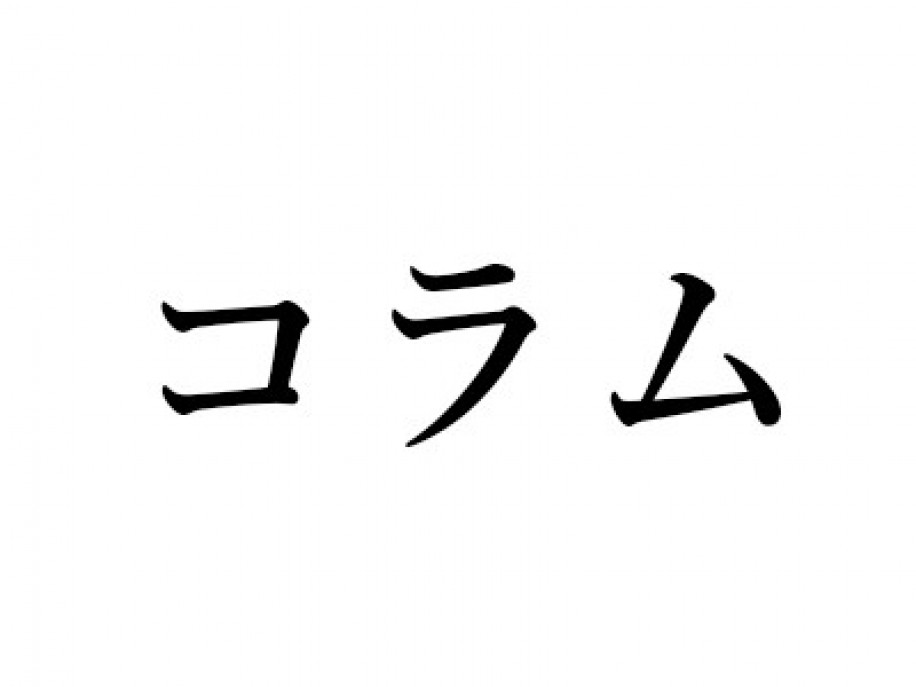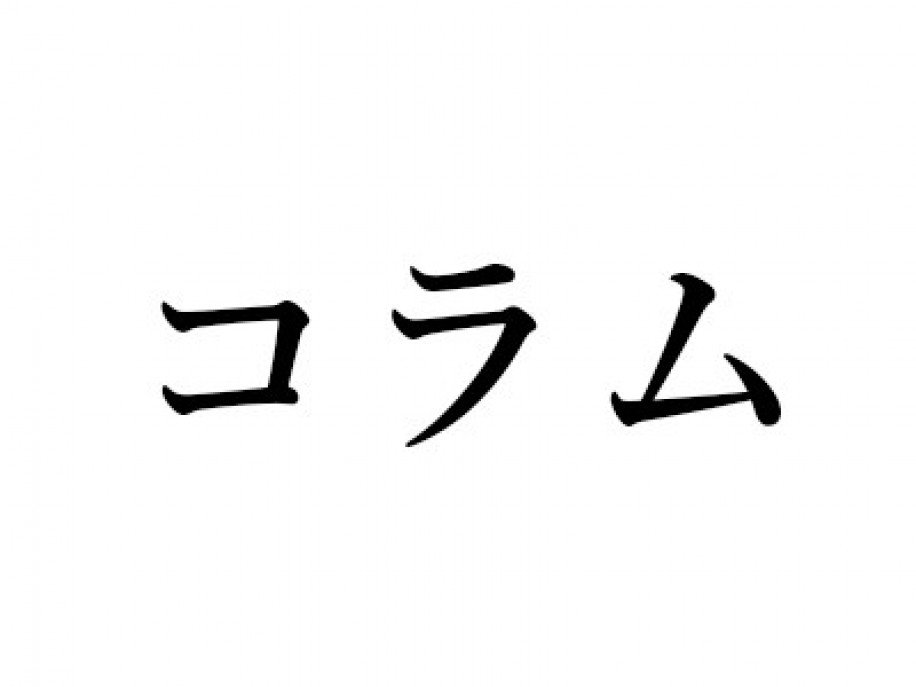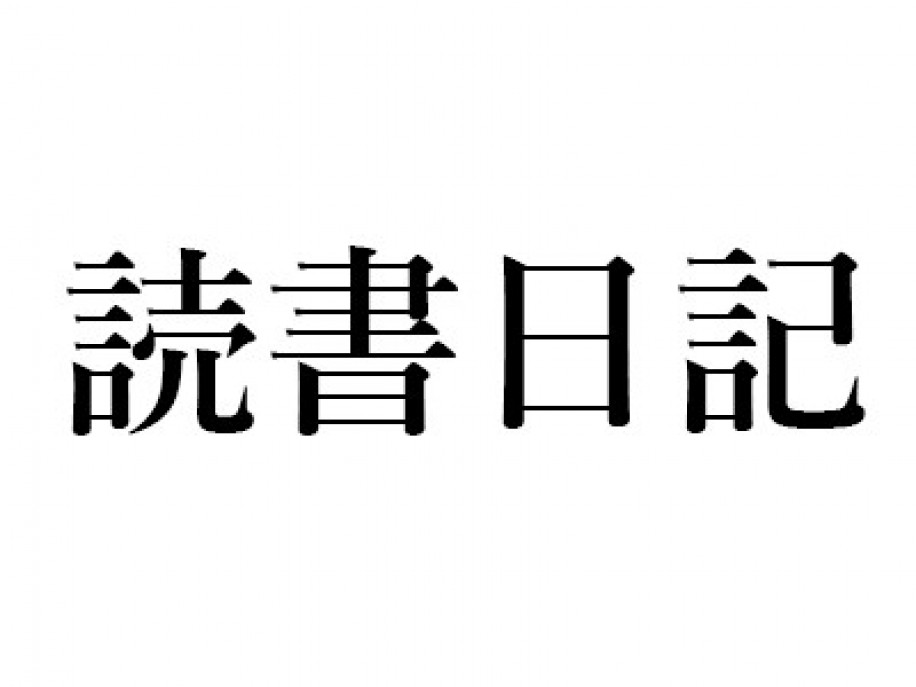コラム
アンドルー・チェイキン『人類、月に立つ』(日本放送出版協会)、海部 宣男『宇宙をうたう』(中央公論新社) ほか
星に願いを
出張先のホテルで「ニュースでも見るか」とテレビをつけると、ちょうど映画がはじまったところらしかった。ぼーっと眺めていたが、だんだんに引き込まれ、画面のまん前に移動して、本格的に見はじめた。風呂にお湯をためてあったが、終了まで、画面に張り付いたまま微動だにしなかった。トム・ハンクス主演「アポロ13」。発射後のトラブルで、三人のクルーが命の危険にさらされながら、奇跡的な生還を遂げた事実に基づくものだ。
もともと私は、人間が困難を乗り越えるドラマが好きなのだが、その映画は、無重力空間などがうまく撮影されていて、ほんとうにもうのめり込んでしまった。NASAの優秀な頭脳が知力の限りを尽くし、みごと生還を果たしたシーンは、感動ものだった。この一作でトム・ハンクスのにわかファンになったほどである。
出張から帰って、ヘンリー・クーパーJr.著、立花隆訳『アポロ13号 奇跡の生還』(新潮文庫)、ジム・ラベル、ジェフリー・クルーガー著、河合裕訳『アポロ13』(新潮文庫)のドキュメントをむさぼり読んだ。カタカナの名や専門用語が多いが、映画であらましをつかんでいたせいで、苦にならなかった。
アンドルー・チェイキン著、亀井よし子訳『人類、月に立つ(上・下)』(日本放送出版協会)は、アポロ計画のすべてを描いた、スケールの大きい、かつ緻密なノンフィクションだ。他ならぬトム・ハンクスが序文を寄せている。
トム・ハンクスも少年のとき、テレビが伝える打ち上げの映像を、胸ときめかせながら見守っていたひとりだという。夜空は、いつの時代も、人々にとって知的好奇心の最初の対象のひとつだが、六〇年代の人々には、とりわけそうだったに違いない。
「あの月はどれだけ遠くにあるのだろう」
「いったいどんなところだろう」
いにしえより、人々が抱いてきた問いに対する回答が、もうすぐ与えられようとしている。そこには私たちの住む惑星の成り立ちを知る手がかりも、あるのだろうか。
一九六九年、アポロ11号が月面着陸。八歳だった私にはおぼろげな記憶しかなく、今あわてて宇宙に関する本を読んでいるのも、世紀のイベントに乗り遅れたぶんを、取り戻したいためもある。
この本は、国の政治との関係から、ひとりひとりの乗組員の苦悩まで、よく取材されている。シュミレーターでの徹底した訓練、月における分刻みのスケジュール。だからこそ、クルーの次のような告白が、かえってリアルに感じられる。「たしかにすばらしい体験だった。しかし、人生観を左右するほどのものではありえない。いまこうして振り返ってみても、あまりにも訓練とそっくりだったので物足りなさを感じる、という思いを振り切ることができない」。
立花隆著『宇宙からの帰還』(中公文庫)は、宇宙体験が飛行士にもたらした精神的なインパクトについてインタビューしたもの。私にとって印象的だったのは、エド・ギプスンの話だ。宇宙は実に美しくみごとに調和していた。こんなものが偶然にできたはずはない、宇宙をかくあらしめた何らかの存在があるに違いない、という。
彼はそれに「神」の名を冠しない。では何かと問われれば、わからないというほかない。わからないとするのが正しいという「積極的不可知論」を自分はとると。
科学技術の粋を集めた最前線にいた人の、行き着くところが不可知論とは、深いものがある。ギプスンによれば、科学にできる説明は「あるレベルの無知を別のレベルの無知に置きかえることでしかない」。根源的な「なぜ」に、科学は答えることができない、と。
宇宙物理学者でNASA主任研究員も務めた桜井邦朋は『宇宙には意志がある』(クレスト選書)で、その領域に踏み込んでいる。物理学を哲学から切り離し、「なぜ」を問わないニュートン的アプローチが、科学を進歩させてきた。が、物理学はそろそろ「なぜ」に向き合うときだ、と。
そこで紹介されるのが、「宇宙の人間原理」なる仮説。アメリカの学者が最初に唱えたもので、人類誕生にいたる宇宙史は、単なる偶然の連続ではなく、自らの内に知的生命体を作り出そうという、宇宙の「意志」による、とする。その人だけの思いつきではないらしいことには、他の学者からも続々とそれに類する論文が出されている。
「創造主」を仮定するヨーロッパの知的伝統を受け継ぐ説のようで、日本人の著者には、とまどいもあるそうだ。読者としてもすぐには受け入れがたいかも知れない。が、物理学者たちが今一度、「自分たちはどこから来たか、何のために存在するのか」の問いに取り組もうとする試みは、新鮮である。
海部宣男著『宇宙をうたう』(中公新書)は世界最大級望遠鏡「すばる」の建設をてがけた著者が、歴史の中で、宇宙は人々のこころにどのように映じてきたか、古今の詩歌に探ったエッセイだ。天文学者としての三十年間の研究のかたわら、「宇宙に惹かれてやまない人間のこころというものについても、おさえきれない興味を感じてきた」。
沖縄の古い歌謡からギリシャ、中国、インドの書物まで、とにかくよく読んでいる。文系、理系の別を超えた、ほんとうの「教養人」を感じさせる。
さまざまな歌が出てくるが、天文学者らしい選だと感じるのは、次の一首。
あらし吹く冥(くら)き宇宙にみづひきの花のごと散る星座星雲 高野公彦
私たちの目に映る星は静的なものだが、望遠鏡で覗く世界は、そうではない。激しいガスの流れ、星の死がもたらす爆発と衝撃波など、めまぐるしいほど動的な、物質の流転がくり広げられる。人類の営みは、その壮大な流れの中の、ほんの一瞬でしかない。
「すばる」建設のためハワイに移り住んだ著者は、千年も昔の人が、海図も羅針盤も持たず、カヌーひとつで漕ぎ出して、星々をたよりにこの島に渡ってきたことに、胸を打たれた。「私たちも古代の人々から冒険の心とうたを受け継いで、どこまでも遠く、未知の世界に分け入ってゆきたいと思う」。
冒険は、果てしなき挑戦、うたの心は、愛と畏れと言い換えてもいいだろう。自分が生かされているこの世界に畏敬の念を抱きつつ、知ることを求めてやまない、健全な知性がここにある。
【このコラムが収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする