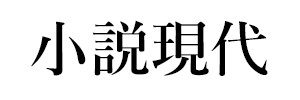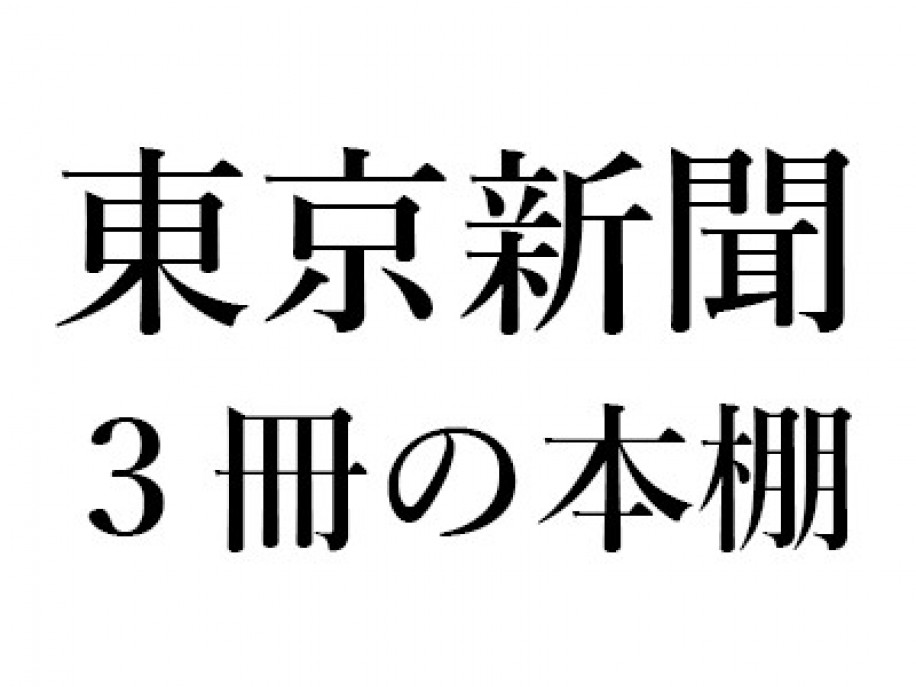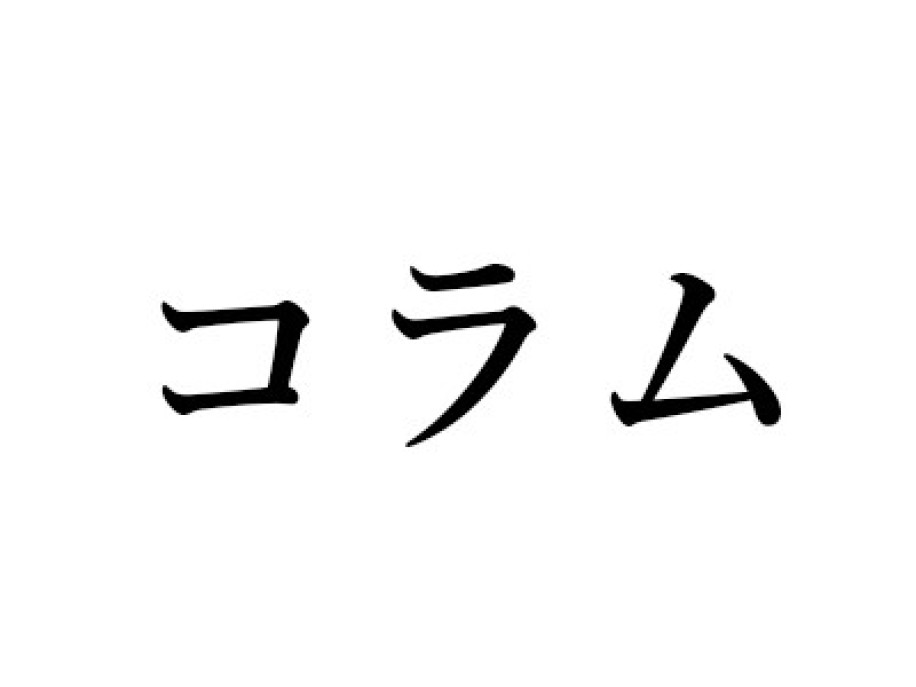読書日記
五木寛之編『うらやましい死にかた』(文藝春秋)、山田風太郎『人間臨終図巻』(徳間書店)、立花隆『臨死体験』(文藝春秋)、中西進『辞世のことば』(中央公論新社)ほか
あの世に行くとき
始発駅で、後から出る空いた方の車内に座っていたら、大股で乗ってきたサラリーマンふうの中年男性が、私の並びに腰を降ろすや、手にしていた本をがばと開いた。ホーム向かいの先発電車も、まだドアを閉めていなかったが、読書のために座っていこうと、はじめから決めていたらしい。本のみならず膝までがばと開き、前かがみになった姿勢には「さあ、読むぞ」という気迫がこもっていた。
ベルが鳴り、向かいの電車が滑り出した。となりの男は、まるめたティッシュでひっきりなしに鼻をこすっては、すすり上げる。
(風邪か? だとしたら、うつりたくないから、さりげなく横へずれようか)
と迷ってから、はたと気づいた。この男、もしかして泣いている?
やがて、「うっうっ」と鳴咽を噛み殺すような声が、歯の間からもれてきた。肩はもう小刻みどころか、はっきりと震えている。本を読んで泣く男性を目撃したのは、はじめてだ。
それにしても、われわれの電車はまだホーム。表紙を開いてから、ものの五分もしないうち、こんなにも泣ける本ってあったっけ?
横目で見れば、五木寛之編『うらやましい死にかた』(文春文庫)。
その本ならば、さもありなん。全国から寄せられた、身近な人の死をめぐる文章、四十編。編者が選ぶため読むうちに、こみ上げる思いをおさえられなくなり、涙のみならず鼻水まで「ぐじゃぐじゃになって流れる始末だった」と、広告にあった。
五木さんといえば、私にとって、田村正和の作家版というべき「ハンサム」のイメージがある。なのに、鼻水まで出てしまったと、てらいもせず書き、しかも広告に載せるとは、(この人、すごくいい人なのかも知れないなあ)
と思っていた。そこへ、この泣き男出現。これはもう、読むっきゃない。
死に方の本としては、古今東西の有名人の例を集めた、山田風太郎の『人間臨終図巻』(徳間文庫)があるが、『うらやましい死にかた』は、日本人の無名の人版と言えようか。
饅頭を十二個食べて死んだ人。「俺は行くぞ、泣くな」とひとこと言って逝った人。自らのがんの進行を正確につかみ、別れの挨拶を述べた後、点滴をはずさせ「モルヒネをお願いします」と最後の指示を出した医師。枕べに集い、お茶を楽しむ家族に、覗き見てきたあの世のさまを話して聞かせ、笑い声の絶えない中で、息をひきとった人。実にさまざま。
りっぱな最期ばかりではなく、滑稽な死、間の抜けた死もあるが、「生を終えるときに、人間は大きなものを残して去るのだ」と編者。
死が避けられないものである限り、人々が望むのは「安らかに死にたい」ということだろう。私はそれに「死んだ後は、生まれ変わりたくない」をつけ加える。
戦争のない時代に生まれ合わせ、つくづく運がいい人間だと、自分のことを思っている。
歴史上のさまざまな悲惨を振り返ると、この先生まれ変わっても、今以上に、恐怖から解放された生を全うできる世があるとは、考えにくい。だから私は私の命を、この一代で終わりにしたい。
死後の世界に関しては、臨死体験者が報告している。もしそれが現実の体験なら、死後の世界は存在することになり、生まれ変わる可能性も否定できない。それに対し、現実体験ではなく、脳内の情報伝達の異常に過ぎないとする説もある。立花隆著『臨死体験(上・下)』(文春文庫)は両説をたんねんに検討する。死んだらどこへ行くかということが、かねてより気になっていた私は、むろん読んだ。
本によれば、いずれの説も完全ではなく、どちらをとるかは、各人の世界観の違いに帰着するようだ。すなわち、物質界と別に精神界があるとする二元論か、すべてが物質で説明できるとする一元論か。
取材をはじめた頃の著者は、どちらが正しいか、早く知りたいと願っていたという。が、取材を重ねるうち、現段階ではいくら調査研究しても、答の出る問題ではないらしいとわかってきた。だとしたら「生きてる間は生きることについて思い悩むべきである」が、下巻のまとめの言葉である、
同感だった。仮に答がAであったとしても、「BならいいがAなら嫌だ」と拒否することはできないのだから。AであれBであれ、私たちは必ず死ぬのだから、著者の結論は、すこぶるまっとうだ。
(健全な知性とは、こういうのを言うのだろう)
と思う。緻密な論理を積み上げていく思考力と同時に、あるところでぱっと、ものごとの本質をつかみとり、価値判断が下せる。ミクロとマクロとの間を自在に行き来できる著者の頭は、やっぱりすごい。
死が現実に迫ったとき、人が抱く感慨を、次の歌ほどよく表したものはあるまい。
つひに行く道とはかねて聞きしかど昨日今日とは思はざりしを
在原業平が詠んだ歌だ。板垣退助が襲撃され、命の危機に瀕したときに「板垣死すとも自由は死せず」と叫んだというのは眉唾(まゆつば)ものだが、昔から多くの人が、死出の旅路に赴く思いを、言葉に託してきた。
中西進著『辞世のことば』(中公新書)は、真偽のほどのあやしいものや、時期的には死のかなり前に語られたものをも含め、六十人の「生の総体を訴えたことば」を、とりあげる。
それぞれに含蓄があるが、蕪村の臨終の句は、視覚的に印象深い。
白梅に明くる夜(よ)ばかりとなりにけり
目前に広がる、死後の世界を、一幅の絵として切り取ったようだ。その前の二句は、
冬鶯むかし王維が垣根かな
うぐひすや何ごそつかす藪の霜
聴覚は、鶯の気配をとらえながら、頭の中では、過去と現在とが交錯し、意識がめまぐるしく明滅する。
やがて、すべての音と動きが断ち切れ、ふいの静止画像となる。ビデオで言えば、無期限のポーズ。暁の梅の枝に、時間はひっかかったまま止まり、朝が来ることはない、永遠に続く薄明。
死に方に関して、もう一冊だけつけ加えたい。藤沢周平の回想録、『半生の記』(文春文庫)だ。著者の師範学校時代の師が、結核で亡くなったときのようすが出てくる。枕べに寄る生徒たちに、先生は乱れる息を整えながら「死ぬということは、なかなか苦しいもんですなあ」と語りかけた。
臨終の言葉として、まことに味わい深いものがある。
ALL REVIEWSをフォローする