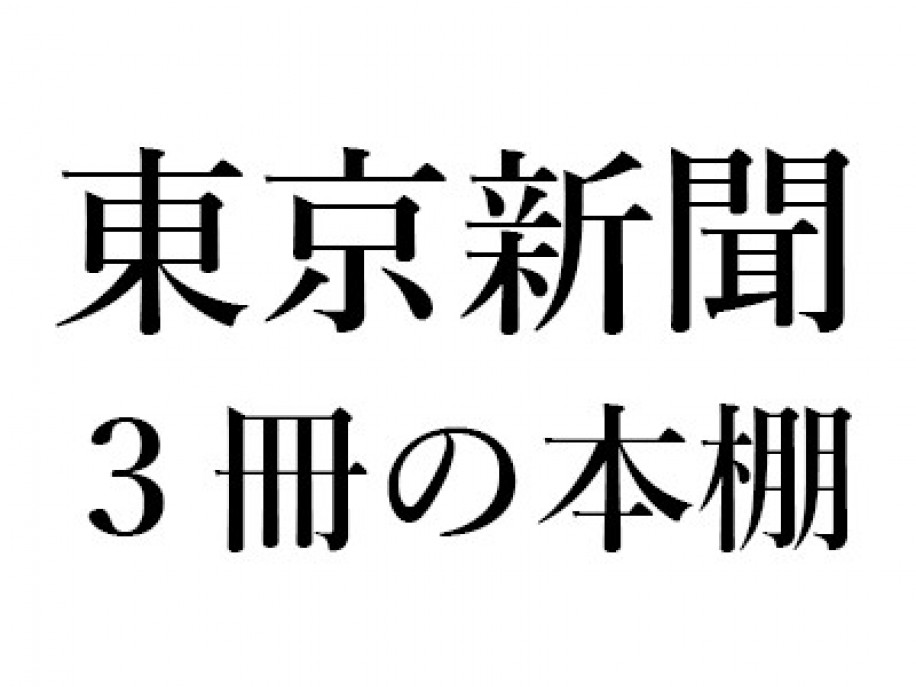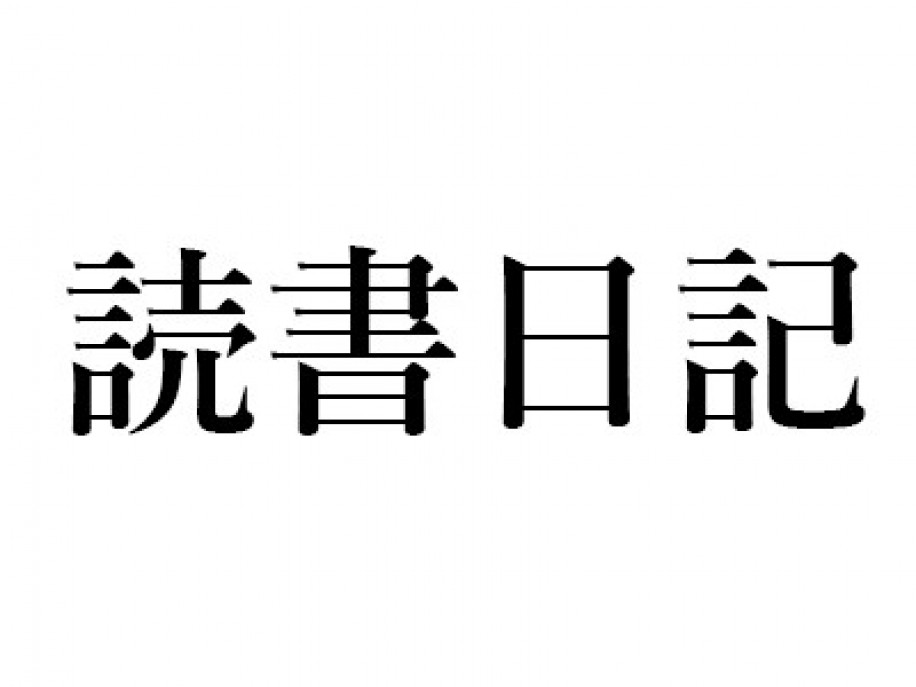書評
『下山の思想』(幻冬舎)
下り坂だからこそある喜び
デフレをとめて、ちょっとインフレになれば、いろんなことが解決するだろう。経済が成長しているときは、格差もそれほど大きな問題とは感じられない。そういうことは一応わかっているつもりだ。でも、必死になって働いて成長した向こうに何がある? 「日本の技術を世界に売り込め!」と発破をかけられても、「うーん、もういいよ」と言いたい気分。登った山は、下りなければならない。五木寛之の『下山の思想』は、そんないまどきの気分にぴったりくるエッセイだ。そういえば、法然も親鸞も山を下りて教えを説いた。
論理だてて、あるいは大きな声で、何かを主張する本ではない。書かれていることは、ほとんど著者のつぶやきに近い。大声でないからこそ受け容れられる。
東日本大震災について「下山中に大きな雪崩に見舞われたようなものかもしれない」という。経済が収縮し、人びとの気持ちが萎縮しているときに、とてつもない災害が襲ってきた。
登りよりも下りのほうが要注意なのだ。浮き石に足をとられやすいし、膝の関節も痛めやすい。転べばけがをする。
下りるというとネガティブなイメージだが、陰気な話題ばかりではない。下りには下りのおもしろさがある。登山だってそうだ。登っているときは足元しか見えていないけれども、下りになると視界が開けて景色を楽しむ余裕が出る。
「ノスタルジーのすすめ」という章が楽しい。とくに靴の話。欧米の靴屋は、きつめの靴をすすめるという。はいているうちに革が伸びて足にぴったり合うからだ。しかし、室内で靴を脱ぐ日本の生活には無理がある。いつのまにか著者の部屋には、買ったけれどもほとんどはいていない靴が大量に。
ところが若いころはきつかった靴が、いまは楽にはけるというのである。歳を重ねることで、足の肉が落ちたのだろう。これも下り坂で見つけた喜びではないか。呑気に下っていこう。
ALL REVIEWSをフォローする