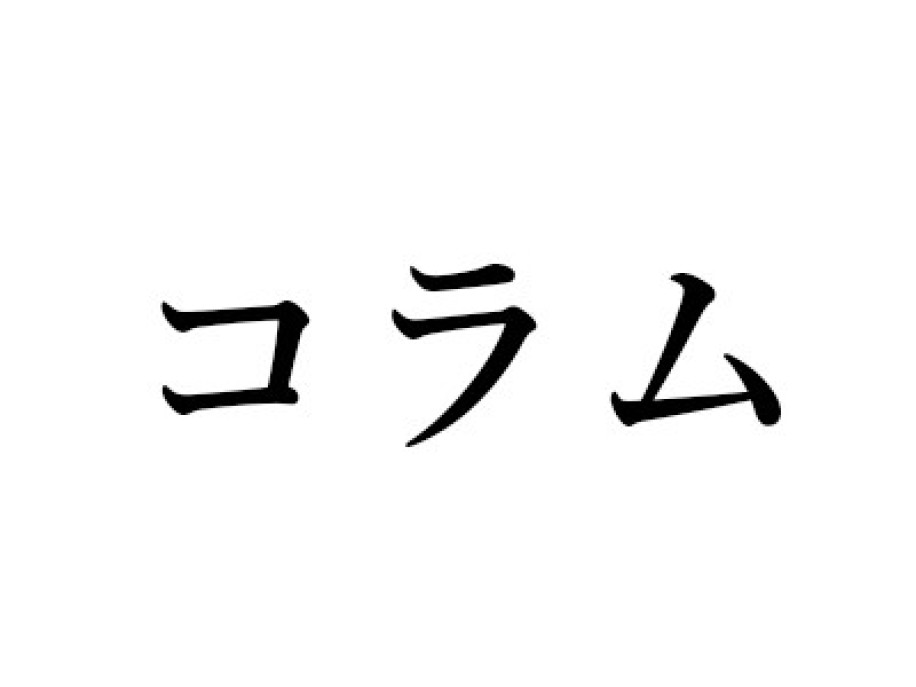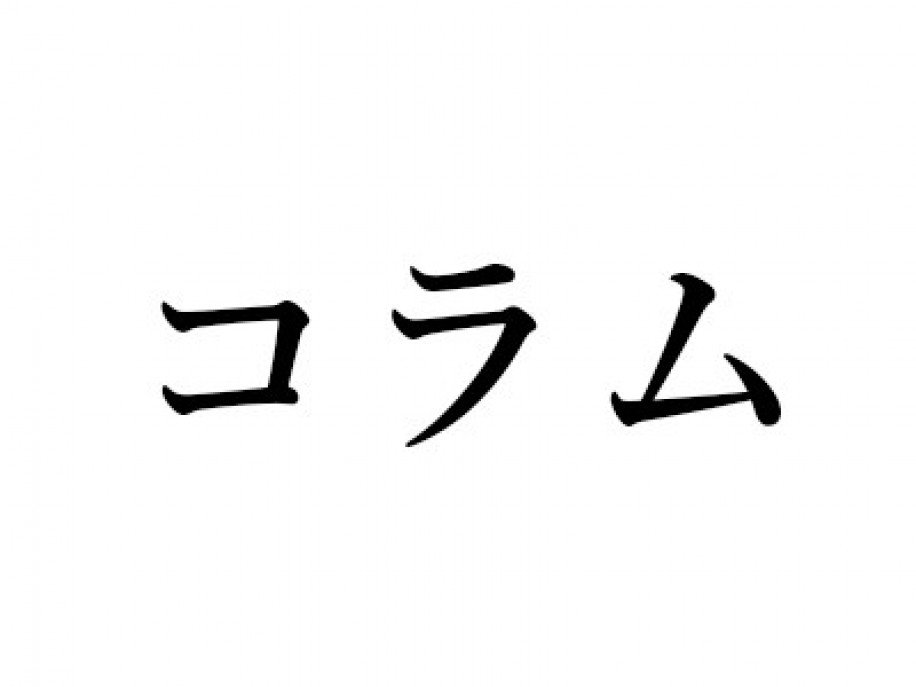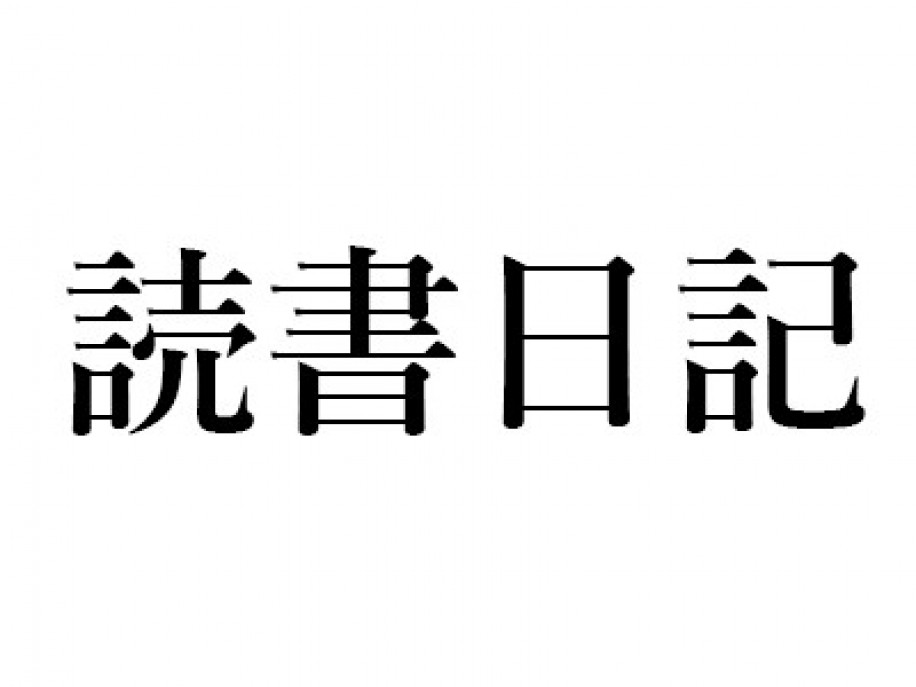書評
『天皇と東大〈1〉大日本帝国の誕生』(文藝春秋)
立花隆『天皇と東大』を読む
本書(立花隆『天皇と東大――大日本帝国の生と死』上下巻、文藝春秋、二〇〇五年)のもとになった『文藝春秋』連載論文のタイトルは、「私の東大論」。いささか芸がない題名とおもったものである。しかし、さすが立花氏、あるいはさすが文藝春秋の編集者。「天皇と東大」という、思わず膝を打つ表題にしている。いずれも近代日本を読み解くキーワードにとどまらず、天皇への距離(宮中席次)によって人間の価値が定まったように、学歴社会では、偏差値によって東大にどれだけ近いかで学校価値が示される。天皇制と東大はいろいろな意味で同型性をもっている。
だから、この卓抜な表題が、読者に天皇制と東大を「覗き窓」に日本の近代のはじまりから敗戦までをみるというかまえを準備させる。そのぶん連載時からくらべてはるかに読みやすくなっている。東大についての論稿や書物は少なからぬものがあるが、本書に独自性を添えているのは、これまでの論が東大を左翼の震源地としてのみ描くことが多かったのに対して、新人会の向こうを張った興国同志会や美濃部達吉のライバル上杉慎吉(一八七八~一九二九)らに光を当て、東大を右翼運動というもうひとつの反体制の震源地として、複眼で読み解いていることにある。「これまでの歴史書以上に詳細に、天皇と右翼について書いてきたのは、それがあの時代を読みとく歴史のカギだと思ったからだ」(下、六三八頁)と著者はいっている。
したがって「悪のファシズムvs.正義の共産党」というレッテル史観ではなく、なぜ右翼思想や右翼運動が生まれたのかを対象の内部から描く姿勢につながっている。国体学者平泉澄についても、来歴と人物交流を克明に追究しているから、奇怪なカリスマ人間が浮かびあがり、動きはじめ、謎が謎を呼ぶ。
大の健啖家で膨大な著作をまとめたエネルギーの塊、河合栄治郎(東京帝大教授、一八九一~一九四四)を解く鍵がバセドー病にあるとする立花流病跡学にはうなる。しかし、天皇機関説糾弾などの仕掛け人蓑田胸喜の思想を病気(狂気)にのみ還元してしまうのは、安易で、断定の根拠も薄弱ではないかと「?」をつけてしまうのだが……。
ALL REVIEWSをフォローする