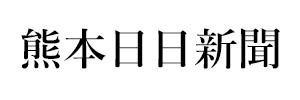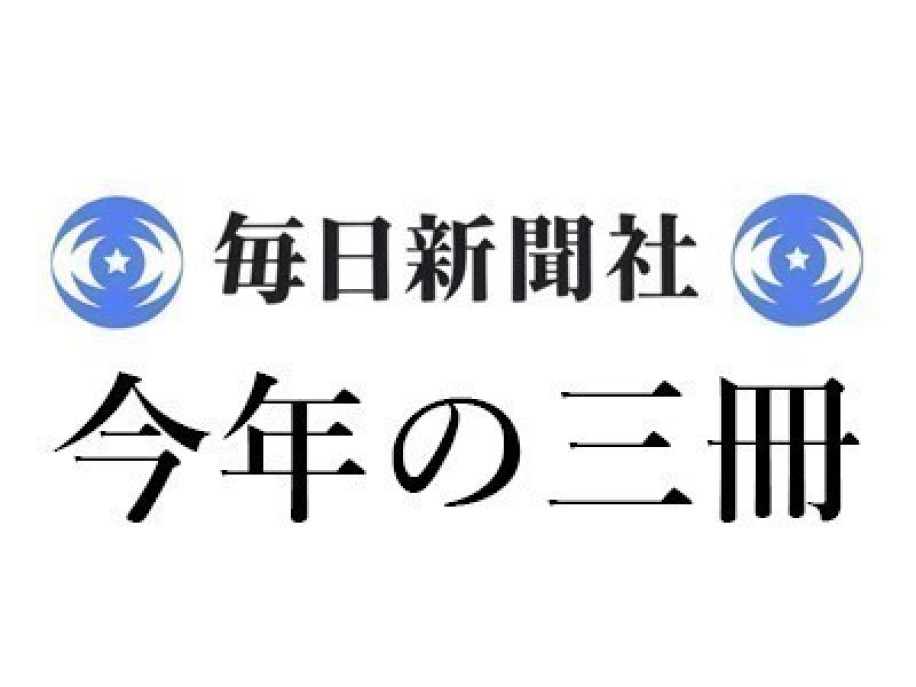書評
『「反戦」のメディア史―戦後日本における世論と輿論の拮抗』(世界思想社)
戦争の記憶
『「反戦」のメディア史』を読む
『二十四の瞳』や『ビルマの竪琴』を映画やビデオで観た人は多いだろう。しかし、この二つの作品のアピールの軌跡をたどると正反対なのである。『二十四の瞳』が映画化されたのは一九五四年(高峰秀子主演)、『ビルマの竪琴』は、その二年後、五六年である。『二十四の瞳』は、『君の名は』(第三部)とならんでホームラン級の興行成績をあげたが、『ビルマの竪琴』のほうは、興行成績で二十位にもはいらなかった。
ところが、それから三十年ほどたち、両作品は新しい陣容で再び映画化された。今度は『ビルマの竪琴』が観客動員数で『二十四の瞳』を圧倒的に凌駕した。中井貴一が演じた水島上等兵が記憶にある人も多いだろう。『二十四の瞳』は製作費すら回収できなかった。この事実からだけでも、敗戦後数十年の間に日本人の戦争への感情と論理が大きく変化していることがうかがえる。
本書(福間良明『「反戦」のメディア史――戦後日本における世論と輿論の拮抗』世界思想社、二〇〇六年)は、学徒出陣や沖縄戦、原爆などを題材にした戦後の反戦文学や反戦映画の名作について、そこでなにが語られているかだけではなく、作品をめぐる人々の感動や反撥を雑誌記事などによってほりおこすことで「いかに読まれたか」についての受容分析をおこなったものである。
反戦の感情や論理は時代とともに変化するだけではなく、同時代においても一枚岩ではない。沖縄戦と原爆に人々が読み込んだものはちがうからである。単行本か映画か、単行本であっても文庫本か新書かのメディア(器)の種類によって受容層と受容内容はちがってくる。
読者は、戦争をめぐる戦後の感情と論理の振幅の大きさ、重層性、脆さにあらためて驚くはずである。全共闘がわだつみ像を破壊したことが、当時大きな話題になり賛否両論が渦巻いたが、そもそもなぜそのような暴挙がなされたかについても、腹にすとんと落ちるように理解できる。
戦後自体が遠くかすんだ若い世代の著者であるがゆえに、かえって予断なく膨大な資料にあたり、全体を見通した明察となっている。
ALL REVIEWSをフォローする