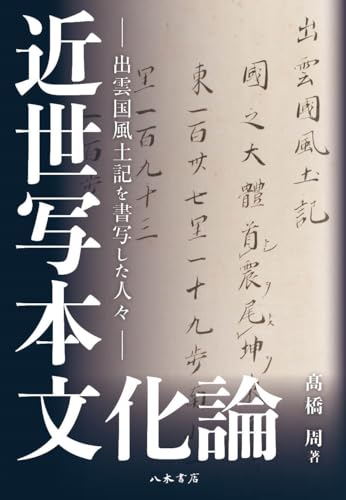書評
『集団就職の時代―高度成長のにない手たち』(青木書店)
高度成長を支えた人々
『集団就職の時代』を読む
いまから五十年ほど前、わたしは北国の小さな町の中学一年生だった。三月終わりに中学三年生の女子数人に呼び出された。明日、就職で東京に旅立つ仲間(女子)の見送りにいこうというもの。唐突だからと断ると、口調は一転して命令じみてきた。上級生とはいえ、女子の「脅迫」にまけてなるものかと意地になって、ことわった。
しばらくたって、小包が届いた。東京に就職した彼女からである。わたしのぶんも勉強してくださいとあって、参考書と人生雑誌、それに彼女の東京での写真が同封されていた。そんなことが数回つづいた。しかし女子から手紙などもらったことのないわたしは、狼狽し、にべもない手紙をそえ、小包をそっくり送り返した。
当時の高校進学率は五〇%程度(全国平均)だったから、この彼女がそうであるように、中学卒で都会に就職する人がかなりいた。中卒就職者のための上野行き特別列車が用意され、集団就職といわれた。加瀬和俊『集団就職の時代――高度成長のにない手たち』(青木書店、一九九七年)は、一九五五年の十~十四歳人口をもとにその十年後(二十~二十四歳)の地域別人口を計算している。東京や大阪では二倍近くに膨らみ、東北や九州では半減している。いかに多くの若者が地方から都会に移動したかがわかる。もちろんこの中には、短大や四年制大学に進学するために都会に移動した者もいるが、中卒で都会に就職した者も多い。日本の高度成長が大企業の力というよりも、下請けの零細企業の懸命な努力のたまものであるように、集団就職世代の頑張りが大きな力になったことは否めない。
本書は、一九五五年から六四年までの十年間にわたっての地方出身中卒大都市就職者に焦点をあてている。どのような職種につき、どのような悩みをもっていたかなどを克明に追跡している。地方出身中卒者は小規模企業就職が多く、労働条件は悪かった。事業主の家事手伝いさえさせられた。そうだからこそかれらは、仲間をもとめ、「若い根っこの会」などをともに語る癒しの場にしていた。わたしに手紙をくれた彼女がそうであったように、『葦』や『人生手帖』などの雑誌もかれらの生きるささえになっていた。
過酷な現在と不安な未来をなんとかのりきろうとする十代のけなげさにあらためて心打たれる。本書を読みながら十五歳で故郷を離れ、住み込みで働き、人生雑誌を愛読していた彼女に、激励の手紙ひとつ書かなかったことが悔やまれてならなかった。
ALL REVIEWSをフォローする