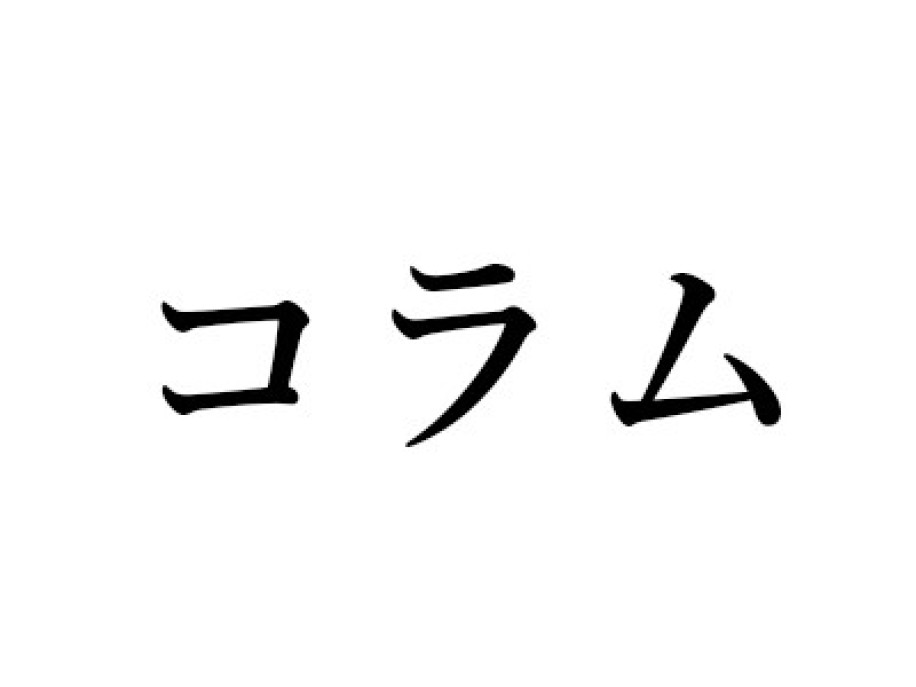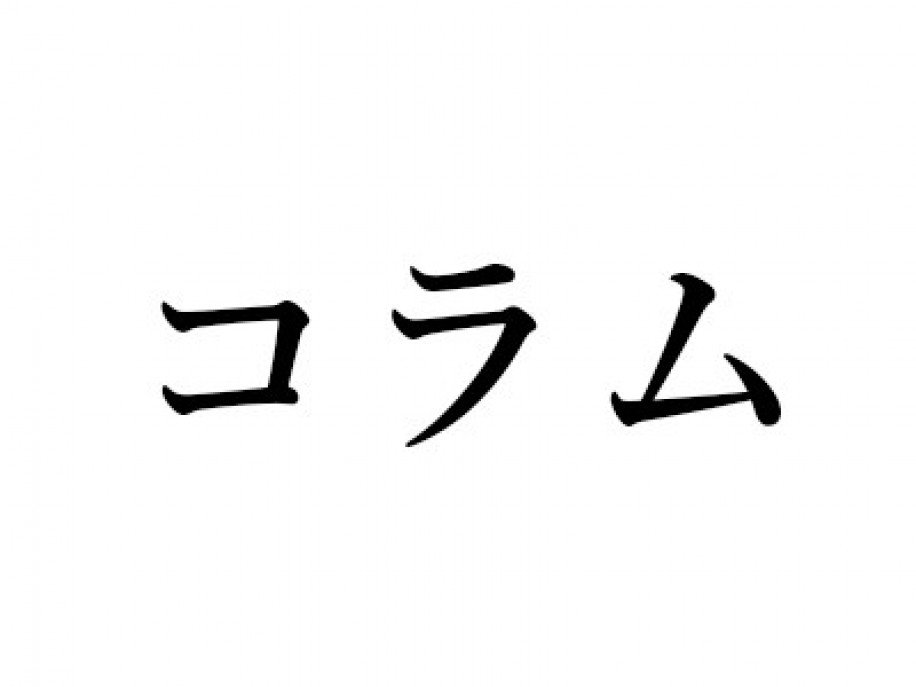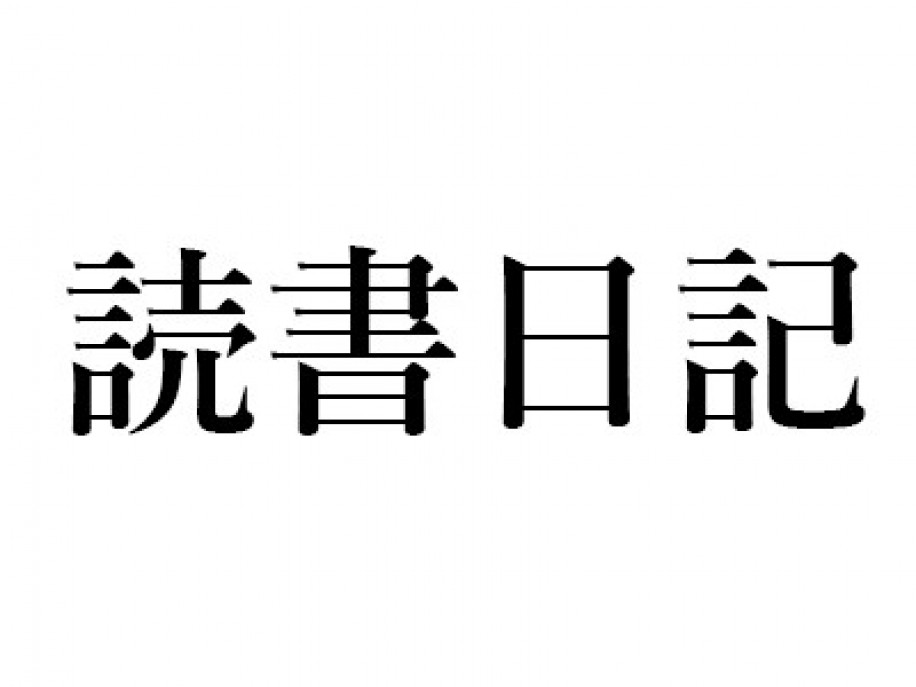書評
『天皇と東大 大日本帝国の誕生』(文藝春秋)
時代を変えた狂信的右翼の系譜
日本人は負けると解っている愚かな戦争をなぜ、どのようにして始めてしまったのか?東大に客員教授として招かれ、東大生の学力低下の原因を探っていた著者は、東大の歴史資料を渉猟するうち、次第にこの近現代史の大問題に心を捉えられるようになる。
なぜなら東大こそは「天皇の問題」が露出するトポスだったからである。すなわち近代国家建設のための官吏養成機関として創立された東大は官吏が仕えるべき国家のあり方(政体)を問う必要から、復古的天皇制と近代的国民国家をどう和解させるかという難問題と正面からぶつからざるを得なかったが、やがて、この相克から生まれ出た「国体」という観念が魔術的に日本を支配し、ついに大破局を用意することとなったのである。
とはいえ、一八七七年(明治十)に設立された東京大学の初代総理(総長)加藤弘之が説いたのは立憲君主制であり、専制君主制は「蛮夷の政体」とされていた。だが明治十四年の政変を機に自由民権運動が盛り上がると、危機感を抱いた国粋主義者たちは加藤の『国体新論』を非難し、「不敬」として絶版に追い込む。以後、左翼運動が活発化すると国粋主義者が不敬キャンペーンを展開するというパターンが常態化する。
大正デモクラシーの到来で時代が左に振れたときにも同じように右翼バネが働くが、その中心となったのが東大法学部教授で天皇絶対主義者だった上杉慎吉。
本書の最大の功績は、この上杉慎吉が組織した右翼学生団体「興国同志会」や「七生社」の系譜を丹念にたどって、そこから生まれた狂信的右翼学者や学生テロリストが時代の空気を変えていく過程をヴィヴィッドに描きだした点にある。
その源流にあるのが東大助教授森戸辰男のクロポトキン論を「朝憲紊乱(びんらん)」として槍玉にあげ、訴追に成功した「興国同志会」である。「興国同志会」は解散したが、ここから分かれたメンバーが右翼学生運動の源流をつくる。
一つは「七生社」から「一人一殺」の血盟団にいたる流れで、メンバー四人は井上日召の指導のもと西園寺公望や牧野伸顕を狙う。
第二は上杉と高畠素之(『資本論』の最初の訳者)が協力して造った国家社会主義団体「経綸学盟」の天野辰夫の流れ。血盟団事件と五・一五事件の弁護士をつとめた天野は大規模な陰謀「神兵隊事件」を知り、その首謀者となる。同時にこの流れからは戦争の遂行者となった岸信介らの革新官僚が出てくる。
しかし、なんといっても時代の空気を一変させたのは、狂信的右翼蓑田胸喜(みのだむねき)の流れだろう。というのも、興国同志会の指導的会員だった蓑田は、亡き上杉の衣鉢を受け継いで『原理日本』を創刊すると、代議士を使って「危険思想」を国会で追及させる手口を駆使して滝川幸辰京大教授を追い落とし、美濃部達吉の天皇機関説を葬り去ったばかりか、時代を「国体明徴」の方向に変えたからである。
ここで彼らの政治力は大学を力でねじ伏せ、思いを達した。天皇機関説問題以後、右翼国粋主義者たちの攻撃は全方位的になり、左翼的、あるいは自由主義的傾向を持つ東大教授たちはのきなみ攻撃の的になり、それに対して大学側が敗退に次ぐ敗退を重ねていくうちに、時代の風潮が大きく変り、日本は、過激右翼と軍部に支配された国になってしまったのである
ラ・ロシュフーコーのいう「伝染病のように感染(うつ)る狂気」を克明なノンフィクション・レポートとして描いた壮大なドラマである。
ALL REVIEWSをフォローする