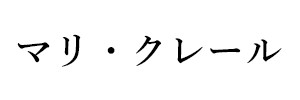書評
『脳死』(中央公論社)
脳死とはなにか、どうして脳死がいま死の判定基準として問題になっているのか。わたしはこの本から啓蒙され、はじめてわかった。普通の死は九九パーセントまでは心臓が止まり、そのあとで数秒から数分のあいだに脳に血流がなくなるために機能が停止して、脳死が起る。ところがあとの一パーセントくらいの死のばあい、まず脳死がさきに起り、心臓死があとからやってくることがある。この順序が逆なばあい、脳死が起ってから心臓がとまるまでの期間、脳は死んでいるが心臓は止まっていない状態がつづく。このばあいだけが、臓器の移植問題とからめて、いま社会問題になっている脳死を意味している。
脳死から心臓死という順序は、たとえば交通事故などで頭を強く打って脳挫傷を起したとか、ピストルで脳をブチ抜いたとか、脳内出血、脳梗塞、脳腫瘍などの病気や、一酸化炭素中毒などによって起りうる。
わたしはいままで脳死と植物状態の生存とを混同していた。この本の著者にいわせれば、これでは脳死を判定する是非をいうのは、とぼけたことになる。脳の損傷による脳死には、くわしくいえば、(1)内臓の働きや感官の働きをコントロールしている脳幹が死んで、高次な精神機能を営む大脳は生きている状態もあるし、(2)脳幹は生きているが大脳は死んでいる状態(これが植物状態)もあるし、(3)脳の全部が死んでしまった全脳死もある。そして普通は(3)の全脳死だけを脳死という。心臓の働きはぜんぶ脳に依存しているわけではないため、脳が死んでも心臓は生きているという状況がでてくる余地がある。そしてこの状態のうちの内臓ならばとり出して病者に移植できることになる。
ここまでくれば全脳死が、ほんとうに〈死んだこと〉の疑問の余地のない証拠でありうるかどうかが、重大なことになる理由が、誰にでもはっきり判ってくる。少しでも不確定なまま、臓器を切りとって他人に移植すれば、生体を切りとったことになるからだ。この本の著者によれば、厚生省がしめした脳死の判定基準は、(1)深昏睡、(2)自発呼吸の消失、(3)瞳孔が固定し、瞳孔径が左右とも四ミリ以上になる、(3)対光反射その他の反射の消失、(5)平坦脳波、(6)上の条件が満されて六時間以上経過して変化がない。二次脳障害、六歳以上の小児では六時間以上観察する。そうなっている。
著者はこの判定基準がかえって疑問を拡大したものだとして、ひとつひとつ詳細に検討している。記述は迫力と説得力にあふれていて、あくことなく専門的な知識を吸収し、専門家に問いただし、たぶん普通の医老よりももっと綜合的な知識と判断力を発揮している。この個所の記述を読みながら、著者の膨大な資料の追跡と綜合力に舌をまく思いがした。
あるひとつの判定基準に叶うということは、その事柄をその判定領域の枠組みの内部におくことは確かだ。だが逆に、ある判定領域の内部にある事柄が、かならずその判定基準に叶うとはかぎらない。もし判定領域が実体集合であるばあいには、判定領域の枠組みの内部にありながら、基準に叶わない要素が、いくらでも存在しうることになる。著者が厚生省やそれ以前の日本脳波学会の、脳死の判定基準に、執ように喰いさがり、疑問を提出している根拠は、つづめていえばここにあるようにおもえる。この誰でもが陥りやすい錯誤にたいして、著者は実例をあげ、委曲をつくして、一見すると抜け穴のないようにみえる判定基準が、ほんとは多義的な含みとあいまいさをもっていて、一義的な確証性がないことを説きつくしている。著者がつかっている説得力のある比喩でいえば、宇宙人が人間とは何かという判定基準をつくろうとして、人間をつかまえてきて共通項として「二足歩行のできる翼のない動物」という判定の基準を作った。これは間違いではない。だがもし人間以外にも「二足歩行のできる翼のない動物」が一匹でもいたとすれば、この基準には抜け穴があることになる。ニュージーランドには、キウイという「二足歩行のできる翼のない動物」が少数だがいる。すると一見間違いではない判定基準が、不都合な抜け穴をもつばあいがありうることになる。
この本の著者は、ひとつひとつの基準項目について、現在の判定基準があいまいで、この基準に従ったために、まだ生存しているうちに臓器を切りとって、他人に移植してしまう可能性がありうることを論証している。
わたしが興味をもったことがいくつかある。ひとつは、著者が、瀕死を体験したものが、外からは完全に意識を失ったのちに、上方から横たわっている自分や、あわただしく蘇生の心臓マッサージや注射をしている医者や看護婦たちの姿がみえ、会話の声さえきこえていて、みんな承知していたと記述している例を、瀕死から蘇った者の体験手記を通していくつか挙げたうえで、これは意識が外からは失われたとみなされても、「内的意識」は残存しているばあいだと述べている個所だ。この状態がほんとうならじぶんの臓器が摘出されると、その「内的意識」はじぶんが臓器を切りとられるのを知っていて、ただ外に訴えられないだけだということになる。著者はそれはゆゆしいことだと述べていて、脳死判定にいだく疑問へのおおきな支えとしている。わたしも以前にこんな瀕死者の記述を集めてみたことがあった。わたしは、このばあい自己客体視をともなっているので、「内的意識」が残存するというよりも、減衰した意識の最終段階で実現する自己客体視の映像とみなしたが、著者のいうようにこの状態で臓器を摘出すれば、その像を瀕死者は「視」ながら、叫びも訴えも外側に伝えられずに死んでいくことになる。これはどうしても避けられるべきだという著者の主張は、疑いない根拠をもっている。
さらに著者は、わたしなどの考えも及ばなかった注目すべき事実を記述している。大脳が人間性の中枢だとすれば、脳幹は生命体維持の中枢であり、やがて脳幹をとりかえ、人間性だけを最後まで生かすという時代がくるかもしれないということだ。もうひとつは脳死後に、ADHのようなホルモンを投与することで、心臓だけを一年も二年も動かすことは可能であり、もっと極端なことをいえば、このように生かし続けられた人間の頭脳のない身体部位を、血液を採取する資源に使うという着想も可能だということだ。M・フーコーが『臨床医学の誕生』で記述したように、「死」は身体の部位でせめぎあう連続した領域と領域の分布占有の問題であり、点でもなければ過半数でもない。そして部分的な領域を「死」から守護するために、外から技術的な加工を身体内部に施すこともできる。この本を読みながら、わたしたちは身体の概念の変更を迫られているのだと、つくづく感じた。
【この書評が収録されている書籍】
脳死から心臓死という順序は、たとえば交通事故などで頭を強く打って脳挫傷を起したとか、ピストルで脳をブチ抜いたとか、脳内出血、脳梗塞、脳腫瘍などの病気や、一酸化炭素中毒などによって起りうる。
わたしはいままで脳死と植物状態の生存とを混同していた。この本の著者にいわせれば、これでは脳死を判定する是非をいうのは、とぼけたことになる。脳の損傷による脳死には、くわしくいえば、(1)内臓の働きや感官の働きをコントロールしている脳幹が死んで、高次な精神機能を営む大脳は生きている状態もあるし、(2)脳幹は生きているが大脳は死んでいる状態(これが植物状態)もあるし、(3)脳の全部が死んでしまった全脳死もある。そして普通は(3)の全脳死だけを脳死という。心臓の働きはぜんぶ脳に依存しているわけではないため、脳が死んでも心臓は生きているという状況がでてくる余地がある。そしてこの状態のうちの内臓ならばとり出して病者に移植できることになる。
ここまでくれば全脳死が、ほんとうに〈死んだこと〉の疑問の余地のない証拠でありうるかどうかが、重大なことになる理由が、誰にでもはっきり判ってくる。少しでも不確定なまま、臓器を切りとって他人に移植すれば、生体を切りとったことになるからだ。この本の著者によれば、厚生省がしめした脳死の判定基準は、(1)深昏睡、(2)自発呼吸の消失、(3)瞳孔が固定し、瞳孔径が左右とも四ミリ以上になる、(3)対光反射その他の反射の消失、(5)平坦脳波、(6)上の条件が満されて六時間以上経過して変化がない。二次脳障害、六歳以上の小児では六時間以上観察する。そうなっている。
著者はこの判定基準がかえって疑問を拡大したものだとして、ひとつひとつ詳細に検討している。記述は迫力と説得力にあふれていて、あくことなく専門的な知識を吸収し、専門家に問いただし、たぶん普通の医老よりももっと綜合的な知識と判断力を発揮している。この個所の記述を読みながら、著者の膨大な資料の追跡と綜合力に舌をまく思いがした。
あるひとつの判定基準に叶うということは、その事柄をその判定領域の枠組みの内部におくことは確かだ。だが逆に、ある判定領域の内部にある事柄が、かならずその判定基準に叶うとはかぎらない。もし判定領域が実体集合であるばあいには、判定領域の枠組みの内部にありながら、基準に叶わない要素が、いくらでも存在しうることになる。著者が厚生省やそれ以前の日本脳波学会の、脳死の判定基準に、執ように喰いさがり、疑問を提出している根拠は、つづめていえばここにあるようにおもえる。この誰でもが陥りやすい錯誤にたいして、著者は実例をあげ、委曲をつくして、一見すると抜け穴のないようにみえる判定基準が、ほんとは多義的な含みとあいまいさをもっていて、一義的な確証性がないことを説きつくしている。著者がつかっている説得力のある比喩でいえば、宇宙人が人間とは何かという判定基準をつくろうとして、人間をつかまえてきて共通項として「二足歩行のできる翼のない動物」という判定の基準を作った。これは間違いではない。だがもし人間以外にも「二足歩行のできる翼のない動物」が一匹でもいたとすれば、この基準には抜け穴があることになる。ニュージーランドには、キウイという「二足歩行のできる翼のない動物」が少数だがいる。すると一見間違いではない判定基準が、不都合な抜け穴をもつばあいがありうることになる。
この本の著者は、ひとつひとつの基準項目について、現在の判定基準があいまいで、この基準に従ったために、まだ生存しているうちに臓器を切りとって、他人に移植してしまう可能性がありうることを論証している。
わたしが興味をもったことがいくつかある。ひとつは、著者が、瀕死を体験したものが、外からは完全に意識を失ったのちに、上方から横たわっている自分や、あわただしく蘇生の心臓マッサージや注射をしている医者や看護婦たちの姿がみえ、会話の声さえきこえていて、みんな承知していたと記述している例を、瀕死から蘇った者の体験手記を通していくつか挙げたうえで、これは意識が外からは失われたとみなされても、「内的意識」は残存しているばあいだと述べている個所だ。この状態がほんとうならじぶんの臓器が摘出されると、その「内的意識」はじぶんが臓器を切りとられるのを知っていて、ただ外に訴えられないだけだということになる。著者はそれはゆゆしいことだと述べていて、脳死判定にいだく疑問へのおおきな支えとしている。わたしも以前にこんな瀕死者の記述を集めてみたことがあった。わたしは、このばあい自己客体視をともなっているので、「内的意識」が残存するというよりも、減衰した意識の最終段階で実現する自己客体視の映像とみなしたが、著者のいうようにこの状態で臓器を摘出すれば、その像を瀕死者は「視」ながら、叫びも訴えも外側に伝えられずに死んでいくことになる。これはどうしても避けられるべきだという著者の主張は、疑いない根拠をもっている。
さらに著者は、わたしなどの考えも及ばなかった注目すべき事実を記述している。大脳が人間性の中枢だとすれば、脳幹は生命体維持の中枢であり、やがて脳幹をとりかえ、人間性だけを最後まで生かすという時代がくるかもしれないということだ。もうひとつは脳死後に、ADHのようなホルモンを投与することで、心臓だけを一年も二年も動かすことは可能であり、もっと極端なことをいえば、このように生かし続けられた人間の頭脳のない身体部位を、血液を採取する資源に使うという着想も可能だということだ。M・フーコーが『臨床医学の誕生』で記述したように、「死」は身体の部位でせめぎあう連続した領域と領域の分布占有の問題であり、点でもなければ過半数でもない。そして部分的な領域を「死」から守護するために、外から技術的な加工を身体内部に施すこともできる。この本を読みながら、わたしたちは身体の概念の変更を迫られているのだと、つくづく感じた。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする