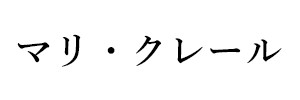書評
『トロツキー自伝〈1〉』(筑摩書房)
トロツキーの自伝は、ユングのそれとならんで、わたしが読んだ自伝では、ずばぬけていいものだ。自伝が文学作品として自己主張できるとして、このふたつからは第一級の文学作品からうけとるものと、まったくおなじ芸術的感銘をうける。ユングの自伝は、かれの神秘主義的な性向が、宗教的な迷信とすれすれに、もちこたえられながら、人間の共同無意識の偉大な探求者の魂をじゅうぶんにみせてくれる。トロツキーの自伝は、ロシアの民衆の自然に発生したツアーへの蜂起にであったひとりの知識人が、その渦のなかにあって考えぬき、出口をみつけようとして民衆と一緒にたたかう方法と思想をしだいに身につけてゆき、とうとう民衆の前衛に立って仲間たちと国家権力を獲得し、蜂起と反乱のあと始末をつけ、人類の歴史ではじめてのあたらしい国家権力の輪郭を、どうやらつくりかけたところで、仲間割れのあげくにはじき出されて、亡命してゆくまでの、波瀾と激動に富んだ生涯を、繊細な感受性と、大胆な行動力と、すぐれた理念と、一級の文学的表現とで、体験的に描ききっている。一個人の体験と理念が、そのまま人類の歴史的な激動と一致する場面にであったときの、はげしい現実のうごきと、はりつめた個人の精神の感受性とが、いってみれば、歴史のうえでただ一回きりといったおおきな規模とせつなさで描かれていて、歴史はこんな自伝をふたたび繰返し生むことはできまいと思わせるだけの貴重なドキュメントになっている。
どこからこの本の批評をはじめてもいいとして、これだけ偉大で純粋な知識人の魂の記録が、権力に抗して蜂起し、ためらい、揺動し、疲労し、また立ちあがるといった場面の間近で、顔の色や眼のしわがわかるような鮮やかな背景で描かれているのだから、はじめからはっきりした言葉で書評すべきだとおもう。政治的な行動にかられた知識人と知的な大衆とが、共同してつくる政治の僧院があるとすれば、この自伝は頭のさきから足のさきまでどっぷりその僧院につかり、僧院内の僧侶たちの指導者として振舞ったひとりの知識人の魂の行動が、おおきな枠組になっている。これははじめに強調しておいていいことだ。
政治的な僧院内の出来ごとも、僧侶たちの理念や行動のゆき違いも、ほんとうはそのまま民衆の運命をあらわしてはいないのだから、そう言っておかないと誤解を生じる。じじつこのトロツキーの自伝には、ごくふつうの民衆の魂をもった人物は二人くらいしかでてこない。ほんとうはそれほど特異な世界なのだ。その稀な人物のひとりはマルキンという内気で無愛想で、色の浅黒い純粋な水兵あがりだ。彼は何くれとなくトロツキーの家族の面倒をみたり、雑務を陰でうまく片づけてくれ、報いをもとめず働いてくれる。内戦がはじまると戦線の危険なところで、敗北の穴をふさぐように立働き、ひとびとに活力をあたえて転戦するが、とうとう両足をとばされ戦死する。かれはふだんからトロツキーの子供たちを対等にあつかってくれ、愛していた女性に背かれてこころに暗いかげをもつようになった過去のことなど、涙ながらにうちあけたりする。かれがたおれたときトロツキーは、「あたかも花崗岩の石杭が音をたてて崩れ落ちたように感じ」、トロツキーの二人の子供たちは、「この悲しい知らせが届いた夜の静けさのなかで」、掛けぶとんにくるまってふるえ、すすり泣く。じつはこの政治的な僧侶たちの多彩な活動や、理念や、方針のゆきちがいや、対立において、レーニンとともにいちばん非凡で偉大だったトロツキー自身の非凡で張りつめた行動を綴った自伝のなかで、水兵あがりのボルシェヴィキ、マルキンを叙述した個所は、トロツキーがいちばんふつうの人のふつうの感情に近づいた、ほとんど唯一の個所なのだ。そしてこの本のなかでたいへん感銘をあたえる個所のひとつだ。民衆の解放を理念とする政治的な僧院のなかの、非凡で偉大な僧侶たちと、偏頗で病的な僧侶たちの物語でありながら、肝腎の民衆はめったに顔を出さないのが、よくもわるくも、この本の特徴だということは、どうしてもいっておかなくてはならない。これは世界史的に重大な特徴であり、現在、ロシアの政治的な僧院が、興隆してきた民衆のまえに揺さぶられている理由と、はるかにつながっている。
この本に描かれているトロツキーの理念は、かれ自身の言葉をつかって、簡単に要約できる。かれはマルクスの理念を、無意識のうちに人類がつみかさねてきた歴史の過程を意識化した思想だというふうにうけとっている。そして歴史がいまの次に表現する過程が、圧迫された大衆が圧迫をはねのけるために支配者にむけた自然に発生した蜂起の行動だとすれば、歴史の無意識を意識化したマルクスの思想(トロツキーのうけとったマルクス主義)は、この大衆の蜂起と融合すべきものでなくてはならない。だれでも自分の力量より以上のことがひとりでにできてしまうインスピレーションの瞬間があるように、歴史もまた個人とおなじく無意識の総力をあげて意識化された歴史理念とむすびついて最高度のことを出現してしまう瞬間がある。それは「有機体の隠された諸力、その深い本能、祖先からうけついだ獣の如き直観」、それらがすべてたちあがり総合されて発揮されるときだ。それが七月の革命だった、とトロツキーは、述べている。彼の魅力の本流も、もちろんここにあるといっていい。いいかえれば、政治的共同体という僧院のなかの偉大な僧侶(革命家)という特殊な身分が、僧院外の一般社会の大衆の無意識の力能を手探りにさぐりあて、その力能のイメージを解放させ、政治制度を根抵から変えてしまおうとするところに本領があった。権力が獲得された直後、疲れきった顔のレーニンが、親密でぎこちないはにかみを浮べて、やさしくこの本の著者トロツキーに語りかけるところがある。官憲からの追及と地下活動のあと、いきなり権力を握って茫然としていたレーニンは「めまいがするね(esschwindelt)」というようにトロツキーにいう。そしてもし白衛軍がきみ(トロツキー)とぼく(レーニン)を殺したら、あとをスウェルドロフとブハーリンはうまくやって行けるだろうかと、問いかける。トロツキーは、たぶん奴らはわれわれを殺さないでしょうと答える。ここもまたこの自伝のなかで感動的なところだ。ちょうどユングの自伝で、フロイトとユングが、ふたりの眼のまえでおこる超常現象をめぐって交す会話の場面とおなじ気がする。一方は歴史の激動を眼のまえに体験している政治革命家どうしの会話なのに、一方は人間のこころの無意識の世界の、眼にみえない激動を体験している心理学者の会話だというちがいがあるだけで、偉大な巨匠たちの理念を語るエピソードだということにかわりない。
もうひとつトロツキーの自伝をつらぬく特色がある。それはトロツキーが、政治的僧院(ボルシェヴィキ)による権力の獲得を生涯の目的としながら、トロツキー個人はどんな権力につくことにもためらいがちで、積極的でなかったことだ。これはトロツキーの芸術家的な無垢の純粋さだったが、同時にスターリンのようにぬけめのない、こつこつとひとのこころと職務を侵蝕してものにしてゆく現実家にしてやられた理由でもある。権力を獲得したあとトロツキーは、外科医が手術をおわって、手を洗い、手術着を脱ぎ、一服するように、国家権力の外にとどまろう、何よりも休息したいと内心でかんがえる。レーニンはそれを聞き入れない。つまりここにはトロツキーの美しくもあり、また弱点でもある資質がある。この自伝の文体の端々までも滲透しているのは緊張して一瞬のたるみもない張りつめられた膜のようなトロツキーの行動と理念の世界だ。そしてその裏側には一級の芸術家だけがもっている隠棲したいという欲求と、権力や俗臭の匂う世界から遠ざかりたいという願望がいつもくっついていた。これはトロツキーの自伝をすぐれた文学作品にしている理由にもなっているが、レーニンとトロツキーの政治的僧院(党)が、やがてスターリンによって世界史的な視野を失い、民族の利益と感情を至上とするように変質していったとき、歴史的な民衆の原像と遠ざかり、民衆を抑圧し、僧院の特殊利益のために民衆を殺りくする集団にかわっていった根本的な原因をつくったといってよい。たとえばトロツキーの文体は、張りつめた純粋で無私な理念の響きを爽やかに伝えるが、肩に力がはいりすぎて無理をしている文体だ。スターリンの文体は、ぬけめのない用心ぶかくガードを固めた中学校の道徳の教師のような偽善者のくそ面白くもない文体だ。これにくらベレーニンの文体は論理と感性を分裂させないで強くしなやかな曲線を描いて走る明晰な文体だ。これは翻訳を介しても、わたしたちに伝わってくる特性だといえよう。スターリンの著作で、現在わたしたちが検討して、プラスの意味があるものは、一冊もない。レーニンの著書では『哲学ノート』、すこしおまけして『国家と革命』が検討に価するとおもう。トロツキーの著書では『文学と革命』と、この『自伝』、すこしおまけして『永続革命論』が検討に値する。現在、ロシアと東欧における民衆の蜂起は、もちろんトロツキーの著書をすべて解放するところまでゆくにちがいない。でも政治的な僧院の内部で、トロツキーの名誉回復がなされるかどうかに、そんなに意味などあるはずがない。その段階はすぎてしまった。いま先進社会の中軸にまでせりあがってきた大衆は、政治的な僧院の扉をひらき、隔壁をとりはらうことを要求して蜂起している段階なのだ。そこではレーニンやトロツキーのような偉大な僧侶の理念が、民衆の歴史的な無意識につめよられて、問われているのだ。
この本のなかで著者トロツキーのナイーヴで繊細で、やさしい情操とはうらはらに、恐怖を感じさせる側面があって、この自伝にちぐはぐな印象をあたえている。それは軍事指導者として「革命軍事会議長列車」に司令部をもうけて転戦してあるくトロツキーの姿だ。自伝のなかでかれはその体験をふまえて書いている。「軍隊は、上からの抑圧なくして編成することはできない。また統帥部が兵器庫に死刑の道具を持たずして、人民大衆を死の途につかせることはできない。おのれの技術的成果を誇る、邪悪な、尻尾のない猿同然の、人間という名の動物が、軍隊を組織し、戦争を行なうかぎり、統帥部は、前線での死の可能性と後方での死の不可避性との間に兵士を立たせざるをえないであろう。だが、だからといって軍隊は、恐怖にそって創設することはできない」。これははっきりとしたトロツキーの言明だ。この個所はなぜかわたしには金切声をあげたような、嫌な、乾いた印象をあたえる。かれのこの考えはふえんすれば政治的僧院(党)は上からの抑圧と死刑の武器がなくては民衆の前衛部をつくり、民衆を死におもむかせることができないといっていることを意味する。いいかえればレーニンやトロツキーの考えがスターリンと等価なところにおちこんでゆく経験的な価値観が語られているといっていい。この記述はいたるところでトロツキーの自伝にちぐはぐな分裂した印象を与えずにはおかないものだ。つまり革命家というものは革命を遂行することを第一義とする主観的な知識を指すので、民衆をすべての意味で解放することを第一義とする普遍的知識をいうのではないことを、あらためて実感させるといっていい。トロツキーはじぶんでいっているようにたんなる革命家なのだ。
あるひとりの個人が、ひとつの歴史的な事態にたまたま生涯を偶然に遭遇させ、なみはずれておおきな歴史の揺さぶりをうけて、なみはずれておおきく特異な資質をつくりあげた。それは歴史の工房が一時期に造りあげた偉大な、そして特異な作品なので、鑑賞するほかにわたしたちがやることは何もない。いま現在このとき、歴史は個々の民衆の偶然の総和としてしか歴史の偶然を造らなくなっている。そんなところでは、個々の民衆の必然の総和としてしか歴史の必然を造らなくなっていることを意味する。いまロシアと東欧で民衆が政治的な僧院を揺さぶっているのはそのことを意味しているのだ。
【この書評が収録されている書籍】
どこからこの本の批評をはじめてもいいとして、これだけ偉大で純粋な知識人の魂の記録が、権力に抗して蜂起し、ためらい、揺動し、疲労し、また立ちあがるといった場面の間近で、顔の色や眼のしわがわかるような鮮やかな背景で描かれているのだから、はじめからはっきりした言葉で書評すべきだとおもう。政治的な行動にかられた知識人と知的な大衆とが、共同してつくる政治の僧院があるとすれば、この自伝は頭のさきから足のさきまでどっぷりその僧院につかり、僧院内の僧侶たちの指導者として振舞ったひとりの知識人の魂の行動が、おおきな枠組になっている。これははじめに強調しておいていいことだ。
政治的な僧院内の出来ごとも、僧侶たちの理念や行動のゆき違いも、ほんとうはそのまま民衆の運命をあらわしてはいないのだから、そう言っておかないと誤解を生じる。じじつこのトロツキーの自伝には、ごくふつうの民衆の魂をもった人物は二人くらいしかでてこない。ほんとうはそれほど特異な世界なのだ。その稀な人物のひとりはマルキンという内気で無愛想で、色の浅黒い純粋な水兵あがりだ。彼は何くれとなくトロツキーの家族の面倒をみたり、雑務を陰でうまく片づけてくれ、報いをもとめず働いてくれる。内戦がはじまると戦線の危険なところで、敗北の穴をふさぐように立働き、ひとびとに活力をあたえて転戦するが、とうとう両足をとばされ戦死する。かれはふだんからトロツキーの子供たちを対等にあつかってくれ、愛していた女性に背かれてこころに暗いかげをもつようになった過去のことなど、涙ながらにうちあけたりする。かれがたおれたときトロツキーは、「あたかも花崗岩の石杭が音をたてて崩れ落ちたように感じ」、トロツキーの二人の子供たちは、「この悲しい知らせが届いた夜の静けさのなかで」、掛けぶとんにくるまってふるえ、すすり泣く。じつはこの政治的な僧侶たちの多彩な活動や、理念や、方針のゆきちがいや、対立において、レーニンとともにいちばん非凡で偉大だったトロツキー自身の非凡で張りつめた行動を綴った自伝のなかで、水兵あがりのボルシェヴィキ、マルキンを叙述した個所は、トロツキーがいちばんふつうの人のふつうの感情に近づいた、ほとんど唯一の個所なのだ。そしてこの本のなかでたいへん感銘をあたえる個所のひとつだ。民衆の解放を理念とする政治的な僧院のなかの、非凡で偉大な僧侶たちと、偏頗で病的な僧侶たちの物語でありながら、肝腎の民衆はめったに顔を出さないのが、よくもわるくも、この本の特徴だということは、どうしてもいっておかなくてはならない。これは世界史的に重大な特徴であり、現在、ロシアの政治的な僧院が、興隆してきた民衆のまえに揺さぶられている理由と、はるかにつながっている。
この本に描かれているトロツキーの理念は、かれ自身の言葉をつかって、簡単に要約できる。かれはマルクスの理念を、無意識のうちに人類がつみかさねてきた歴史の過程を意識化した思想だというふうにうけとっている。そして歴史がいまの次に表現する過程が、圧迫された大衆が圧迫をはねのけるために支配者にむけた自然に発生した蜂起の行動だとすれば、歴史の無意識を意識化したマルクスの思想(トロツキーのうけとったマルクス主義)は、この大衆の蜂起と融合すべきものでなくてはならない。だれでも自分の力量より以上のことがひとりでにできてしまうインスピレーションの瞬間があるように、歴史もまた個人とおなじく無意識の総力をあげて意識化された歴史理念とむすびついて最高度のことを出現してしまう瞬間がある。それは「有機体の隠された諸力、その深い本能、祖先からうけついだ獣の如き直観」、それらがすべてたちあがり総合されて発揮されるときだ。それが七月の革命だった、とトロツキーは、述べている。彼の魅力の本流も、もちろんここにあるといっていい。いいかえれば、政治的共同体という僧院のなかの偉大な僧侶(革命家)という特殊な身分が、僧院外の一般社会の大衆の無意識の力能を手探りにさぐりあて、その力能のイメージを解放させ、政治制度を根抵から変えてしまおうとするところに本領があった。権力が獲得された直後、疲れきった顔のレーニンが、親密でぎこちないはにかみを浮べて、やさしくこの本の著者トロツキーに語りかけるところがある。官憲からの追及と地下活動のあと、いきなり権力を握って茫然としていたレーニンは「めまいがするね(esschwindelt)」というようにトロツキーにいう。そしてもし白衛軍がきみ(トロツキー)とぼく(レーニン)を殺したら、あとをスウェルドロフとブハーリンはうまくやって行けるだろうかと、問いかける。トロツキーは、たぶん奴らはわれわれを殺さないでしょうと答える。ここもまたこの自伝のなかで感動的なところだ。ちょうどユングの自伝で、フロイトとユングが、ふたりの眼のまえでおこる超常現象をめぐって交す会話の場面とおなじ気がする。一方は歴史の激動を眼のまえに体験している政治革命家どうしの会話なのに、一方は人間のこころの無意識の世界の、眼にみえない激動を体験している心理学者の会話だというちがいがあるだけで、偉大な巨匠たちの理念を語るエピソードだということにかわりない。
もうひとつトロツキーの自伝をつらぬく特色がある。それはトロツキーが、政治的僧院(ボルシェヴィキ)による権力の獲得を生涯の目的としながら、トロツキー個人はどんな権力につくことにもためらいがちで、積極的でなかったことだ。これはトロツキーの芸術家的な無垢の純粋さだったが、同時にスターリンのようにぬけめのない、こつこつとひとのこころと職務を侵蝕してものにしてゆく現実家にしてやられた理由でもある。権力を獲得したあとトロツキーは、外科医が手術をおわって、手を洗い、手術着を脱ぎ、一服するように、国家権力の外にとどまろう、何よりも休息したいと内心でかんがえる。レーニンはそれを聞き入れない。つまりここにはトロツキーの美しくもあり、また弱点でもある資質がある。この自伝の文体の端々までも滲透しているのは緊張して一瞬のたるみもない張りつめられた膜のようなトロツキーの行動と理念の世界だ。そしてその裏側には一級の芸術家だけがもっている隠棲したいという欲求と、権力や俗臭の匂う世界から遠ざかりたいという願望がいつもくっついていた。これはトロツキーの自伝をすぐれた文学作品にしている理由にもなっているが、レーニンとトロツキーの政治的僧院(党)が、やがてスターリンによって世界史的な視野を失い、民族の利益と感情を至上とするように変質していったとき、歴史的な民衆の原像と遠ざかり、民衆を抑圧し、僧院の特殊利益のために民衆を殺りくする集団にかわっていった根本的な原因をつくったといってよい。たとえばトロツキーの文体は、張りつめた純粋で無私な理念の響きを爽やかに伝えるが、肩に力がはいりすぎて無理をしている文体だ。スターリンの文体は、ぬけめのない用心ぶかくガードを固めた中学校の道徳の教師のような偽善者のくそ面白くもない文体だ。これにくらベレーニンの文体は論理と感性を分裂させないで強くしなやかな曲線を描いて走る明晰な文体だ。これは翻訳を介しても、わたしたちに伝わってくる特性だといえよう。スターリンの著作で、現在わたしたちが検討して、プラスの意味があるものは、一冊もない。レーニンの著書では『哲学ノート』、すこしおまけして『国家と革命』が検討に価するとおもう。トロツキーの著書では『文学と革命』と、この『自伝』、すこしおまけして『永続革命論』が検討に値する。現在、ロシアと東欧における民衆の蜂起は、もちろんトロツキーの著書をすべて解放するところまでゆくにちがいない。でも政治的な僧院の内部で、トロツキーの名誉回復がなされるかどうかに、そんなに意味などあるはずがない。その段階はすぎてしまった。いま先進社会の中軸にまでせりあがってきた大衆は、政治的な僧院の扉をひらき、隔壁をとりはらうことを要求して蜂起している段階なのだ。そこではレーニンやトロツキーのような偉大な僧侶の理念が、民衆の歴史的な無意識につめよられて、問われているのだ。
この本のなかで著者トロツキーのナイーヴで繊細で、やさしい情操とはうらはらに、恐怖を感じさせる側面があって、この自伝にちぐはぐな印象をあたえている。それは軍事指導者として「革命軍事会議長列車」に司令部をもうけて転戦してあるくトロツキーの姿だ。自伝のなかでかれはその体験をふまえて書いている。「軍隊は、上からの抑圧なくして編成することはできない。また統帥部が兵器庫に死刑の道具を持たずして、人民大衆を死の途につかせることはできない。おのれの技術的成果を誇る、邪悪な、尻尾のない猿同然の、人間という名の動物が、軍隊を組織し、戦争を行なうかぎり、統帥部は、前線での死の可能性と後方での死の不可避性との間に兵士を立たせざるをえないであろう。だが、だからといって軍隊は、恐怖にそって創設することはできない」。これははっきりとしたトロツキーの言明だ。この個所はなぜかわたしには金切声をあげたような、嫌な、乾いた印象をあたえる。かれのこの考えはふえんすれば政治的僧院(党)は上からの抑圧と死刑の武器がなくては民衆の前衛部をつくり、民衆を死におもむかせることができないといっていることを意味する。いいかえればレーニンやトロツキーの考えがスターリンと等価なところにおちこんでゆく経験的な価値観が語られているといっていい。この記述はいたるところでトロツキーの自伝にちぐはぐな分裂した印象を与えずにはおかないものだ。つまり革命家というものは革命を遂行することを第一義とする主観的な知識を指すので、民衆をすべての意味で解放することを第一義とする普遍的知識をいうのではないことを、あらためて実感させるといっていい。トロツキーはじぶんでいっているようにたんなる革命家なのだ。
あるひとりの個人が、ひとつの歴史的な事態にたまたま生涯を偶然に遭遇させ、なみはずれておおきな歴史の揺さぶりをうけて、なみはずれておおきく特異な資質をつくりあげた。それは歴史の工房が一時期に造りあげた偉大な、そして特異な作品なので、鑑賞するほかにわたしたちがやることは何もない。いま現在このとき、歴史は個々の民衆の偶然の総和としてしか歴史の偶然を造らなくなっている。そんなところでは、個々の民衆の必然の総和としてしか歴史の必然を造らなくなっていることを意味する。いまロシアと東欧で民衆が政治的な僧院を揺さぶっているのはそのことを意味しているのだ。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする