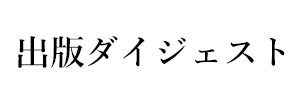コラム
『本朝文粋』(岩波書店)、『雨夜のともし火』(勉誠出版)、『五雑俎』(明徳出版社)、『日本書紀』(岩波書店)
一葉は何を読んだか
林芙美子の『放浪記』を何度となく読み返している。作家として有名になってからの芙美子は、もちろん小説はうまいが、人に対していじわるで、あまり共感できない。でも『放浪記』(ことに「女人芸術」に初出のもの)と、あのころの正直な詩はいつも私の生活を励ます。のちに作家になる少女は本が読みたくてたまらない。芙美子は太物の行商人である養父にくっついて旅をして歩いた。三銭小遣いをもらい、双児美人の豆本と水饅頭を買った。小学校に通うかわりに粟おこしの工場に日給二十三銭で通い、それで夜は近所の貸本屋から、「腕の喜三郎や横紙破りの福島正則、不如帰、なさぬ仲、渦巻」などという小説本を借りて読んだ。このように書名すらはっきりしないが、ともかく彼女はそう書いている。せちがらい金の話ばかりにとり囲まれていた芙美子にとって、ヒロイズムとセンチメンタリズムの世界は現実を忘れさせてくれた。小説はここでたしかに本来の効用を発揮している。
汚ない宿屋の大部屋のような所で、腹ばいになって貸し本を読む林芙美子の姿が目に浮ぶ。私も学校に行かなくてすんで、ひがな一日寝ころんで本を読めたらどんなにいいかと夢想した。授業中も家に帰って読む本のことばかり考えていたのだから、何のために学校に行ったかわからない。学校では週に一度の図書館の時間というのがあって、それが一番の楽しみだった。
先日、『清水紫琴全集』というのを用があって読み直した。この人は自由民権家と交際して初期の女性ジャーナリストとなり、「女学雑誌」の主筆をつとめ、作家としても活躍したが、のちに東大総長となる古在由直と結婚、筆を折った人である。古在は妨害にも屈せず足尾鉱毒事件の調査を行い、妻の過去の結婚や恋愛にもこだわらなかった人だったが、妻が作家活動することだけは許さなかった。そのことについてのみ、両親にいさかいがあった、と次男の古在由重氏は書いている。
「しかしそれでも母は、その老年まで読書をおこたらなかった。毎日の家事をすませた深夜の二時間を、「いまだけは自由なとき」といって書物をよんでいた。晩年には中条百合子の『貧しき人々の群』や佐多稲子の『キャラメル工場から』をよみ、ようやく女性の手によって小説らしい小説がまたでてきそうだと心をはずませていた」
女性の読書は、なにも当時に限ったことではないが、やむを得ず深夜になる。私も子どもが生れたころ、三時間おきの授乳の合間に本を読んでいた。
明治に入って最初に、筆で一家を養った樋口一葉の読書は、主に上野の図書館に頼っていた。
明治二十年代にはいまほど出版点数も、一冊あたりの部数も少なく、しかも父を失い零落した一葉の家で本などそう買えるはずはなかった。日記ではよく新聞記事を引いて、世の動きに敏感なことがうかがわれるが、どうも樋口家では新聞を借りて読んでいたらしい。
上野の図書館が日記に初めて出てくるのは、明治二十四年六月十日「若葉かげ」。中島歌子の歌塾萩の舎に一葉は入門していたが、その相弟子の田中みの子と約束して行き、夕方六時まで書見をしている。正式には東京図書館といい、いまの東京芸術大学の構内にあったらしい。閲覧は有料で一回二銭、一回に和本は七種十冊、洋書は三種三冊まで借り出すことができた。
ここの特徴は婦人室があったことで、東陽堂刊の「風俗画報」にもその絵が載っている。男女七歳にして席を同じうせずの時代に、女性だけで落ちついて本を読めるのは一葉にとって天国だったろう。この月十九日、二十三日にも行っている。弁当を持ってゆくこともあった。
図書館について一番くわしく書かれているのはこの年八月八日である。朝のうち、一葉は腸カタルで臥せる師中島歌子を見舞う。本郷の菊坂下から小石川安藤坂までは徒歩二十分くらいだろうか。容体は大したことなく、出来上った浴衣を届けたところ、また次の綿入れを頼まれる。
とにかく明治の人は早朝から動く。朝九時には帰宅して、今度は徒歩で東京図書館へ出かけるのである。図書館は夏は八時半、秋は九時から開いたが、それより早く一葉は着いて、まだ開かないので谷中墓地の知人の墓に参ったり、根岸辺を散歩した日もある。
菊坂を上り、本郷の通りから東京大学をぬけて池の端へ出る。ちょうど夏の盛りで蓮の花が満開で、清い香を放っている。池をめぐって東照宮の石段をのぼると木陰がすずしい。
一葉はよく歩く。といってもまだバス、地下鉄はおろか、市電も通っていない時代なので歩くほかはない。図書館はいつ来ても男性は多いのに女は一人もいない。身の縮む思いである。閲覧室は別でも出納所は一つなので、目録で本を請求するとき、番号が違う、書き直しをなどといわれると、それだけで顔がほてるようだ、と書いている。
本を借りてさえしまえば、代言人試験が近づいて混む男子室を尻目に、階上の婦人席はすいていて天国。これはうらやましい。私のいた大学でも司法試験の学生に図書館は占領され、学部は男四十対女一の学生数で、どこも男くさくて女性用の閲覧室があればいい、と思った。女子学生専用のトイレすらなかったのである。
夏の陽は長いといっても夕暮になりひぐらしが鳴き、一葉がギリギリまでねばって、閉館のすずの音に驚いて出るともう人気がない。明治のさびしい上野の森を、どうやって一人で抜けたのだろう。からすが群れてねぐらに帰る、それと連れだって本郷へ向う。母たきが今日は早く帰りなさいよ、昨日も夜更かししたのだから、といったのにこんなに遅れて、とつい足早になる。
根津で土産に皮の色鮮やかな新芋を買い、本郷の空橋(からはし)辺では書生の群にからかわれて腹を立てる。家に帰ると妹の邦子が夕飯の仕度をしながら、「暑かったでしょ、疲れたでしょ、着物ぬいで、お湯も湧いているわよ」とやさしい言葉をかけてくれ、一葉はようやくホッとした。
本一つ読むのに、明治の女はどれほど苦労したか、粛然とする。
東京図書館で一葉が何を借りて読んだかにも興味がある。ちょっと挙げてみよう。
『本朝文粋』『雨夜のともし火』『五雑俎』『日本書紀』『花月草紙』『月次消息』『太平記』『大和物語』『大山夜譚』「哲学会雑誌」大田南畝・藤井懶斎の随筆、『御伽草子』……ずい分、難かしい本を読んでいる。その後に出版され、一葉が目にしなかった何千の書物をたしかに私は見ているが、古典の基礎教養に関するかぎり、二十四歳で亡くなった彼女にかなわない。
もっとも一葉も漢文の『五雑俎』などは読み切れずに断念して返している。馬琴の小説によく出る書名なので興味を引かれて借りてみたまでのこと。『日本書紀』の神代の巻がむずかしくて居眠りもしたそうだ。とはいえ、一葉が読んだのはほとんど江戸時代の木版本らしい。
『太平記』などは小説『埋れ木』の中につかう陶器のことを調べるために読んでいるし、「図書館にたねさがしにいく」とも書いている。いくら想像力創作力の旺盛な作家でも無からは有を生ぜられはしない。私小説を書くには若すぎたかもしれない。一葉その人の体験は貧しいものである。一葉の作品は、こうした図書館での読書と、身近な人々の物語の双方からインスピレーションを得てできあがった。
婦人席にたまに人がいると、一葉はうれしく懐しく思っただろう。下谷区谷中町三番地に住む、田中みの子とは待ち合せ、先に来ているのが脱ぎ捨てられた草履の模様でわかると、うれしくなって一緒に下駄箱にしまったりしている。また越後長岡出身で夫は洋画家、自分は神学に興味があるが学校へ行けなかった、という人と図書館で出会って、身の上話を一葉は聞き、その池の端の家まで同行したりしている。明治女学校の生徒、産婆の学生、駒場農学校の某氏の妻で刀剣の図の模写に来た人など、図書館で遭遇した人を日記に書きとめているが、明治のそのころ、どんな女性たちが図書館を利用したかが分かってじつに面白い。
明治二十六年になると、一葉は筆一本で立つことは無理と知り、下谷区竜泉寺町で小間物屋を始めるが、これは本郷から上野の山の反対側へ来たわけで、依然、図書館通いを続けていたようである。
もちろん、一葉の読書は図書館だけではない。日記には細々と友人から借りた本のことが書きとめられている。
たとえば明治二十四年八月一日の日記には、前嶋きく子から饗庭篁村の『むら竹』や黒岩涙香のものなど小説本を十二冊借り、三時すぎから十時まで本にとりついて十冊ばかり読んだと書いている。速読である。
この日記の最後には『栄花物語』を田中みの子へ、『平家物語』を野々宮菊子へ、『源氏物語』を中嶋倉子へ貸した、という心覚えがあるから、これらは持っていたのだろう。一方『日本外史』を関場君より、『足利北条』を吉田君より、『楽雅記』『夢』を半井君より、『新約全書』「女学雑誌」を野々宮君よりなどのメモがある。これらは一葉が借りたのである。
この東京図書館はのちに帝国図書館となり、明治四十年ころ、帝冠様式の壮麗な建築になった。もっとも日露戦争の戦費がかさんで図書館の建築費が削られ、一部しか出来なかったともいわれる。現在、国会図書館上野分館として用いられているが、利用者が少なく、近く日本の児童書専門センターとする計画があるらしい。(ALL REVIEWS事務局注:本書評執筆時期は1995年頃)。私にはそれがいいことかどうか判断できない。児童書の研究者や作家は利用するかもしれないが、上野の山の奥という場所柄、どうも子どもたちがひんぱんに使うようになるとは思えないからである。
【このコラムが収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする
初出メディア