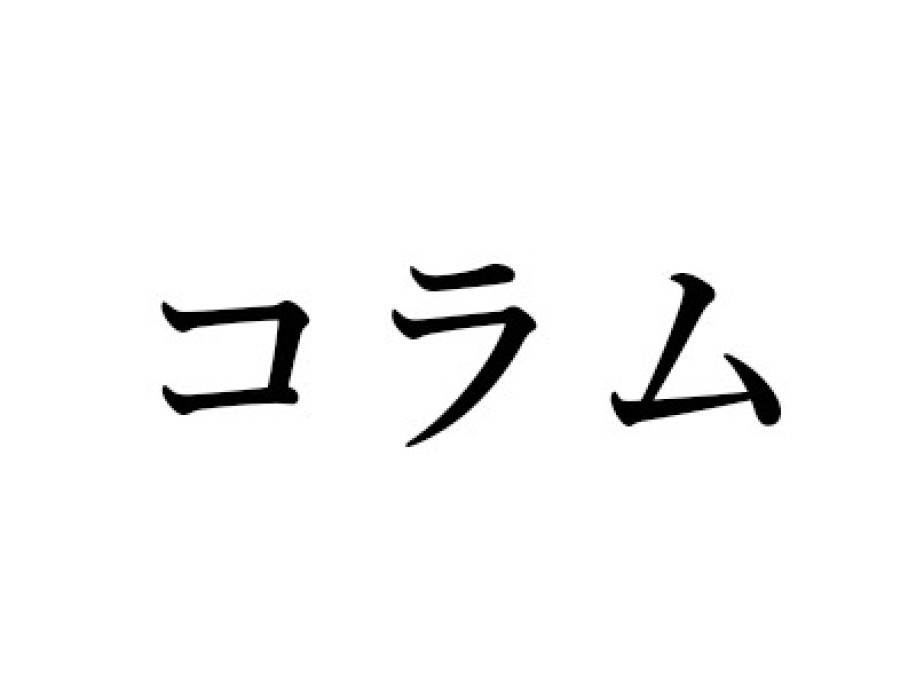書評
『史書を読む』(吉川弘文館)
立ち帰るべき場所
本書が最初に刊行されたのは、1981年だが、今、読んでも古びないのだ。この間、研究は日進月歩であったにも拘らずである。やはり、大家の書なのだ。自分で考えて、確実なことだけを、言葉を選んで記述する。あたりまえのことだが、ついつい時流に乗ってしまうと、1年後に読んでも、古くなっていることがある。例えば、こんなくだりがある。戦後古代史学の大きな成果の一つに、大化改新の詔(みことのり)は、ほとんど大宝令の文章を転載しているから、大化当時の文ではないとし、詔の存在を否定する論がある。本書はそこを、「しかし、必ずしもすべてがそうだとも言い切れない所がある。畿内の四至の規定などは、大宝令文には全くない。大化の時のものとしか考えるほかはない」とさらりと述べる。確かに、大宝令から転載したところはある。しかし、大宝令にないところは、どう考えるのか?畿内の四つの境を定めた規定などは、まずは大化改新の詔と見ておくべきではないのか。史学・文学を含めた日本学を志す学徒が、立ち帰るべき場所が示されている。
[書き手] 上野 誠(うえの まこと・万葉学者 奈良大学教授)
ALL REVIEWSをフォローする