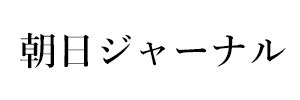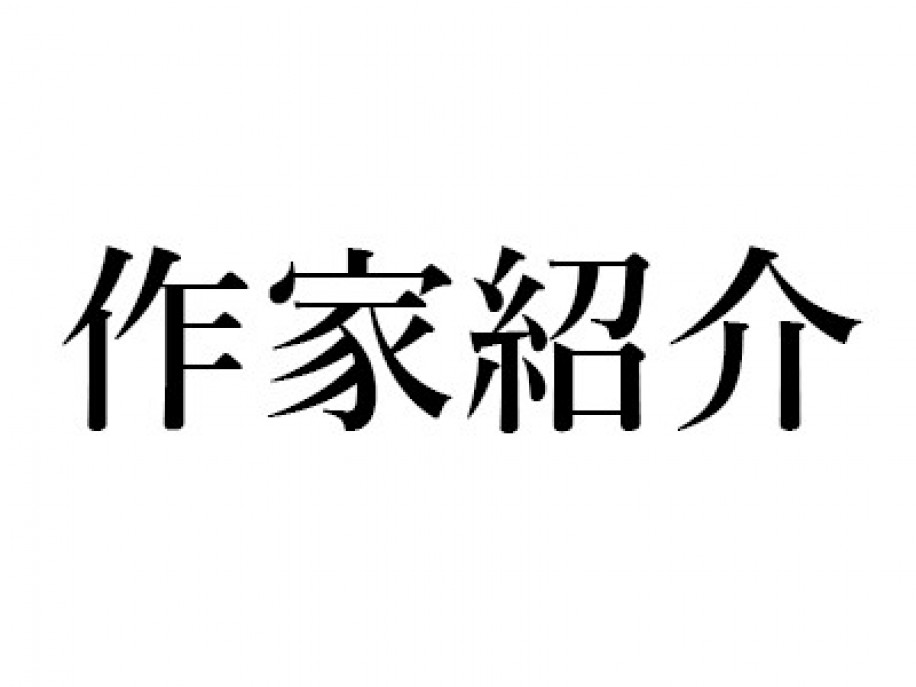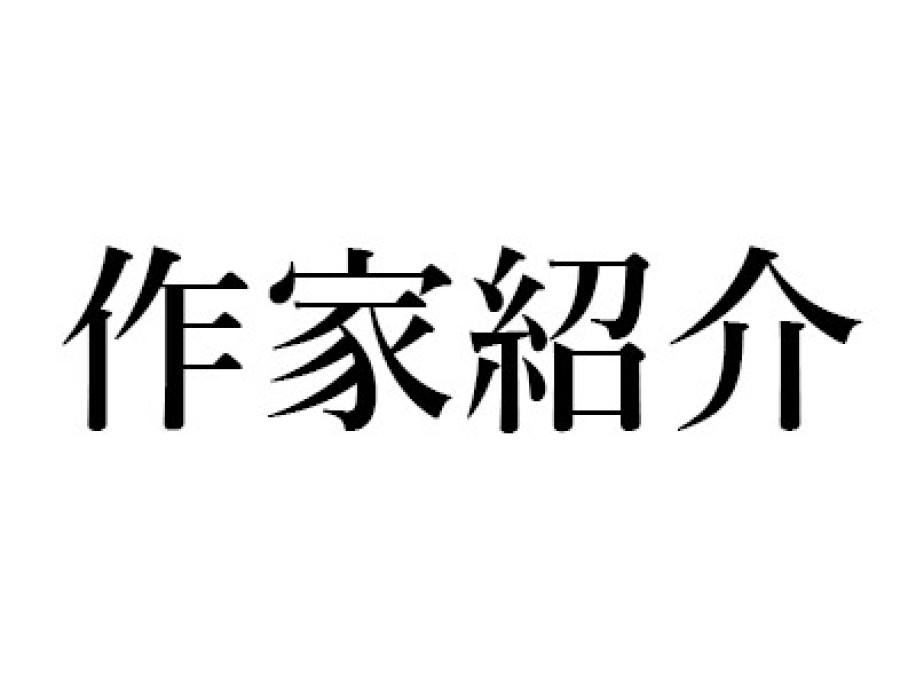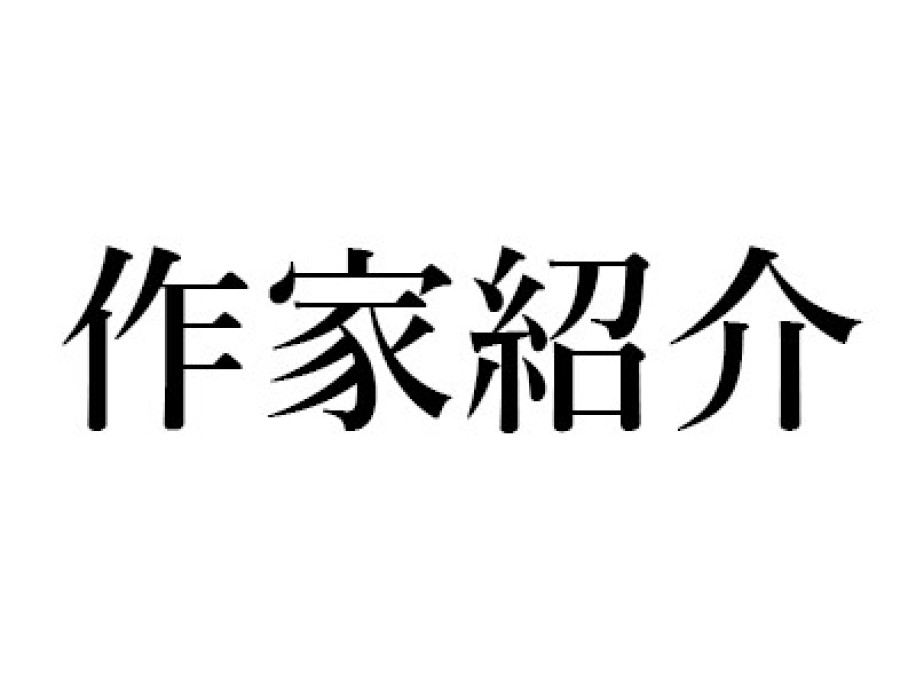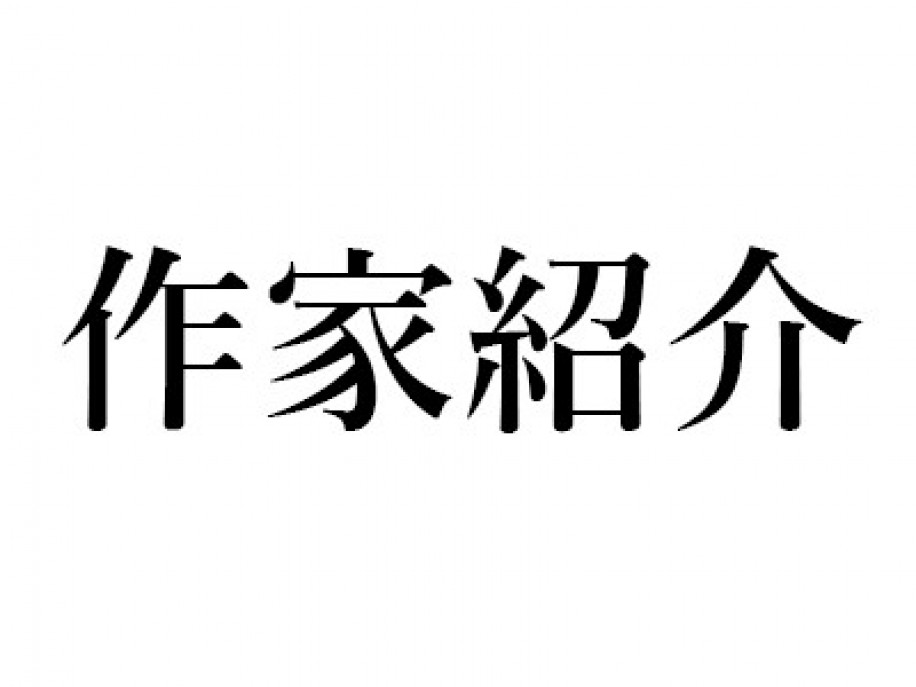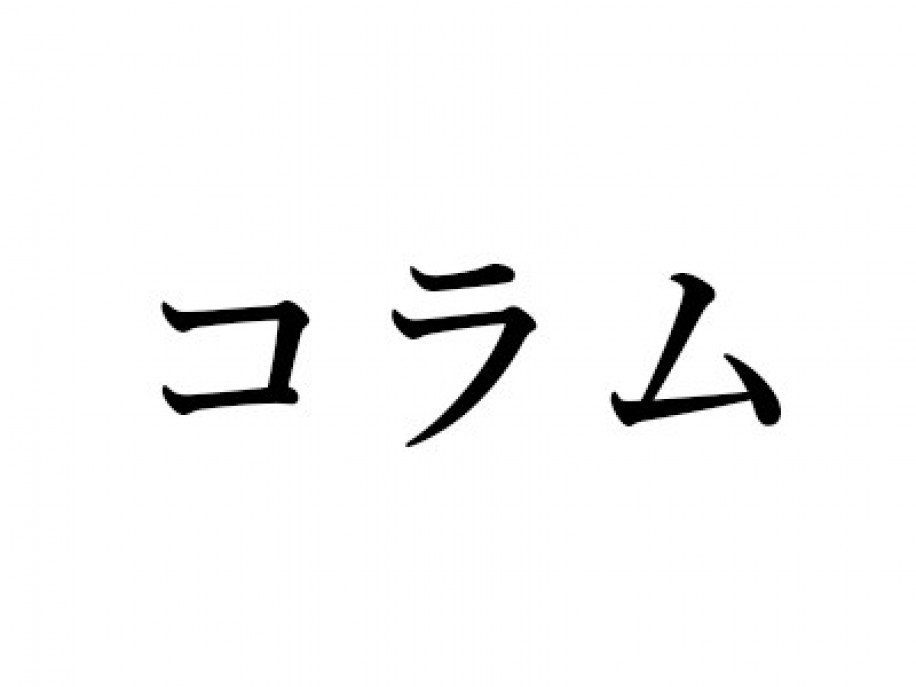作家論/作家紹介
マヌエル・プイグ『ブエノスアイレス事件』(白水社)、『天使の恥部』(白水社)、『この書を読む者に永遠の呪いあれ』(現代企画室)
永遠の謎を残して逝った――。マヌエル・プイグのアルゼンチン的な客死。
マヌエル・プイグが七月二十二日、メキシコで急逝した。サン・マルティン、ガルデル、コルタサル、ボルヘスを先例とするアルゼンチン的な死、すなわち客死を遂げたのが印象的だ(ALLREVIEWS事務局注:本書評執筆時期は1990年)。一九七三年、『ブエノスアイレス事件』によってブラックリストに載った彼は亡命の道を選び、以後二度と祖国の土を踏むことはなかった。スペインの亡命作家が祖国のことしか考えないのと違って、アルゼンチンの作家は亡命を新たな現実として巧みに受け入れることができる。根無し草性が身についているのだろう。もちろんこれは極論だが、客死の歴史を見ると、そう思わざるをえない。
ことにプイグの場合、『天使の恥部』や『この書を読む者に永遠の呪いあれ』がそうだが、亡命者を登場させる作品を書くことで、亡命をプラスに転化してしまうのだ。この才能はおそらくラテンアメリカ作家の中でも類まれといえるだろう。
メキシコに長く住むガルシア=マルケスはメキシコを舞台にした作品を書かない。十七年間のヨーロッパ体験があり、一年の半分をロンドンで暮らすバルガス=リョサが書くのは常にラテンアメリ力の現実である。だったらドノソがスペイン体験を作品にしているし、アレナスがニューヨークを舞台にした小説を最近書いたではないかと言われるかもしれない。確かにそうなのだが、プイグの小説はちょっと違う。
彼は亡命者のノスタルジーやアイデンティティ・クライシスなどには関心を示さないし、ラテンアメリカの命運などという壮大なテーマに取り組むわけでもない。彼の興味はもっぱら、きわめて個人的なテーマに限られるのだ。
おそらくここに、肉体的にはタフとはいえない彼が、亡命と創作を両立できた秘密がある。つまり、彼は自分のテーマを体現している人物を亡命先で見つけ出し、その人物をモデルに作品を書くことができるのだ。ただし、スペイン語、英語、ポルトガル語など、彼が理解できる言葉を話す人物でなければならないことはいうまでもない。なぜなら、作中の会話はリアルでなければならない。
プイグの作品のテーマは様々だ。性という謎、中産階級の偽善的モラル、マチスモ(男性優越主義)、サディズムとマゾヒズム……。しかし、作品を注意深く読めば、それらに通底するテーマが見えてくる。
月並みな言い方をすればコミュニケーションの問題、男女に限らず人間同士がなぜ対等な関係を持てないのかということである。来日時のインタビューによれば、このテーマは子供時代の経験に由来するようだ。言い換えれば、彼の作品は同じテーマのバリエーションなのである。
その意味で、彼がふたたび一九四〇年代の故郷を舞台にした小説を構想していたという事実は興味深い。それを単なるノスタルジックな回帰と解釈するのはおそらく誤りだ。
時期はともかく彼がメキシコで一生を終えるつもりでいたことは、自身の言葉によって明らかにされている。そうではなく、創作の原点へ帰ろうとしていたにちがいないのである。ノスタルジーなら初期の二作にすでにこめられている。彼は多分、個人的なテーマを託せる人物を過去の中に、見出したのだ。だが、繰り返しになるが、早過ぎた死によって、それは永遠の謎となってしまった。
ALL REVIEWSをフォローする
初出メディア