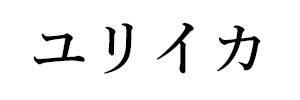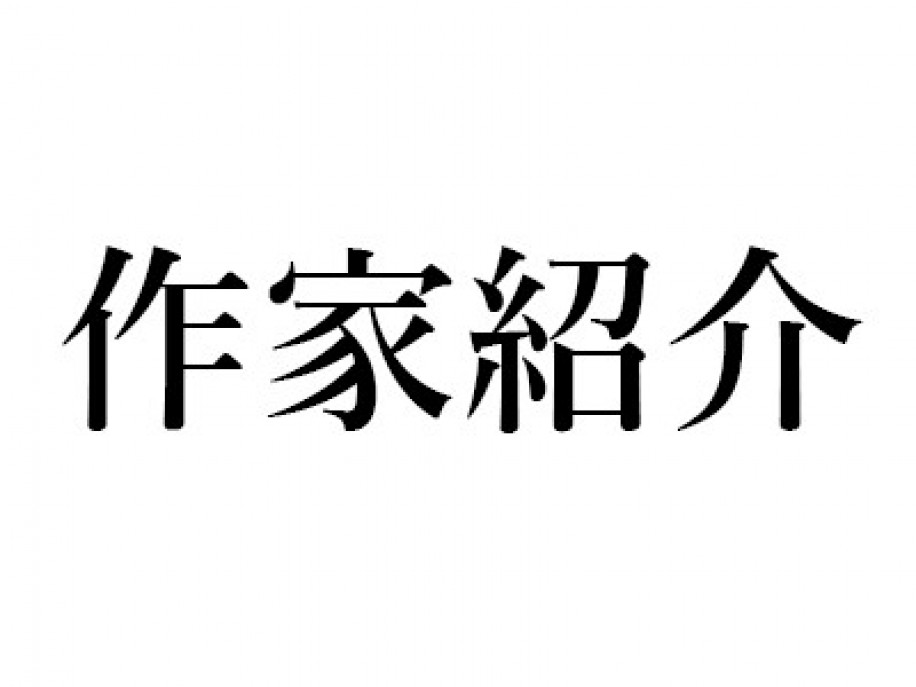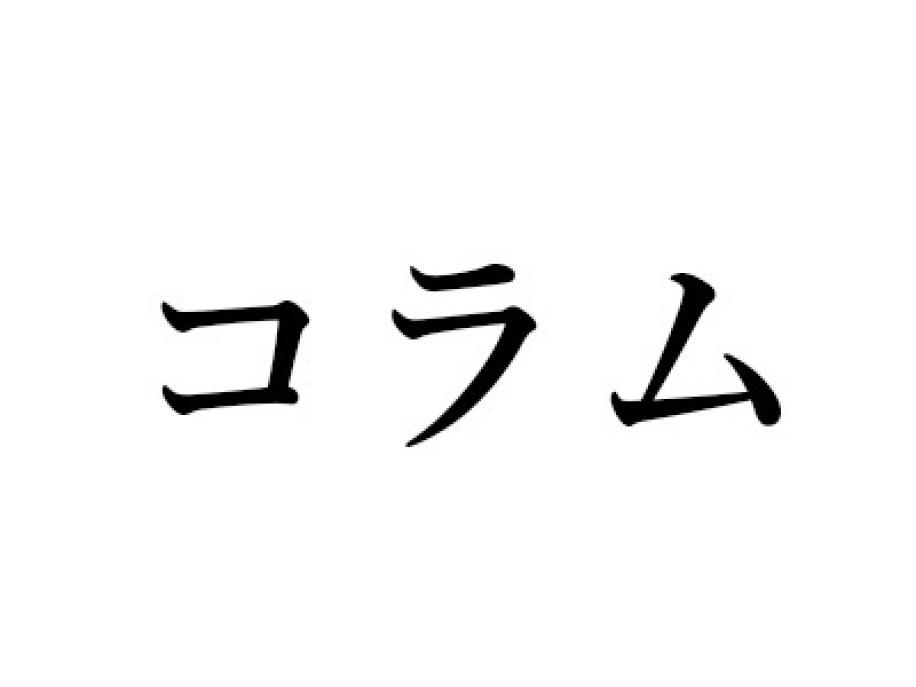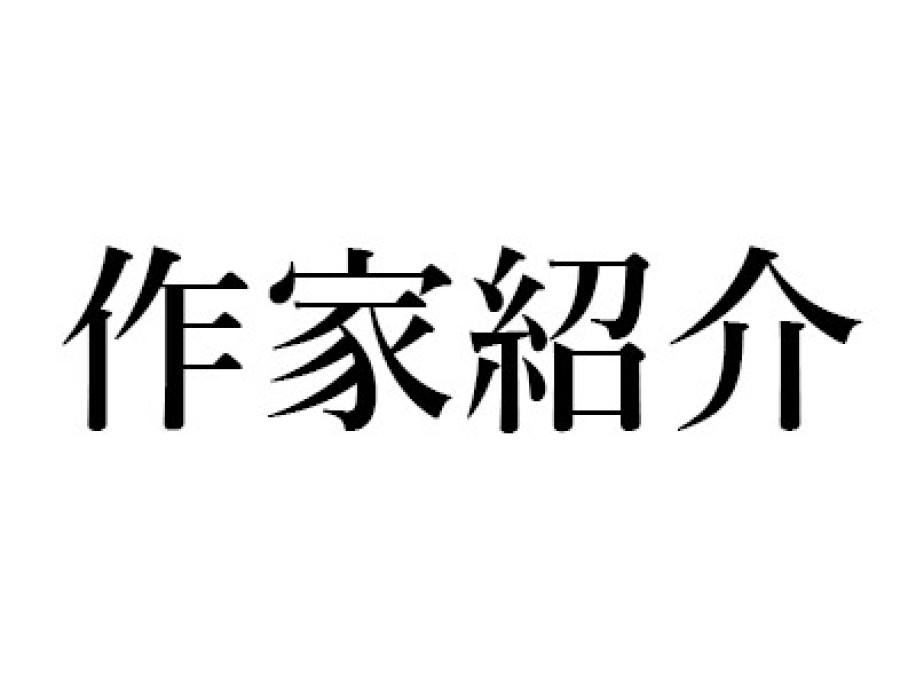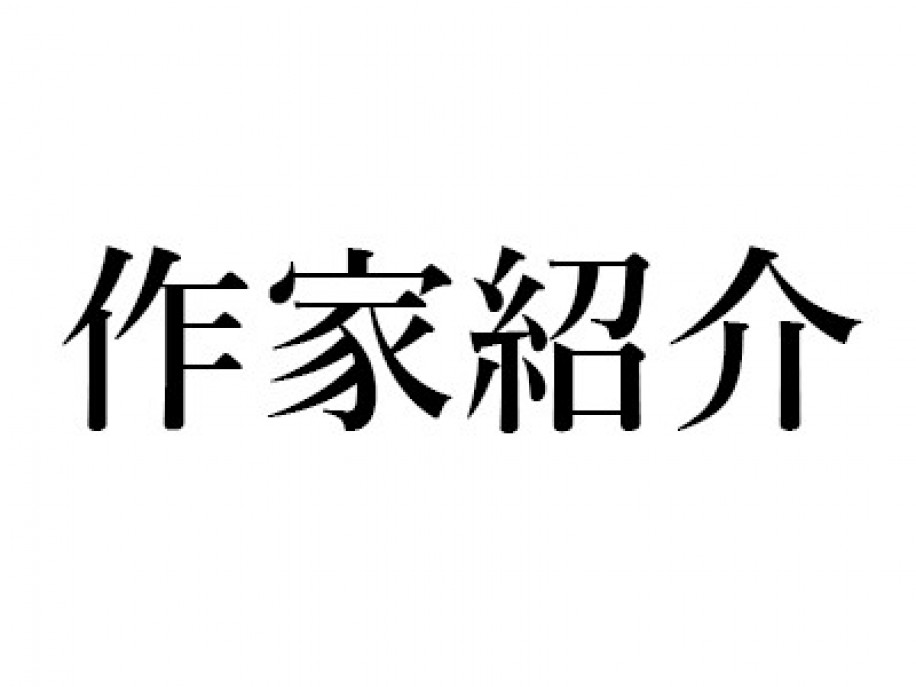作家論/作家紹介
G.ガルシア=マルケス,P.A.メンドーサ『グアバの香り』(岩波書店)、オクタビオ・パス『泥の子供たち』(水声社)、オクタビオ・パス『孤独の迷宮』(法政大学出版局)、他
革命二百周年のパリで――パスとマルケス
革命二百周年を祝うパリは、まだ燃えているのだろうか(ALL REVIEWS事務局注:本論執筆時期は1989年)。その式典については、前夜祭の模様とシャンゼリゼの軍事パレードを、テレビで断片的に見た程度の知識しかないが、それにしてもフランスはしたたかだ。大統領立会いのもとに、武器の移動見本市を堂々と催すのだから。ラテンアメリカのどこかの国の将校がほしがりそうな品物のオンパレードだ。もっともアルゼンチンはイギリスとどうやら国交回復しそうだし、もうエグゾセ・ミサイルを買い込む余裕はないだろう。それよりむしろ、一見民政を装いながら、その実軍部が牛耳っているグアテマラのような国の方が可能性があるかもしれない。いやそれも無理だ。この国の軍事政権は長い間米国のバックアップによって維持されてきたのだった。ではキューバはどうか。ソ連製の武器で当面間に合っている。この国は軍備の問題よりも、「ペレストロイカ」の問題で、これから大きく揺さぶられることになるだろう。カストロは、余計なお世話とばかりにゴルバチョフの政策を批判したが、彼の盟友ガルシア=マルケスはモスクワに行ってゴルバチョフに会い、ペレストロイカを称える発言をした。東欧の動きを見れば、いつまたマリエル港からマイアミへ難民が向うとも限らないが、それにしても興味深いのは、カストロとガルシア=マルケスでは評価が明らかに違っていることだ。キューバもペレストロイカということになれば、亡命した詩人エベルト・パディーリャや作家のレイナルド・アレナスは帰国するのだろうかとか、イギリスに帰化してしまったやはり作家のカブレラ=インファンテはどうするのだろうなどと、先走って考えてしまう。それからもうひとつ興味深いことがある。あのパリの革命式典に、ガルシア=マルケスが出席していたという噂の存在である。なぜ噂かといえば、彼がミッテランのすぐそばに座っていたことを証すテレビの映像も報道写真も、ぼくはまだ実際に見てはいないからだ。だが確かに見たという人がいる。噂のフォークロアはあの作家とは切っても切れない関係にあるだけに、眉唾物とは思えないのが我ながらおかしい。それにガルシア=マルケスとミッテランもまた実は仲がいい。そのことは『グアバの実の香り』で明らかにされている。それだけに、この噂には信憑性が感じられるのだ。このミッテランも先のゴルバチョフもガルシア=マルケスの作品をよく読んでいるという。例の「権力者ゆえの孤独」について教えられるところもたくさんあるのだろう。我が国の首相はどうだろう。信長、家康に学ぶのも結構だが、ブエンディーア大佐や族長のことを知っていても悪くないのではないか。それから、バルガス=リョサの小説も読んでおいた方がいい。先日来日したとき、応接した自民党議員のうち彼の作品を読んだ者がいただろうか。首相候補になったばかりの議員=作家ぐらいは読んでいるだろうと期待しているのだが。
それにしてもラテンアメリカの大作家のフットワークのよさはどうだろう。世紀末の詩人たちでさえ船を使って放浪していたくらいだが、飛行機の時代になってからは神出鬼没といえるほどだ。そのフライング・ラテンアメリカンのひとり、オクタビオ・パスが、二百周年記念に燃える直前のパリを訪れていた。六月二十二日、アレクシス・ド・トックヴィル賞の授賞式に出席したのだ。この国際賞は比較的新しいもので、二年に一回、歴史学・政治学に貢献した人を対象とし、これまでにレーモン・アロン、カール・ポッパー、デヴィッド・リースマン、ルイ・デュモンと、そうそうたる顔触れが受賞者となっている。この中で文学者、まして詩人というのはパスただひとりであり、彼自身、その受賞記念講演で、「なぜ詩人であるこの私に?」と、驚きを率直に告白している。講演の内容は「ブエルタ」誌の七月号に「詩、神話、革命」というタイトルで全文が掲載されているが、最後に「四月二十九日、メキシコ市にて」とあるところから、受賞決定の報は二ケ月前には知らされていたのだろう。それだけに、テキストはいかにも彼らしい評論となっている。付記にしたがえば、『泥遊びの子供たち』(一九七五)および二年前にやはり「ブエルタ」に戴った評論「ロマン主義と現代詩」の続きである。しかしパスもさる者、自分が公的生活に参加し、歴史と政治に関する著書を何冊か書いているからだろうと、自らの受賞をただちに正当化する。実際、彼には『博愛の食人鬼』や『交流』、『曇り空』といった評論集があり、そこで単に現代の歴史・政治情況を世界的視野で分析し論評するばかりでなく、キリスト教的時間、直線的歴史の批判を行ない、起点へ戻るべきであるという、一見古くさいように見えるが、結局はもっともラジカルな提言を行なっている。なぜなら、いかなる未来学、未来論も、直線的時間を前提としている限り限界があるからだ。それはいわば終末の到来を先送りし、恐怖感をバラ色のオブラートに包むことで柔らげようとしているにすぎない。
パスの評論がラジカルなのは、そこでは革命もまた批判の対象となっているからだ。彼は革命が、歴史の地平に現れたときから、歴史の産物であると同時に神話の産物でもあったという、その二重性を我々に想起させる。もちろんその姿勢は、単なる保守回帰による反動的批判とは区別されなければならないし、また単なるリベラルとも違っている。パスはリベラリズムの限界が、宗教以前のメタ歴史を提起できないところにあると指摘する。リベラリズムの「自由」とは、意識の自由と他人の意識の自由を認めることにほかならず、それはすばらしいと同時に、「私」と「あなた」とをつなぐ橋を壊し、どちらも三人称の「他者」と「他者たち」の範疇に閉じ込めてしまうがゆえに危険であるという。つまりそこに自由はあっても、友愛はなくなってしまうというのだ。
この友愛は宗教や哲学によって説かれてきたが、パスによれば、近代詩はそれとは異なるとともにもっと古くからある友愛を提示する。それは敵対する自然の中で原始人が抱いていたのと同じ孤独感から生れた友愛である。彼によれば、「ただちがうのは、我々は今その孤独を宇宙に対してばかりでなく、我々の隣人に対して感じながら生きている」ことである。しかし、「我々はみんな、それぞれが自分の部屋にいること、自分たちが真に孤独ではないこと、を知っている」のだ。パスはそこから生れる友愛を、「虚空の上の友愛」と呼ぶ。このあたりは『孤独の迷宮』の延長でもある。
パスは結論として、「現代の課題」は自由と友愛の収斂する点を探し求めることであり、リベラリズムと社会主義という、近代が生んだ二つの偉大な伝統を和解させることだとする。それがおそらく彼のいう「民主的リベラリズム」なのだろう。
それにしても、革命二百周年記念の年に、パスに革命批判をさせる一方で、噂が本当なら、ガルシア=マルケスを呼びつけるとは、フランスはやはりしたたかだ。
ALL REVIEWSをフォローする