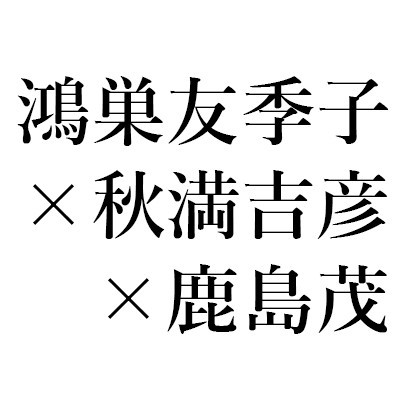本を閉じると、廃墟が広がる 『ホテル・アルカディア』のデカダントな創造力―第30回ドゥマゴ文学賞レポート
本を閉じると、廃墟が広がる――『ホテル・アルカディア』のデカダントな創造力
今年で30回目を迎えるドゥマゴ文学賞が11月3日に発表された。受賞作は、石川宗生さんの『ホテル・アルカディア』。これまで石川宗生さんの著書は読んだことがなかった、というか、石川宗生さんという方自体を存じあげなかったのだが、タイトルから想起される異国情緒感に惹かれて手に取ってみた。これが大変なシロモノだった。そもそもドゥマゴ文学賞とは何か。その成り立ちは1990年にさかのぼる。時はバブル崩壊の前年。今は亡きデヴィッド・ボウイやプリンスをはじめ、ローリング・ストーンズやスティーヴィー・ワンダー、ビリー・ジョエルといった大物海外ミュージシャンが来日公演をおこなった華やかなりしころ。資生堂やセゾングループなどを中心に企業が社会貢献の一環として芸術文化を支援する「メセナ活動」が始まったのもこのころだ。ドゥマゴ賞もそのひとつだったのだろう。主催は、株式会社東急文化村。1933年に創設されたパリの「ドゥ・マゴ賞」のもつ先進性と独創性を受け継ぎ、既成の概念にとらわれることなく、常に新しい才能を認め、発掘することが目的だという。小説・評論・戯曲・詩を毎年「ひとりの選考委員」が審査し、年1回発表するスタイルだ。このあと未曾有の経済不況に突入した日本の「失われた10年」のなかで、さまざまな文化事業が縮小され、消えていった。ドゥマゴ文学賞がその苦難の時代を乗り越えこんにちまで脈々と続いているのは、「先進・独創・脱既成概念」というほかにはない視点で作品を選び続けてきたからではないかと思う。
過去の受賞作を見てみると、昨年は我らがALL REVIEWS主宰の鹿島茂さんを選考委員とする小田光雄さんのエッセイ『古本屋散策』が受賞。矢作俊彦さん『あ・じゃ・ぱん』(第8回)、多和田葉子さん『球形時間』(第12回)、米原万里さん『オリガ・モリソヴナの反語法』(第13回)といった小説のほかに、日記スタイルの中原昌也さん『中原昌也 作業日誌 2004→2007』(第18回)、評論では武田砂鉄さん『紋切型社会 言葉で固まる現代を解きほぐす』(第25回)など、とがった作品が並ぶ。
過去の受賞作をすべて読んでいるわけではないが、『ホテル・アルカディア』のとんがりはひときわ深々と突き刺さるものだった。その理由は、今年度の選考委員を務めた哲学者の野矢茂樹さんが授賞式に先立って述べられた選評のなかの一言に尽きる。「読み始めてすぐに、私の手に余るなと感じた。だから、つまらなかったらすぐに読むのをやめようと思っていた。でも、読まされて読んでいくうちに、参りましたという気持ちになった」。どんな内容の本なのか、集英社の作品紹介ページにはこのようにある。
ホテル〈アルカディア〉支配人のひとり娘・プルデンシアは、敷地のはずれにあるコテージに理由不明のまま閉じこもっていた。投宿していた7名の芸術家が同情を寄せ、元気づけ外に誘い出すべく、コテージ前で自作の物語を順番に語りだした。突然、本から脱け出した挿絵が「別にお邪魔はしないさ」と部屋に住みつづける「本の挿絵」、何千年も前から上へと伸び続けるタワーマンションの街を調査するも、1万階を過ぎたあたりで食糧が尽きてくる「チママンダの街」など7つのテーマに沿った21の不思議な物語。この朗読会は80年たった今も伝説として語り続けられ、廃墟と化したホテル〈アルカディア〉には聖地巡礼のようにして、芸術家たちのファンが何人も訪れる。80年前、あの朗読会の後、7名の芸術家たちはどうしたのか、そしてひとり娘のプルデンシアはどうなったのか。
あらすじだけを読むと、『千夜一夜物語』の逆パターンか、あるいは天岩戸伝説を彷彿とさせられるのだが、「愛」、「性(さが)」、「死生」、「文化」、「都市」、「時」、「世界」の各「アトラス(地図帳)」におさめられた短編は、本来は人(プルデンシア)に聞かせる物語でありながら、設定や前提を一切説明することなく、いきなり奇天烈な世界へと引きずり込む強引さに満ちている。いま流行のマジックリアリズムの対極をいくマジックロマンティシズムが、散文詩的な文体で軽やかに展開される。そう、この文章のリズムが本書で私の魅せられたひとつの要因だ。戯曲風だったり、ゲームの記録風だったり、詩の朗詠風だったり。最後までまったく意味のわからないものもある。そして、ほとんどが相互に関連をもたない作品たちであるにもかかわらず、いつの間にか堅牢な城壁のように頭のなかに張りめぐらされ、半分を過ぎるころには自分がそのなかに取り込まれていることに気がつく。
奇想天外、荒唐無稽な話のようでいて、心にくさびを打たれるのは、ひとつには、それらが今の世相を巧みに反映しているからではないかと思う。例えば、ゾンビ化が推奨される世界で抵抗を試みる男の末路を描いた「ゾンビのすすめ」は、ソーシャルメディアやマスコミに踊らされる気質と同調圧力への皮肉を感じさせる。ノアの方舟をモチーフにした「恥辱」は、根拠のない正論のもとにおこなわれる一方的支配関係と個の圧殺がもたらす、身につまされる悲劇である。もうひとつは、石川さんが親しんだカルチャーがメタモルフォーゼされてそこかしこに顔を出すことだ。“プリズマ”と呼ばれる朗読会にやって来た「実在の」著名人の描写には笑ってしまった。「『キャプテン翼』、お好きですよね?」と突っ込みたくなる箇所もある。もっとも大きいのは、3年をかけて世界各国を放浪したという石川さんのご経歴だろう。作品には実際の地名などは出てこないが、石川さんはご自身のなかにイメージしている国や地域があり、その土地の空気感を思い出しながら執筆されたという。野矢さんが会場で述べられた「単に独創的で異色の作品ではない。全員にアピールするわけではないけれども、マニアとか趣味を同じくする人に向けて以上の広がりをしっかりもっている作品だ」という普遍性の理由がここにある。
壮大な物語の旅を経て、80年後のどこかにたどり着く最後。プルデンシアとはいったい何者だったのか。その答えが、朽ち果てた石積みの光景とともに脳裏に広がる体験は「強烈」というほかない。
授賞式の会場にあらわれた石川さんは、のっぽの吟遊詩人みたいだった。旅の途中でエライ人に捕まって連れてこられ、「ひとくさり詠ってみせよ」と命じられたかのように、ちょこんと壇上にお立ちになった。そしてご自身のなかにこんこんと湧く書くことへの情熱をふわりと語り風のように去っていった。次回作は、2017年に中央アジア、コーカサス、東欧を旅した記録をまとめた旅行記になる予定だという。これらの地が、石川さんの目をとおり頭のなかでどのように再構成され描かれるのか、とても楽しみだ。
[書き手]小島ともみ(ALL REVIEWS友の会・会員)
フリーランスの映画好きライター、ときどき映画宣伝。インタビューなど取材に基づくライティング、レビュー執筆、宣伝企画など。マカロニと血肉のしたたる映画が大好きです。映画パンフレットを偏愛する自主団体「映画パンフは宇宙だ」で活動中。編集長としてアリアスター短編読本、映画『ハッピー・デス・デイ/2U』ファンジン刊行。趣味はホームズと積ん読。Twitterアカウント:@Drafting_Dan
ALL REVIEWSをフォローする