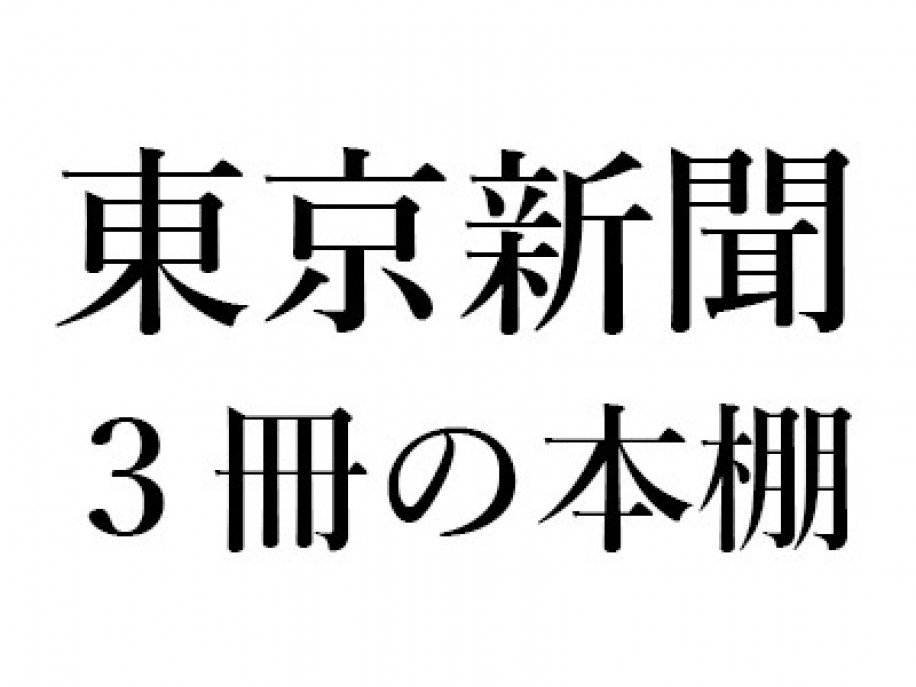書評
『衣裳術 《新装版》』(リトル・モア)
衣裳をまとう人の魅力を表現に昇華させる
スタイリスト北村道子、1949年生まれ。約四十年にわたって映画や広告を中心に活躍する異能の人。そのオリジナルな仕事を写真と文章で構成した映画衣裳作品集が、新装版『衣裳術』、続刊『衣裳術2』だ。『衣裳術2』の冒頭、「私はスタイリストだと思っていない」と宣言する。とはいえ服を人に着せるのが彼女の仕事なのだが、型破りの発想、妥協のない表現、イメージ喚起力。その非凡な才能の内側を知りたいと思わずにはいられない人物が北村道子だ。
彼女の人生と仕事は直結している。十八歳からアフリカやアメリカ大陸を放浪、行き着いたパリで『ヴォーグ』『エル』のファッション撮影の手伝いをしたことが発端になった。帰国後、スタイリストとして広告や音楽の分野を中心に広く活躍、そののち映画の衣裳を手がける。
エピソードひとつひとつ、じつに北村道子的だ。初仕事は「それから」(監督・森田芳光 1985)、松田優作の指名だった。映画の終盤、松田本人が提案した衣裳を拒否。「徹底的に喧嘩になった」あげく、提案した衣裳に松田優作は納得し、降参した。または「殺し屋1」(監督・三池崇史 2001)。浅野忠信の役柄は、金髪の設定だった。
「わたしが『腋毛も胸毛も下の毛も金色じゃなきゃ嫌なんだ』って言ったら、浅野君は全部染めてくれた! ラストシーン、パーッと浅野君がビルから落下していく。あそこが一番大事なシーンだから、黒い胸毛が出たら最悪じゃない。でも、あそこまでやってくれる奴っていないよ」
映像化されない下着や生活道具まで、映画を成立させるための準備は当たり前。自分で衣裳を制作することもあれば、尊敬するデザイナーでなければその服を使う表現はできないと言い切る。交渉や借り集める段階まで自分でやる。好きな監督はリドリー・スコットやデヴィッド・リンチ。アジアでは、韓国の映画スタッフが「最もちゃんと人間を撮ろうとしている」。いっぽう日本の映画は「お金がヒトじゃなくてモノにいっている」。そう語る著者は、現在は映画とは距離を保っているように見える―。
衣裳を語りつつ、映画、芸術、文化……縦横に話題は広がるのだが、映画を総合芸術として捉える著者にとって、衣裳は人間を創造的に表す手立て。浅野忠信、オダギリジョー、香川照之、石橋凌、菊地凛子、松田龍平、桃井かおり……衣裳をまとう各人の写真は、服の力によって未知のポテンシャルが引き出されているさまを実証している。
「才能とは化学反応できること」(『衣裳術2』)
自身の定義を地でゆく。
三十八歳で亡くなった父は、小学生の娘にモノクロの男物を着せていたという。クラスでひとり、時代に先駆けたコム デ ギャルソン的ないでたち。本能でつかんだ独立独歩が、著者の武器なのだった。
以前、著者の発言にどきっとさせられたことがある。何十年もファッションを見続けているが、その本質は変わらない、現在のファッションが面白くないと思うのは、その人自身が面白くなくなっただけだ、と。問答無用の斬り方にスカッとした。
人間が服をまとう意味への問いかけ。映画であれ、日常であれ、服は表現手段であり、尊厳なのだと突きつけてくる。
ALL REVIEWSをフォローする