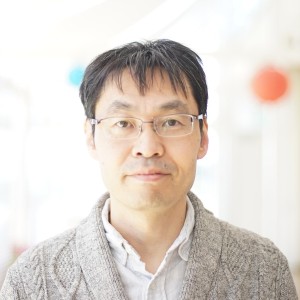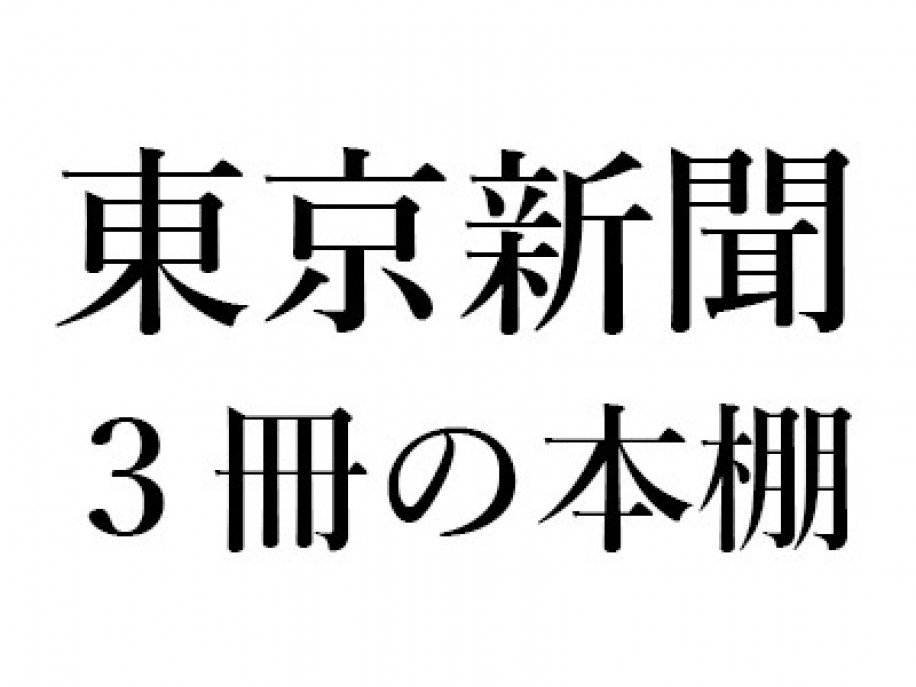書評
『マリアさま』(リトル・モア)
見えないものたちの声を聞く
「いしいしんじ祭」に参加したことがある。神奈川の漁港、三崎でのことだ。かつてここに住んでいた彼の名を冠したこの祭りで、神社の神楽殿の扉が突然開かれ、中に彼が座っている。机に向かった彼は、その場で小説を書き始める。湧き上がる物語は彼の声となって流れ、境内の観客たちの体を浸す。観客の思いは渦となり、彼に押し寄せる。一人の声だけが響く奇妙な会話。そして作品が終わったとき、全員が不思議な満足感を抱いている。
あのとき彼は何をしていたのか。見えないものに目をこらし、聞こえないものに耳を澄ませていた。そのことは本短編集所収の「自然と、きこえてくる音」を読めばわかる。
祖父は京都に住む録音技師だ。久しぶりに訪れた孫の「わたし」を赤いスポーツカーに乗せて、琵琶湖まで旅に出る。旅の目的は音を拾い集めることだ。鰻の焼ける音。クイナの鳴声。
そうしているうちに、固く閉じた「わたし」の心はほぐれていく。祖父は言う。「自然と、むこうからきこえてくるもんだけで、だいたいのほんとうは、わかるもんやで」。なぜか。すべてのものは常に語りかけているからだ。
すべてのものとは何か。「せせらぎ」では山だ。「とってください」では白いテニスボールだ。だが何と言っても動物たちだ。
「犬のたましい」で飼主の老婆に先立たれた犬は、墓の中から漂ってくるビーフジャーキーの香りを通じて彼女の声を聞く。「においだけでじゅうぶんです。私は犬なのですから」
目に見えず、耳に聞こえず、手で触れられず、でも確かにそこにいる。いしいの作品で、生者と死者、人間と動物、生物と物は区別されない。みなが魂を持って、いつもそこにいる。
いしいが児童文学作家に見えるのは、大人の文学がそうした感覚を失っているからだ。他界は今、ここにある。彼の作品はそのことを思い出させてくれる。
朝日新聞 2019年11月02日
朝日新聞デジタルは朝日新聞のニュースサイトです。政治、経済、社会、国際、スポーツ、カルチャー、サイエンスなどの速報ニュースに加え、教育、医療、環境、ファッション、車などの話題や写真も。2012年にアサヒ・コムからブランド名を変更しました。
ALL REVIEWSをフォローする