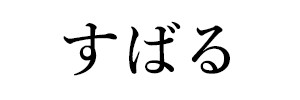書評
『港、モンテビデオ』(河出書房新社)
港と灯台、死者と生者をつなぐ
「トツーツート……」本書を読み終えた私は指先で机を叩いていた。どこかの港のスナックで、船乗りの老人がコツコツ変拍子で力ウンターを叩いている姿を思い浮かべながら。
舞台は、三浦半島の先端にある三崎。かつてはマグロの遠洋漁業で知られた町で魚屋を営んでいるのは、原爆マグロのせいで指先が今なお光る宣(のぶ)と、父の死後熟睡できなくなってしまった美智世の夫婦。太った猫が行きかう町で、ある日、スナックのなかが空っぽになるという奇妙な事件が起きる。騒動があったのは、「稚内」、「勝浦」、「ボストン」と港の名前がついている店ばかり。ひとくせもふたくせもある三崎のひとたちがスナックで対策を練っているうちに、美智世と宣、そして二人の店に出入りする船乗りの慎二の三人による想像譚が交錯していく。
横須賀で見た画家アルフレッド・ウォリスの作品に魅了された美智世は、いつの間にか、画家の住んでいた英国の港町セント・アイヴスにタイムスリップしてしまい、亭主の宣はスナックを巡り歩いていくうちに「バルパライソ」という店にたどりつき、そこでチリの詩人パブロ・ネルーダの声(身体は見えない)と遭遇する。初めての縄船「もんてびでお丸」で航海に出た慎二は、通信士の黒さんからモールス通信を打つよう頼まれる。次第に「目をとじているのに、むこうからなにか浮かびあがってくるような感覚」に襲われ、黒さんが大事にしている娘の写真が美智世にそっくりであるのに気づく……。
美智世、宣、慎二は、それぞれの港、それぞれの灯台を探しもとめて死者たちと交感していくのだが、その背景で流れたり、詠まれたりする詩や歌が物語を味わい深いものにしている。ネルーダをはじめ、セント・アイヴスで毎夏を過ごした『燈台へ』のヴァージニア・ウルフ、「燈台へ行く道」を書いた西脇順三郎、都はるみの「涙の連絡船」といった世界と共鳴していくさまは、本のかたちをとったジュークボックスのようだ(ところどころ使われる「ジョワアアアン」などの擬音語もすばらしい)。
「港と名のつくところなら、きっと、世界じゅうどこでも似たような感じがある。飲み屋街とせせこましい路地と船のペンキ、そして目には映らないそれ以外のこと」と美智世は語るが、本書の主役はあまたの港なのかもしれない。
港と灯台、記憶と追憶、船乗りと詩人、死者と生者を見えない音と言葉でつなぐ稀に見る作品が三崎から生まれた。
ALL REVIEWSをフォローする