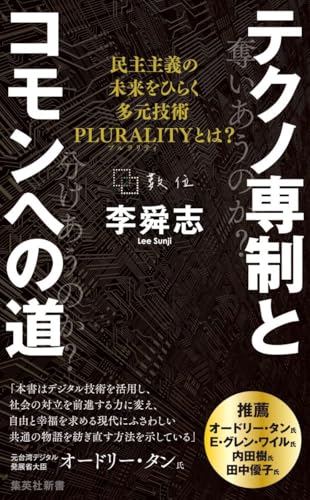解説
『開高健のパリ』(集英社)
作家には、完成型と成長型とがあると私は思っている。完成型の作家は、十代だろうが二十歳そこそこだろうが、デビューしたときにすでに確固たる文体を持っている。その文体で提示する世界観もすでに会得している。対して成長型は、デビューしてからじょじょに文体を獲得し、模索しながら自身の世界観を作り出していく。こちらの作家の文体は、デビュー作と十年後でいちじるしく変わることもある。
開高健は、完璧な前者だ。満二十六歳のときに発表した『パニック』はすでに開高健作品として完成されている。その翌年、『裸の王様』で芥川賞を受賞する。二十七歳という年齢を考えると、ずいぶん早い受賞だったのだなとあらためて驚くけれど、でも、開高健作品にとっては二十七歳も四十七歳も、あんまり関係ないのかもしれない。作品を発表したときに、すでに開高健として完成されていたのだから。興味深いことに、キャッチコピーとしても、小説としても、である。
こんなふうに完成された作家のことを、天才と呼んでもいいのだと思う。が、開高健は悩める天才だった。書くことに苦しんだ天才だった。私はそのことと、この作家の「異国への旅」を関連付けて考えずにはいられない。
開高健は、少年時代に日本から密出国することをひたすら夢見ていた。異国に亡命することに焦がれていた。「外国に逃げられないから」読書に亡命していた、とみずから書いている。戦後、貧困を極める時代に、開高少年は働きながらひたすら書物の大海を泳ぐ。そうすれば本に描かれる異国に泳ぎ着けるかのようにむさぼり読む。
二十一歳、まだ学生の時分に父となり、結婚し、その後大学を卒業、壽屋に勤務し、数年して芥川賞を受賞する。すでに開高健として作品は完成されていると先にも書いたが、でも、決定的に足りないものがあった。異国だ。旅だ。
開高健は芥川賞の受賞前から、「自身の内心によりそって作品を書くことはするまいと決心していた」。だから受賞後、七年間のあいだに書いたものはみな「‟外へ!”という志向で文体を工夫すること、素材を選ぶことにふけった」。それを本人は「遠心力で書く文学」と書いている(以上の引用は『青い月曜日』)。外へ、外へ! 彼の思う「外」は社会である。小説の中心を、自己ではなく社会に置く。しかし、それには日本社会という限界があった。この場合の「外へ!」はまったく異なる意味だけれど、でも、私には、日本の外へ、と願う声にも思えるのである。もっと外へ。限界の外へ。
この作家に、はじめて異国に足を踏み出す機会が訪れたのは一九六〇年。三十歳になろうとしている作家は、中国訪問日本文学代表団の一員として中国を訪問している。同年九月、招待を受けルーマニア、チェコスロバキア、ポーランドをまわり、十二月にパリを通って帰国している。この年の二度の旅は、作家にとって文字通りはじめてのこの国の「外」、言葉の外にある未知の世界だった。
そうしてこの旅が、開高健という作家を、完成されているにもかかわらず大きく変容させ、同時に、ものすごく深い困難をも与えた、と私は思う。
と、本書に触れる前に長々と書いてしまったのは、本書に収録された開高健の文章が、いつ書かれたものであるかということが、非常に重要な気がするからだ。いや、私にとって、非常に興味深いからだ、というほうが正確だ。
本書のおおもとになっている画集『現代美術15 ユトリロ』(みすず書房)が刊行されたのは一九六一年二月。はじめての旅ののちだ。しかし作家が、人間がいやでいやでたまらなくなって、ユトリロの絵を見ることで、すれっからしになった「内部のある領域」にみずみずしさを蘇らせていたのは、実際のパリを見る前のことだろう。作家は、ユトリロの絵でパリを見て、パリと同化した。一枚一枚の作品紹介は、実際にパリに滞在したのちに書かれたのではないかと私は想像する。
ユトリロの描いたパリと、開高健の書いたパリは、私にはまったく異なる印象を残す。異なるどころか対極だとすら思う。かたや、人のまったくいない、「人間への拒絶」を示すパリであり、かたや、食べもののにおいと人間の熱と絶え間ないおしゃべりに満ちたパリである。ユトリロの描くパリは静で、開高健の書くパリは川のように止まることのない動だ。だから、この作家がユトリロの絵に惹かれた、というのは不思議なのである。
でも、実際にパリにいく前に、その目で一度も異国を見るより前に、この画家の絵を見ていたら……と考えると、その不思議は消える。まさに「眼は木を眺めて木になり、壁を眺めて壁になる」ように、開高健はユトリロの眼によって生まれた「新しいパリ」を見ることで、パリそのものになったのだろう。
そしてもうひとつ、三十歳になるかならないかの開高健が、ユトリロの絵に寄り添った理由に、きっぱりとした孤独があるように思う。
私はユトリロの絵を見て、なんと寒々しい光景ばかりなのだろうと思ってしまう。人間が描かれていないからばかりではない。音も聞こえてこない。陽射しにあふれていても寒々しく感じる。開高健が書く「生への愉悦」を、私は感じ取ることはできない。
その孤独は、堂々とただそこにある。ひねくれてもいないし、ひけらかしてもいない。いじけてもおらず、胸を張ってもいない。ほかのものを何も付随させていない。ただ、しんとしてそこにある。この孤独の堂々さ具合を、開高健は「透明なオプティミズム」と見たのかもしれない。
人間を拒絶しながら、でも、生への愉悦がある、地上の生活にたいする静謐な喜びがある、というのは、後に開高健が自身を説明する言葉、「人間嫌いなのに、人間から離れられない」(『地球はグラスのふちを回る』)とまったく同じである。
さて、そして三十歳の開高健は現実のパリに降り立つ。ユトリロのパリと実際のパリはところどころで重なって、若い作家を歓喜させただろう。
先に、作品紹介は実際のパリ滞在の後ではないかと書いた。それは、絵に寄せられた文章が、あきらかに絵よりもはるかに人間くさく、生き生きと躍動しているからである。たとえば「パリのアンドレア・デル・サルト通り」の絵に開高健は、
と、書く。しんと孤独な絵を見て、そう書く。かつてユトリロのパリを見ていた開高健は、旅をしたのちは、ユトリロの絵に自身の眼がとらえたパリを見るようになったのではないか。まさに「タケシのパリ」を。
一九六〇年にはじめて訪れたのち、翌年は二度もパリにいっている。このうちの一度は、本書でも触れているサルトルとの会見のときだ。
異国に逃亡することに焦がれていた作家は、実際に異国を旅して、パリにも、旅にも取り憑かれた。何かを取り戻すかのように幾度も長い旅をくり返し、ルポルタージュは書くが、不思議なことに小説はほとんど書いていない。書けなくなったのではないかと私は思う。日本という限界を超えていって、「遠心力で書く文学」は意味をなさなくなった。あるいは、異国という自身の「経験」と「小説」の折り合いが見つけられなかったのか。
それを打破するのは一九六四年、特派員としてのベトナム戦争体験である。ここで彼は「経験」と「小説」を奇跡のように融合させた。遠心力と求心力を同時に使って小説を書いた。すでに完成されていた開高健作品の、さらなる高みに到達した。しかしそのことは、作家をさらに苦しめる。この作家は小説においては怠けることをしない。同じことをくり返さない。完成されているのに、もっと完成させなければならないと思っている。
こののち、ときがたって一九七一年、開高健は自身のパリを完成させる。『夏の闇』という小説が切り取るパリが、彼のパリの完成形のように思える。倦怠に襲われた無気力な作家が、騒々しくて薄汚くて、あらゆる食べもののにおいがひしめく生き生きとしたパリに暮らしている。未だパリを見ぬ作家が絵画のパリを見たように、未だパリを知らなかった二十代の私はこの小説でパリを知った。
ところで、どうも開高健は小説を書けなくなるとルポルタージュやエッセイを書いたような印象がある。具体的には、旅に取り憑かれて以降と、ベトナム戦争体験以降だ。『夏の闇』の主人公も書けなくなった作家である。彼には「頭の地獄に堕ちたら手足を動かせ」という名言があり、それは釣りについての言葉だったけれど、でもそれはこの作家の姿勢だったように思う。書けないときは、東京を、あるいは世界を、自身の足で歩いて取材し、人の声に耳を傾け、釣りをして、旅をして、そうすることで、ともかく文章を書き続けた。それは、アルコール依存症のために精神を病み、そこから脱出するために絵を描き続けたという若きユトリロの姿と重なりもする。
中年以降のユトリロの絵について、開高健は「幸福な馬鹿」「いたましい駄作、凡作」と痛烈極まりない。これを読むと、裕福になっておいしいものを食べて贅沢をしながら、人間はよいものは作れない、とこの作家が考えていたのだとわかる。ものを作り出すことはこの作家にとってつねに苦しみだった、というよりも、自身に苦しみを課して課して書いていた、のかもしれない。
この作家も、上等なぶどう酒を飲み、贅を尽くした料理を食べ尽くしたはずである。でもそれは、本書の「続・思いだす」に書かれているとおり、「両極端は一致する」という定理に則ったものだ。上等な酒と贅を極めた食事は、この作家にとって、飢えと同じことだった。飢えながら彼は食べ続け、飲み続けた。そうすることで飢えを手放さなかった。
その定理について考えると、人間嫌いで人間から離れられない、ということも、一致している。開高健の人間嫌いは極端なものだったのだろうし、人間にたいする興味、あるいは人間を描きたいと思う執念も、極端なものだったのだろう。一致するほどに。
実際のパリに何度も通った開高健は、ベトナムから帰った開高健は、『夏の闇』でパリを描いた開高健は、やはりユトリロのパリを好んだだろうか。無人のパリに思いを馳せただろうか。知りようがないけれど、そう考えてみるだけで、ユトリロの絵も私には変わって見えてくる。
開高健は、完璧な前者だ。満二十六歳のときに発表した『パニック』はすでに開高健作品として完成されている。その翌年、『裸の王様』で芥川賞を受賞する。二十七歳という年齢を考えると、ずいぶん早い受賞だったのだなとあらためて驚くけれど、でも、開高健作品にとっては二十七歳も四十七歳も、あんまり関係ないのかもしれない。作品を発表したときに、すでに開高健として完成されていたのだから。興味深いことに、キャッチコピーとしても、小説としても、である。
こんなふうに完成された作家のことを、天才と呼んでもいいのだと思う。が、開高健は悩める天才だった。書くことに苦しんだ天才だった。私はそのことと、この作家の「異国への旅」を関連付けて考えずにはいられない。
開高健は、少年時代に日本から密出国することをひたすら夢見ていた。異国に亡命することに焦がれていた。「外国に逃げられないから」読書に亡命していた、とみずから書いている。戦後、貧困を極める時代に、開高少年は働きながらひたすら書物の大海を泳ぐ。そうすれば本に描かれる異国に泳ぎ着けるかのようにむさぼり読む。
二十一歳、まだ学生の時分に父となり、結婚し、その後大学を卒業、壽屋に勤務し、数年して芥川賞を受賞する。すでに開高健として作品は完成されていると先にも書いたが、でも、決定的に足りないものがあった。異国だ。旅だ。
開高健は芥川賞の受賞前から、「自身の内心によりそって作品を書くことはするまいと決心していた」。だから受賞後、七年間のあいだに書いたものはみな「‟外へ!”という志向で文体を工夫すること、素材を選ぶことにふけった」。それを本人は「遠心力で書く文学」と書いている(以上の引用は『青い月曜日』)。外へ、外へ! 彼の思う「外」は社会である。小説の中心を、自己ではなく社会に置く。しかし、それには日本社会という限界があった。この場合の「外へ!」はまったく異なる意味だけれど、でも、私には、日本の外へ、と願う声にも思えるのである。もっと外へ。限界の外へ。
この作家に、はじめて異国に足を踏み出す機会が訪れたのは一九六〇年。三十歳になろうとしている作家は、中国訪問日本文学代表団の一員として中国を訪問している。同年九月、招待を受けルーマニア、チェコスロバキア、ポーランドをまわり、十二月にパリを通って帰国している。この年の二度の旅は、作家にとって文字通りはじめてのこの国の「外」、言葉の外にある未知の世界だった。
そうしてこの旅が、開高健という作家を、完成されているにもかかわらず大きく変容させ、同時に、ものすごく深い困難をも与えた、と私は思う。
と、本書に触れる前に長々と書いてしまったのは、本書に収録された開高健の文章が、いつ書かれたものであるかということが、非常に重要な気がするからだ。いや、私にとって、非常に興味深いからだ、というほうが正確だ。
本書のおおもとになっている画集『現代美術15 ユトリロ』(みすず書房)が刊行されたのは一九六一年二月。はじめての旅ののちだ。しかし作家が、人間がいやでいやでたまらなくなって、ユトリロの絵を見ることで、すれっからしになった「内部のある領域」にみずみずしさを蘇らせていたのは、実際のパリを見る前のことだろう。作家は、ユトリロの絵でパリを見て、パリと同化した。一枚一枚の作品紹介は、実際にパリに滞在したのちに書かれたのではないかと私は想像する。
ユトリロの描いたパリと、開高健の書いたパリは、私にはまったく異なる印象を残す。異なるどころか対極だとすら思う。かたや、人のまったくいない、「人間への拒絶」を示すパリであり、かたや、食べもののにおいと人間の熱と絶え間ないおしゃべりに満ちたパリである。ユトリロの描くパリは静で、開高健の書くパリは川のように止まることのない動だ。だから、この作家がユトリロの絵に惹かれた、というのは不思議なのである。
でも、実際にパリにいく前に、その目で一度も異国を見るより前に、この画家の絵を見ていたら……と考えると、その不思議は消える。まさに「眼は木を眺めて木になり、壁を眺めて壁になる」ように、開高健はユトリロの眼によって生まれた「新しいパリ」を見ることで、パリそのものになったのだろう。
そしてもうひとつ、三十歳になるかならないかの開高健が、ユトリロの絵に寄り添った理由に、きっぱりとした孤独があるように思う。
私はユトリロの絵を見て、なんと寒々しい光景ばかりなのだろうと思ってしまう。人間が描かれていないからばかりではない。音も聞こえてこない。陽射しにあふれていても寒々しく感じる。開高健が書く「生への愉悦」を、私は感じ取ることはできない。
その孤独は、堂々とただそこにある。ひねくれてもいないし、ひけらかしてもいない。いじけてもおらず、胸を張ってもいない。ほかのものを何も付随させていない。ただ、しんとしてそこにある。この孤独の堂々さ具合を、開高健は「透明なオプティミズム」と見たのかもしれない。
人間を拒絶しながら、でも、生への愉悦がある、地上の生活にたいする静謐な喜びがある、というのは、後に開高健が自身を説明する言葉、「人間嫌いなのに、人間から離れられない」(『地球はグラスのふちを回る』)とまったく同じである。
さて、そして三十歳の開高健は現実のパリに降り立つ。ユトリロのパリと実際のパリはところどころで重なって、若い作家を歓喜させただろう。
先に、作品紹介は実際のパリ滞在の後ではないかと書いた。それは、絵に寄せられた文章が、あきらかに絵よりもはるかに人間くさく、生き生きと躍動しているからである。たとえば「パリのアンドレア・デル・サルト通り」の絵に開高健は、
「……生きよう!」
キャフェに人は集り、春の芽のように路上に姿が生まれ、空に鐘は鳴る。
と、書く。しんと孤独な絵を見て、そう書く。かつてユトリロのパリを見ていた開高健は、旅をしたのちは、ユトリロの絵に自身の眼がとらえたパリを見るようになったのではないか。まさに「タケシのパリ」を。
一九六〇年にはじめて訪れたのち、翌年は二度もパリにいっている。このうちの一度は、本書でも触れているサルトルとの会見のときだ。
異国に逃亡することに焦がれていた作家は、実際に異国を旅して、パリにも、旅にも取り憑かれた。何かを取り戻すかのように幾度も長い旅をくり返し、ルポルタージュは書くが、不思議なことに小説はほとんど書いていない。書けなくなったのではないかと私は思う。日本という限界を超えていって、「遠心力で書く文学」は意味をなさなくなった。あるいは、異国という自身の「経験」と「小説」の折り合いが見つけられなかったのか。
それを打破するのは一九六四年、特派員としてのベトナム戦争体験である。ここで彼は「経験」と「小説」を奇跡のように融合させた。遠心力と求心力を同時に使って小説を書いた。すでに完成されていた開高健作品の、さらなる高みに到達した。しかしそのことは、作家をさらに苦しめる。この作家は小説においては怠けることをしない。同じことをくり返さない。完成されているのに、もっと完成させなければならないと思っている。
こののち、ときがたって一九七一年、開高健は自身のパリを完成させる。『夏の闇』という小説が切り取るパリが、彼のパリの完成形のように思える。倦怠に襲われた無気力な作家が、騒々しくて薄汚くて、あらゆる食べもののにおいがひしめく生き生きとしたパリに暮らしている。未だパリを見ぬ作家が絵画のパリを見たように、未だパリを知らなかった二十代の私はこの小説でパリを知った。
ところで、どうも開高健は小説を書けなくなるとルポルタージュやエッセイを書いたような印象がある。具体的には、旅に取り憑かれて以降と、ベトナム戦争体験以降だ。『夏の闇』の主人公も書けなくなった作家である。彼には「頭の地獄に堕ちたら手足を動かせ」という名言があり、それは釣りについての言葉だったけれど、でもそれはこの作家の姿勢だったように思う。書けないときは、東京を、あるいは世界を、自身の足で歩いて取材し、人の声に耳を傾け、釣りをして、旅をして、そうすることで、ともかく文章を書き続けた。それは、アルコール依存症のために精神を病み、そこから脱出するために絵を描き続けたという若きユトリロの姿と重なりもする。
中年以降のユトリロの絵について、開高健は「幸福な馬鹿」「いたましい駄作、凡作」と痛烈極まりない。これを読むと、裕福になっておいしいものを食べて贅沢をしながら、人間はよいものは作れない、とこの作家が考えていたのだとわかる。ものを作り出すことはこの作家にとってつねに苦しみだった、というよりも、自身に苦しみを課して課して書いていた、のかもしれない。
この作家も、上等なぶどう酒を飲み、贅を尽くした料理を食べ尽くしたはずである。でもそれは、本書の「続・思いだす」に書かれているとおり、「両極端は一致する」という定理に則ったものだ。上等な酒と贅を極めた食事は、この作家にとって、飢えと同じことだった。飢えながら彼は食べ続け、飲み続けた。そうすることで飢えを手放さなかった。
その定理について考えると、人間嫌いで人間から離れられない、ということも、一致している。開高健の人間嫌いは極端なものだったのだろうし、人間にたいする興味、あるいは人間を描きたいと思う執念も、極端なものだったのだろう。一致するほどに。
実際のパリに何度も通った開高健は、ベトナムから帰った開高健は、『夏の闇』でパリを描いた開高健は、やはりユトリロのパリを好んだだろうか。無人のパリに思いを馳せただろうか。知りようがないけれど、そう考えてみるだけで、ユトリロの絵も私には変わって見えてくる。
ALL REVIEWSをフォローする