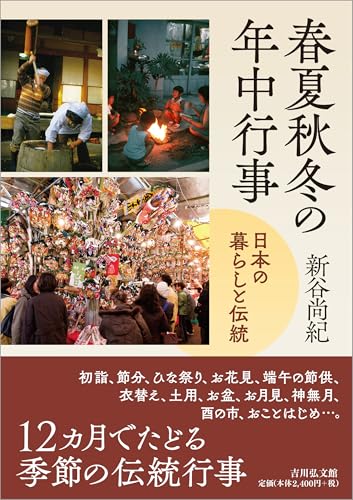解説
『失われた時を求めて フランスコミック版 花咲く乙女たちのかげに』(祥伝社)
2022年はマルセル・プルースト没後100年に当たる年。
20世紀最高で最大の小説といわれる『失われた時を求めて』。
このフランスコミック版 第2篇『花咲く乙女たちのかげに』が
第1篇『スワン家のほうへ』に続き邦訳出版されました。
この本の読みどころを、翻訳者の中条省平先生の「解説」から一部抜粋してお届けします。
この 『失われた時を求めて』のコミック版は、様々な刊本を総計してフランスだけで10万部も売れています。フランスのコミックはオールカラーで大判のハードカバー本なので、日本のマンガに比してかなり高価ですから(本書の場合、 概算で5000円超)、この売れ行きは驚きに値するものです。しかも、フランスの大学や高校でプルーストの文学を教えるために採用されたりもしました。
なぜ、これほどコミック版の『失われた時を求めて』が読者の熱心な支持を獲得し、文学教育の現場でも高く評価されたのでしょうか。
マルセル・プルーストの『失われた時を求めて』は20世紀最高の小説です。その評判を聞いて、 多くの本好きがこの小説に挑んだはずです。 しかし、この小説は20世紀最大の小説でもあるのです。実際、日本語訳の文庫版で全13巻総計7000ページ (鈴木道彦訳、集英社文庫)。 そんなわけで、私のまわりのそうとう熱心な読書家に聞いてみても、『失われた時を求めて』 の通読に挫折したという人が多いのです。
かくいう私も何度か挫折しました。
しかし、東大の大学院に進んで、高名なブロック=坂井夫人という先生の授業に出るにあたり、やはり読まねばなるまいと思い、歯を食いしばって、もちろん日本語の翻訳で(!)なんとか通読しました。 私を支えていたのは、義務感でした。
その後は、 日本語の翻訳や原書でつまみ食いならぬつまみ読みをしていますが、やはり全巻を通読したからこそ、こういう好きなように読むという方法が可能になったのだと思います。
『失われた時を求めて』 が本になる前、第1篇 『スワン家のほうへ』 の出版を打診されたオランドルフ社の編集者は、そのタイプ原稿を読んで、「ある男が眠りにつく前に、ベッドでどんなふうに寝返りを打ったかを描くのに、なぜ30ページも必要なのか理解できない」 という断り状を送ってきたのです。小説の読み巧者として有名なアンドレ・ジッドを頼りにNRF(のちのガリマール社)にもプルーストは原稿を送りますが、ジッドから拒否されてしまいます。こうしたエピソードだけで、大変な難物であるということは理解できるでしょう。
もちろん、プルーストの本当の価値は『失われた時を求めて』を全巻読んで初めて理解できるものです。 しかし、それをいうなら、フランス語の原文で読まなければ本当の味わいは分からない、ということにもなりかねません。けれども、プルーストの味わい深さは、そんなけちなものではありません。 この日本語訳のコミック版でも十分に感じとることができると確信しています。
本書では、プルーストの原文をやさしく書き直すのではなく、原文から煩瑣な枝葉をとって、すっきりと読みやすく編集してあります。 このコミック版を読めば、 絵の支えがあるために、 人物や舞台装置や出来事の具体的なイメージが立ちあがってきます。 文章もすっきりと整理されているので読みやすいし、1冊は全体で200ページちょっと。 これなら誰もがプルーストを読みとおすことができ、『失われた時を求めて』という作品の構造を明確に把握することができるでしょう。そのうえ 『失われた時を求めて』の本質は、プルーストの文章もふくめて、しっかりと保たれています。 ぜひこのコミック版で『失われた時を求めて』の困難な第一歩を乗りこえてほしいと思います。
映画監督のルキノ・ヴィスコンティは『失われた時を求めて』全巻を映画化するという壮大な計画を抱き、長大なシナリオも完成させていました(チェッキ・ダミーコとの共作で死後出版。日本では筑摩書房から刊行)。このシナリオのまさに冒頭の場面が、バルベックに向かって黒煙を吐きながら進む汽車の描写で始まっているのです。
『花咲く乙女たちのかげに』では、閉鎖的なサロンの空間から、開放された海辺へと舞台転換が行なわれて、なんとも清々(すがすが)しい気分になるのです。『失われた時を求めて』そのものは、主人公の有名な就寝のドラマで始まりますが、ヴィスコンティはあえてその常識をうち破り、『花咲く乙女たち~』の空間の開放の感動を映画の冒頭で印象づけようとしているかのようです。ヴィスコンティもまた、プルーストと同じく、『山猫』のような開放された空間と、『家族の肖像』のような閉鎖された空間の両極に心惹かれる芸術家でした。
バルベックのグランド・ホテルに到着したのち、ホテルの食堂で主人公の祖母が窓を開けてしまい、室内に空気が流れこんでブルジョワ客たちを慌てさせる場面があります。そんな大気の生々しい流れを感じさせるところに、『花咲く乙女たちのかげに』の特色があり、それは『失われた時を求めて』のなかでもほかの諸篇に見られない独自の個性です。端的に言って、読んでいて心躍る気分をいちばん強く感じるように思えます。
主人公がグランド・ホテルに到着した翌朝、海を見て感じる大いなる解放感や、浜辺で「花咲く乙女たち」と出会った瞬間の古典古代的な明澄さは、『失われた時を求めて』全体を通しても、詩的な高まりの頂点のうちに数えられるでしょう。
(本稿は『失われた時を求めて フランスコミック版 スワン家のほうへ』と『失われた時を求めて フランスコミック版 花咲く乙女たちのかげに』の「解説」から一部抜粋し編集しました)
[書き手] 中条省平
20世紀最高で最大の小説といわれる『失われた時を求めて』。
このフランスコミック版 第2篇『花咲く乙女たちのかげに』が
第1篇『スワン家のほうへ』に続き邦訳出版されました。
この本の読みどころを、翻訳者の中条省平先生の「解説」から一部抜粋してお届けします。
フランスで10万部超、大学の授業でも採用されているコミック版
本書は、マルセル・プルーストの小説『失われた時を求めて』第2篇『花咲く乙女たちのかげに』をほぼ原作に忠実にコミック化した作品です。邦訳・第1篇『スワン家のほうへ』の刊行から6年。このたび第2篇の刊行となりました。この 『失われた時を求めて』のコミック版は、様々な刊本を総計してフランスだけで10万部も売れています。フランスのコミックはオールカラーで大判のハードカバー本なので、日本のマンガに比してかなり高価ですから(本書の場合、 概算で5000円超)、この売れ行きは驚きに値するものです。しかも、フランスの大学や高校でプルーストの文学を教えるために採用されたりもしました。
なぜ、これほどコミック版の『失われた時を求めて』が読者の熱心な支持を獲得し、文学教育の現場でも高く評価されたのでしょうか。
マルセル・プルーストの『失われた時を求めて』は20世紀最高の小説です。その評判を聞いて、 多くの本好きがこの小説に挑んだはずです。 しかし、この小説は20世紀最大の小説でもあるのです。実際、日本語訳の文庫版で全13巻総計7000ページ (鈴木道彦訳、集英社文庫)。 そんなわけで、私のまわりのそうとう熱心な読書家に聞いてみても、『失われた時を求めて』 の通読に挫折したという人が多いのです。
かくいう私も何度か挫折しました。
しかし、東大の大学院に進んで、高名なブロック=坂井夫人という先生の授業に出るにあたり、やはり読まねばなるまいと思い、歯を食いしばって、もちろん日本語の翻訳で(!)なんとか通読しました。 私を支えていたのは、義務感でした。
その後は、 日本語の翻訳や原書でつまみ食いならぬつまみ読みをしていますが、やはり全巻を通読したからこそ、こういう好きなように読むという方法が可能になったのだと思います。
多くの人が、最初の『スワン家のほうへ』で挫折してしまう
通読できなかったという人たちによく聞いてみると、大半は1巻目の『スワン家のほうへ』で挫折しているようです。 しかも、数十ページで諦め、もう一生読むことはないと誓ったという人もいます。これは日本だけの話ではありません。『失われた時を求めて』 が本になる前、第1篇 『スワン家のほうへ』 の出版を打診されたオランドルフ社の編集者は、そのタイプ原稿を読んで、「ある男が眠りにつく前に、ベッドでどんなふうに寝返りを打ったかを描くのに、なぜ30ページも必要なのか理解できない」 という断り状を送ってきたのです。小説の読み巧者として有名なアンドレ・ジッドを頼りにNRF(のちのガリマール社)にもプルーストは原稿を送りますが、ジッドから拒否されてしまいます。こうしたエピソードだけで、大変な難物であるということは理解できるでしょう。
この人類文化の宝物を読まないままでいるのはもったいない
しかし、 『失われた時を求めて』という人類文化の宝物を、この早い挫折で放りだしてしまうのは、あまりにももったいないことです! ここには人間が到達した芸術的真実のひとつの極限があるからです。なんとかそのエッセンスを伝えることができないだろうか、というのは、プルースト愛好家の抱く夢のようです。もちろん、プルーストの本当の価値は『失われた時を求めて』を全巻読んで初めて理解できるものです。 しかし、それをいうなら、フランス語の原文で読まなければ本当の味わいは分からない、ということにもなりかねません。けれども、プルーストの味わい深さは、そんなけちなものではありません。 この日本語訳のコミック版でも十分に感じとることができると確信しています。
本書では、プルーストの原文をやさしく書き直すのではなく、原文から煩瑣な枝葉をとって、すっきりと読みやすく編集してあります。 このコミック版を読めば、 絵の支えがあるために、 人物や舞台装置や出来事の具体的なイメージが立ちあがってきます。 文章もすっきりと整理されているので読みやすいし、1冊は全体で200ページちょっと。 これなら誰もがプルーストを読みとおすことができ、『失われた時を求めて』という作品の構造を明確に把握することができるでしょう。そのうえ 『失われた時を求めて』の本質は、プルーストの文章もふくめて、しっかりと保たれています。 ぜひこのコミック版で『失われた時を求めて』の困難な第一歩を乗りこえてほしいと思います。
ヴィスコンティが描きたかった、『花咲く乙女たちのかげに』の清々しさ
さて、『失われた時を求めて』が、第2篇『花咲く乙女たちのかげに』の第2部「土地の名―土地」に入ると、舞台も雰囲気も『スワン家のほうへ』とはがらりと一転します。舞台はパリの閉鎖的な社交界から、旅先の海水浴地であるバルベックへと移ります。映画監督のルキノ・ヴィスコンティは『失われた時を求めて』全巻を映画化するという壮大な計画を抱き、長大なシナリオも完成させていました(チェッキ・ダミーコとの共作で死後出版。日本では筑摩書房から刊行)。このシナリオのまさに冒頭の場面が、バルベックに向かって黒煙を吐きながら進む汽車の描写で始まっているのです。
『花咲く乙女たちのかげに』では、閉鎖的なサロンの空間から、開放された海辺へと舞台転換が行なわれて、なんとも清々(すがすが)しい気分になるのです。『失われた時を求めて』そのものは、主人公の有名な就寝のドラマで始まりますが、ヴィスコンティはあえてその常識をうち破り、『花咲く乙女たち~』の空間の開放の感動を映画の冒頭で印象づけようとしているかのようです。ヴィスコンティもまた、プルーストと同じく、『山猫』のような開放された空間と、『家族の肖像』のような閉鎖された空間の両極に心惹かれる芸術家でした。
バルベックのグランド・ホテルに到着したのち、ホテルの食堂で主人公の祖母が窓を開けてしまい、室内に空気が流れこんでブルジョワ客たちを慌てさせる場面があります。そんな大気の生々しい流れを感じさせるところに、『花咲く乙女たちのかげに』の特色があり、それは『失われた時を求めて』のなかでもほかの諸篇に見られない独自の個性です。端的に言って、読んでいて心躍る気分をいちばん強く感じるように思えます。
主人公がグランド・ホテルに到着した翌朝、海を見て感じる大いなる解放感や、浜辺で「花咲く乙女たち」と出会った瞬間の古典古代的な明澄さは、『失われた時を求めて』全体を通しても、詩的な高まりの頂点のうちに数えられるでしょう。
(本稿は『失われた時を求めて フランスコミック版 スワン家のほうへ』と『失われた時を求めて フランスコミック版 花咲く乙女たちのかげに』の「解説」から一部抜粋し編集しました)
[書き手] 中条省平
ALL REVIEWSをフォローする