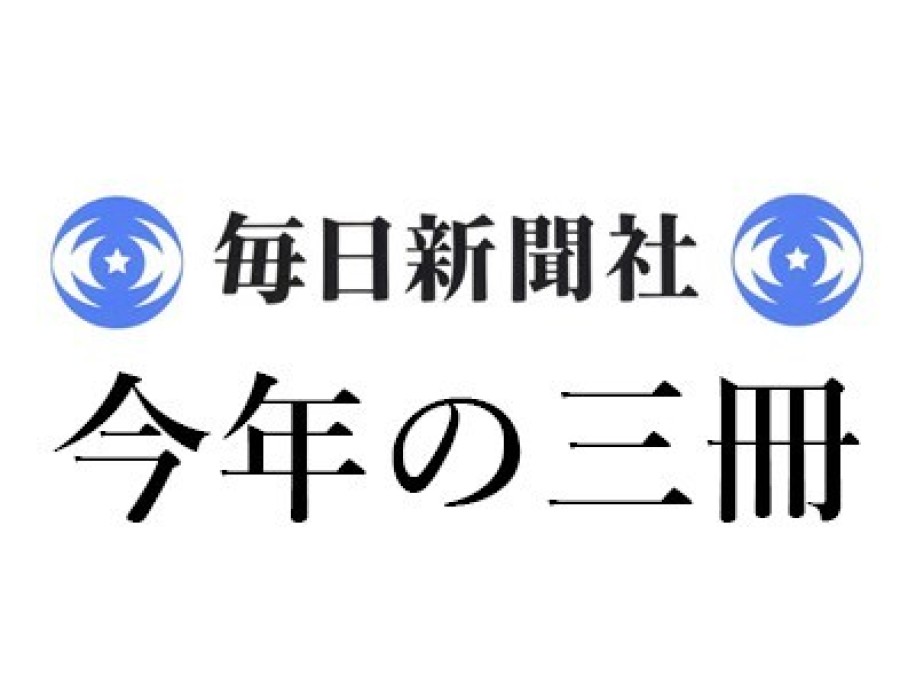書評
『薬物戦争の終焉――自律した大人のための薬物論』(みすず書房)
厳罰主義が招く負の連鎖 正しい情報は
衝撃的な書物である。著者は名門コロンビア大学の心理学部・精神医学部教授にして依存症の神経科学の研究者として知られる。彼は現役のヘロインユーザーでもあり、鎮痛薬のオピオイドは幸福感をもたらす薬物として群をぬいており、彼自身は責任ある大人として、依存症をはじめ薬物の問題を抱えたことが一度もないと断言する。彼はこう主張する。「ほとんどの薬物は使用しても、もたらされる害はほとんどゼロ(中略)人々の健康と社会生活に有益な影響をもたらすこともある」と。いやいや、そんなわけあるか。そんなら僕の愛するジャニス・ジョプリンは、リヴァー・フェニックスは、ヒース・レジャーは、プリンスは、なぜ死ななければならなかった? ドラッグ以外の何が彼らを殺したというの? しかしハートは冷静に指摘する。それはドラッグそのものよりも混入物の問題だ。ドラッグを合法化してきちんと品質管理していれば済む話なのだ、と。
ある程度薬物問題に関心のある人なら、ここでまず「大麻合法化」や「ハームリダクション」といった言葉を連想するだろう。しかしハートの主張はさらに過激だ。彼は大麻はおろか、すべての薬物の非犯罪化を主張し、ハームリダクションには批判的だ。ハームリダクションという言葉は薬物と有害性を強く結びつけ、薬物使用者を劣った存在に貶(おとし)めてしまう。彼は薬物使用者の健康と幸福を支持すべく、用量、摂取方法、セット(摂取する個人の状況)、セッティング(摂取する場面、環境など)についてのアドバイスが必要であるとする。
あるいはフェンタニルのように、トランプの関税政策の根拠にもなった「史上最悪の麻薬」の問題はどうなのか。ハートは薬物についての知識不足が問題であると指摘する。現実的な解決策として、政府が無料かつ匿名の薬物安全性検査を提供すべしと主張する。これは薬物のサンプルを提供すれば、ただちに成分や含有量の情報を教えてくれるサービスで、ポルトガルやスペインなどではすでに導入済みという。なぜアメリカではそれが難しいのか。
薬物問題の歴史には、階級や人種を巡る価値観が色濃く反映されている。本書で繰り返し指摘されているように、黒人の薬物使用は、白人よりも高い確率で犯罪として処遇される。例えば白人が使用するパウダー・コカインと黒人が使用するクラック・コカインは、同一成分であるにもかかわらず、クラック密売の量刑の方が百倍重くなる。あるいはPCP(フェンシクリジン)。一九九二年のロサンゼルス暴動の発端となった前年のロドニー・キングの事件では、PCPがもたらす暴力性が問題視された。背景にあるのは「PCPに狂った黒人」という、事実無根の都市伝説めいたイメージだった。
カール・エリック・フィッシャー『依存症と人類』(みすず書房)によれば、この傾向の発端は、連邦麻薬局の初代局長、ハリー・アンスリンガーが主導した厳罰主義である。日本もアメリカに追随するかのように「ダメ、ゼッタイ」の厳罰主義をとり続けている。厳罰主義の何が問題か。この主義のもとで薬物の売買や所持は犯罪化される。刑事罰を受けた少年の再犯リスクは格段に高くなる。薬物の使用が倫理的に堕落した行為と捉えられ、使用者は社会的に孤立しやすくなり、孤立は依存症のリスクを高める。さらに人種の問題がここに加わる。黒人の検挙率は高く、前科によって社会から排除された黒人がありつける仕事は薬物の密売くらいしかなくなる。密売ゆえに薬物の品質は低下し健康被害が出る。監修者の松本俊彦が指摘するように、薬物規制法は合法的な人種差別システムになってしまっているのだ。厳罰主義は、中流以上の階層にとっては社会防衛的な意義を持つかもしれないが、それは黒人が多くを占める貧困層の人々の依存症リスクと高めることとトレードオフの関係にあるのかもしれない。
本書の重要性を正しく受け止めるためにも、懸念をひとつ表明しておこう。ハートは現行の薬物政策の問題を強調するあまり、例えばヘロインの危険性を過小評価しているかもしれない。ヘロインの強い依存性や急性リスク(過剰摂取死、感染症など)についてはすでに頑健なエビデンスがあり、それはハートが批判するNIDA(米国国立薬物乱用研究所)の調査研究以外にも、CDC(米国疾病予防管理センター)やWHOによるガイドラインなど信頼性の高い文献が多数存在する。
そうした意味で、本書は薬物を巡る価値観を一八〇度ひっくり返す類いの書物ではない。行き過ぎた厳罰主義を緩和すること。現実に多くの人々が、コカインやヘロインや覚せい剤など、禁止薬物を安全に用い、依存症になることもなく平穏で快適な日々を送っている事実を受け容れること。そして正しい情報にもとづいて、薬物を巡る不毛な戦争を終わらせること。社会全体の「健康と幸福」を高めるであろう彼の提言は、あたかも「愛」と同様に、薬物を適切に用いよという、きわめて穏健な主張なのである。
ALL REVIEWSをフォローする