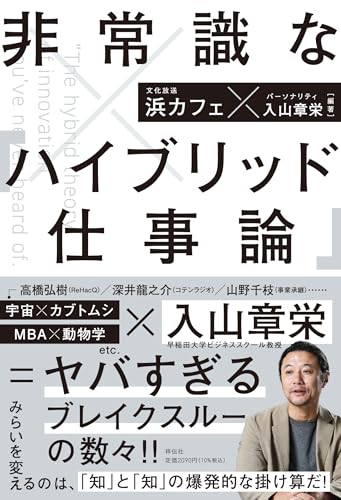前書き
『家族は知らない真夜中の老人ホームーーやりきれなさの現場から』(祥伝社)
介護者の不足や老人ホームでの虐待に関する報道が続き、自身や両親の老人ホーム入居について、不安や迷いを感じる方も多いのではないでしょうか。
メーター検針員としての就労記『メーター検針員テゲテゲ日記』で話題となった著者、川島徹さんが、検針員を辞めた後10年間働いた老人ホーム夜勤者の経験をまとめた『家族は知らない真夜中の老人ホーム』を出版。入居者たちの多彩な人生最後の物語から施設スタッフの過酷な就労状況まで、他では知れない老人ホームのリアルな姿を、どこかユーモラスで温かみのある視線で描き出します。
今回、この本の中から「まえがき」を全文公開してお届けします。
イラッとする。
Aさんのトイレである。
これで20回目のトイレ。夜明けまでにはあと10回は行かれる。
しかもおちんちんをちょろっと出しておられるので歩きながら廊下を濡らされる。
ときには洗面台の流しに放尿される。
夜勤者はたまったものではない。
ひと晩に30回仮眠から起こされ、30回廊下の拭き掃除をさせられるのである。
注意すると杖を振りまわされ殴られかねない。
認知症のお年寄りの介護の現場である。
わたしが介護の仕事を始めたのは60歳のときだった。
それまで10年間働いていた電気メーターの検針の仕事をクビになった。
その詳細は『メーター検針員テゲテゲ日記』(三五館シンシャ)に書いた。
60歳、まだ若い。遊び暮らしてなどいたくなかった。仕事の緊張感がないと生活のリズムを失ってしまう。それに遊び暮らしている余裕はなかった。作家になりたいという途方もない夢を追って、40代半ばで会社を辞めたこともあり年金だけでは生活できなかった。わたしは贅沢をするつもりはないが、多少のお金は必要だった。
ハローワークの仕事を検索すると介護の仕事がつぎつぎに出てきた。
夜勤だとひと晩で1万円、高いところは1万5千円。作家になるという夢はまだ諦めてはいなかった。夜勤だと人間関係に煩わされることはないだろう。それに夜中に本が読めるかもしれない。
そんな不埒な動機で、わたしはあるグループホームの夜勤の仕事を始めた。
そこを皮切りに70歳まで10年間、8カ所あまりの老人ホームを転々とした。
10年間、真夜中の老人ホームを見てきた。
その経験を書いたのが本書である。
介護保険法は2000年に施行されたばかりである。
そして戦後のベビーブーム世代が介護される年齢になり、介護施設は雨後の筍のごとく造られている。
しかし介護の現場は典型的な3K、4Kである。
きつい、汚い、給与が安い。希望が持てる職場ではない。
世間の人手不足もあり、働き手がいない。
2025年には30万人あまりの介護者が不足するとの予測がなされている。
そのこともあり、介護職は引く手あまたの職業となった。
それゆえ未成熟な介護者が多い、といえるかもしれない。
わたし自身仕事を始めたとき介護のことはなにも知らなかった。
グループホームと特別養護老人ホームの区別もつかなかった。
いまや介護に関する本がたくさん書かれている。
老人ホームの経営の仕方、その選び方から、さらには老人ホームの闇の部分が暴かれるようになった。事実、老人ホームにおける事故、事件がニュースになるようになった。虐待、さらにはお年寄りが老人ホームで殺される事件まで報道されるようになった。
もちろん老人ホームにはほのぼのとした物語もあった。
わたしもそうした場面を望んだ。
が、老人ホーム、そこは人生最後の物語の場である。
そこで人はみんな自分の健康との闘いに臨まなくてはならない。
そしてその闘いに負けてこの世を去っていかなければならない。
人生最後の物語が混乱や無力さに満ちているのはいたしかたないことだろう。
ちびまる子ちゃんの友蔵さんのようにほのぼのとした物語などめったにないのはいたしかたないことだろう。
この本でわたしは夜勤者として見た介護の現場を書いた。
わたしは介護の専門家ではない。ただ夜勤者として週2回10年間働いてきただけである。たまたまわたしが経験したことを書いただけであり、本書が老人ホームのすべてを物語っているわけではない。
みんなが寝静まった真夜中にどんな物語があっただろうか。
イレズミ男もいれば刑務所帰りの女性もいた。元歯科医もいれば認知症の女性に恋した元社長もいた。
彼らの人生の最後の物語が、みんなが寝静まった真夜中だからこそわたしには見えたように思う。
なお、この本は読みやすいように小説に近い文体で書いてあるが、書いてあることは事実である。
「事実をして語らしめよ」(柏耕一『交通誘導員ヨレヨレ日記』三五館シンシャ)の名言をいつも手元に書いたものである。
ただし、本書に登場する人物および施設名はすべて仮名としている。また、個人を特定されないよう、記述の本質を損なわない範囲で性別・職業・年齢などを改変してある。
[書き手]川島 徹
メーター検針員としての就労記『メーター検針員テゲテゲ日記』で話題となった著者、川島徹さんが、検針員を辞めた後10年間働いた老人ホーム夜勤者の経験をまとめた『家族は知らない真夜中の老人ホーム』を出版。入居者たちの多彩な人生最後の物語から施設スタッフの過酷な就労状況まで、他では知れない老人ホームのリアルな姿を、どこかユーモラスで温かみのある視線で描き出します。
今回、この本の中から「まえがき」を全文公開してお届けします。
老人ホーム、そこは人生最後の物語の場
仮眠をしている耳にゴトゴトと音がした。イラッとする。
Aさんのトイレである。
これで20回目のトイレ。夜明けまでにはあと10回は行かれる。
しかもおちんちんをちょろっと出しておられるので歩きながら廊下を濡らされる。
ときには洗面台の流しに放尿される。
夜勤者はたまったものではない。
ひと晩に30回仮眠から起こされ、30回廊下の拭き掃除をさせられるのである。
注意すると杖を振りまわされ殴られかねない。
認知症のお年寄りの介護の現場である。
わたしが介護の仕事を始めたのは60歳のときだった。
それまで10年間働いていた電気メーターの検針の仕事をクビになった。
その詳細は『メーター検針員テゲテゲ日記』(三五館シンシャ)に書いた。
60歳、まだ若い。遊び暮らしてなどいたくなかった。仕事の緊張感がないと生活のリズムを失ってしまう。それに遊び暮らしている余裕はなかった。作家になりたいという途方もない夢を追って、40代半ばで会社を辞めたこともあり年金だけでは生活できなかった。わたしは贅沢をするつもりはないが、多少のお金は必要だった。
ハローワークの仕事を検索すると介護の仕事がつぎつぎに出てきた。
夜勤だとひと晩で1万円、高いところは1万5千円。作家になるという夢はまだ諦めてはいなかった。夜勤だと人間関係に煩わされることはないだろう。それに夜中に本が読めるかもしれない。
そんな不埒な動機で、わたしはあるグループホームの夜勤の仕事を始めた。
そこを皮切りに70歳まで10年間、8カ所あまりの老人ホームを転々とした。
10年間、真夜中の老人ホームを見てきた。
その経験を書いたのが本書である。
介護保険法は2000年に施行されたばかりである。
そして戦後のベビーブーム世代が介護される年齢になり、介護施設は雨後の筍のごとく造られている。
しかし介護の現場は典型的な3K、4Kである。
きつい、汚い、給与が安い。希望が持てる職場ではない。
世間の人手不足もあり、働き手がいない。
2025年には30万人あまりの介護者が不足するとの予測がなされている。
そのこともあり、介護職は引く手あまたの職業となった。
それゆえ未成熟な介護者が多い、といえるかもしれない。
わたし自身仕事を始めたとき介護のことはなにも知らなかった。
グループホームと特別養護老人ホームの区別もつかなかった。
いまや介護に関する本がたくさん書かれている。
老人ホームの経営の仕方、その選び方から、さらには老人ホームの闇の部分が暴かれるようになった。事実、老人ホームにおける事故、事件がニュースになるようになった。虐待、さらにはお年寄りが老人ホームで殺される事件まで報道されるようになった。
もちろん老人ホームにはほのぼのとした物語もあった。
わたしもそうした場面を望んだ。
が、老人ホーム、そこは人生最後の物語の場である。
そこで人はみんな自分の健康との闘いに臨まなくてはならない。
そしてその闘いに負けてこの世を去っていかなければならない。
人生最後の物語が混乱や無力さに満ちているのはいたしかたないことだろう。
ちびまる子ちゃんの友蔵さんのようにほのぼのとした物語などめったにないのはいたしかたないことだろう。
この本でわたしは夜勤者として見た介護の現場を書いた。
わたしは介護の専門家ではない。ただ夜勤者として週2回10年間働いてきただけである。たまたまわたしが経験したことを書いただけであり、本書が老人ホームのすべてを物語っているわけではない。
みんなが寝静まった真夜中にどんな物語があっただろうか。
イレズミ男もいれば刑務所帰りの女性もいた。元歯科医もいれば認知症の女性に恋した元社長もいた。
彼らの人生の最後の物語が、みんなが寝静まった真夜中だからこそわたしには見えたように思う。
なお、この本は読みやすいように小説に近い文体で書いてあるが、書いてあることは事実である。
「事実をして語らしめよ」(柏耕一『交通誘導員ヨレヨレ日記』三五館シンシャ)の名言をいつも手元に書いたものである。
ただし、本書に登場する人物および施設名はすべて仮名としている。また、個人を特定されないよう、記述の本質を損なわない範囲で性別・職業・年齢などを改変してある。
[書き手]川島 徹
ALL REVIEWSをフォローする