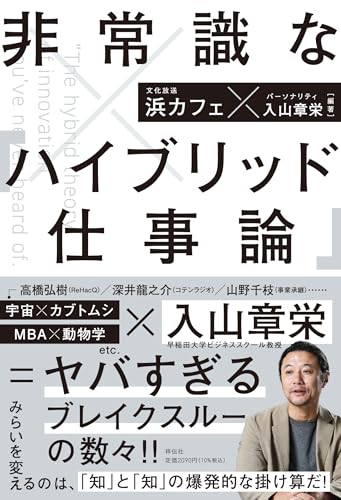内容紹介
『非常識な「ハイブリッド仕事論」』(祥伝社)
経営学の第一人者として知られる入山章栄早稲田大学ビジネススクール教授が、ビジネス、アカデミズムのフロントランナー、異端児と仕事、組織、ビジョン、そしてイノベーションの未来について熱く語り合う文化放送「浜松町イノベーションカルチャーカフェ」、通称浜カフェ。6年間におよぶ放送から選りすぐりの10回に、入山教授の解説を新たに加えた話題の書、それが『非常識な「ハイブリッド仕事論」』です。今回、この本より一部を抜粋してお届けします。
これからの時代は、圧倒的に変化が激しい。新型コロナウイルスを経てもなお、経済の不安定化は収束しておらず、加えて雇用の流動化が進み、多くの企業が困難に直面している。
とりわけ、ChatGPTに象徴される生成AIの出現は、仕事のあり方そのものを根底から揺さぶっている。オックスフォード大学のマイケル・オズボーン教授は2013年に「今後、10〜20年でアメリカにおける雇用の47%がAIに代替される」という論文を発表し、世界的な注目を集めた。だが実際には、将来的に60〜70%の仕事がAIに奪われる可能性すらあるのではないか、と私は考えている。
この時代において、日本人すべてに求められているのが「個人のイノベーション」である。イノベーションとは、突き詰めればすべて人の発想力から生まれるものだ。実際、世の中には、ときに突飛なアイデアを思いつき、それを実行に移してしまう人物がいる。その結果、キャリアとして大成功を収める者もいる。ソフトバンクの孫正義氏、スティーブ・ジョブズ氏、近年であればイーロン・マスク氏などが代表例であろう。
しかしこれからは、孫氏やジョブズ氏のような“超人”だけでなく、われわれのような一般人にとっても「新しい着想」は必要不可欠だ。なぜなら誰もが変化が激しく、そしてAIに仕事が奪われる時代に、否応なく直面しているからである。
したがって、これからキャリアを築いていくためには、一人ひとりが自らの発想で、新しい挑戦に踏み出していくしかない。大企業の管理職であれ、中小企業の経営者であれ、現場の社員であれ、個人事業主であれ、あるいは学校の教員や公務員であれ、これは誰にとっても変わることがない事実だろう。
では、その「発想力」はどこから生まれるのか。それは、間違いなく「知の探索」(=ハイブリッド思考)だ。そもそも新しいアイデアとは、既存の知と既存の知を新たに組み合わせることでしか生まれない。人はゼロから何も生み出せないのであり、ゼロに何を掛けてもゼロにしかならない。
本書を手に取った皆さんも「新しい発想が浮かんだ」と感じた経験があるかもしれないが、そのときは知らず知らずに、まだ結びついていない「知」と「知」を組み合わせているのだ。
たとえば、ある企画が途中で頓挫したとして、「では、今度はこの企画を別の顧客と組み合わせてみよう」といった「企画と顧客の新しい組み合わせ」が一例だ。あるいは、メーカーで素材開発が止まってしまったなら、「では、別の最終製品のアイデアとこの素材を組み合わせてみよう」という「素材と製品の新しい組み合わせ」なども典型だ。
この思考法は、イノベーションの父と呼ばれた経済学者ジョセフ・シュンペーターが、100年近く前に“New Combination(新結合)”として提唱したものであり、いまなお世界のイノベーション研究の根本原理なのだ。
しかし、人には認知の限界がある。平たく言えば、脳のキャパシティに限界があるわけだ。そのため、人は遠くの知を見通すことが難しく、目の前の認知できる知だけを組み合わせがちになる。ところが、目の前の知の組み合わせはすでに試され尽くしているので、やがて枯渇してしまうのである。
現在、日本でイノベーションが不足している理由のひとつは、多くの企業が創業から何十年も経過しており、同じ業界、同じ場所で、同じような人々が長期間働き続けていることにある。結果として、目の前の知の組み合わせが何度も試し尽くされ、新たなイノベーションが生まれにくくなっているのだ。
個人のキャリアも同様だ。長らく日本では固定的な雇用慣行が続き、ひとりの人間が多様で幅広い知見を得る機会は限られていた。もちろん「この道一筋」のキャリアを否定する意図はない。しかし、変化の激しいこの時代においては、ひとつの専門性だけでなく、それを異なる分野の知見・アイデアと組み合わせることが不可欠なのである。
これこそが「知の探索」(=ハイブリッド思考)である。この考え方は、アメリカやヨーロッパを中心としたイノベーション研究の分野において、きわめて重要な概念だ。しかし日本のビジネス界では、長らく知の探索の重要性が軽視されてきた。
とはいえ、私が十数年前にアメリカから日本に帰国し、「知の探索」「両利きの経営」といった言葉を提起するようになって、少しずつではあるがビジネス界でこの考え方が浸透しつつある。実際、いまでは多くの企業の経営会議で、これらの用語が使われるようになっているようだ。
では、本書を手に取った皆さんが、これからのキャリアのために「知と知の組み合わせ」を試みるために、まず知っていただきたいことは何だろうか。それは、「離れた知と知」の突飛な組み合わせが実に面白い、ということなのだ。意外な組み合わせにも、実は驚くような共通点があったり、そこからまったく新しい視点が生まれたりする。
読者のなかには、「離れた知と自分の知を、どう組み合わせればよいのか?」と戸惑う方もいるだろう。しかし重要なのは、まずは「面白い」と感じた組み合わせを、楽しんでみることなのだ。楽しむからこそ継続でき、継続するからこそ新しいアイデアが生まれ、それが結果として新たな仕事の可能性やキャリア形成に資するのである。
この目的のもとに企画されたのが、私がパーソナリティを務める文化放送のラジオ番組「浜松町イノベーション・カルチャーカフェ」(通称「浜カフェ」)である。この番組は単なるラジオ番組ではなく、ひとつの「知の探索プロジェクト」として始まった。異分野からユニークで突き抜けたふたりをゲストとして招き、まったく異なる知見を掛け合わせるという試みである。
番組の発案者は、文化放送の当時のプロデューサー・村田武之氏である。2019年に村田氏の掛け声でスタートし、私に加えて、スタートアップのPRをプロフェッショナルで手がける田ケ原恵美氏(通称:たがえみちゃん)が番組開始以来アシスタントとして参加してくれている。現在では、文化放送の毎週月曜夜7時に放送される人気番組として定着しており、ポッドキャスト配信も多くの聴取者を獲得している。
番組に登場するゲストは、まさに“変わった組み合わせ”の方々ばかりである。たとえば本書の「02」では、「宇宙ビジネスの専門家」石田真康氏と「カブトムシの専門家」石田陽佑氏をゲストに迎えた放送を文章化している。カブトムシと宇宙ビジネス――この組み合わせでゲストを招く番組が、ほかにあるだろうか。
また「03」では、「雑草の専門家」静岡大学の稲垣栄洋教授と「事業承継の専門家」山野千枝氏を招き、知の掛け合わせを展開している。「04」は「MBA」と「動物学」で、「08」は「大企業」×「発酵」×「人材育成」だ。このような突飛な組み合わせを試みているラジオ番組は、日本広しといえどもほかにないだろう。
そして、こうした離れた知の組み合わせ・ハイブリッドこそが、さらに強烈な発想や視点を生む。正直なところ、プロデューサーの村田氏からあまりにも突飛な組み合わせ案を提示されたときには、私も「さすがにムリではないか」と思うこともある。しかし、私は幸いなことに、人の話を引き出すのが比較的得意であり、そこにアシスタントのたがえみちゃんの鋭い切り込みが加わることで、番組は毎回大いに盛り上がる。
出演者のほぼ全員から「とても楽しかった」「もっと話したかった」と言っていただけるのも、この番組の大きな魅力のひとつだ。
本書を手に取った皆さんには、気になる項目からでいいので読んでいただき、離れた知と知のハイブリッドがもたらす知的な興奮、面白さを味わっていただきたい。そして、そうした会話のなかにこそ、変化の激しく不確実な時代において、新しい仕事の仕方やキャリアを切り拓くヒントが詰まっていることを実感していただきたい。
今後、AIに仕事を代替される時代が訪れるなか、現状維持を好み、過去のやり方に固執することは、もはやリスクでしかない。これからは誰もが離れた知と知をハイブリッド化させ、自らの手で新しいアイデアを創出し、自分自身に小さくてもいいので変化をもたらしていく時代である。そうでなければ、これからの皆さんの仕事は、きわめて困難なものになるだろう。
その意味でも大切なのは、とにかく「知の掛け合わせ」を楽しむことだ。そして本書ほど、その出発点となる刺激を与えてくれる一冊はほかにない。本書を通じて、離れた分野の人々による「ハイブリッド対話」の面白さを味わい、それが皆さんの仕事やキャリアにとって小さな前進のきっかけとなれば、このラジオ番組を長らくやってきた者として、これ以上の喜びはない。
では、10組の「ヤバい知の組み合わせ」をご堪能いただきたい。
[書き手]入山章栄
本書を手にされた方へ
本書は、通常では決して出会うことのないような、突き抜けた活動をしている異分野のふたりを引き合わせ、まったく異なる「知」と「知」の掛け算、すなわち「知のハイブリッド化」によって、さらに突き抜けた知見を引き出していく――「知の探索プロジェクト」を書籍化したものだ。本書を通じて、かけ離れた知を交流させるハイブリッド思考が、これからのビジネスパーソンや社会人(あるいは学生)にとって、いかに重要かを感じていただきたい。これからの時代は、圧倒的に変化が激しい。新型コロナウイルスを経てもなお、経済の不安定化は収束しておらず、加えて雇用の流動化が進み、多くの企業が困難に直面している。
とりわけ、ChatGPTに象徴される生成AIの出現は、仕事のあり方そのものを根底から揺さぶっている。オックスフォード大学のマイケル・オズボーン教授は2013年に「今後、10〜20年でアメリカにおける雇用の47%がAIに代替される」という論文を発表し、世界的な注目を集めた。だが実際には、将来的に60〜70%の仕事がAIに奪われる可能性すらあるのではないか、と私は考えている。
この時代において、日本人すべてに求められているのが「個人のイノベーション」である。イノベーションとは、突き詰めればすべて人の発想力から生まれるものだ。実際、世の中には、ときに突飛なアイデアを思いつき、それを実行に移してしまう人物がいる。その結果、キャリアとして大成功を収める者もいる。ソフトバンクの孫正義氏、スティーブ・ジョブズ氏、近年であればイーロン・マスク氏などが代表例であろう。
しかしこれからは、孫氏やジョブズ氏のような“超人”だけでなく、われわれのような一般人にとっても「新しい着想」は必要不可欠だ。なぜなら誰もが変化が激しく、そしてAIに仕事が奪われる時代に、否応なく直面しているからである。
したがって、これからキャリアを築いていくためには、一人ひとりが自らの発想で、新しい挑戦に踏み出していくしかない。大企業の管理職であれ、中小企業の経営者であれ、現場の社員であれ、個人事業主であれ、あるいは学校の教員や公務員であれ、これは誰にとっても変わることがない事実だろう。
では、その「発想力」はどこから生まれるのか。それは、間違いなく「知の探索」(=ハイブリッド思考)だ。そもそも新しいアイデアとは、既存の知と既存の知を新たに組み合わせることでしか生まれない。人はゼロから何も生み出せないのであり、ゼロに何を掛けてもゼロにしかならない。
本書を手に取った皆さんも「新しい発想が浮かんだ」と感じた経験があるかもしれないが、そのときは知らず知らずに、まだ結びついていない「知」と「知」を組み合わせているのだ。
たとえば、ある企画が途中で頓挫したとして、「では、今度はこの企画を別の顧客と組み合わせてみよう」といった「企画と顧客の新しい組み合わせ」が一例だ。あるいは、メーカーで素材開発が止まってしまったなら、「では、別の最終製品のアイデアとこの素材を組み合わせてみよう」という「素材と製品の新しい組み合わせ」なども典型だ。
この思考法は、イノベーションの父と呼ばれた経済学者ジョセフ・シュンペーターが、100年近く前に“New Combination(新結合)”として提唱したものであり、いまなお世界のイノベーション研究の根本原理なのだ。
しかし、人には認知の限界がある。平たく言えば、脳のキャパシティに限界があるわけだ。そのため、人は遠くの知を見通すことが難しく、目の前の認知できる知だけを組み合わせがちになる。ところが、目の前の知の組み合わせはすでに試され尽くしているので、やがて枯渇してしまうのである。
現在、日本でイノベーションが不足している理由のひとつは、多くの企業が創業から何十年も経過しており、同じ業界、同じ場所で、同じような人々が長期間働き続けていることにある。結果として、目の前の知の組み合わせが何度も試し尽くされ、新たなイノベーションが生まれにくくなっているのだ。
個人のキャリアも同様だ。長らく日本では固定的な雇用慣行が続き、ひとりの人間が多様で幅広い知見を得る機会は限られていた。もちろん「この道一筋」のキャリアを否定する意図はない。しかし、変化の激しいこの時代においては、ひとつの専門性だけでなく、それを異なる分野の知見・アイデアと組み合わせることが不可欠なのである。
これこそが「知の探索」(=ハイブリッド思考)である。この考え方は、アメリカやヨーロッパを中心としたイノベーション研究の分野において、きわめて重要な概念だ。しかし日本のビジネス界では、長らく知の探索の重要性が軽視されてきた。
とはいえ、私が十数年前にアメリカから日本に帰国し、「知の探索」「両利きの経営」といった言葉を提起するようになって、少しずつではあるがビジネス界でこの考え方が浸透しつつある。実際、いまでは多くの企業の経営会議で、これらの用語が使われるようになっているようだ。
では、本書を手に取った皆さんが、これからのキャリアのために「知と知の組み合わせ」を試みるために、まず知っていただきたいことは何だろうか。それは、「離れた知と知」の突飛な組み合わせが実に面白い、ということなのだ。意外な組み合わせにも、実は驚くような共通点があったり、そこからまったく新しい視点が生まれたりする。
読者のなかには、「離れた知と自分の知を、どう組み合わせればよいのか?」と戸惑う方もいるだろう。しかし重要なのは、まずは「面白い」と感じた組み合わせを、楽しんでみることなのだ。楽しむからこそ継続でき、継続するからこそ新しいアイデアが生まれ、それが結果として新たな仕事の可能性やキャリア形成に資するのである。
この目的のもとに企画されたのが、私がパーソナリティを務める文化放送のラジオ番組「浜松町イノベーション・カルチャーカフェ」(通称「浜カフェ」)である。この番組は単なるラジオ番組ではなく、ひとつの「知の探索プロジェクト」として始まった。異分野からユニークで突き抜けたふたりをゲストとして招き、まったく異なる知見を掛け合わせるという試みである。
番組の発案者は、文化放送の当時のプロデューサー・村田武之氏である。2019年に村田氏の掛け声でスタートし、私に加えて、スタートアップのPRをプロフェッショナルで手がける田ケ原恵美氏(通称:たがえみちゃん)が番組開始以来アシスタントとして参加してくれている。現在では、文化放送の毎週月曜夜7時に放送される人気番組として定着しており、ポッドキャスト配信も多くの聴取者を獲得している。
番組に登場するゲストは、まさに“変わった組み合わせ”の方々ばかりである。たとえば本書の「02」では、「宇宙ビジネスの専門家」石田真康氏と「カブトムシの専門家」石田陽佑氏をゲストに迎えた放送を文章化している。カブトムシと宇宙ビジネス――この組み合わせでゲストを招く番組が、ほかにあるだろうか。
また「03」では、「雑草の専門家」静岡大学の稲垣栄洋教授と「事業承継の専門家」山野千枝氏を招き、知の掛け合わせを展開している。「04」は「MBA」と「動物学」で、「08」は「大企業」×「発酵」×「人材育成」だ。このような突飛な組み合わせを試みているラジオ番組は、日本広しといえどもほかにないだろう。
そして、こうした離れた知の組み合わせ・ハイブリッドこそが、さらに強烈な発想や視点を生む。正直なところ、プロデューサーの村田氏からあまりにも突飛な組み合わせ案を提示されたときには、私も「さすがにムリではないか」と思うこともある。しかし、私は幸いなことに、人の話を引き出すのが比較的得意であり、そこにアシスタントのたがえみちゃんの鋭い切り込みが加わることで、番組は毎回大いに盛り上がる。
出演者のほぼ全員から「とても楽しかった」「もっと話したかった」と言っていただけるのも、この番組の大きな魅力のひとつだ。
本書を手に取った皆さんには、気になる項目からでいいので読んでいただき、離れた知と知のハイブリッドがもたらす知的な興奮、面白さを味わっていただきたい。そして、そうした会話のなかにこそ、変化の激しく不確実な時代において、新しい仕事の仕方やキャリアを切り拓くヒントが詰まっていることを実感していただきたい。
今後、AIに仕事を代替される時代が訪れるなか、現状維持を好み、過去のやり方に固執することは、もはやリスクでしかない。これからは誰もが離れた知と知をハイブリッド化させ、自らの手で新しいアイデアを創出し、自分自身に小さくてもいいので変化をもたらしていく時代である。そうでなければ、これからの皆さんの仕事は、きわめて困難なものになるだろう。
その意味でも大切なのは、とにかく「知の掛け合わせ」を楽しむことだ。そして本書ほど、その出発点となる刺激を与えてくれる一冊はほかにない。本書を通じて、離れた分野の人々による「ハイブリッド対話」の面白さを味わい、それが皆さんの仕事やキャリアにとって小さな前進のきっかけとなれば、このラジオ番組を長らくやってきた者として、これ以上の喜びはない。
では、10組の「ヤバい知の組み合わせ」をご堪能いただきたい。
[書き手]入山章栄
ALL REVIEWSをフォローする