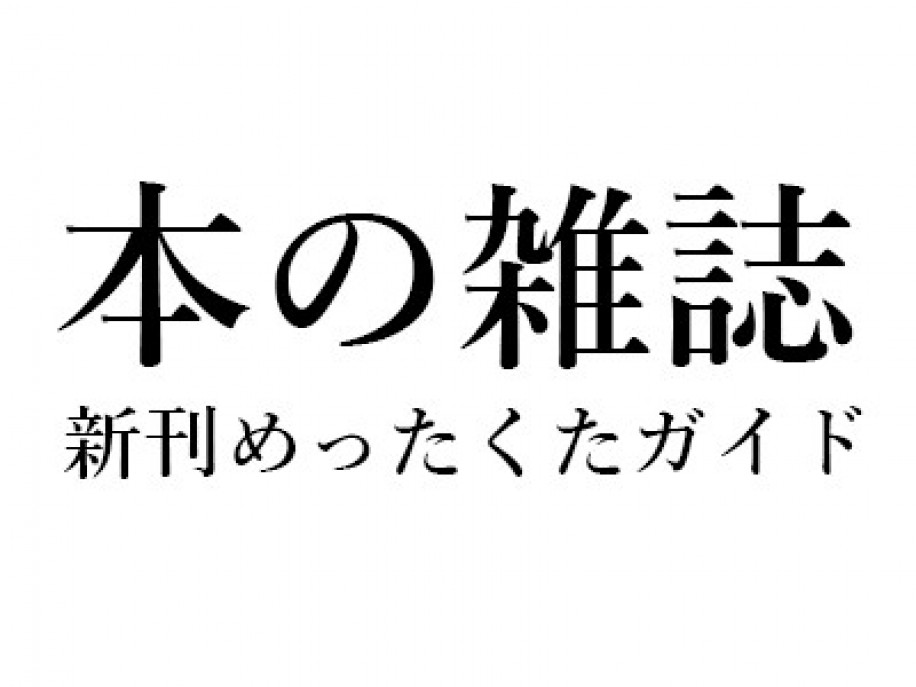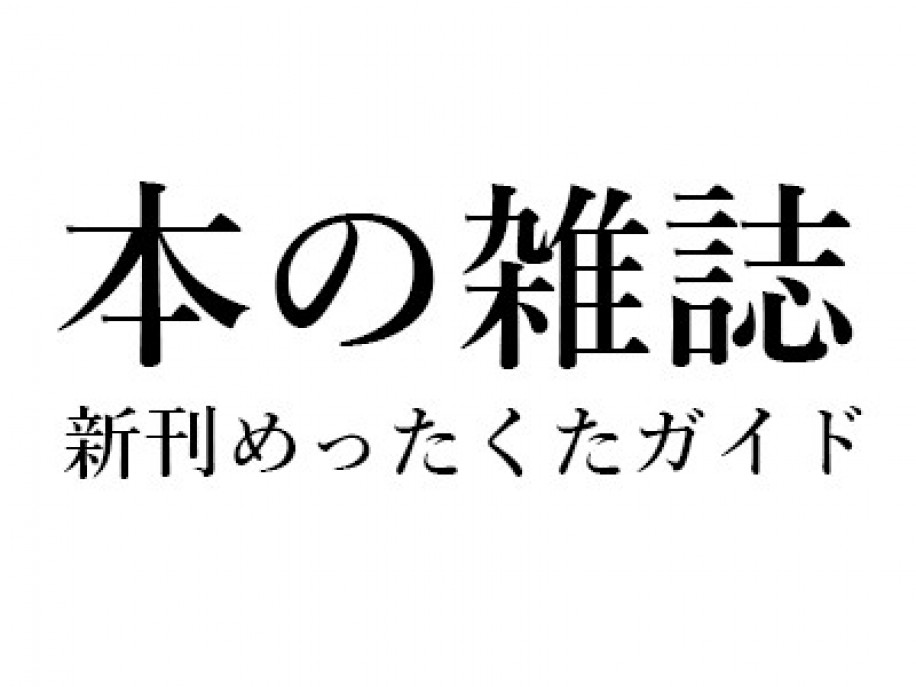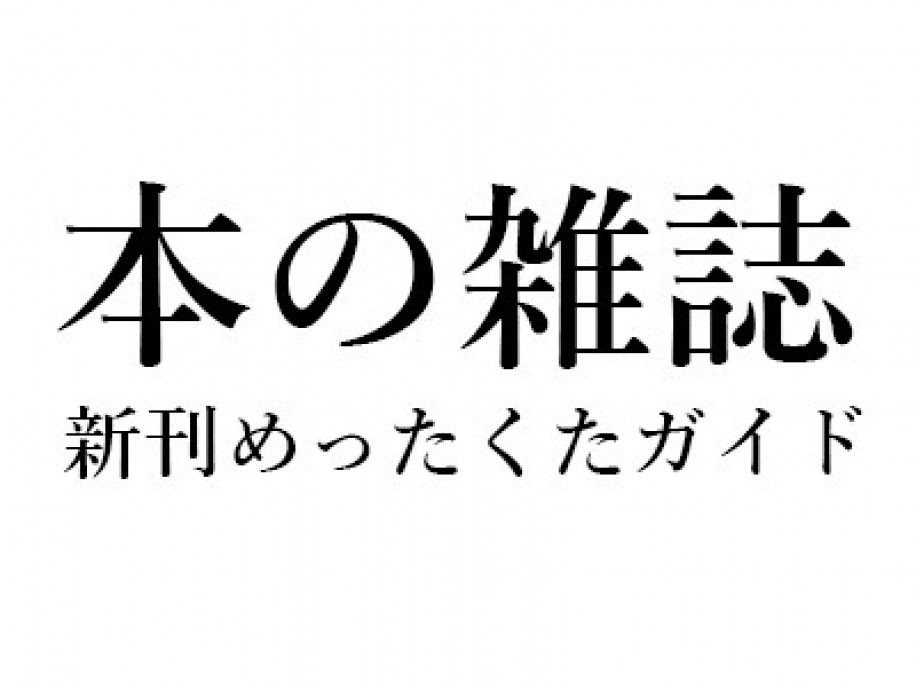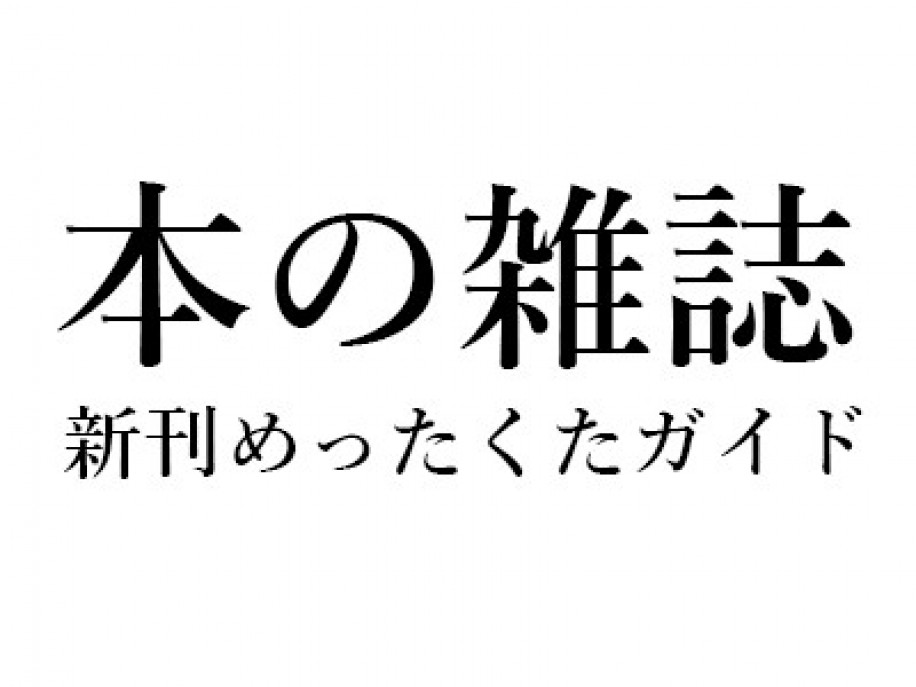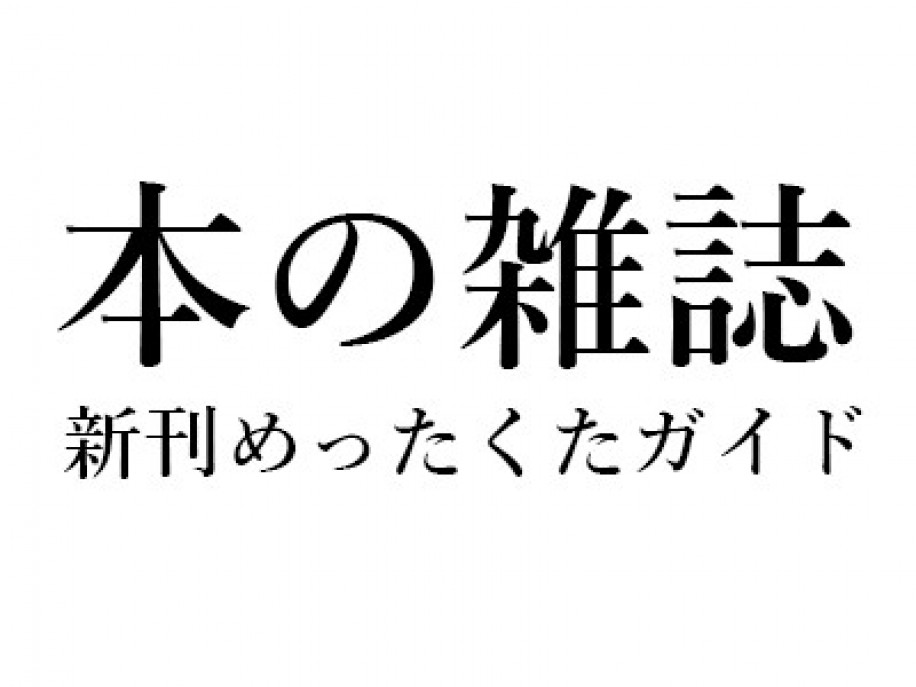文芸時評
大森望「新刊めったくたガイド」本の雑誌2001年2月号『エリ・エリ』他
”大きな物語”の復活なるか?小松左京賞受賞作『エリ・エリ』
一九八○年代以降(米国では七〇年代以降)のSF界では、"神"とか"人類"とか、そういう大上段に振りかぶった話を今さら大マジで書くのはどうよ。みたいな気分がなんとなく一般化し、読者の日常感覚に合った話が好まれる傾向が強かったんですが、二〇〇一年到来を機に"大きな物語"が復活の気配。第1回小松左京賞に輝く平谷美樹『エリ・エリ』(角川春樹事務所)★★★☆は、神の問題とファーストコンタクトを正面から描く、まさに小松左京的な本格SFだ。題名の出典は、SF読者にもおなじみのイエス様の捨て台詞、「エリ、エリ、レマ・サバクタニ」(かみさま、かみさま、なんでおれをみすてるんや)。各章冒頭に革命家イエスとユダの物語を配しつつ、信仰に疑問を持ち始めた神父・榊の話と、地球外生命探査計画の進展とが並行して語られる。前作の『エンデュミオン エンデュミオン』は意欲的なアイデアに挑みつつも語りのレベルで消化不良を起こしていたが、本作では小説技術が見違えるように進歩し、SFに不慣れな読者でも問題なく読める(その意味ではむしろ、映画版の「コンタクト」に近いかもしれない)。宇宙へのアプローチは工学的というより哲学的・審美的で、日本的な文系SFの伝統を強く感じさせる。理工学系の宇宙SFが急増する中で、こうした小説が登場したのは、はたして特例的な先祖帰りか、それとも新世紀の先触れか。いずれにしても、二〇世紀日本SFの締めくくりにふさわしい力作だ。ただし問題は、百パーセント本格SFの雰囲気を持ちながら、SF的な驚きを提示する直前で優雅に幕が引かれること。構想中という続篇に期待したい。
一方、同賞佳作入選の浦浜圭一郎『DOMESDAY』(ハルキ・ノベルス)★★★☆は、恵比寿ガーデンプレイス(みたいな場所)に物体O(みたいなもの)が落ちてきて周囲から完全に孤立する話。外の状況は最後までわからない。閉鎖環境でのサバイバル物かと思えば、次々にとんでもない事態が。どうも異星人かなんかが人間を使って実験しているらしいが、意図も論理も不明。このブラックボックスの法則性の解明が登場人物たちの課題となる。ある意味で、現代版『ソラリス』的な構造だが、先の読めない展開と怪現象の描写が抜群に面白い。WHYを括弧に入れて現象だけを語る作風は「いまどきのSF」の典型にも見えるが、人間には理解できない論理を予感させる部分にSF的な興奮がある。『エリ・エリ』と正反対の思いきりへんてこな小説なので、両方とも必読。
ハルキ・ノベルスからそれと同時に出た大迫純一の書き下ろし『ゾアハンター』(→GA文庫)★★★は、スーパーヒーローがモンスターと闘うB級痛快SFアクション。リーダビリティは抜群で、ノベルス娯楽SFの王道を再開拓する娯楽作だ。
角川春樹事務所の新刊をさらにもう一冊。岡本賢一の『ワイルド・レイン 3 覚醒』(ハルキ文庫)★★★☆は三部作の完結篇。トクマノベルズ版を改稿した『1』は、テグタニオ空間という魅力的なアイデアはあるものの文章スカスカの超能力アクションで、続巻を読む気力が萎えそうになるが、そこでやめてはもったいない。『1』を設定説明と割り切れば、『2』で元がとれて『3』でお釣りが来る。ディック的な世界観+超能力活劇のブレンドは竹本健治のSF作品とも共通するが(とりわけ、同時期に書かれた『鏡面のクー』とはプロットや肌合いも意外なほどよく似ている)、可読性ではこちらが上。たぶん読者層は全然違うと思うので、竹本ファンには岡本賢一を、岡本ファンには竹本健治をおすすめする。
岬兄悟・大原まり子編の書き下ろしアンソロジー《SFバカ本》シリーズが、今度はメディアファクトリーから二冊同時に再々登場。七〇年代テイストの巻き込まれ型サラリーマンSF(平凡な会社員を奇想天外な事件が襲う)が中心で、野心的な実験とは縁がない分、リーダビリティは高く、一種ぬるま湯的な心地よさに浸れる。『宇宙チャーハン篇』★★★では、スケールの無意味な大きさが笑える谷甲州「スペース・ストーカー」と、本書収録作では例外的にオリジナルなネタを用意した牧野修「メロディー・フィアー」、『華氏四五一度』と『刺青の男』を自分の土俵で合体させた館淳一「お熱い本はお好き?」が収穫。『黄金スパム篇』★★☆のほうでは、大場惑の妙に切実感のあるワンアイデア・ストーリー「秒を読まれる」と、語りのうまさが光る岡崎弘明「とんべい」がいい。
徳間デュアル文庫の新刊を二冊。久々のオリジナル作品として大いに期待していた中井紀夫『遺響の門』★★は、ジュブナイルSF的な定型を意識しすぎ。この人のもっと型破りな小説が読みたい。東野司『真夏のホーリーナイト』★★★は《ミルキーピア物語》の姉妹篇的な新シリーズの第一弾。あいかわらず達者。
続いて海外。前回積み残したオースン・スコット・カード『エンダーズ・シャドウ』上下(田中一江訳/ハヤカワ文庫SF)★★★は、もうひとつの『エンダーのゲーム』。主役は、一歳
のときから(!)スラムで浮浪児として自活してきたビーン。ひ弱な彼が人間関係の力学に対する洞察のみを武器に生き延びてゆく前半はカード節の真骨頂。いい子すぎて苛立たしいエンダーに比べるとむしろビーンの話のほうが読ませるね──と思ったが、バトルスクール入所後はプチ・エンダー化。後半は原典と同じ話が別視点から語られる。小説技術と訳文の読みやすさでは原典を凌ぐが、ピーターが出てこないので画竜点睛を欠く。惜しい。
これが初翻訳となるデニス・ダンヴァーズの『天界を翔ける夢』(川副智子訳/ハヤカワ文庫SF)★★☆は、人類の大半が仮想現実環境〈ビン〉に移住した二〇八一年が舞台(現実世界の人口二百五十万に対し、ビンの人口は百二十億)。頑なに移住を拒む若者ネモは、ビンに住む両親を訪ねた折、運命の女性と出会う──ってことで、これは仮想現実版「ロミオとジュリエット」(+『レベッカ』とヒチコックを少々)。ミステリ的な謎は最初からバレバレなので驚きようがありませんが、ハリウッド・ロマンス的な語り口は手慣れたもの。イーガンが『順列都市』で捨てた部品を集めてつくったような小説なんだけど、楽屋落ちの小ネタはけっこう笑える。
国産ホラーに触れる行数がない。岩井志麻子の第二作『岡山女』(角川書店)★★★☆は探偵小説趣味も楽しい快作。
【この文芸時評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする