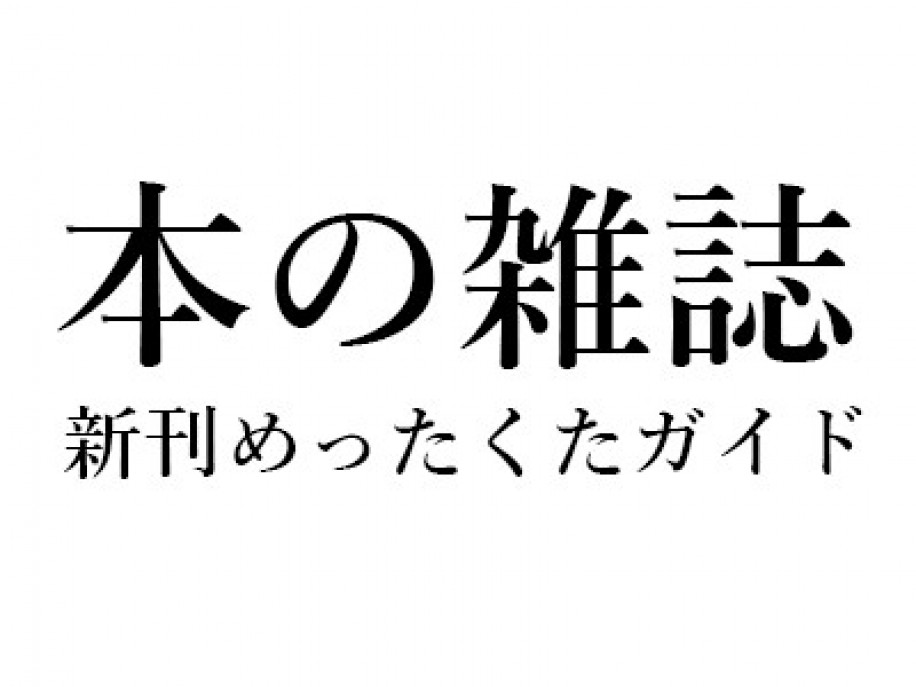読書日記
J・K・ローリング『ハリー・ポッターとアズカバンの囚人』、ジョン・ベレアーズ『闇にひそむ影』、マイケル・マーシャル・スミス『オンリー・フォワード』ほか
マイケル・マーシャル・スミスの妙ちきりんなセンスを堪能
全世界で一億部の大ヒットとか聞くと、それだけで読む気が失せる人も(本誌読者には特に)多いと思う。実際、訳者(兼発行人)あとがきを先に読むと、その異様な熱狂ぶりに読書意欲が著しく減退するが、面白い本が売れるとは限らないのと同様、ベストセラーだからつまらないとは限らない。というわけで、今月の一番手は、読まず嫌いの人にすすめる《ハリー・ポッター》シリーズ。まだ三十代の英国作家、J・K・ローリングは、児童文学ファンタジーの伝統と、いまどきのライトノベル的な軽さ/俗っぽさとをうまく融合させ、意外とユニークで楽しい物語世界を構築している。設定自体はよくある魔法学校ものだが、エンデ的な異空間じゃなくて、むしろ学園ものライトノベルの感覚。歴代有名魔法使いがトレーディングカードになってたり、箒にまたがって戦う空中ラグビー的なスポーツ(クィディッチ)が人気の的だったりと、日本の少年マンガ誌に載っててもおかしくない。ご学友のハーマイ
オニーは萌えキャラだし、脇役陣の性格の誇張ぶりもアニメ的。現実世界と魔法世界が同居するエブリデイマジック型だから、この分野になじみがない読者もとっつきやすく、トールキンやエンデ作品の象徴性・観念性が希薄な分だけ読みやすい。それでいて、西欧幻想小説・怪奇小説の歴史はしっかり吸収し、ゴシック・ホラー的な描写にもソツがない。
一巻で一年が経過するシステムなので、第三巻『ハリー・ポッターとアズカバンの囚人』(松岡佑子訳/静山社)★★★☆のハリーくんは、ホグワーツ魔法学枚の三年生。つらい夏休みが明けて新学期の初登校をはたす冒頭から笑わせてくれる。今回は、亡き両親の若かりし日々に起きた事件が背景で、後半はミステリタッチ。どんでん返しの連続はこのシリーズに似合わない気もするが、伏線の張りかたは堂に入ったものだし、笑いと恐怖のブレンドも絶
妙。もちろん、小説としての格では、ゲイマン『ネバーウェア』やプルマン《ライラの冒険》三部作のほうがはるかに上だけど、これはこれで、下世話な感じが悪くない。
一方、"ハリー・ポッターの原点"を売り文句に刊行が始まったジョン・ベレアーズの《ルイスと魔法使い協会》シリーズは、よくも悪くもオーソドックスな児童文学。RPGの「勇者」型主人公(生まれながらのヒーロー)であるハリポタに対して、ルイスくんはあくまで平凡。いじめられっ子の肥満児が魔法に触れることで成長していく──という意味では、むしろハリポタより『はてしない物語』の元祖かもしれない。第二巻『闇にひそむ影』(三辺律子訳/アーティストハウス)★★☆では、ルイスくんの彼女、ローズ・リタが大活躍するが、ハリポタのハーマイオニーにくらべると、あまりにもいい子過ぎてリアリティがない(というか、ルイスと仲良くなる理由が謎)。大人キャラも理想化された類型で、善良な親が子供に読ませたがる本ではあっても、いまの子供が自分で読みたがるかどうかは疑問。ベレアーズの死後、ヤングアダルト畑のストリクランドが書き継いだ四巻以降がどうなってるのか、むしろそっちのほうに興味がある。
SF方面で今月のイチ押しは、英国の新鋭、マイケル・マーシャル・スミスの『オンリー・フォワード』(嶋田洋一訳/ソニー・マガジンズ)★★★★。邦訳三冊めだが、これが著者の第一長篇で、オーガスト・ダーレス賞、P・K・ディック賞を受賞している。帯には近未来ミステリーとあるが、実際は、ハードボイルド仕様のダークファンタジーに近未来SF風味を少々という感じ。デビュー作だけあって、『スペアーズ』の二百階建て旅客機や『ワン・オブ・アス』の"走る目覚まし時計"に代表される著者独特の妙ちきりんなセンスがぎゅっと凝縮されている。
小説の舞台は、近隣区(ネイバフッズ)と呼ばれる、それぞれ個性豊かなご町内に細分化された世界。主人公のスタークは豊富な人脈と秘密の特殊能力を誇るトラブルシューター。品質管理(QC)と効率的マネジメントの悪夢が結晶化したような近隣区〈行動センター〉の"とりわけすぐやる部とことんがんばる課課長補佐"から、失踪人探しを依頼されるのが話の発端。もっとも、圧倒的にへんなこの世界の成り立ちをめぐる謎が小説の隠れた中心で、異世界を発見する理屈にはほとんどラファティ的なセンスがある。発想のユニークさでは、この十年のSF長篇でも十指に入るかも。外形的には二重化された異世界ファンタジーだけど、サイバーパンクの英国的展開、あるいはブリティッシュ・ニューウェーヴの現代的な亜種として読むのが正解か。へんな小説が読みたい人はお見逃しなく。
あとは国内作品を駆け足で。川端裕人の第三長篇『ニコチアナ』(文藝春秋→角川文庫)★★☆も相当にへんな話で、現代アメリカの煙草産業にマヤ神話をからめ、近代を煙草で総括するタバコ伝奇SF。着眼は面白いが、情報小説的なスタイルがプロットとモチーフになじまず、煙草の豊饒な味わいを伝える物語にはなりきれていない。
伝奇SFと言えば、柴田よしきの《炎都》シリーズ第四弾が開幕。その第一巻、『宙都 第一之書 美しき民の伝説』(トクマ・ノベルズ)★★★の序章にある「これまでのお話」を読むと、ここまで荒唐無稽な話だったのかと呆れちゃいますが(ふつうの読者はちょっと引くと思う)、小説の中身はおなじみの人間ドラマ/妖怪ドラマ。キャラクターのレベルで強固な日常的リアリティが保持されているため、トンデモ話も楽しくすらすら読めちゃうのが柴田マジックか。
全三巻が完結した中井紀夫『モザイク』(徳間デュアル文庫)★★は、M震と呼ばれる局地的な群発小地震によって崩壊した未来の東京が舞台。ノスタルジックな少年SFとしてはそれなりに楽しめる。しかし、だったら新興宗教とかクローンとかの話は入れなくてもよかったのでは。
今月最後の一冊、筒井康隆『天狗の落し文』(新潮社)★☆はなんと形容すべきかよくわからない。フォローのしようがないギャグとか会話の流れと無関係な逸話とかを唐突に披露して対応に困る人がたまにいますが、その困った感じを一冊にまとめたような本。盗用自由と言われましても。
【この読書日記が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする