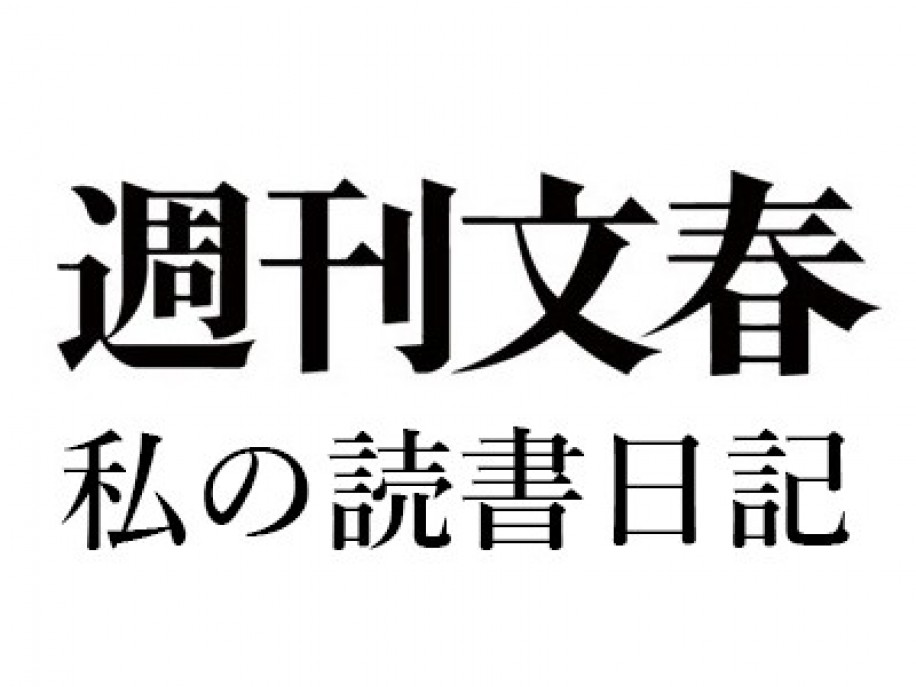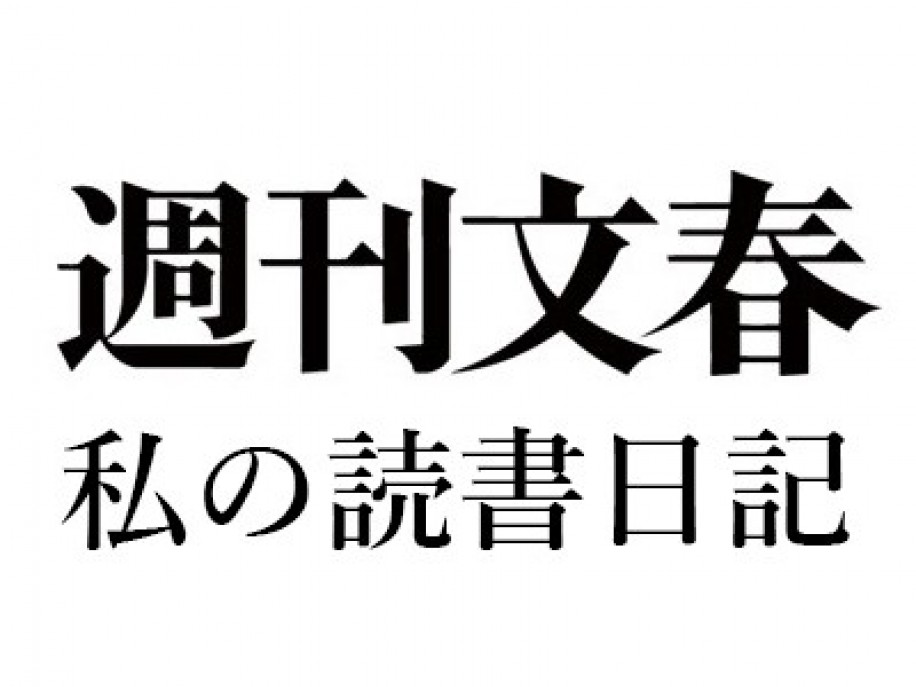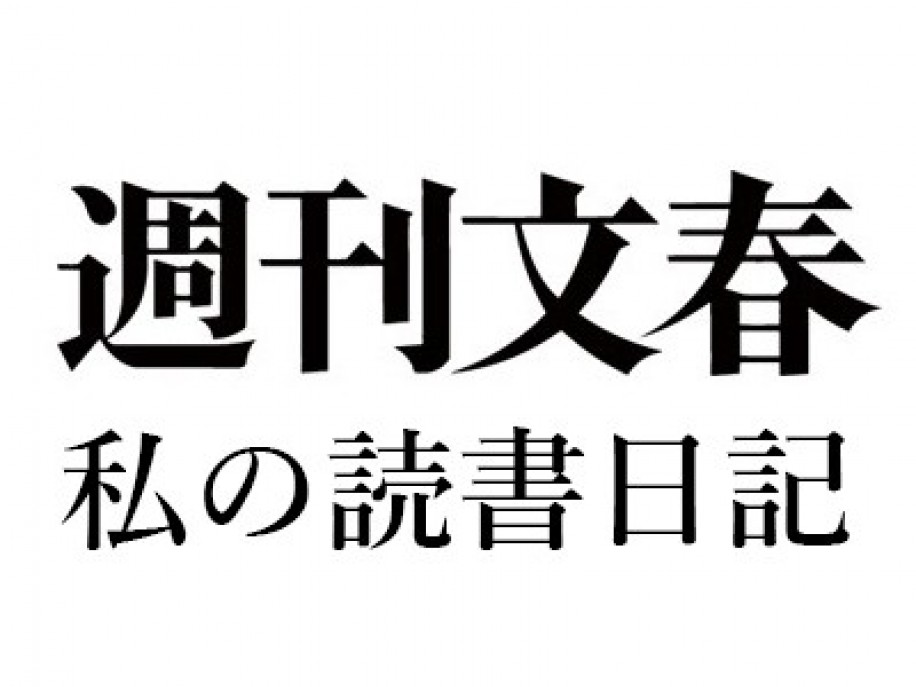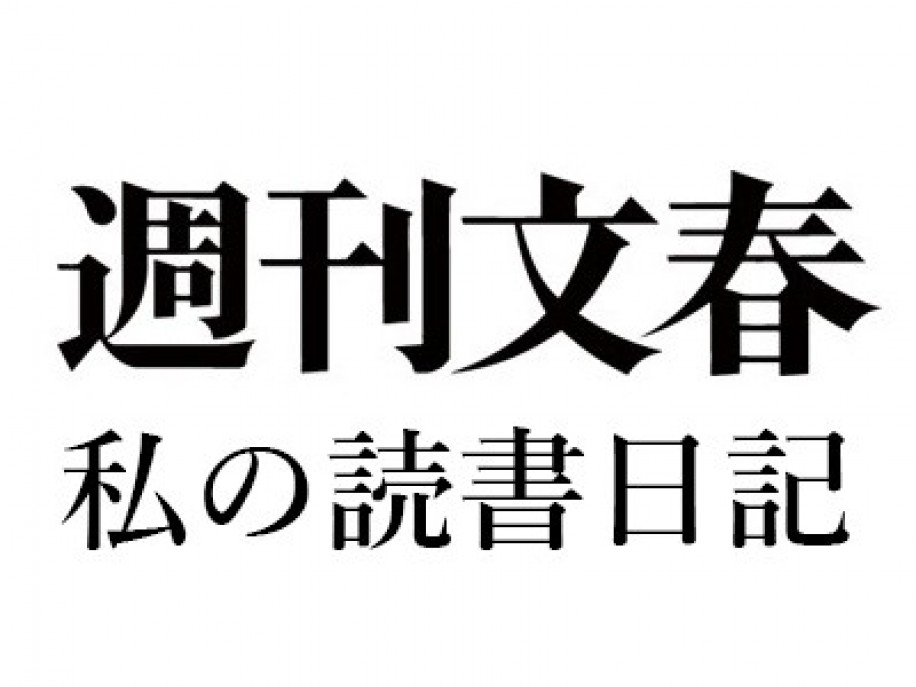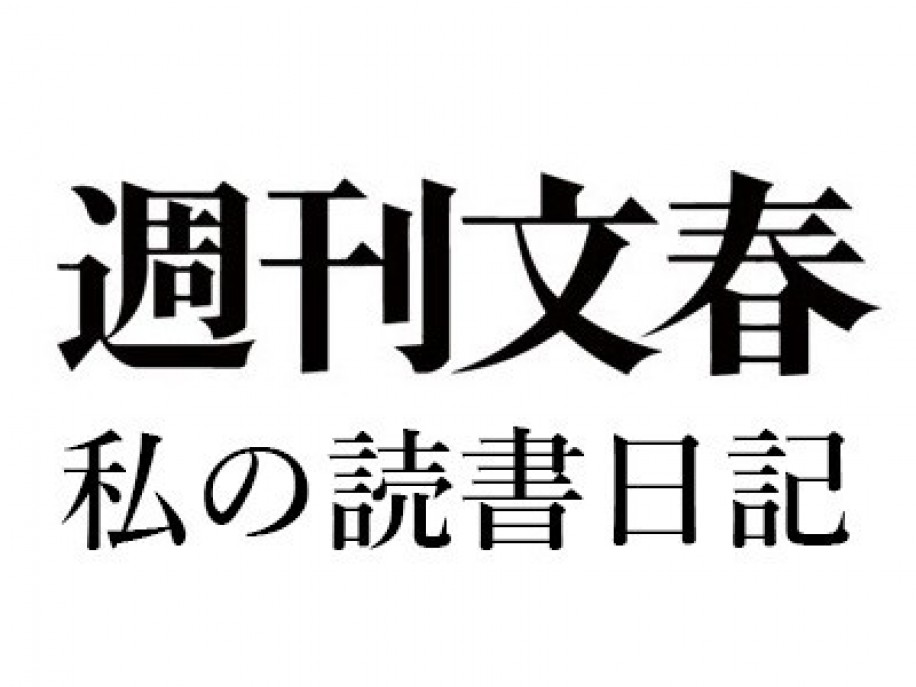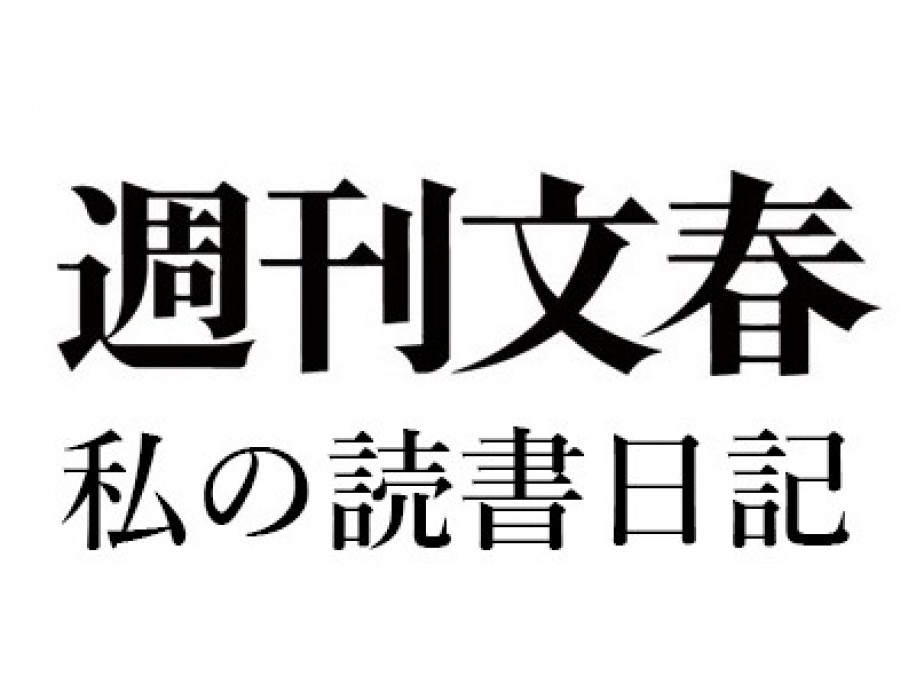読書日記
米原万里「私の読書日記」週刊文春2001年5月24日号『過去と思索』『スターリン秘録』『「スターリン言語学」精読』
面白すぎる「自分史」と毛嫌いのスターリン本
×月×日
小谷野敦が『軟弱者の言い分』(晶文社/ちくま文庫)のなかで、最近の「自分探し」ブームについて、”世の中、探したって実現するほどの自分がない人間が大半だ”と身も蓋もないことを直言していて、笑ってしまったが、逆に頭脳明晰、博学多識で途轍もなく視野が広く、感受性鋭く、他者をも己をも突き放して観察できる器量の人間が、波瀾万丈の半生と激動の時代を綴ったら、これほど面白いものは無いはずである。というのも、アレクサンドル・ゲルツェンの「自分史」を読み出したら止まらなくなった。面白すぎるせいでもあるが、長すぎるせいでもある。『過去と思索』全三巻(金子幸彦/長縄光男訳 筑摩書房各九八〇〇円+税)。「ルソーの『告白』やゲーテの『詩と真実』と並ぶ自伝文学の白眉」といっても、各巻六〇〇頁、一三一年前に没したロシア作家の文章を、活字離れが叫ばれて久しいこの国で刊行しようなんて、市場原理に照らしてみたら愚挙以外の何ものでもない。それでも翻訳者が翻訳せずにはいられない、編集者が出版せずにはいられなくなるような力を、作品自体が持っているということだ。この値段では、ただでさえ少ない潜在的読者を、さらに遠ざけてしまいそうなのが歯がゆいが。
皇帝に連なる名門地主貴族の父がドイツ人下級官吏の娘に生ませた私生児であるゲルツェンは、感じやすく早熟な子供として育つ。モスクワ大学理数学部に入学後、農奴制と専制に戦いを挑む革命的サークルを組織し西欧社会主義者の理論を研究する。卒業後、二度の流刑を経て、一八四七年に亡命。ロンドンに居を構えて「自由ロシア出版所」を創設し、論文集『北極星』や新聞『鐘』を発行。祖国の農奴解放運動を応援し続けた。
本書執筆の動機は、最愛の妻ナターリアのドイツ詩人ヘルヴェークとの浮気。ヘルヴェークの愛が本物ならば身を引く覚悟さえしていたゲルツェンは、その不誠実さに憤り、決闘を覚悟する。しかし、不実の子を宿して病に倒れ、瀕死の床に伏す妻に懇願されて思いとどまる。この「家庭の悲劇」を解明してヘルヴェークを非難することを目的に筆をとったゲルツェンは、当初の目的を超えて、己の幼年時代からの回想を記すことになった。執筆は結局一六年間も続き、その間次々と家庭の不幸に見舞われる。ツルゲーネフが、「涙と血をもって書かれている。人の心を焼き焦がす」と絶賛するゆえんである。流刑と幅広い交友関係の中から知った当時のロシア社会の詳細な報告、亡命後の各国革命家との交流で浮き彫りになるヨーロッパ社会の歴史的流れ。それが、抽象議論ではなく、興味尽きない同時代人たちの姿を通して語られる。ベリンスキイ、バクーニン、プルードン、マルクス、ガリバルディ、ミツキェーヴィチ、オーエンなどの有名人と並んで、著者に仕えた農奴たちなど無名の人々の姿が生き生きと印象深い。
もっとも、私がたまらなく惹かれるのは、以下のようなくだり。『コペルニクスの太陽系の分析的解明』という論文を書き優秀な成績で卒業したゲルツェンは、そのときの指導教官で天文学界の第一人者だったペレヴォーシチコフ教授と卒業後、食事をする機会があった。教授は、ゲルツェンが天文学を続けなかったことをさかんに惜しむ。「でも誰もかれもが、先生の後について天に昇るというわけには行かないでしょう。わたしたちはここで、地上で、何かかにか仕事をやっているのです」と答えるゲルツェンに教授は反論する。「どんな仕事ですか。ヘーゲルの哲学ですか!あなたの論文は読ませていただきました。さっぱりわかりません、鳥の言葉です。これがどんな仕事なものですか」
鳥の言葉。何と言い得て妙なのだろう。人文系の学問に携わる人々の言葉が、恐ろしく難解になっていく一方で、一日平均三〇語で事足りている若者たちの群れ。この二者間の距離は絶望的に隔たるばかりで、同じ民族どころか、同じ人類とも呼べない状況になってきている現実は、同時通訳として、あれこれの学会の通訳に動員されるたびに、思い知らされている。でも、一五〇年前のロシアでもそうだったのかと思うと、悲壮がってた自分が可笑しくなる。
(次ページに続く)
ALL REVIEWSをフォローする