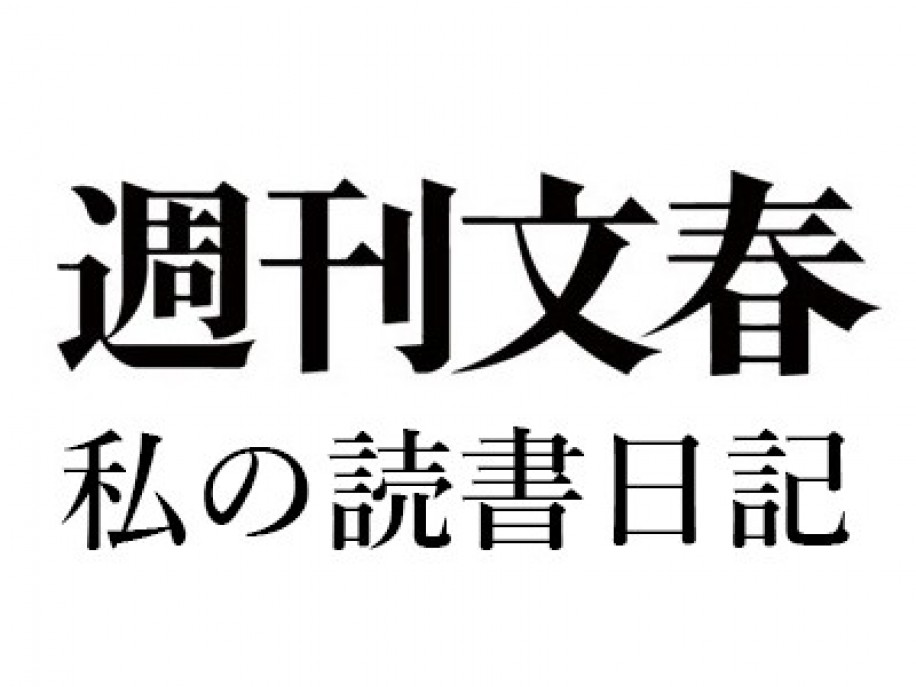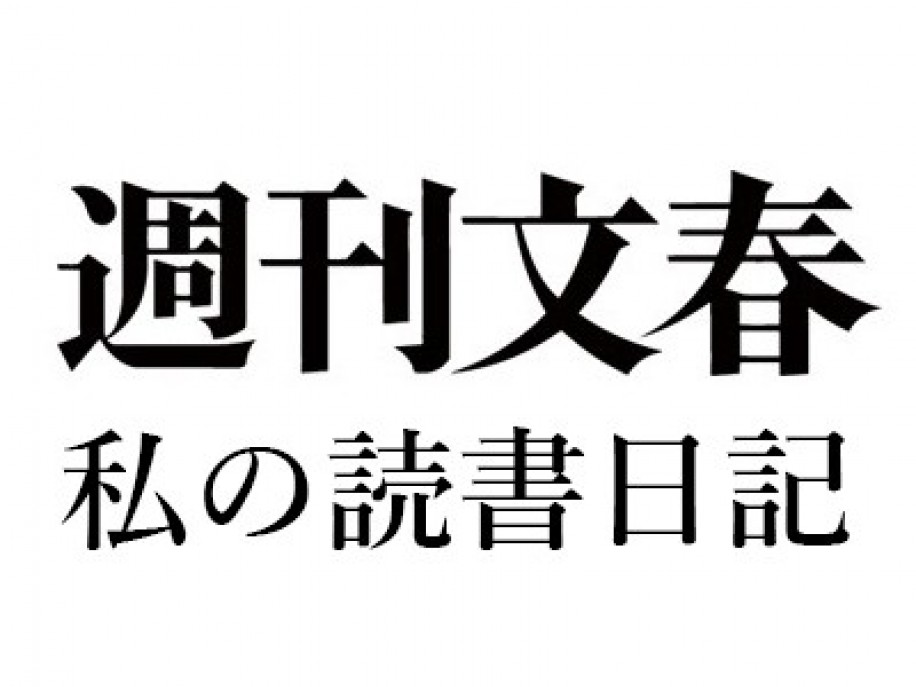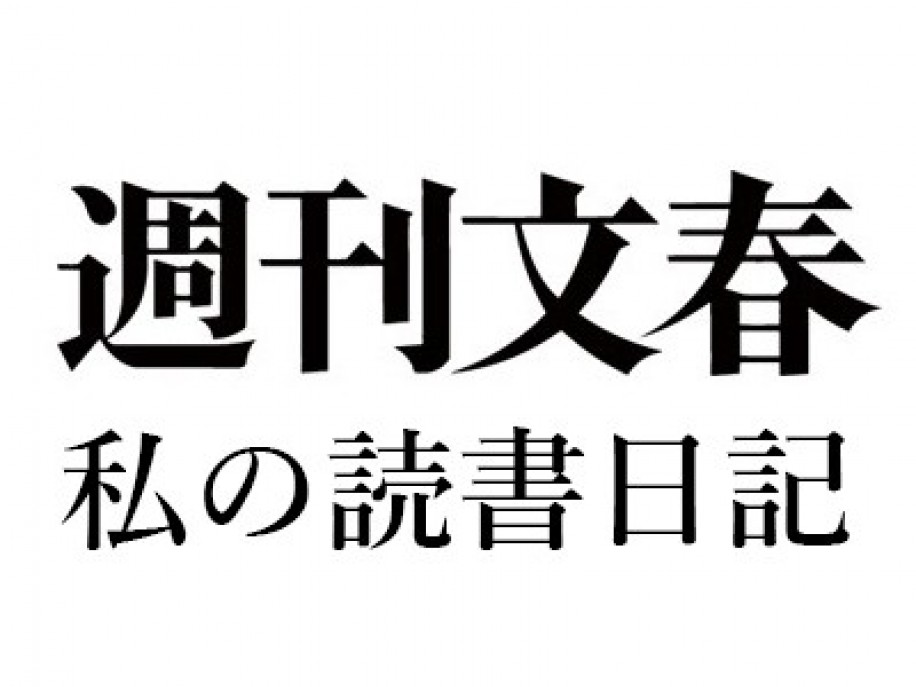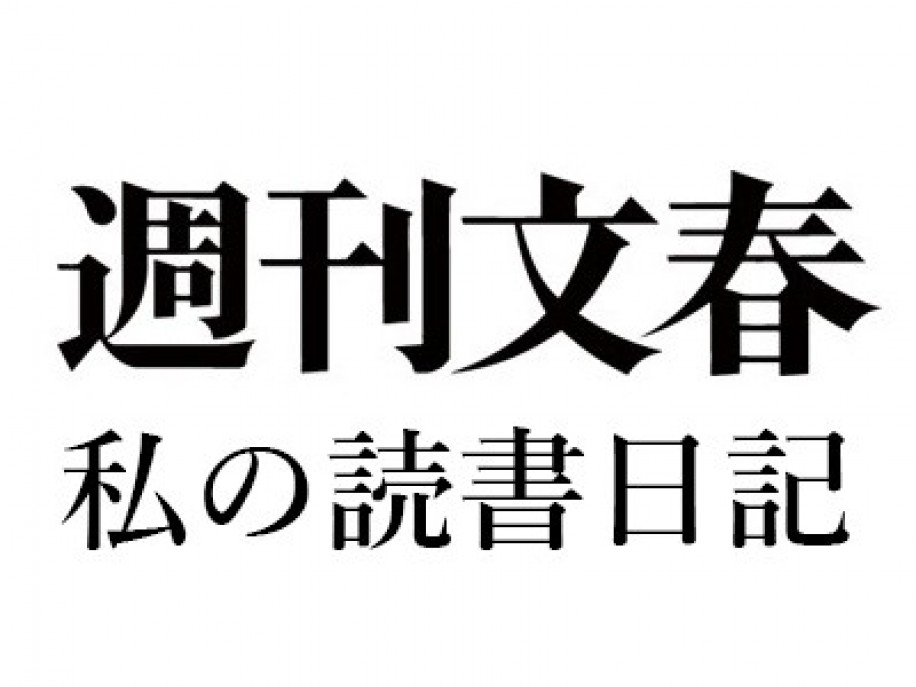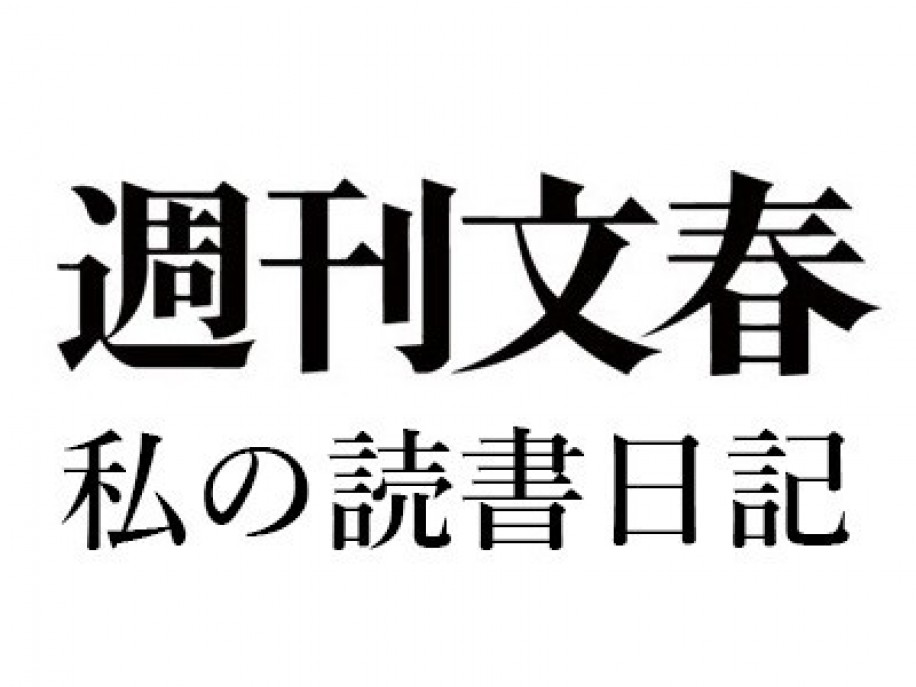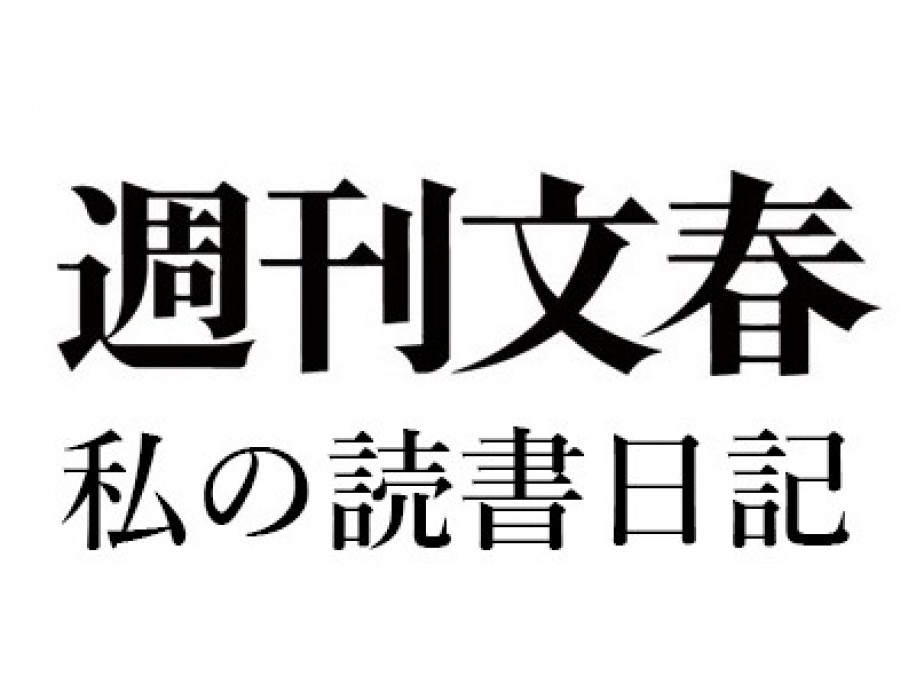読書日記
米原万里「私の読書日記」週刊文春2001年5月24日号『過去と思索』『スターリン秘録』『「スターリン言語学」精読』
×月×日
ゲルツェンが夢見た社会主義が、ロシアにおいてどんな形をとったか、それを明らかにしようとする本がまた出た。『スターリン秘録』(産経新聞/斎藤勉著 産経新聞ニュースサービス)。一九九九年菊池寛賞を受賞した『毛沢東秘録』の、おそらく二匹目のどじょうを狙った連載を単行本化したものである。さて、二匹目のどじょうは捕まえられたかというと、かなり苦しい。秘録と銘打った以上、読者としては、今まで世の中に知られていなかった新事実の報告を期待するものだ。ところが、あとがきで、「取材に入る直前、プーチン政権は大方の古文書館を閉鎖してしまっていた。エリツィン時代に古文書にアクセスした人と、古文書をできるだけ多く使用した書籍や雑誌、新聞、論文などを探し出すことが最大の仕事であり続けた」と著者も断っているとおり、すでに、何らかの形で、どこかで発表済みの資料に基づいた記述が大半を占めているのである。ペレストロイカ以降、ロシアで発表されたスターリンの罪状に関する新事実は、日本のジャーナリズムも競って取り上げていた。もちろん、それを、手際よくまとめてくれたという功績は認めねばならないが。
巻末に列挙された参考文献目録は、ほとんどが九〇年代以降にロシアで刊行された文献なのだが、中には、優れた邦訳がすでに出ているものがあり、それを紹介していないのはなぜだろう。ラジンスキーの『赤いツァーリ』(NHK出版)のような傑作やヴォルコゴーノブの一連の力作など、読まなきゃ一生の不覚ぐらい面白いというのに。
歴史的資料として価値があるのは、スターリンの命令に従って、金日成傀儡(かいらい)政権誕生、さらには朝鮮戦争を引き起こすための謀略に直接関わったソ連軍人たちの証言である。スターリンと毛沢東の会談の通訳をつとめたフェドレンコ元駐日大使の証言も貴重だ。
気になったのは、ヒトラーと並ぶ「二〇世紀最大の悪者」としての定評が確立してしまっているスターリン像を自明の理としているため、列挙されるその悪逆非道ぶりが、まるで不可避な異常現象のようで、逆にその犯罪性が霞んで見えてしまうことである。なぜこのような怪物が生まれ、三一年間も大国に君臨し続けられたのか、という背景や原因探究への姿勢が希薄なことである。これでは、いかに屍(しかばね)が累々と積み上げられたおぞましい歴史であれ、教訓にはなりえないのに。
×月×日
田中克彦著『「スターリン言語学」精読』(岩波現代文庫)は、その意味では、実に斬新なスターリン論であり、言語と民族、社会の関係についての優れて刺激的な論考である。「悪夢の如く忘却されたスターリンの言語・民族理論を左翼運動のドグマから解放し、同時代の正統派アカデミズムの潮流と対比して論じる史上はじめての試み。現代の民族紛争の本質を探るために必読」という惹句が、いみじくも本書の内容を言い当てていて、読後興奮して眠れなくなったほどだ。『ことばと国家』、『名前と人間』などの名著で知られる田中克彦の、言語学者としての来し方をたどるエッセイともなっているので、かなり学術的な部分も、時には若き日の著者とともに悩み、時には論争を交わしながら、楽しく読み進められる。
考察の対象となっている、スターリンの「マルクス主義と言語学の諸問題」の訳文も併載してあり、毛嫌いしていたスターリンの文章に直に目を通すことが出来た。そして、ぶったまげた。内容の圧倒的大部分が、とくに、「民族」の概念規定に「言語」を不可欠の決め手としている点や、「言語」を「下部構造」でも「上部構造」でもないとしている点、「言語」に「階級性」は無いとしている点など、今日の常識に照らしてみても、客観的で説得力がある。これは当時のソ連言語学界、世界と日本の左翼にとって、今まで信じてきた学説をひっくり返す大事件だった。逆に、当時の日本言語学界のオーソリティ時枝誠記(もとき)は、中央公論社からスターリン論文の感想文を求められて「感想文を引き受けたのを後悔している。多くの指摘に好意を寄せることが出来そうだから」と述べたそうだ。
「歴史の歩みによって、無慈悲に踏みつぶされたこれら民族(ナツィオン)の残骸、民族の屑は、完全に根絶やしになるか民族のぬけがらになるまでは、反革命の狂信的な担い手であることをやめない。というのも、そもそもその存在そのものが、偉大な歴史的革命に対する反抗だからである」というエンゲルスに代表されるような、優性民族・言語が劣性民族・言語を吸収淘汰して当然とする見方がマルクス主義の主流に根強かった頃に、「十月革命は、古い鎖をたちきって、わすれられた多くの民族を登場させ、彼らに新しい生活と新しい発展をあたえた」というスターリンの言葉は画期的に響く。
もちろん、この言語・民族観はスターリン自身が、ゴミ屑扱いされたグルジア民族の出であること、またロシアが諸民族の牢獄と言われた多民族国家であったことと無関係ではない。スターリンの言語論が同じ多民族国家オーストリアの革命家、あの「背教者カウツキー」から多くを借用しているという指摘も、興味深い。
ソ連憲法にロシア語を国家語として定めなかったのも、民族自決権がうたわれ、あらゆる民族や少数民族が母語で教育を受ける権利を保障されたのもここから来る。一方で、言語と民族の関係を正確に把握していたからこそ、スターリンは、あれほど徹底的、残虐かつ効果的にチェチェンや、クリミヤ・タタールなどの連邦内少数民族に対する絶滅作戦を展開しえたのだろう。
悪は「まともさ」の延長線上にある。だからこそ恐ろしい。
【この読書日記が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする