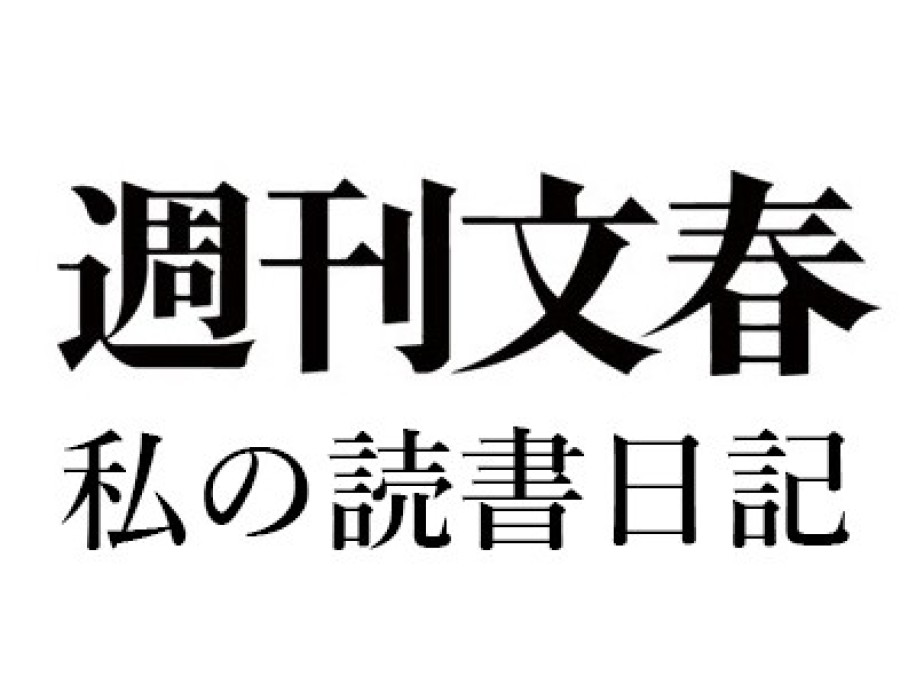書評
『昆虫学事始: 日本の昆虫研究を支えた人々』(青土社)
自国語で科学を築いた近代史各論
これはべつに昆虫学の解説本ではない。明治時代から日本の昆虫学の草創期を担った虫好きの人たちの評伝で構成され、昆虫好きから見た日本近代史の各論とでもいうべきか。人物伝なので、虫そのものが好みではない人でも面白く読めると思う。前半は四分の三くらいまでは札幌農学校出身で、のちの北海道大学農学部昆虫学教室の教授であった松村松年(しょうねん)の評伝と、それに続いて台湾総督府農事試験場昆虫部長から台北帝大教授兼総督府中央研究所技師となった松村の高弟、素木(しらき)得一、後半には台湾つながりで同研究所に所属し、セミの専門家であった加藤正世、さらに採集人としての経歴から始まり、当時版を重ねた昆虫図鑑の著者平山修次郎、平山の店に丁稚奉公し、のちに独立して渋谷宮益坂上に志賀昆虫普及社を開いた志賀夘助(うすけ)、最後にファーブル『昆虫記』を翻訳した大杉栄について触れ、こうした明治人たちが活躍した大正から昭和初期という時代背景を紹介する。
著者は現代の虫好きの一人で、専門はフランス文学だが、虫に関する著作が多い。とくにファーブル『昆虫記』の完訳があり、おそらく今となってはその内容について原著者ファーブルよりも訳者奥本のほうが詳しいと私は思う。
表題に付された「事始」は杉田玄白の『蘭学事始』を連想させるが、このつながりはたぶん偶然ではない。評者自身は解剖学と昆虫を研究したが、この両者の関係を訊(き)かれることが多い。
昆虫は自然の大きな一部を占める存在で、人体は我々自身が抱えている自然そのものである。どちらに対してもヒトは強い好悪の念を持つことがあり、「事始」という言葉で結ばれた二つの学問分野は、近代日本の草創期に虫と人体という二つの大きな自然の領域を日本語に取り入れた業績を示している。松村松年が心血を注いだ分野は昆虫の標準和名の制定であった。つまり日本の虫を分類学的に「正しい」位置に置き、標準となる日本語名を付けることだった。 自然の領域を構成する要素に名前を与えていく作業は、現代語でいえば自然を情報「化」する、すなわち情報の世界に取り込む基礎であって、大変なエネルギーと情熱を必要とする。しかも当面は実利も効用も見えないので、いわゆる「金にならない」ムダな仕事に思われてしまう。現代人は既成の情報の流通と獲得に専念しているから、情報化の重要性を知らない、ないし忘れることが多い。その意味で情報化という作業は実業の世界でいう典型的な一次産業であり、社会的な評価は低くなりがちである。
松村の著書『日本昆虫学』と『日本千虫図解』について、著者奥本は書く。「あえて言えば、日本の昆虫学の世界で、『ターヘルアナトミア』を翻訳し、解剖学の訳語を工夫しながら、『解体新書』を書き上げたことにも匹敵する業績と言えるのではないか」
欧米の科学を取り入れているアジアの国で、自国語で科学を教えられるのは日本だけだということに気づいている人がどれだけいるだろうか。もちろん現代では英語のままでいいことになっているので、言っても仕方がないが、それは手抜きで、その報いを受けるのは将来の世代である。
ALL REVIEWSをフォローする