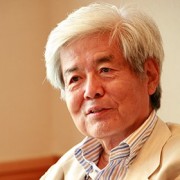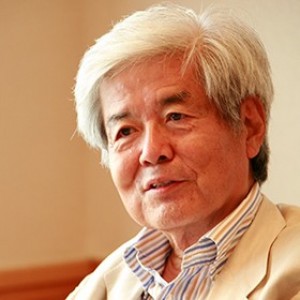書評
『もっと! : 愛と創造、支配と進歩をもたらすドーパミンの最新脳科学』(インターシフト (合同出版))
欲することに別れを告げて幸福を得る
人はなぜ熱愛に陥り、一年もすれば冷め、場合によって、アルコールや薬に依存し、新奇なものを追い求め、移民し、起業するのか。本書は以前から報酬系として知られた脳内のドーパミン回路のはたらきからそれらを具体的に説明する。私事ではあるが、評者はこの種の化学物質による脳機能の説明を苦手としてきた。欲求や快楽のような典型的に「主観」と呼ばれる世界と、脳という物質系との関連がどうしても直観的につながらなかったからである。このことは意識という機能が物質科学から説明できないことと根本的に関係している。同じ脳の機能でも、論理なら話は別である。神経細胞の電気的活動の基本はオン・オフであり、これはコンピュータで外部的なシミュレーションが可能である。だからその結果は現在AIに結実している。個々の神経細胞のオン・オフは次の神経細胞にドーパミンのような神経伝達物質によって伝えられる。しかしコンピュータの中にドーパミンを入れても、快楽や欲求のシミュレーションはできないであろう。ドーパミンのような化学物質を中心にして論じると、こうした化学物質自体に特殊な機能があるように錯覚されることがある。そうではなくて、ドーパミンが重要な要素としてたまたま機能するようなシステムが存在することが中心の問題なのであって、そのシステムは非常に長い進化の過程を経て成立した脳という複雑で微妙な回路系の中に位置している。問題はこの回路系にあってドーパミン自体にあるわけではない。
ドーパミンは、以前はたとえば食物のような報酬が得られた時に活動するものとして、「快楽物質」と呼ばれたこともある。じつはそれは間違いで、ドーパミン・ニューロンは予期されない報酬の際にのみ活動することがわかった。つまり、ネズミの実験で明かりをつけたら餌が出るという風な状況に置くと、条件付けの初期段階では餌によりドーパミン回路の活動が生じるが、学習が進んで報酬(餌)の到来が予期できるようになると活動が減少する。このことから、ドーパミン・ニューロンは、ただ報酬刺激に反応するのではなく、報酬の予測に関係することが判明した。著者はこれを報酬予測誤差と呼んでいる。思わぬ報酬であるほど活動が大きくなるからである。
ドーパミンの本質は快楽ではまったくない。(中略)ドーパミンは、それよりもはるかに影響の大きい感情を生み出している。(中略)ドーパミンに対する理解こそが、さまざまな領域での人類の努力を説明し、さらには予測(・・)するための鍵を握っているのだ。その領域は、目をみはるほどに広い。
ドーパミンは快楽物質などではない。まったく違う。
ドーパミンの本質は、期待物質だ。可能性にすぎないものではなく、いま手にしているものを楽しむためには、未来志向のドーパミンから現在志向の化学物質に脳を移行させる必要がある。そうした現在志向の神経伝達物質を、ここではまとめて『ヒア&ナウ(いまここ:H&N)』と呼ぶことにする。(中略)たとえば、セロトニン、オキシトシン、エンドルフィン、そしてエンドカンナビノイド。
こうした両者の区別は、どこから生じたのか。それには進化上の理由があると著者はいう。われわれが見る空間は二つに分かれる。「身体近傍空間」と「身体外空間」である。著者はそれを「上を見る」「下を見る」と具体的に表現する。上にあるものは大方手が届かない。下にあるものは手に入るか、入りやすいものである。自分が手にしているものと、手にしていないものは生物にとって決定的に違う。この区別が身体近傍空間と身体外空間の区別を生み、その処理に関して脳内で別々の経路と化学物質が進化したのだ、と著者は説明する。常習性のある薬物はいわばドーパミン回路を乗っ取り、やがて脳はすべては薬物に関係すると決めることになる。
新しいパートナーや情熱的なあこがれというドーパミン的スリルに別れを告げるのは簡単ではないが、それができるのは成熟の証であり、長続きする幸福への一歩でもある。
欲することと、好きだということは違う。著者はそういう。欲するのはドーパミン回路であり、好きはいまここH&Nに関係している。大切なのは両者の微妙なバランスである。
本書の内容はまだまだ尽きないがその内容は人生や社会を考える上での重要な示唆を含んでいる。本書の内容は世間の一般常識とするに値すると思う。私は仏教の五欲を去れという教えを連想した。まだ手に入れていないものを欲するのは人の常だが、それはドーパミン回路の働きである。ドーパミンを産生する細胞は脳の僅か0・0005%である。
私は八十歳を超えたいまだに昆虫採集に行くが、目的の虫が採れた時より、思いもしなかった珍しい虫に出会った時のほうが嬉しい。これがまさに報酬予測誤差であろう。敢えて採集に出かけなくても標本を見ているだけで十分に楽しめる。これこそいまここH&Nの典型であろう。
ALL REVIEWSをフォローする