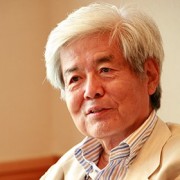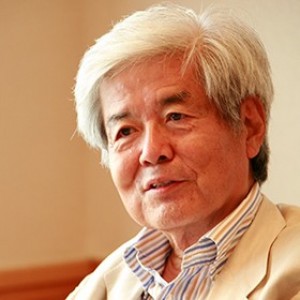書評
『京大 おどろきのウイルス学講義』(PHP研究所)
常識から未来への展望を網羅
このところ一年以上、ウイルスという言葉を見聞きしない日はないであろう。それでは、と改まって、「ウイルスとはどういうものか」と訊(き)かれると困惑する人も多いのではないか。本書は大学での講義をもとに、著者が現代のウイルス学の成果を語ったもので、たいへん時宜を得た出版物といっていい。私自身は学生時代に医学を学んだが、そのころの微生物学は細菌と抗生物質の関係が中心だったから、「ウイルス学」という本を読んだのは、学部卒業後だったと思う。当時のトピックはタバコモザイクウイルスが結晶化されたというもので、果たしてウイルスは生物か否かといった議論がなされていたような記憶がある。その後のウイルス学の進展で、生物界でのウイルスの位置づけが当時よりはるかに明瞭になり、具体的かつ深い議論がなされるようになった。その詳細は本書にも見るとおりである。
第1章は「『次』に来る可能性がある、動物界のウイルス」と題され、コロナ・ウイルス以外にどのようなウイルスがヒトに感染を起こす可能性があるか、が紹介される。著者の背景は獣医学で、ペットや家畜も対象として扱わなければならないから、感染症を典型として、獣医学研究のほうがヒトだけを中心とする医学研究より現代では進んでいると指摘されることがある。第2章は「人はウイルスとともに暮らしている」で、われわれの日常生活はウイルス・フリーというわけにいかないことが示され、第3章は「そもそも『ウイルス』とは何?」で、ウイルスの構造や定義が紹介される。第4章は「ウイルスとワクチン」であり、現在のワクチン接種をごく素直に受け入れている人にも、多分に懐疑的な人にとっても、参考になると思われる解説がなされている。
本書の後半、第5章から第7章は、著者が強い関心を抱いているレトロウイルスに関する記述で、それだけに力が入っており、第5章「生物の遺伝子を書き換えてしまう『レトロウイルス』」では、レトロウイルスとはなにかが説明され、第6章「ヒトの胎盤はレトロウイルスによって生まれた」は、著者の研究の中心となる部分で、多くの哺乳類の特徴である胎盤形成がレトロウイルスの関与によって可能になったこと、さらにはiPS細胞に関係する細胞の初期化にも、レトロウイルスの関与があることが説明される。第7章は「生物の進化に貢献してきたレトロウイルス」と続き、レトロウイルスが過去において進化上の大きな出来事に関わったことを示唆する事実を列挙する。
ウイルスという言葉はコンピューターの世界でも普通に使われている。もちろんコンピューターウイルスは物質的基盤を持たないから、医学生物学の領域で扱われないのは当然だが、やがて情報学の進展に伴い、非物質的な(質量をもたない)情報系の中で両者が共通に理解され、定義される日が来るかもしれない。
全体として、現代ウイルス学の総説として、よく書かれており、しかも著者の研究への情熱が伝わってくる。さらに未来への展望も含まれ、若い研究者を鼓舞する内容となっている。ウイルスに関する「常識」を持ちたい一般の人にも推薦したい一冊である。
ALL REVIEWSをフォローする