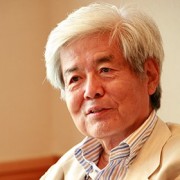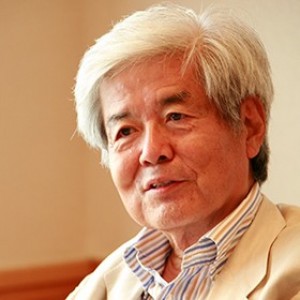書評
『うんちの行方』(新潮社)
「誰かが何とかする」ではいけない
日本人は万事を水に流すのが得意だという。八十年超の年月を生きてきて、日常生活で一番変化したと思うことの一つは、水洗トイレであろう。水洗以前から水洗への変化を具体的に追求したのが本書の主題である。著者たちは私よりずっと若い世代であるが、水洗以前のトイレにまつわる思い出から話を始めているから、昔のトイレはそれなりに印象が深いのであろう。ともあれ、現在の社会状況の下で、実際に下水がどのように創られ、管理されているか、それを子細承知している市民は多くないであろう。「もしタワマン全戸で一斉に流したら?」と帯にあるが、当然ながら下層階では逆流が起こるに違いない。排水管の太さが決まっているからである。
トイレの水洗化は日本だけのことではない。全世界的な傾向であって、私はこの種の傾向を都市化ないし脳化と呼んでいる。小学生くらいの子どもの質問に「口の中にある時に、ツバキは汚くないのに、いったん外に出すとなぜ汚いの」というのがあるが、トイレが急激に水洗化していく傾向と、そうした「進歩」にかける人々の情熱は、この種の嫌悪感と無関係ではあるまい。
本書ではむしろそれよりも富士山や列車のトイレ事情など、具体的な局面に関わる調査の結果が示されていて、たいへん興味深い。天安門広場に百万人が集まったなどと知らされると、トイレの事情はどうなってたんだという疑問が生じる。現場にいた人ならそれに答えられるはずで、山本七平が当時の中国人の報告を読んで、臭いがすることに触れてあったので、本人が現場に直接参加していたと判断していたという記憶がある。そうした考察をどの程度有益と見なすべきか、よくわからない。
し尿処理のシステム全体からすれば、水洗トイレはシステムの最末端に過ぎない。私の自宅でも水洗化の際にまず置かれたのは浄化槽だった。浄化槽とバキューム・カーの記憶が鮮明な人はまだ多いのではないか。し尿処理場が完成するまでやむを得ず行われた中間的な処理が海洋投棄であった。本書ではその歴史も詳しい。
コロナ禍におけるワクチン投与のシステムも、個人の段階で受ける受けないの議論は多いが、住民全体をカバーするような上手なシステムの構築には、かなりの精力が消費されるはずである。水洗トイレは現在九一%の普及率だという。これを百%にする必要はない。し尿処理の進展のいきさつは、さまざまな新しい社会システムの構築の際の参考になるはずだから、「うんちの行方」を単にそのものだけの特殊事情として読み飛ばしてほしくないなあと感じる。特に日本は災害列島と呼ばれるくらいで、有事の事情を抜きにすることはできない。本書には有事の際のマンホールトイレに関する言及があるが、洪水の際には使えないとはいえ、興味深い指摘だった。
下水の整備はまさにインフラ整備そのものだが、これは議論の問題ではなく、実行の問題である。多くの人が、誰かが何とかするだろう、で済ませてしまいがちだと思うが、高度に組織化、システム化された社会では、誰が、どのようにそれを実行するかが肝心な点で、少なくとも問題についてのある程度の常識と具体的なイメージを各人が持つ必要があろう。
ALL REVIEWSをフォローする