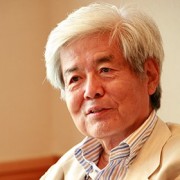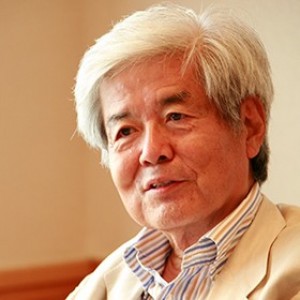書評
『心臓とこころ:文化と科学が明かす「ハート」の歴史』(化学同人)
古代~現代 感情と機能のあれこれ
現在では心という文字で表現されるはたらきは、心臓ではなく、ほぼ脳の機能とみなされるようになった。では心臓は、一般に言われる心というはたらきとは、無関係なのだろうか。米国の循環器内科医である著者が本書を書いた動機の一部は、心を代表する感情と、心臓という臓器の経験的な関係である。第34章「『傷心症候群』――たこつぼ心筋症」および第35章「心臓―脳接続」でやや詳しく論じられる。応援しているチームがスーパーボウルで負けたり、サッカーワールドカップのPKを外したりした後に心臓発作や突然死に見舞われた患者たちもいる。私は長年連れ添ったカップルが数か月以内に相ついで亡くなるのもよく目にしてきた。
心臓移植をすると、心臓の受け手の側に贈り手の癖や好みがうつる。そうした例が時に報告される。これを全くの勘違いと考える人は、今では多いと思われる。著者は本書でそうした事例をとくに扱うわけではない。心臓という臓器は、人類史の中でどう見られてきたのか。本書の原題は「好奇心をそそる心臓の歴史」である。臓器としての心臓と、いわゆる「こころ」との関係はどうなのか。全体は5部に分けられ、章番号は通算で記され、全部で36章になっている。
第1部「古代の心臓」は、人類史で心臓がどう考えられてきたかを示し、第2部「闇に埋もれ、再び光を浴びる心臓」は歴史の記述だ。第1部にはこうある。「心(心臓)はキリスト教の新約聖書(紀元50年~150年)に105回登場する。心臓はその壁の内側に神についての知識を収めていた。心臓によって、人は神の高次の愛を得ることができた。初期のキリスト教徒たちは心臓が魂の場だと考えていた」
日本人の場合、聖心を「清い御心(みこころ)」と受け取り、まさかキリストの心臓そのものとは思わないのが普通であろう。パリのモンマルトルの丘の上の白亜の大教会は、まさに「聖なる心臓(サクレ・クール)の教会」なのである。ハプスブルク家が心臓を身体の他の部分や内臓とは分けて埋葬する習慣があったことは、私も自著に詳細に記したことがある。
第3部は「アートのなかの『ハート』」と題され、「美術のなかの心臓」「文学のなかの心臓」などの項目がある。第4部は「心臓学入門」で、機械的なポンプとしての心臓の機能がわかりやすく説明される。最後の第5部では「近現代における心臓」として、現代医療における心臓が論じられる。
本書はある特定の理論や思想を紹介するものではない。だから話題があちこちに飛び、心臓の歴史散歩みたいになってしまうのはやむを得ないと思う。本書に記された心臓の歴史くらいは、医学関係者でなくても常識として心得ていてよいと思う。
本書の題「心臓とこころ」は日本語では問題にされないと思うが、厳密には心臓と心を「と」で並列するのを私は好まない。心臓は構造で、心は機能だからである。こうした抽象名詞のカテゴリー分けとその混乱に日本語は寛容で、学生が日本語で論文を書き、それを英語に直訳する時に、私は年中注意していた。日本語では「と」でつなぐことが許されても、英語ではアンドでつなげてはいけない場合がたくさんあるからである。
ALL REVIEWSをフォローする