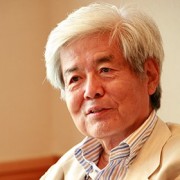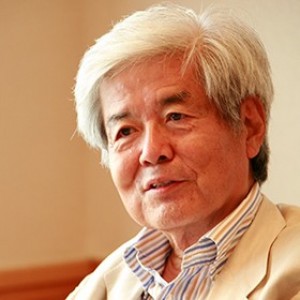書評
『夢を見るとき脳は――睡眠と夢の謎に迫る科学』(紀伊國屋書店)
「新たな知を発見する脳の働き」提示
夢とはなにか。どこからどう生まれ、どんな役に立っているのか。著者はそうした疑問に導かれて、夢の研究を始める。最初に断っておくが十分な答えはまだない。夢に関する近年の科学研究の結果が著者の仮説を含めて丁寧にまとめて報告されるだけである。日本語の文脈では、「夢みたい」「夢のような」と表現されるように夢は現実にはほぼあり得ない、都合の良い理想的な状態を指すことが多く、「夢がない」や「夢を持て」「夢を果たす」のように「理想」に近い意味で用いられることも多い。夢を科学的に分析しても、夢のような結論が出るとはとうてい思えない。科学とはそういうものだ、という諦めが必要であるらしい。著者らは数千にわたる夢の報告を読み、さまざまな視点でそれを整理する。私ならとうていやる気にもならない作業である。
夢に明確な定義はまだない。「夢か現(うつつ)かまぼろしか」と昔から言うくらいだから、寝ているときの脳の働きとでも言うしかない。著者は「夢とは睡眠中に出現する一連の思考、心象、情動である」と、とりあえずの定義から本書を始める。就学以前の子どもは夢と現実の区別がつかないという。学童期になると、夢は頭の中で起こることだと、たいていは理解するようになる。
夢はごく主観的なもので、そんなものが「科学」の対象になるのか。そう思う人もあろう。評者の意見だが、夢は形式と内容を分けて考えるべきで、夢は寝ているときに見るというのは、夢の形式の一例で、「一富士、二鷹(たか)、三なすび」のように何の夢を見るかは内容である。形式は客観的に扱えるが、内容は難しい。ただし客観的な扱いが不可能というわけではない。
本書の最初の部分は、夢研究の歴史である。夢に関する言及はほぼ人類文明の最初から存在する。日本では中国由来の荘子の「胡蝶(こちょう)の夢」、ないし「邯鄲(かんたん)の夢」の故事が古典ともいえよう。欧米ではフロイトの『夢判断』が大流行してしまったので、それ以前の夢に関する研究がいわばうずもれてしまった。本書の第2章はフロイト以前の研究を丁寧に拾う。第3章は「夢の秘密を発見した とフロイトは思った」と題され、フロイトの『夢判断』批判となる。
第4章「新しい夢科学の誕生 睡眠中の精神をのぞく窓が開いた」からが神経科学としての本題に入り、レム睡眠の発見と睡眠のパターンと段階が解説され、夢との関連が紹介される。第5章は「睡眠 それは眠気を解消するだけのもの?」と題され、睡眠の意味が論じられる。それには身体を日常的に維持するハウスキーピング機能、記憶の強化、ピアノ、タイピング、楽器などの運動機能の向上、世界への理解や問題解決に資する、さらには記憶の整理というオフライン機能など、睡眠の意味が具体的に紹介される。
第6章は「犬は夢を見るのか?」で、意識に関わる議論がなされる。「睡眠中に脳が処理する情報は途方もない量だ。この作業を助けるために、脳のあちこちから拾ってきた意識のかけらの集まり、それが夢である」そう考える著者にとっては意識は当然無視できない話題である。第7章で著者は夢の働きを考察した近年の仮説を数え上げて、それぞれを論評する。(1)夢の働きはレム睡眠と同じである(2)夢は問題解決を助けてくれる(3)夢には進化に関わる働きがある(4)夢は情動を調節する働きをする(5)夢には適応の働きや生物学的な働きはない(6)夢には記憶に関わる働きがある。
第8章ではいよいよ著者たちの独自の仮説が「NEXTUP」と名付けられたモデルとして、提唱される。「夢を睡眠に依存する記憶処理の一形式と考える私たち独自のモデルを提案する。現象としては複雑だが、手つかずだった連想を発見し、強化して、既存の情報から新しい知識を抽出するものだととらえてほしい」。私の勝手な解釈を加えれば、意識の周辺に散らばる連想の弱いかけらを、進化における突然変異のようにとらえて、その変異を上手に有用な記憶に組み込み、いわば脳の中の世界に適応させるということであろう。
第9章「夢の中身はひと癖もふた癖もある」では夢の内容を扱い、「夢にはそのときどきの物語に納得できる感覚経験が埋めこまれているが、全体を通した連続性はない」との結論に達する。第10章「その夢はなぜ見たのか」はありふれた夢、典型的な夢つまり誰でもが見るような夢を扱い、反復夢や性的な夢を論じ、そうした内容と著者らの仮説が矛盾しないことを示す。
第11章「夢と内なる創造性」、第12章「夢の活用法」、第13章「夜中に大きな音がする PTSD、悪夢、その他夢に関連する障害」、第14章「意識する心、眠りつづける脳 明晰夢(めいせきむ)の手法と科学」はいずれも特殊な夢を扱い、最終章は第15章であり「テレパシー夢と予知夢 あるいは、なぜあなたはこの章の夢をすでに見たのか」というかなり挑発的なタイトルになっている。
ALL REVIEWSをフォローする