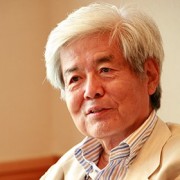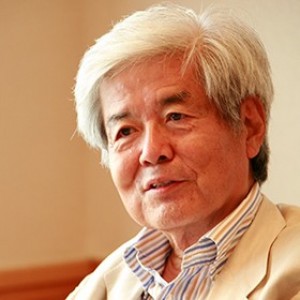書評
『情動はこうしてつくられる──脳の隠れた働きと構成主義的情動理論』(紀伊國屋書店)
既存の概念見直し脳機能を考える
最近の脳科学の動きを知るために、たいへん良い本である。ただし著者のいう古典的な脳科学の教育がしっかり入っている人には、いささか読みにくいかもしれない。主題は喜怒哀楽という言葉に代表される情動である。脳には主として情動を担う部位がある。たとえば大脳辺縁系。私のように古い教育を受けた者には、そういう知識がしっかりと入っている。
著者はそれをほぼ全面否定する。そもそも喜怒哀楽、情動とはどういう基準で確定されるか。顔の表情でわかる。ではそれを解析してみよう。表情は顔面筋の動きで測定可能なはずである。では怒りの場合に、どの筋肉がどのくらい動いているか、たとえば筋電図で調べてみよう。結論ははっきりしている。定まった結果が得られない。
調査不足じゃないのか。もちろん、いくら調べても、そう反論することは可能である。無限にデータをとることはできないからである。でもともあれ、事実は通説とは逆のことを指しているらしい。その方向で考えてみたらどうか。
ここ三十年の脳科学では、生きた脳を非侵襲的に調べることができるようになった。fMRIはその典型である。脳磁図も脳波も近赤外線も使える。それでわかることは、活動している脳の部位である。逆に言えば、それしかわからない。その結果を見ていれば、なにをする時に、脳のどの部位が働くか、その解析が中心になってしまう。例数が少ないうちはそれでよい。しかしたくさんの例が調べられるようになって、データが蓄積すると、いくらでも例外が出てくる。著者の仕事はまさにその段階で始まった。
脳機能に関する研究には、はじめから二つの立場がある。全体論と局在論である。非侵襲的な手段による脳研究は局在論にならざるを得ない。脳のどこが働いているか、いわばそれを見るだけだからである。その意味では著者の立場は全体論である。たとえば縮重という現象がある。良い訳語ではないが、まあやむを得ない。これは同じことをするのに、脳内の違う経路が使われる場合をいう。物理学者のファインマンは、自伝の中で黙って数を数えるという例を挙げている。この時に、声を出さずに、でも頭の中で声を出して数える人が多い。日めくりカレンダーを使う人もいる。日本人ならソロバンをはじくという方がわかりやすい。声で数える人は、数えながら本が読める。カレンダーをめくる人は、数えながらおしゃべりができる。どちらの人も逆はできない。同じ結果を出すのに、違う経路を使われたら、ある働きに関して、脳のどこが使われているのか、簡単に結論が出せない。
同様にして、さまざまなことをあらためて考え直す必要がある。著者はそれを試みる。従って、多くの概念をあらためて見直し、さらには新語を作りださなければならない。だから古典的な脳科学の教育を受けた人には、読みにくいだろうと思う。古典的には常識になっていることを変えなければならない。著者は学会で聴衆の一人を怒らせたという挿話を紹介する。無理もないと思う。常識を変えるのは簡単ではないからである。
新しい見方は、新しい用語を必要とする。水は子どもでも知っている物質である。しかし化学ではそれをHとOで記す。HもOも日常とはなんの関係もない、その意味では未知の概念である。HやOという未知の概念で、水という既知の物質を説明する。既知を延長すればわかる。それは知的怠惰である。著者と訳者は、巻末に丁寧な解説資料を付している。これを大いに参考にしてほしい。
ALL REVIEWSをフォローする