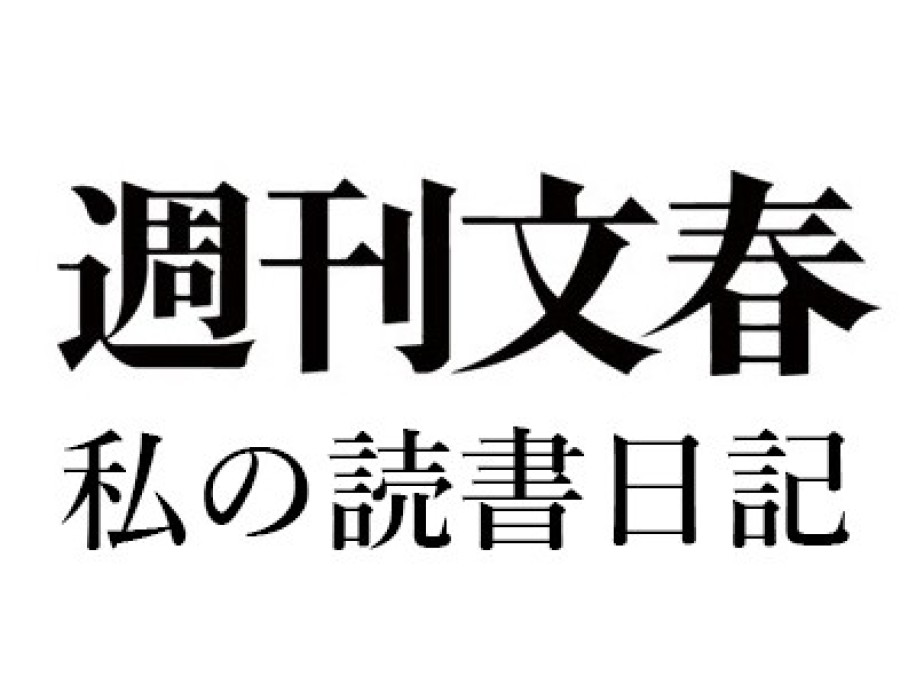書評
『奥本大三郎随想集 織田作之助と蛍』(教育評論社)
小うるさく小難しいのを脇に置き 等身大の著者の姿を刻みつけた
タイトルにそえて小さく「奥本大三郎随想集」とある。随想とは懐かしい言葉だ。ちかごろは随筆、エッセイに席をゆずって、あまり使われないのではなかろうか。ここでは、いかにも似合っている。想に随(したが)ってしるされた。想のまにまに生まれては消えた。だから1「作家論」、2「鶏肋集」とに二分され。――それにしても「鶏肋」とは、これまたとても懐かしい。意味の怪しい方は辞書を引いてください。「ケイロク」と訓(よ)みます。精肉店の店先で、買おうか買うまいか思案する状態とかさなります――。
奥本大三郎の随想がたのしいのは、どのエッセイにも等身大の著者の姿が刻みつけられているからである。そもそもタイトルの一篇にしても、誰が天下の織田作を、蛍にかこつけて語ったりするだろうか。それも夜店大好きだった青年作之助が、並んでいる露店を際限なくあげていくなかで、「橋のたもとの暗がりに出ている蛍売りの蛍火の瞬き」と出会ったのがきっかけだった。そんな一行に目をとめるのは、あとにも先にも奥本大三郎ひとりと思われる。
あるいはモダニスト牧野信一の華やかな文学意匠には目もくれず、かかわり合ったのはただ一つ、友人坂口安吾が「牧野さんが時々庭球選手のような颯爽たる服装でやってきて、おい昆虫採集に行こうと言う」の一文だった。当時、「庭球選手」のような格好で虫とりに行くのは、よほどのマニアであったと思われるが、それにこだわって文学を語ろうとするなど、奥本大三郎以外にいるとは思えない。
すっかりファーブルの先生として有名になってしまったが、もともと気鋭のフランス文学者としてランボーのレトリックなどを論じ、虫が顔を出す前は博学で知られていた。外国文学を論じても、難解な言葉、背のびした言葉、自分には感触のない言葉は一切使わなかった。おのずと外国文学などとは離れて、自分が幼いころからやしなってきたイキモノの世界に落ち着いたが、巧みなレトリックと博学の素地は、随想の味づけに生きてくる。文字どおりの自分を語って、「親父が製粉会社を経営していた」につづき、こんなふうに言う。「私は、水車屋の三男である。ただし、長靴を履いた猫は付いていなかった。自分でカラバ侯爵にでも何にでも成りすまし、世渡りをして行かなければならない」
随想には、ときおりおシャレがまじらないとつまらない。フランス語の教師になったのは、給料がもらえるからで、「その日のパン」の心配ばかりしていたのでは趣味の虫どころではないだろうと考えてのこと、カッコして自分で注釈をほどこしている。「こう見えても、一応、ちゃんと考えているのである」
芥川龍之介や南方熊楠や開高健の話があれば、アリやカネタタキの話もあり、ファーブル昆虫館の一日やらお金の話がある。雑多なようで、しかし一貫して読めるのは、人であれ、虫であれ、建物であれ、世相であれ、つねにそこに通底している生活ぶりが語られているからだ。しかつめらしい文学論議や、鬱陶しい社会論などは想のうちに入ってこない。小うるさい議論になりかかると、「それはさておき」のひとことで、あざやかに転論する。どこまでも等身大の著者がいて安心だ。
ALL REVIEWSをフォローする