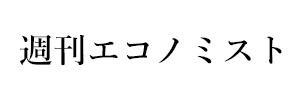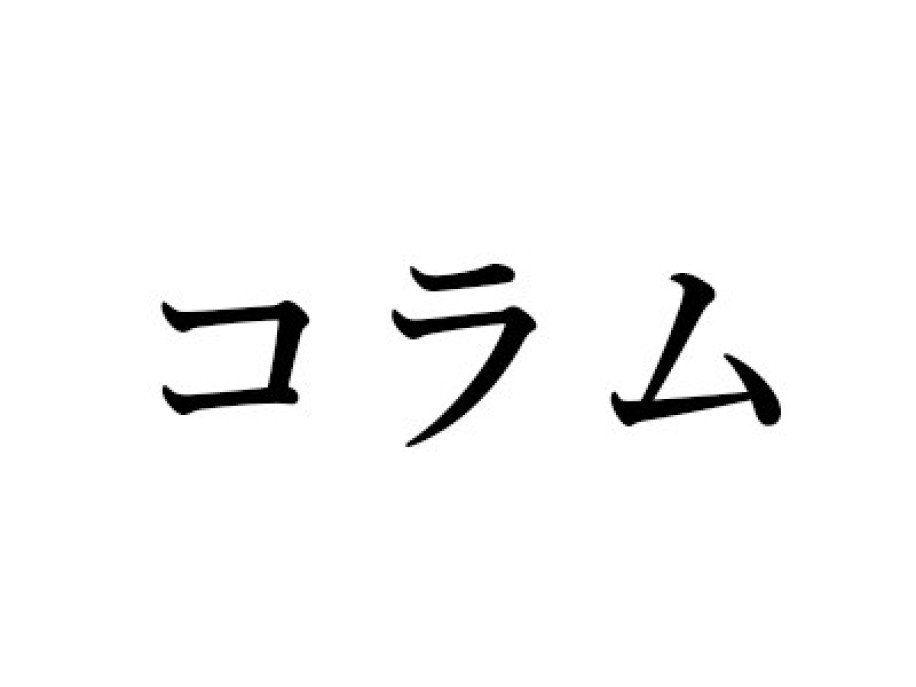読書日記
町田康「読書日記」週刊エコノミスト2016年11月15日号|「追い詰めた言葉が詩や歌になる時」『近現代詩歌』『詩、ってなに?』
追い詰めた言葉が詩や歌になる時
ここ10年ほど。音楽に対する積極的な興味を失い、これを聴くこともあまりせず、自ら人前で演奏することも勿論なかった。ところがこの夏(事務局注:執筆は2016年11月)、にわかに関心が蘇(よみがえ)り、インターネットで未知の音楽を渉猟したり、山中千尋さんの新作を聴くなどした。そういうことをしながらも根底で文学のことを考えてしまう私はやはり文学の鬼なのだろうか。或(ある)いは文学の猿なのだろうか。どちらかというと猿だろうが、もしかしたら犬かも知れない。
まあ、そんなことはどっちゃでもよいのだが、そうして歌を歌い、そしてまた歌詞を書きながら思うのは、言葉を重ねて意味を追い詰めていくと、追い詰まったその一点が爆発し、積み重ねてきた言葉が粉塵(ふんじん)として広いところに舞って、感情が勝(か)った訳のわからぬ無茶苦茶な言葉の繋(つな)がりでありながら魂に真っ直ぐ刺さる言葉、すなわち歌に、なっていくなあ、ということだった。
それはでもそうして言葉を緻密に積み重ねている立場から見ると、ものすごく卑俗だったり、雑だったり、下手くそ・不注意・不正確に見えて情けない気持ちになったりする。けれどもそれはその背景になる音によってそうなるしかなかったからで、それは不細工の方が多い神ならぬ人間の身体の現実に対応して響いている。
しかし言葉はどうしても突き詰める方向に向かうし、西洋の詩みたいな詩が本当の詩であんな詩を書かんとあかん。或いは、もっと言うと漢詩が本当の詩で、とか、欧米のロックが本物のロックで日本語はその拍子に乗りにくいから日本語の発音を変形させる、みたいな屈曲も経るから、元々の歌からどんどん走って遠ざかっていく。
けれどもその走る姿、姿勢こそが歌やんけ。なにが駅伝じゃ、なにがマラソンじゃ。車両通行止め、迷惑なんじゃ。てなもので、その歌の姿が書物から聞こえてくるのが、『日本文学全集29 近現代詩歌』(河出書房新社、2600円)で、池澤夏樹、穂村弘、小澤實がそれぞれ、明治以降の近現代詩、短歌、俳句を紹介していて、私のような素人がこれらをひとつびとつ時代を追って読んでいこうと思ったら、まずなにから読んだらよいかがわからないし、わかったとしても何十年かかるかわからず、その間、有為転変、いろんな出来事が起きて気がつくとそうしたことをさっぱり忘れ、「詩歌?なんのこってす。いまは椎茸(しいたけ)栽培の真っ盛りで忙しいんです。訳のわからないことを言わないでください」なんてことにならないという保証はどこにもない。
人間はその存在が歌
つまりなにが言いたいかというとそんなに時間をかけてもいられない、ということを言いたいのだが、その段、この本は本職の方々が予(あらかじ)め選んで、並べてくれたものを読めばよいのだから大変に楽で、詩歌、詩と歌が近づいたり遠ざかったり、歩いたり走ったり、また戻ったりする姿を読むことができる、まあ言わばセレクトショップのごときもので、ここに行っとけば間違いはおまへぬであろう。なんて言葉遣いを混ぜて遊ぶ姿勢は是か非か。詩というものはもっと厳粛で神聖なものとしなければならない。という具合に詩を尊敬するのはよいのだけれども、尊敬のあまり、拝み方の難しい、なんだか扱いの面倒な神様のように感じて、「詩ぃですか。いやー、いまはいいですわー」みたいに思って遠ざけている人が多く、また詩人に対しても、普通の人間とは余程変わった特殊人間のように思っている人は多いのではないか、っていうか、かくいう自分もそのなかのひとりで、道で知っている詩人を見かけても見て見ぬ振りをして、そそくさと通り過ぎ、牛鍋を食べに行って、「鳴呼(ああ)、ヴェヂタリヤンになりたい」と嘯(うそぶ)くなどしていたのだが、平田俊子編『詩、ってなに?』(小学館、1400円)を読んで蒙(もう)を啓(ひら)かれた。ここでは当代の詩人が、ここまで書いてしまっていいのか? と心配になるくらい、詩について、その秘密を明かしていて、わかりやすくておもしろい。こうなると人間はその存在そのものが歌である、ってことになってしまう。ルルル。とスキャットして頭に丸い玉をつけたくなる。
ALL REVIEWSをフォローする