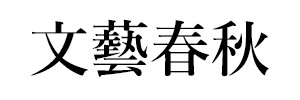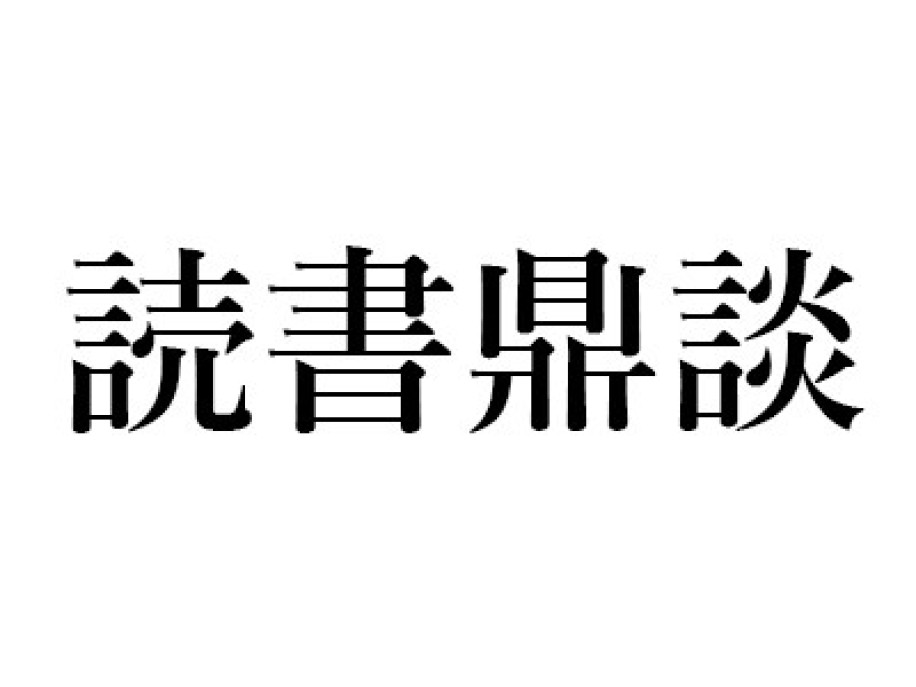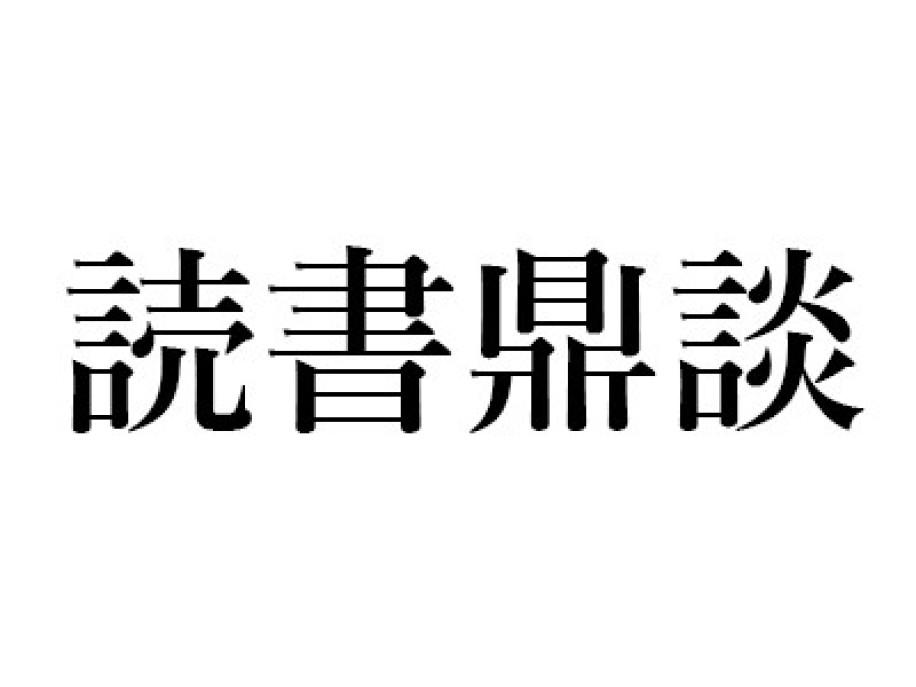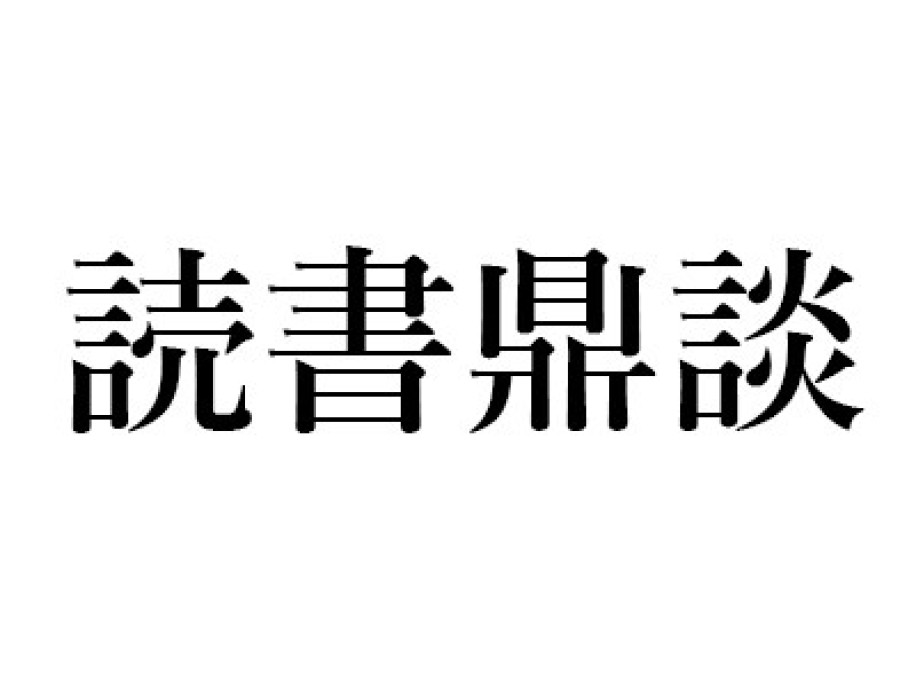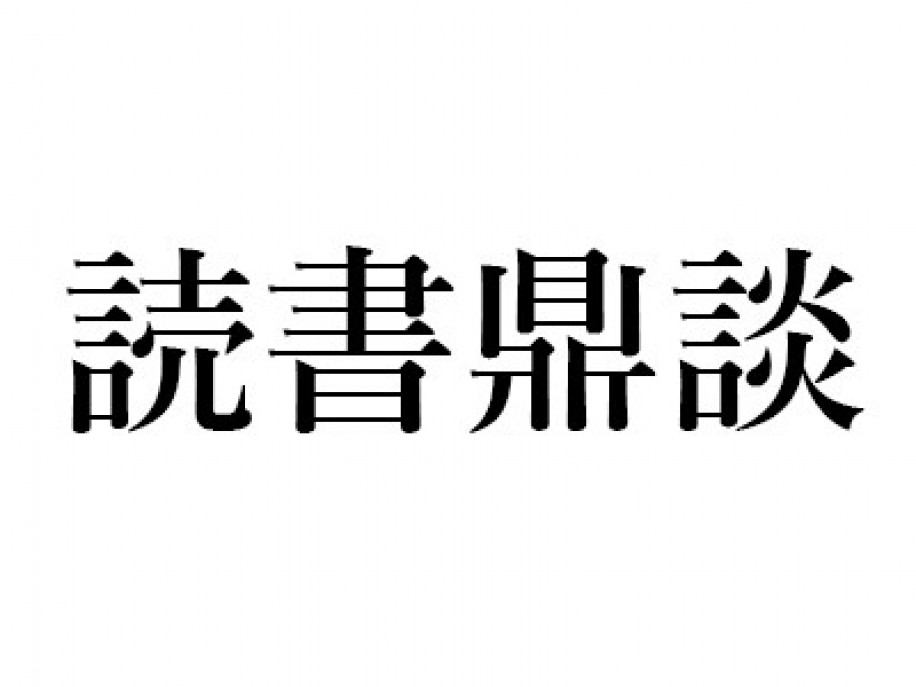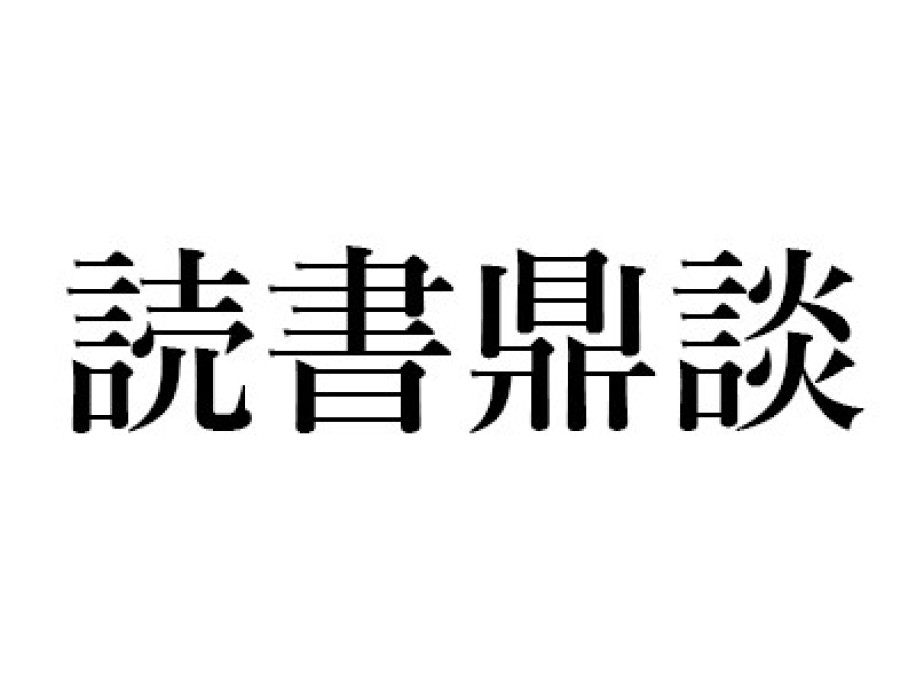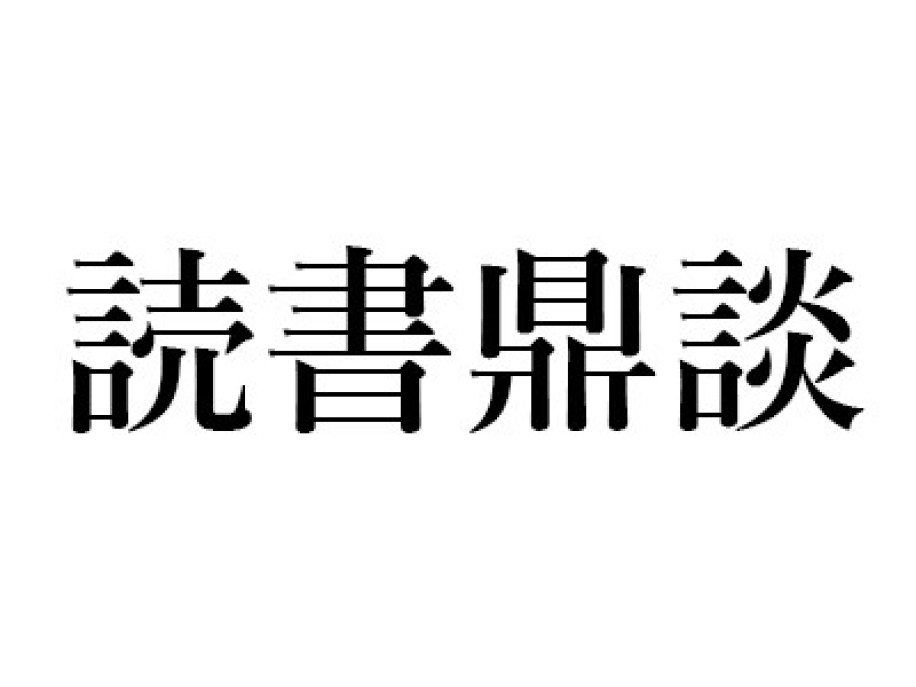対談・鼎談
真鍋博『イラストからの発想―絵地図から国家計画まで』(PHP研究所)|丸谷才一+木村尚三郎+山崎正和の読書鼎談
木村 これは、イラストレーターとして活躍されている真鍋さんが、自由に社会をデザインしたものです。新しいアイデアが次々と出てきて、全体として、発想が非常に爽やかです。たとえば、わたしがいちばん傑作だと思ったのは、子供に与える本をB全判のでっかい絵本にしたらどうかという提案です。
山崎 屏風みたいなものですな。
木村 B全判は七三センチ×一〇三センチの大きさですが、これにマンモスの鼻を実物大で描いたらどうか。いまの子供はテレビでばかりものを見ているから、実物の大きさ、迫力を知らない。何でもテレビ流に横長の小さな画面におさまるよう、かわいく、カラフルな世界でしか映し出されてない。だから巨大な絵本をつくり、みんなで教室へかついできて、その本の中に何が描かれているか、その期待に胸躍らせる。
こういう提言というのは、いまわたしたちが虚像の世界の中に生きているだけに、子供にとっては非常に必要なことではないかと思うわけです。
それから、ニューヨークの絵地図は非常に精密な鳥敵図として描かれている。なぜ東京が絵地図にならないか。東京はあまりにも大きすぎるというわけです。実際に見える範囲が手の届く範囲であり、その程度の小さな都市をつくらなくてはいけない。現代の大都市というものを、われわれの身近なものに取り戻すべく、規模とか、あり方を考え直さなきゃいけない。
こういう自由な発想はだれでもできると思いがちですが、いざ自分がやってみると、案外貧しい考えしか浮かんでこないものです。その点、こういう提言は、貴重なものではないかという気がしたわけです。
山崎 わたくし自身がニューヨークへ行ってこのマンハッタンの絵地図をたいへん重宝もし、それであの街に住むことが愉しくなったという記憶があるので、共感できました。本当にエンパイヤーステートビルの窓の数まで描いてあるんですね。
そういう地図をつくったのはボルマンという男なんですが、自分が生まれた西ドイツの小さな町が完全に空襲で破壊されて、その思い出を絵に描いて残したというのが最初だったというわけですね。確かに、そういうものだろうと思う。町というのは、何か、歌ってやったり、描いてやったりしないと、町そのものもきれいにならないし、人間との関係もできてこないんですね。
われわれが目に見える範囲とか、足で歩ける範囲をあまりにも失ったということを、著者は非常に具体的に書いている。たいへん、わたくしは共感しました。
しかし、それだから大都市は、小さくならなきゃならないというあたりは、ちょっと論理の飛躍がある。そのへんのところは、イラストレーターという立場に立てこもることの限界でしょうね。
丸谷 筆者の職業に密着した部分、自信がある部分についていっていることは、耳朶(じだ)を打つものがある。つまり、絵地図による都市論の部分。それから、たとえばおとぎ話の残酷さが最近はなくなって、これはよろしくないんじゃないかという発言。印刷の問題。そういうところの指摘は、さすがに元がかかっている感じで、教えられるところが多い。
ところが、たとえば納税を目的別にする話がありますね。つまり、税金は目的がわかりにくいから納めにくいのである。それを、わたしの税金は福祉に使ってください、といって納めるならば、納めるほうも気持がいい。まあ、そういう議論だな、いってることを簡単に要約すれば。
でも、ぼくにいわせれば、政治論的にこれほど無知な話はない。ユートピア的思考ってものは、もう少し恰好がついてるものですよ(笑)。
木村 わたしも印刷のところは非常におもしろいと思ったんです。
日本画には絵画的なシステムがあり、〈システムにもとづく決断で描かれている〉というのは、非常にいい指摘だと思いました。
丸谷 反対するわけではありませんけど、ぼくは昔本郷に下宿していたんですが、すぐ隣の家に日本画家が住んでいた。それは、周到な計画性といえばそうなんだけれども、毎日おんなし図柄のおんなし絵しか描いていない(笑)。
そういうステロタイプ化に陥りやすい面もあるわけね。
山崎 この人のいいところは、ある固定的な立場に立っているんじゃなくて、問題が混同されていたり、整理されていないことから起こるおかしさを指摘しているという点ですね。たとえば、自動車というものは、本当の意味の自動車ではなくて、実は手足で動かしているクルマなんだといっている。
木村 手動車である……(笑)。
山崎 したがって、交通は自動化もしていないし、システムもないんだから、交通信号がいくら自動的に点滅しても、うまくゆかないのは当り前だという、つまり、中途半端だからいけないんだというわけですよね。
そういう視点のあり方は、わたくしは、それぞれに共感をおぼえるんです。
ただ、やはり、全体を読んで思うことは、ここに述べられていることが全部漫画でしめされていたら、どんなにかおもしろかったろう。
木村 なるほど。
山崎 たとえば文章のテンポですね。いろいろなイメージが出てきたり、着想が飛躍していく早さが、文章としては妙におもしろくないんですね。これが絵だったら、多分その唐突さ自体微笑を誘ったろうと思う。それが文章になることによって、妙に早口になったり、妙に説明になってしまったりするところがありますね。
木村 人間動物園なんて、確かに絵のほうがよかったかもしれませんね。
山崎 言葉にしてしまえば、何だ、ということになるわけですね。
丸谷 着想はおもしろいんですけれども、本としての奥行きが浅いんですねえ。着想だけで書こうとすると、えてしてこういうことになりがちなんですよ。文章を一つ書くためには、着想だけではダメで、着想を展開してゆく思考のエネルギーがなければならない。この人にはそれがすくないと思う。
山崎 真鍋さんという人は、絵を描く作業の中で、丸谷さんが文章においてなさる作業と同じことを、きっとしていられるにちがいない。一本の線を引き、色を塗る過程において、彼の着想が、もう一段階暖められたと思うんですね。それが文章という、彼にとっては、副次的なコミュニケーションの手段に頼ったおかげで、生で出てくるところがたくさんあるんですね。
木村 だから、丸谷さんが真鍋さんの文章について不満を持たれる点は、丸谷さんが、もし絵を描いたときに、真鍋さんが不満をもつのと同じじゃないか(笑)。
山崎 あいにくこれは文章で書かれていたということですね。
丸谷 ぼくは絵は売らないもの(笑)。
【この対談・鼎談が収録されている書籍】
山崎 屏風みたいなものですな。
木村 B全判は七三センチ×一〇三センチの大きさですが、これにマンモスの鼻を実物大で描いたらどうか。いまの子供はテレビでばかりものを見ているから、実物の大きさ、迫力を知らない。何でもテレビ流に横長の小さな画面におさまるよう、かわいく、カラフルな世界でしか映し出されてない。だから巨大な絵本をつくり、みんなで教室へかついできて、その本の中に何が描かれているか、その期待に胸躍らせる。
こういう提言というのは、いまわたしたちが虚像の世界の中に生きているだけに、子供にとっては非常に必要なことではないかと思うわけです。
それから、ニューヨークの絵地図は非常に精密な鳥敵図として描かれている。なぜ東京が絵地図にならないか。東京はあまりにも大きすぎるというわけです。実際に見える範囲が手の届く範囲であり、その程度の小さな都市をつくらなくてはいけない。現代の大都市というものを、われわれの身近なものに取り戻すべく、規模とか、あり方を考え直さなきゃいけない。
こういう自由な発想はだれでもできると思いがちですが、いざ自分がやってみると、案外貧しい考えしか浮かんでこないものです。その点、こういう提言は、貴重なものではないかという気がしたわけです。
山崎 わたくし自身がニューヨークへ行ってこのマンハッタンの絵地図をたいへん重宝もし、それであの街に住むことが愉しくなったという記憶があるので、共感できました。本当にエンパイヤーステートビルの窓の数まで描いてあるんですね。
そういう地図をつくったのはボルマンという男なんですが、自分が生まれた西ドイツの小さな町が完全に空襲で破壊されて、その思い出を絵に描いて残したというのが最初だったというわけですね。確かに、そういうものだろうと思う。町というのは、何か、歌ってやったり、描いてやったりしないと、町そのものもきれいにならないし、人間との関係もできてこないんですね。
われわれが目に見える範囲とか、足で歩ける範囲をあまりにも失ったということを、著者は非常に具体的に書いている。たいへん、わたくしは共感しました。
しかし、それだから大都市は、小さくならなきゃならないというあたりは、ちょっと論理の飛躍がある。そのへんのところは、イラストレーターという立場に立てこもることの限界でしょうね。
丸谷 筆者の職業に密着した部分、自信がある部分についていっていることは、耳朶(じだ)を打つものがある。つまり、絵地図による都市論の部分。それから、たとえばおとぎ話の残酷さが最近はなくなって、これはよろしくないんじゃないかという発言。印刷の問題。そういうところの指摘は、さすがに元がかかっている感じで、教えられるところが多い。
ところが、たとえば納税を目的別にする話がありますね。つまり、税金は目的がわかりにくいから納めにくいのである。それを、わたしの税金は福祉に使ってください、といって納めるならば、納めるほうも気持がいい。まあ、そういう議論だな、いってることを簡単に要約すれば。
でも、ぼくにいわせれば、政治論的にこれほど無知な話はない。ユートピア的思考ってものは、もう少し恰好がついてるものですよ(笑)。
木村 わたしも印刷のところは非常におもしろいと思ったんです。
油絵が西欧の体質そのまま何回も筆を重ねる重厚な絵画なら、日本画は淡白といおうか簡潔な絵画だ。しかし、その簡潔さは下絵を何枚も描いて、それを和紙や絹布の上に写しとってはじめて筆を入れはじめるという周到な計画性にもとづいている
日本画には絵画的なシステムがあり、〈システムにもとづく決断で描かれている〉というのは、非常にいい指摘だと思いました。
丸谷 反対するわけではありませんけど、ぼくは昔本郷に下宿していたんですが、すぐ隣の家に日本画家が住んでいた。それは、周到な計画性といえばそうなんだけれども、毎日おんなし図柄のおんなし絵しか描いていない(笑)。
そういうステロタイプ化に陥りやすい面もあるわけね。
山崎 この人のいいところは、ある固定的な立場に立っているんじゃなくて、問題が混同されていたり、整理されていないことから起こるおかしさを指摘しているという点ですね。たとえば、自動車というものは、本当の意味の自動車ではなくて、実は手足で動かしているクルマなんだといっている。
木村 手動車である……(笑)。
山崎 したがって、交通は自動化もしていないし、システムもないんだから、交通信号がいくら自動的に点滅しても、うまくゆかないのは当り前だという、つまり、中途半端だからいけないんだというわけですよね。
そういう視点のあり方は、わたくしは、それぞれに共感をおぼえるんです。
ただ、やはり、全体を読んで思うことは、ここに述べられていることが全部漫画でしめされていたら、どんなにかおもしろかったろう。
木村 なるほど。
山崎 たとえば文章のテンポですね。いろいろなイメージが出てきたり、着想が飛躍していく早さが、文章としては妙におもしろくないんですね。これが絵だったら、多分その唐突さ自体微笑を誘ったろうと思う。それが文章になることによって、妙に早口になったり、妙に説明になってしまったりするところがありますね。
木村 人間動物園なんて、確かに絵のほうがよかったかもしれませんね。
山崎 言葉にしてしまえば、何だ、ということになるわけですね。
丸谷 着想はおもしろいんですけれども、本としての奥行きが浅いんですねえ。着想だけで書こうとすると、えてしてこういうことになりがちなんですよ。文章を一つ書くためには、着想だけではダメで、着想を展開してゆく思考のエネルギーがなければならない。この人にはそれがすくないと思う。
山崎 真鍋さんという人は、絵を描く作業の中で、丸谷さんが文章においてなさる作業と同じことを、きっとしていられるにちがいない。一本の線を引き、色を塗る過程において、彼の着想が、もう一段階暖められたと思うんですね。それが文章という、彼にとっては、副次的なコミュニケーションの手段に頼ったおかげで、生で出てくるところがたくさんあるんですね。
木村 だから、丸谷さんが真鍋さんの文章について不満を持たれる点は、丸谷さんが、もし絵を描いたときに、真鍋さんが不満をもつのと同じじゃないか(笑)。
山崎 あいにくこれは文章で書かれていたということですね。
丸谷 ぼくは絵は売らないもの(笑)。
【この対談・鼎談が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする