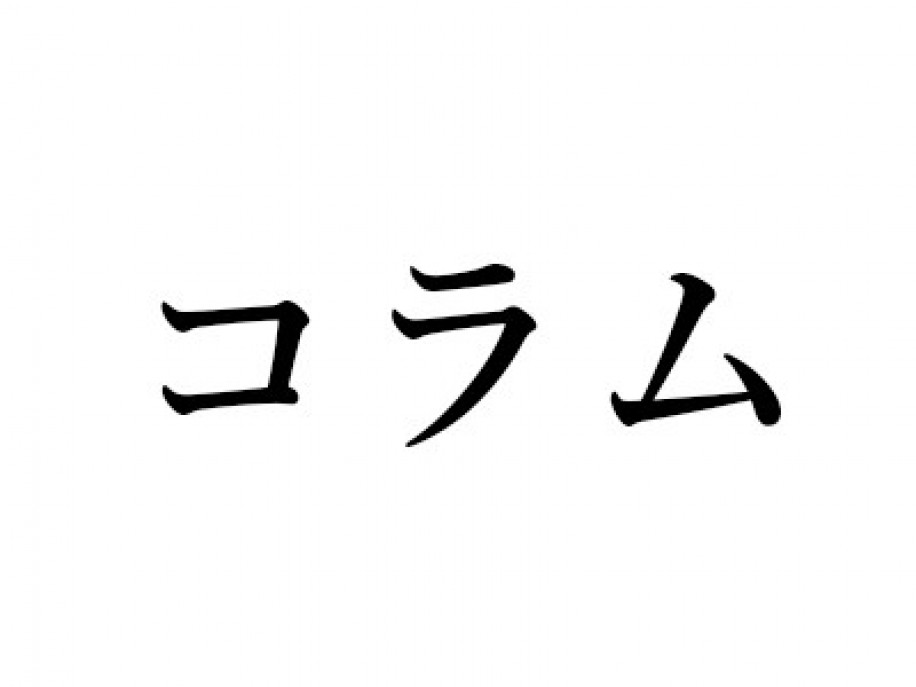書評
紫式部著、角田光代訳『源氏物語 上』(河出書房新社)、紫式部著、毬矢まりえ、森山恵訳『源氏物語 A・ウェイリー版 第1巻』(左右社)
画期的現代語訳と戻り訳で再創造
今年は日本における『源氏物語』にとって、革新的な年となった(ALL REVIEWS事務局注:本書評執筆時期は2017年12月)。一つは、角田光代による画期的な現代語訳の刊行が始まったこと。もう一つは、「源氏」の国際的研究においては、今なお最重要であるアーサー・ウェイリーの英訳、これを日本語に訳し戻す試みが登場したこと。後者は、佐復秀樹に次いで二回目の「戻り訳」である。角田訳を評して、池澤夏樹は「モダニズムに仕立て直すとは、こういうことである」と書いているが、『源氏物語』は平安時代にしてすでに、語り手のポジション、語りの複雑さと多重性、内面描写などにおいて、現代小説の資質を備えていた。そのモダン性を角田訳は鮮やかに引き出しているのだ。「帚木(ははきぎ)」で光君と友人らが女性の品定めをする会話など、今このときにも世界中でなされている気がするし(ほのかにBL風味)、「葵(あおい)」はゴシックホラーである。
角田訳の現代性の一つに、語り手の不可視性がある。英語のIのような語り手は出てこないが、物語の外部に語り手がいる。この語り手はしばしばほぼ存在を消し、現代小説に見られる三人称客観描写のような性質を帯びる。かと思えば、どこからともなく語り手≒作者の声が聞こえてくる部分もあり、「草子地」と呼ばれている。
角田訳が現代小説として読める秘密は、草子地を文体によって区別し、他の地の文から敬語を排した点にある。読者は語り手≒作者の存在を脇において読める。一方、草子地には、このように敬体が使用される。「帝(みかど)の御子(みこ)だからといって、<中略>褒め称(たた)えてばかりいたら、作り話に違いないと決めつける人もいるでしょう。だからあえて書いたのです」(「夕顔」)。
また、各帖の扉にも「真剣な恋だという噂(うわさ)が耳に入れば、紫の上も不安になるというものでしょう。朝顔の姫君は、拒み続けたということですが……」のような敬体のサマリーが、角田の筆で添えられている。訳者が紫式部と一体になって書いたメタ・メタ・テクストと言える。
さて、谷崎潤一郎はウェイリー訳に閃(ひらめ)きを得たというが、今回の「戻り訳」の訳者は、ウェイリー訳によって当時のイギリス読者の脳内に喚起されたであろう、「ヴィクトリアン・GENJI」の再現に努めていて異化効果が楽しい。漱石の英訳書『I Am a Cat』を日本語に訳し戻しても、決して『吾輩は猫である』に還らないという翻訳の隠れた不等号式を顕(あら)わにする。人物は「エンペラー・キリツボ」「コキデン」「ロンリー・プリンセス」などと表記され、彼らはパレスに住んで、ワインを飲み、マミング劇(欧州の冬の祭り)を見たりする。宮中の位は「ワードローブのレディ」に「更衣」と漢字でルビを振る表記が基本のようだが、一方、乳母は「ナース」ではなく、乳母に「めのと」とルビを振る普通の表記だったり、阿闍梨も英訳のdeaconを一度「助祭」と訳して「アジャリ」とカナでルビを振ったりする。「戻り訳」という実験的試みは自由な遊び心を楽しむべきだが、これらが時に訳文の恣意(しい)性に見えてしまった。例えば、町田康が「インディーズ」「スタッフ」などのカタカナ語とくだけた会話文と古語を取り混ぜて自在に新訳した『宇治拾遺物語』に、多くの人が夢中になるのは、町田の作家人生が投影された文体と世界観が読者を圧倒するからだ。
いずれにせよ、二つの『源氏物語』の新訳は、「源氏」の解体分析であると同時に、再統合であり再創造と言えるだろう。
ALL REVIEWSをフォローする