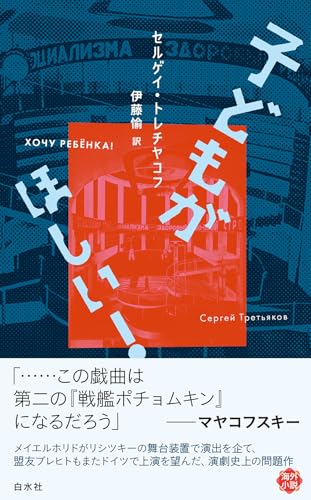書評
『レディ・ムラサキのティーパーティ らせん訳「源氏物語」』(講談社)
時空超え世界が響きかわす創作的翻訳
書名の「レディ・ムラサキ」は紫式部のこと。つまり本書は『源氏物語』をめぐる本なのだが、あまたある源氏関係書の中でも類書がまったくないほどユニークで、しかも魅力的な『源氏物語』への招待である。予備知識がなくても楽しめる平易な書き方になっているが、『源氏物語』の現代日本語訳、英訳、フランス語訳から、ロシア語訳、中国語訳まで視野に入れた本格的な翻訳論でもあり、中国文学、英文学、仏文学などを縦横無尽に参照した比較文学・世界文学論でもある。それと同時に、姉妹である二人の共著者自身の源氏物語翻訳経験を振り返った私的随想の要素も強く、二人の間の親密な対話も文中にしばしば挿入される。たとえば、この二人は、イギリスの天才的東洋学者アーサー・ウェイリーによる英訳版『源氏物語』(一九二五―三三、英語への世界初のほぼ全訳)から日本語への翻訳に取り組んだ際に、なんとも大胆なことに、登場人物名をすべてカタカナ表記にした。ゲンジの親友と言うべき頭中将はトウノチュウジョウとなる。二人の共訳者はさすがにためらった。そこで二人の間で、こんな対話が交わされたという。
「長いよね? カタカナ読みにくいかな?
でも『罪と罰』のラスコーリニコフだって、『カラマーゾフの兄弟』のスメルジャコフだって長いわよ(中略)
そもそもドストエフスキーだって長いものね
世界文学と思えば大丈夫、いける」
かくしてこの二人による『源氏物語』の日本語訳では、光源氏は「シャイニング・プリンス・ゲンジ」、桐壺帝は「エンペラー・キリツボ」として現れることになった。
この日本語訳(『源氏物語 A・ウェイリー版』全四巻、左右社、二〇一七―一九年)は英語から日本語に訳し直したものなので、一般的には「戻し訳」と呼ぶべきだろう。しかし二人の訳者はそれを「らせん訳」と呼ぶ。どういうことだろうか? いまからほぼ千年前の日本語で書かれた『源氏物語』のテクストをAとする。それをほぼ百年前にウェイリーが訳した英訳はB。今度はそのBに基づいて毬矢・森山が新たな現代日本語訳のA(´)を作った。しかしA(´)は単純にAに戻ってくるのではなく、Bに含まれた様々な要素もB以降百年の日本語の発展も吸収した結果の発展バージョンである。それをイメージ化してみると、渦を巻きながら上昇していくらせん、ということになる。
本書で終始強調されているのは、『源氏物語』が閉ざされた狭い宮中に限定されているのではなく、広く世界に開かれたものだということである。『源氏物語』には白居易の「長恨歌」をはじめとする中国詩への言及が織り込まれているだけでなく、「唐物」の織物や中国の風習や文物が頻出する。さらに二人の訳者の探索は、座高が高く、象のようにおそろしく長い鼻をした末摘花の出自にもおよぶ。二人の推測によれば、末摘花の異様な容貌は「西洋人」に近く、ひょっとしたら彼女には渤海(ぼっかい)人の血でも混じっていたのではないか、というのである。突拍子もない思い付きだろうか? しかし当時から「日本は東アジアのなかの一国としても存在した」のだ。かくして、ゲンジの美しい恋人たちの中で単に醜い女と扱われてきた末摘花こそが「世界文学の登場人物としても相応しい」と、評価される。驚くべき転換ではないか。
他方、ウェイリーの英語テクストは英語圏・西洋の様々な先行作品と響きかわしている。ウェイリーが「ムーア」(荒野)という単語を使えば、ブロンテ姉妹の世界(特に『嵐が丘』)が連想され、ライラックとあればエリオットの『荒地』が想起され、美しい顔を花にたとえた和歌が出てくれば、そこにはシェイクスピアのソネットが響いている、といった具合だ。さらに興味深いのは、ウツセミ(空蟬)が脱ぎ落とす小袿(こうちき)(女性衣服の一種)をウェイリーが「スカーフ」と訳している点だ。これを翻訳の失敗とか誤訳と見るむきもあるが、毬矢・森山の二人はここにこそ積極的な意味を見出す。この「スカーフ」とは、シェイクスピアの『オセロー』に登場するハンカチにつながるものだというのだ。
ウェイリーの英訳はこのように西洋の多岐にわたる文脈を踏まえてこそ成り立ったものだが、同時代を見れば、モダニズム文学の隆盛期、ちょうど彼の友人モンクリーフがプルーストの『失われた時を求めて』の英訳に取り組んでいたころで、『源氏物語』はウェイリーの翻訳によってプルーストと並んで二〇世紀の世界文学の星座に入ったのだった。いまやそれが毬矢・森山訳によって二一世紀の世界文学の一翼を担うようになった。本書は時空を超えて様々な文学が響きかわす、その目くるめく世界への招待であると同時に、『源氏物語』をめぐる二人の創作的翻訳(トランスクリエーション)のエッセンスでもある。
ALL REVIEWSをフォローする