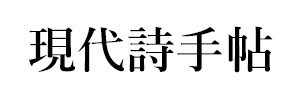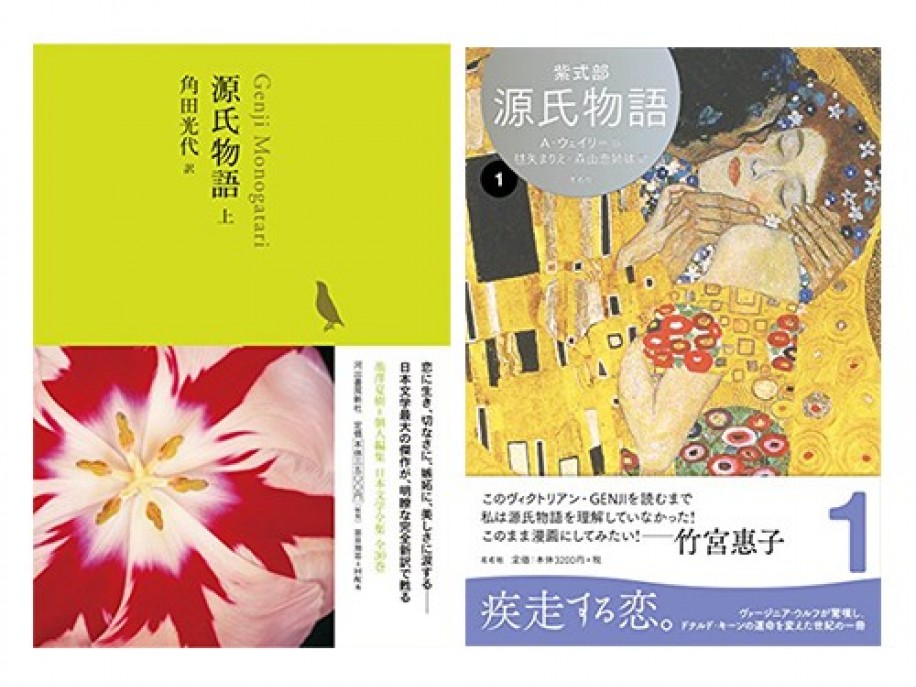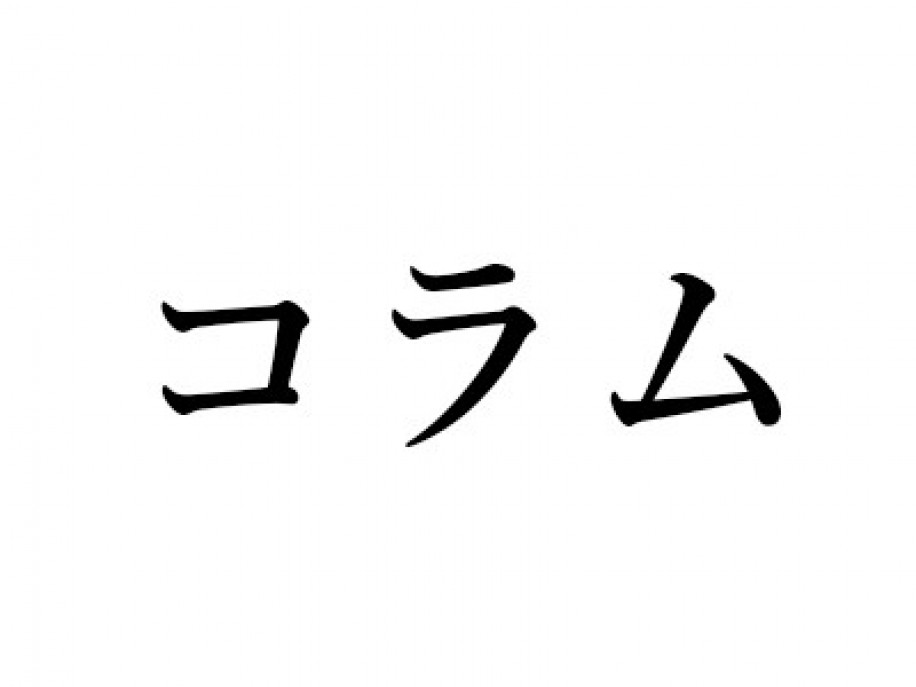書評
『源氏物語 A・ウェイリー版1』(左右社)
世界文学としての『源氏物語』
『源氏物語』の日本語への〈戻し訳〉について考えるとき、「世界文学」という言葉が思い浮かぶ。1880年代に末松謙澄によって初めて英訳が試みられてから、サイデンステッカーらによる複数の翻訳が出版された。まず、本著の〈戻し訳〉はなぜウェイリーでなければならなかったのか。イタリア語訳やドイツ語訳などがウェイリーの英訳版の重訳であることをみても、この版が世界的に重要な位置を占めていることは明らかであるし、『源氏物語』の原文から離れずに比較的忠実な訳をした谷崎潤一郎でさえ、「原作を貫く精神とリズム」を「生かし得てゐる」ウェイリー訳に大いに感嘆している。
それでは、既に刊行されている佐復秀樹訳『ウェイリー版 源氏物語』(平凡社)による〈戻し訳〉と本書の翻訳では何が違うのか。なにより瞠目に値するのは、『源氏物語』をいったん自らの世界に取り込んで再構築するプロセスでモダニズム固有の芸術感覚を色濃く反映させたウェイリーの手法に倣い、毬矢、森山氏も翻訳する過程で、その感覚を重要視した点だ。モダニズム作家ヴァージニア・ウルフがウェイリー訳を読んで、葵、若紫、夕顔、末摘花など、あらゆる階級の女性に目を留める源氏の趣味(テイスト)を高く評価した背景には、彼女自身の incongruity(多様性/不統一)の美学がある。ウェイリーの友人でもあったウルフは、彼が映し出した紫式部の世界観を「美しい」と評する。ウルフの「生い茂る雑草や風に埋もれていく古い家屋、荒漠たる景色、滝の音、砧をうつ木槌の音、雁の鳴き声、赤鼻のプリンセス」という要約からも、その訳の特色が垣間見えるだろう。
毬矢、森山姉妹の挑戦は、まさに視覚に訴える彩り豊かな花にも喩えられうるモダニズム文学の美の再現ともいえる。二人の細部に渡る努力は、Her lodging was in the wing called Kiritsubo.というウェイリーの文の訳ひとつとってみてもわかる。佐復氏のように “wing” を「対」とは訳さず、「本殿から離れたウィング」と訳すことで、その場所をイメージできない現代読者の想像力を喚起すると同時に、イギリス人の言語感覚も残している。シャイニング・プリンスといった表記も同様の効果があろう。森山氏は大学院でウルフを研究していたようだが、言葉の変換過程でそのモダニズムへの深い理解が遺憾なく発揮されている本書は「世界文学」の翻訳と呼ばれるに相応しい。
第一巻は、ゲンジの誕生が描かれる「桐壺」から彼の人生に翳りが見え始める「須磨」「明石」までを収録しているが、近刊の第二巻では、「朝顔」「玉鬘」など、さらに陰翳深く彩られた帖もあるので、そちらをどう〈戻す〉のか、期待したい。
ALL REVIEWSをフォローする