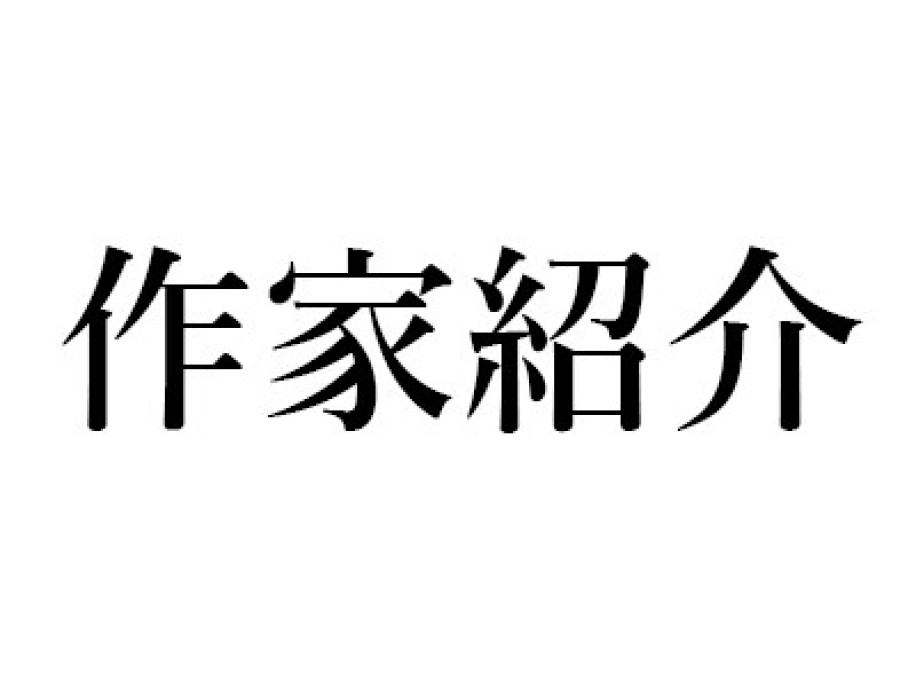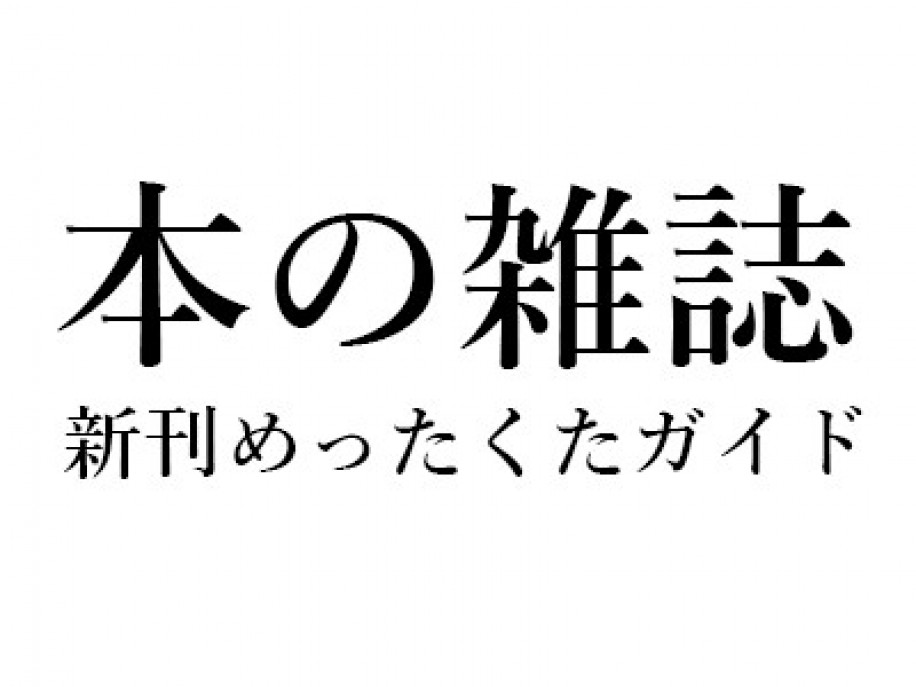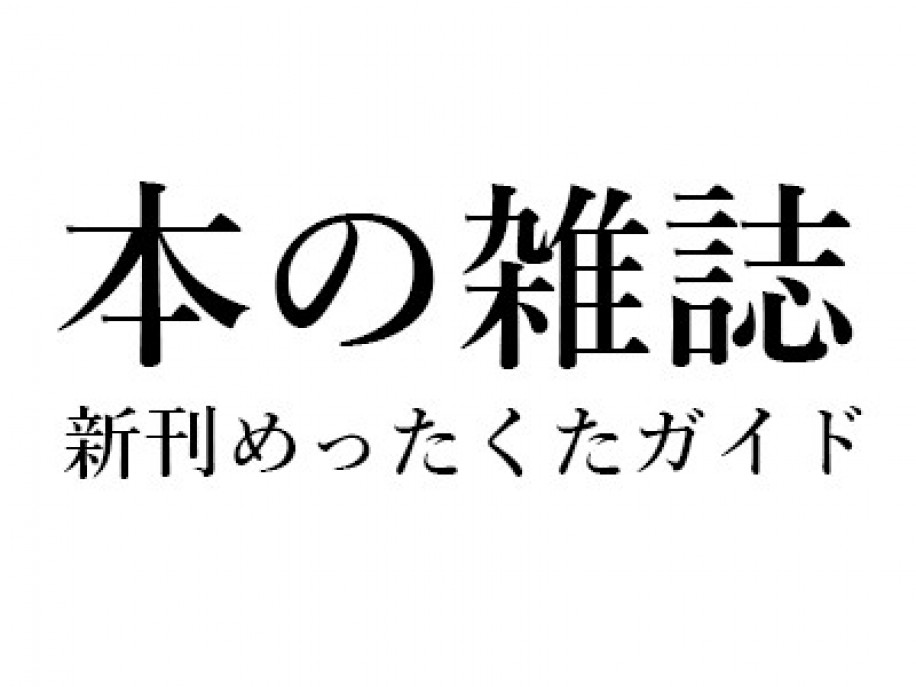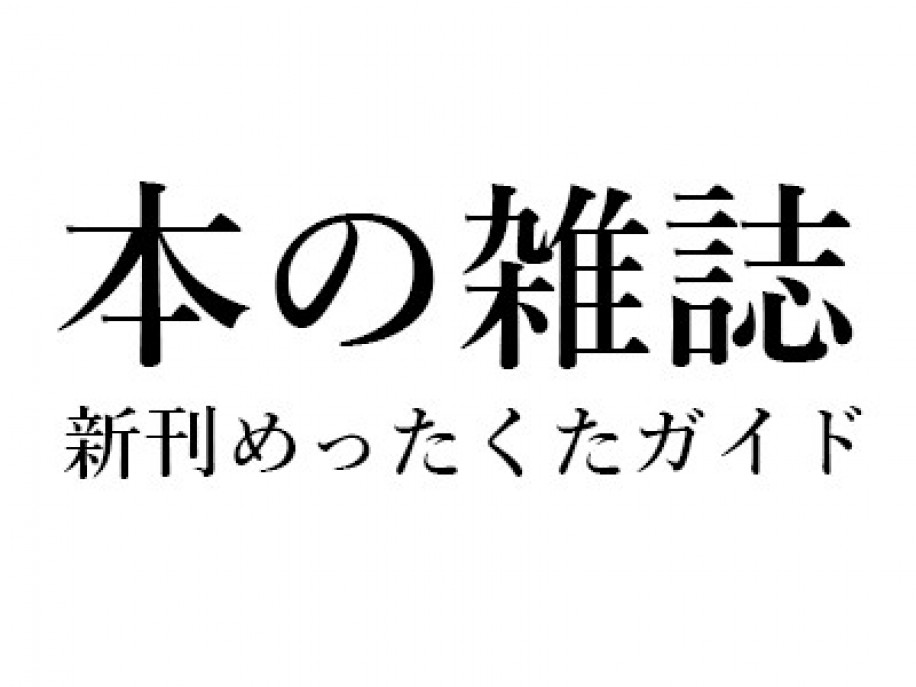読書日記
佐藤幹夫『自閉症裁判』(洋泉社)、本田透『電波男』(三才ブックス)、浜野保樹『模倣される日本 映画、アニメから料理、ファッションまで』(祥伝社)他
今月、最も衝撃を受けた本は、佐藤幹夫『自閉症裁判』(洋泉社/二二〇〇円)だ(ALL REVIEWS事務局注:本書評執筆時期は2005年5」月)。読み終わった今でも、この本のことを、何度も考える。
二〇〇一年四月三〇日、レッサーパンダの帽子をかぶった男が、短大生を刺し殺した。四年に及ぶ徹底取材を経て、この事件をルポルタージュしたのが本書だ。
殺した男は、高等養護学校の出身者であり、発達障害をもっていた。そして、「自閉症」を正面にすえて闘った、自閉症裁判のリーディングケースとなるものだと、弁護士は語る。だが、そんなことをちゃんと報道するメディアはない。
判決が出たときの報道も、責任能力論議を垂れ流すだけだった。弁護士たちは、責任能力を争っていたのではない。裁判所に問いかけてきたのは、自閉性の人たちが見ている世界と自分たちの見ている世界が大きく違うということであり、〝彼らには彼ら固有の世界がある。その平行線をなんとか埋めよう、同じ立場に立ち、同じ世界を見て、できるだけ同じように「責任」という問題を考えよう、共有しよう、そういう思いで弁護をしてきた〟のだ。
このルポルタージュは、そういった事件に関して報道が目を背け続けている部分を、真摯に書き記している。
著者は、養護学校の元教員だ。〝いわば福祉サイドの人間〟なのだが、といって障害者だから罪を軽減すべきだという主張をするわけではない。障害者が犯罪加害者となったこの事件をしっかりと見据えようとする意志で、殺された少女の遺族に取材し、取材することについて悩み、裁判の経過を詳細に再現し、自閉症という障害を少しでも理解するための知識を記述する。
正直なところ、本書をちゃんと紹介できるほど、ここに書いてある複雑で多層的な問題に対して自分の中で整理がついているわけではない。責任能力論議に終始し〝自閉的傾向が〟あったと報道するだけのメディアに、とても傷ついた人が大勢いることを、ぼくは知った。書くことによって、ぼくも同じように人を傷つけてしまうかもしれないと思い原稿を書く手も止まってしまいそうになる。
だが、大勢の人に読んでもらいたい本だから、がんばって書いている。いつもの軽い文体で紹介することが、どうしてもできなかったのは、修行不足だ。悔しい。ぜひ読んでみてください。
さて、切り替える。
さて、切り替える。
一行では切り替えられなかったので二行同じことを書いてしまったが、ここからは、にゃーにゃー途中で猫の鳴き声が挿入されるぐらいのいいかげんな文体でいきますにゃー。
そして、本田透『電波男』(三才ブックス/一五〇〇円)も今月の超絶問題作! すべての思想と世界をオタク視点から読み直そうとする爆笑の哲学書だ。現実の女などいらぬと言い放つ著者が、負け犬女やだめんずたちが、いかに恋愛資本主義幻想に踊らされ、真の愛を見失っているかを鋭く衝くにゃーッ! そして、「恋愛資本主義における搾取の構造」=「あかほりシステム」を暴き、才能や努力に報いない「顔面カースト制度」の構造をあぶりだし、それらが、九〇年以後、日本が衰退した一要因であると喝破するッ。
さらにッ、恋愛資本主義にあらがい、人間が幸福を求めるための戦い、それがオタク文化であると高らかに宣言するのだ。
『日出処の天子』(山岸凉子著)は「仏像=萌えフィギュア説」をいちはやく取り入れた漫画だッ、『電車男』は、恋愛資本主義の罠だ気をつけろッ、宮澤賢治と津山三十人殺しの都井睦雄はどちらも同じオタクだったが人生のエンディングはまるで異なってしまったその訳はッ、『マトリックス』三部作は、「萌えキャラ最高、三次元の女は近寄ってくるな、ちんちん取っちゃうぞ、ザマーミロ!」という一大恋愛革命であったのだッ! とさまざまな根拠を提示しながら、〝萌えは、人間の魂の革命運動だ〟と断言。
恋愛資本主義と闘争し、萌えオタワールドを築き上げようとする男が書いたマニフェスでありますよドーーーンにゃーーん! オタクにもなれなかった「オタク落ちこぼれ」であるぼくは、羨望の気持ちをメラメラさせながら読みました。でも第四章、「萌えオタク」こそがこれからの勝ち組だという未来像は、楽観的すぎると思います。恋愛資本主義が、ただ別の資本主義に変わるだけって罠もあるようにゃ気がします。
オタクのみなさまは必読(あとがきを最後に読んで泣けッ)。非オタクの女性も必読(敵状視察のつもりで読むがよい)!
どんどん創刊してしまう新書だが、またもや創刊。祥伝社新書と日本文芸社パンドラ新書。
浜野保樹『模倣される日本 映画、アニメから料理、ファッションまで』(祥伝社/七四〇円)は、祥伝社新書の一冊。フランスで最も知名度の高い日本人は『ドラゴンボール』の鳥山明だが、日本の財界人は誰一人として鳥山明を知らなかった、というようにゃエピソードが満載で、日本文化が、どのように拡がり模倣されているかがよくわかる。
永六輔『学校ごっこ 六輔、その世界』(日本文芸社/八三八円)は、パンドラ新書の一冊。「学校ごっこ」の講義をにゃーにゃー再構成したもの。「上を向いて歩こう」って、なんで外国では「スキヤキソング」って呼ばれてるんだろうって疑問だったのだけど、本書で解決。歌詞が、〝「桜の散る下で芸者と二人ですき焼きを食いたい」って内容〟に変わってるそうです。えぇぇぇー。あの素晴しい歌詞が、そんな内容になってるなんて、悲しいにゃー。
神奈川新聞報道部『いのちの授業 がんと闘った大瀬校長の六年間』(新潮社/一三〇〇円)は、末期がん宣告を受けた校長先生がおこなった「いのちの授業」を中心にしたルポ。もうすぐ死んでしまうことを生徒たちに告げ、「いきる」ということを一緒に考える様子や、死に対する恐怖、家族のささえなどが描かれる。当事者意識と同僚性を軸とした学校改革部分も興味深い。にゃにゃ。
今月の漫画は、吾妻ひでお『失踪日記』(イーストプレス/一一四〇円)。突然失踪、自殺未遂、路上生活、アルコール中毒、強制入院といった衝撃的な日々を描いたノンフィクションマンガ。悲惨なのに読み心地がいいという変な気持ちよさを味わってみて。傑作。
【この読書日記が収録されている書籍】
二〇〇一年四月三〇日、レッサーパンダの帽子をかぶった男が、短大生を刺し殺した。四年に及ぶ徹底取材を経て、この事件をルポルタージュしたのが本書だ。
殺した男は、高等養護学校の出身者であり、発達障害をもっていた。そして、「自閉症」を正面にすえて闘った、自閉症裁判のリーディングケースとなるものだと、弁護士は語る。だが、そんなことをちゃんと報道するメディアはない。
判決が出たときの報道も、責任能力論議を垂れ流すだけだった。弁護士たちは、責任能力を争っていたのではない。裁判所に問いかけてきたのは、自閉性の人たちが見ている世界と自分たちの見ている世界が大きく違うということであり、〝彼らには彼ら固有の世界がある。その平行線をなんとか埋めよう、同じ立場に立ち、同じ世界を見て、できるだけ同じように「責任」という問題を考えよう、共有しよう、そういう思いで弁護をしてきた〟のだ。
このルポルタージュは、そういった事件に関して報道が目を背け続けている部分を、真摯に書き記している。
著者は、養護学校の元教員だ。〝いわば福祉サイドの人間〟なのだが、といって障害者だから罪を軽減すべきだという主張をするわけではない。障害者が犯罪加害者となったこの事件をしっかりと見据えようとする意志で、殺された少女の遺族に取材し、取材することについて悩み、裁判の経過を詳細に再現し、自閉症という障害を少しでも理解するための知識を記述する。
正直なところ、本書をちゃんと紹介できるほど、ここに書いてある複雑で多層的な問題に対して自分の中で整理がついているわけではない。責任能力論議に終始し〝自閉的傾向が〟あったと報道するだけのメディアに、とても傷ついた人が大勢いることを、ぼくは知った。書くことによって、ぼくも同じように人を傷つけてしまうかもしれないと思い原稿を書く手も止まってしまいそうになる。
だが、大勢の人に読んでもらいたい本だから、がんばって書いている。いつもの軽い文体で紹介することが、どうしてもできなかったのは、修行不足だ。悔しい。ぜひ読んでみてください。
さて、切り替える。
さて、切り替える。
一行では切り替えられなかったので二行同じことを書いてしまったが、ここからは、にゃーにゃー途中で猫の鳴き声が挿入されるぐらいのいいかげんな文体でいきますにゃー。
そして、本田透『電波男』(三才ブックス/一五〇〇円)も今月の超絶問題作! すべての思想と世界をオタク視点から読み直そうとする爆笑の哲学書だ。現実の女などいらぬと言い放つ著者が、負け犬女やだめんずたちが、いかに恋愛資本主義幻想に踊らされ、真の愛を見失っているかを鋭く衝くにゃーッ! そして、「恋愛資本主義における搾取の構造」=「あかほりシステム」を暴き、才能や努力に報いない「顔面カースト制度」の構造をあぶりだし、それらが、九〇年以後、日本が衰退した一要因であると喝破するッ。
さらにッ、恋愛資本主義にあらがい、人間が幸福を求めるための戦い、それがオタク文化であると高らかに宣言するのだ。
『日出処の天子』(山岸凉子著)は「仏像=萌えフィギュア説」をいちはやく取り入れた漫画だッ、『電車男』は、恋愛資本主義の罠だ気をつけろッ、宮澤賢治と津山三十人殺しの都井睦雄はどちらも同じオタクだったが人生のエンディングはまるで異なってしまったその訳はッ、『マトリックス』三部作は、「萌えキャラ最高、三次元の女は近寄ってくるな、ちんちん取っちゃうぞ、ザマーミロ!」という一大恋愛革命であったのだッ! とさまざまな根拠を提示しながら、〝萌えは、人間の魂の革命運動だ〟と断言。
恋愛資本主義と闘争し、萌えオタワールドを築き上げようとする男が書いたマニフェスでありますよドーーーンにゃーーん! オタクにもなれなかった「オタク落ちこぼれ」であるぼくは、羨望の気持ちをメラメラさせながら読みました。でも第四章、「萌えオタク」こそがこれからの勝ち組だという未来像は、楽観的すぎると思います。恋愛資本主義が、ただ別の資本主義に変わるだけって罠もあるようにゃ気がします。
オタクのみなさまは必読(あとがきを最後に読んで泣けッ)。非オタクの女性も必読(敵状視察のつもりで読むがよい)!
どんどん創刊してしまう新書だが、またもや創刊。祥伝社新書と日本文芸社パンドラ新書。
浜野保樹『模倣される日本 映画、アニメから料理、ファッションまで』(祥伝社/七四〇円)は、祥伝社新書の一冊。フランスで最も知名度の高い日本人は『ドラゴンボール』の鳥山明だが、日本の財界人は誰一人として鳥山明を知らなかった、というようにゃエピソードが満載で、日本文化が、どのように拡がり模倣されているかがよくわかる。
永六輔『学校ごっこ 六輔、その世界』(日本文芸社/八三八円)は、パンドラ新書の一冊。「学校ごっこ」の講義をにゃーにゃー再構成したもの。「上を向いて歩こう」って、なんで外国では「スキヤキソング」って呼ばれてるんだろうって疑問だったのだけど、本書で解決。歌詞が、〝「桜の散る下で芸者と二人ですき焼きを食いたい」って内容〟に変わってるそうです。えぇぇぇー。あの素晴しい歌詞が、そんな内容になってるなんて、悲しいにゃー。
神奈川新聞報道部『いのちの授業 がんと闘った大瀬校長の六年間』(新潮社/一三〇〇円)は、末期がん宣告を受けた校長先生がおこなった「いのちの授業」を中心にしたルポ。もうすぐ死んでしまうことを生徒たちに告げ、「いきる」ということを一緒に考える様子や、死に対する恐怖、家族のささえなどが描かれる。当事者意識と同僚性を軸とした学校改革部分も興味深い。にゃにゃ。
今月の漫画は、吾妻ひでお『失踪日記』(イーストプレス/一一四〇円)。突然失踪、自殺未遂、路上生活、アルコール中毒、強制入院といった衝撃的な日々を描いたノンフィクションマンガ。悲惨なのに読み心地がいいという変な気持ちよさを味わってみて。傑作。
【この読書日記が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする