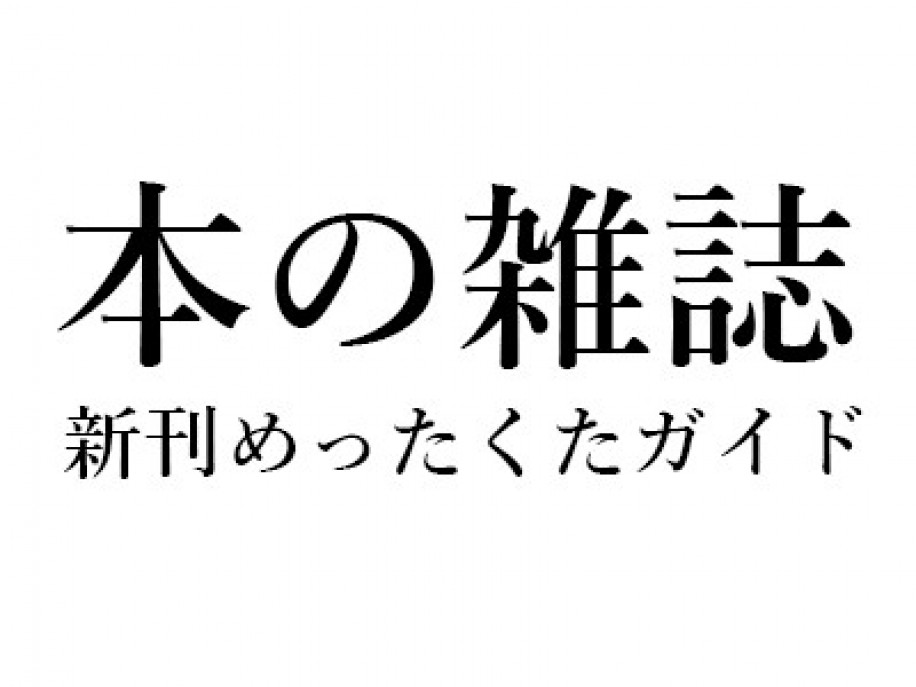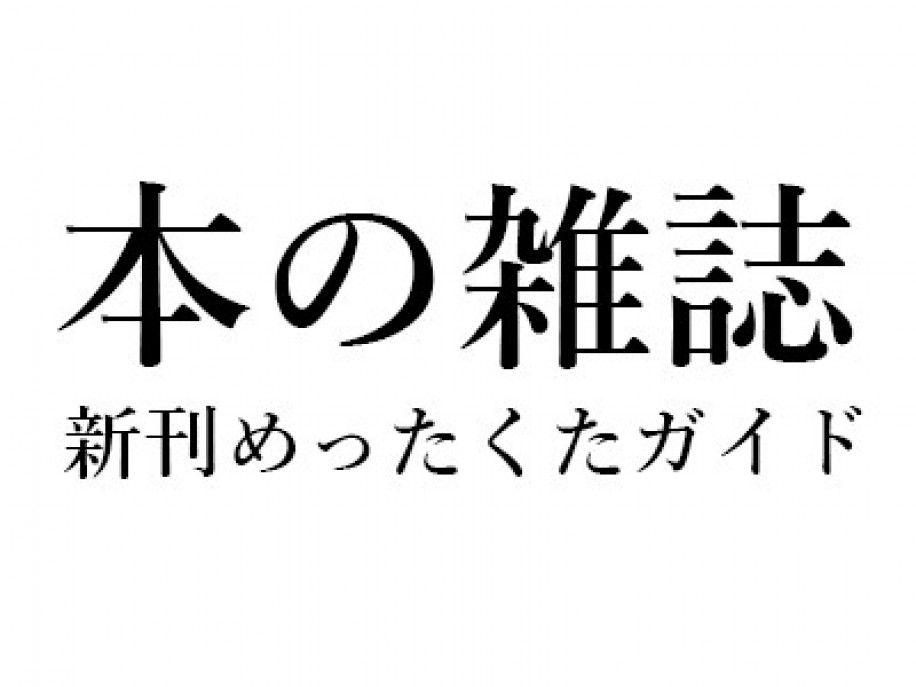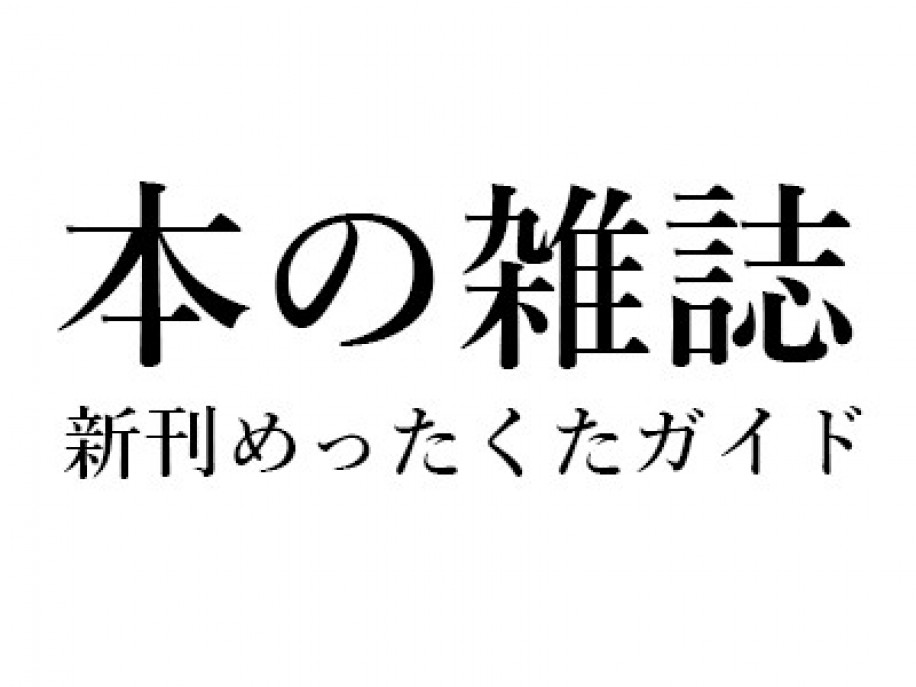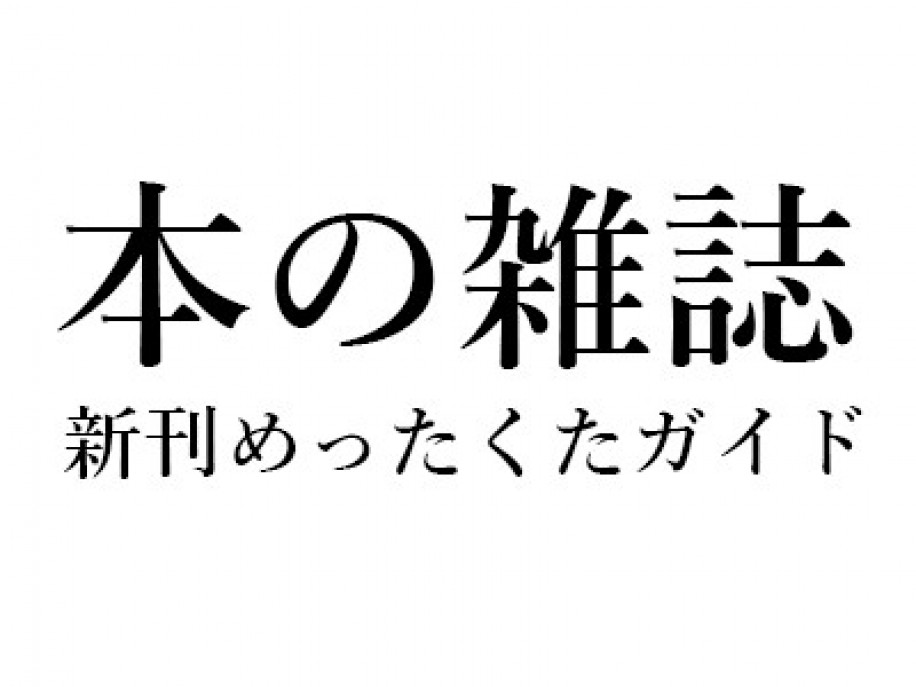読書日記
石原千秋『「こころ」大人になれなかった先生』(みすず書房)、ニキ・リンコ『俺ルール!』(花風社)、長谷川啓三『ソリューション・バンク』(金子書房)ほか
「ベストセラー本ゲーム化会議」というタイトルで鼎談をやっている。ゲームデザイナー三人でベストセラーを読んで、わいわい言いながらゲーム化する会議だ。日本の名作文学を取り上げることもあるのだが、ぼくには、まったくといっていいほど、そのあたりの基礎知識がない。
付け焼き刃で名作の知識を仕入れてもしょうがない、課題となった作品だけをきちんと読むのだというスタイルで挑む。手抜きじゃなくて、文学無垢な俺がどう感じたか、素直に喋ったほうがおもしろいだろう、近代文学に詳しい人には「こいつ馬鹿だなぁー」と笑っていただこうという戦略だ。
夏目漱石の『こころ』も、この鼎談のために初めて読んだ。『三四郎』も、柔道やってる小説だと思ってたぐらいである。
理想の教室シリーズで石原千秋『「こころ」大人になれなかった先生』(みすず書房/一三〇〇円・のち朝日文庫)なんて本が出てると、無知暴言を吐いた身としては気になる。ので、読んでみた。
がーーーーーーーーーーーん。
文学よ、ごめん!
漱石、すまんかった。
俺は本当に無知であった。
すごいな、文学って。
いまさら、こんなことを言うのは恥ずかしい限りだが、小説を読むということはなんと深い営みであることよ、業の深いものであるか。
『こころ』に登場する「先生」が、ほうれんそう(報告・連絡・相談)できないタイプで、ぼくはとても苛立った。ほうれんそうができないとこんな悲惨なことになるという具体例としてフレッシュビジネスマンに読ませるべきだと思った。そんなダメ男を先生と呼び尊敬する青年もダメだと思った。漱石も、漱石だ。青年を成長させるわけでもなく、そのまんま中途半端に終わらせちゃって!
読みが足りぬ!
足りんかった!
「余所々々しい頭文字などはとても使う気にならない」という理由で青年は「先生」と記す。しかし、その先生は親友のことをKと「余所々々しい頭文字」で書いているのだ。ここから、青年が”敬愛の情の表明の形を借りた隠微な批判”を先生にしているのだ、と石原千秋は、指摘する。
その他にも、衝撃の指摘が連続する。何故、先生はあんなに「ほうれんそう」しないのか。未亡人と娘のところに下宿しているというラブコメな状況にわざわざ親友Kを呼び寄せて混乱させる意図はなんなのか。青年が先生をそんなに慕っていたのは何故か。
謎が解けていく快楽。テキストを探る文学的想像力の冒険に興奮しながら読み進めていくと、最後の衝撃的な解釈。どーーーーーーーーーーーん!
その解釈を知った瞬間に、読んだと思っていた作品がまったく違った世界に変貌する驚き。
“ほころびは、実はほころびではなく解釈の重要な手がかりになるかもしれません。そういう可能性を信じない限り、小説の解釈などできはしないのです”
まず夏目漱石の『こころ』を読むことをオススメする。昔、読んだって人も、再読。できれば、三人以上の友達に勧めて、全員で読んで、みんなで『こころ』について話し合って、それから本書を読むと良い。『こころ』が、超絶ミステリィ問題編で、本書がひとつの解決編、そういう読み方をしてみると、すげぇぇぇおもしろい。保証する。
自閉症関連の本を二冊。ニキ・リンコ『俺ルール!』(花風社/一六〇〇円)の著者はアスペルガー症候群。”俺ルール”をキーワードに、自閉特有のこだわりや、編集力の障害を、日常のできごとから具体例をあげて説明するライトエッセイ。四コマ漫画つき。前著の『自閉っ子、こういう風にできてます!』から読むとわかりやすい。朴美景『走れ、ヒョンジン!』(ランダムハウス講談社/一四〇〇円)は、自閉症と診断された息子を持つ母親の手記。「マラソン」というタイトルで映画化(自閉について基礎知識があると滅法泣ける映画)。
長谷川啓三『ソリューション・バンク ブリーフセラピーの哲学と新展開』(金子書房/一八〇〇円)。ブリーフセラピーというのは、小さく・受け入れやすく・ユーモアを持って、介入するカウンセリングの方法。「原因の除去=解決」と考えないのが新鮮。靴箱に「死ね」などという手紙を入れられいじめられてた子には、先生と靴箱を変えてもらうという介入を行って解決した、というような事例がたくさん載っている。
心はファンタジックな性質を持っているもので、精神分析とはこのファンタジーの分析であり、分析結果もまたファンタジーだという認識がこの本で述べられているが、だとすると高橋準『ファンタジーとジェンダー』(青弓社/一六〇〇円)は、ファンタジー小説であつかわれるジェンダーを分析することで、現実のジェンダーの問題をリフレーミングする試みだとも言えるだろう。「男装する女性」「戦う女性」「家族」といったテーマを軸に「十二国記」「ハリー・ポッター」「グイン・サーガ」「指輪物語」と取り上げる作品の幅の広さが嬉しい。
長嶋有『いろんな気持ちが本当の気持ち』(筑摩書房/一三〇〇円)はエッセイ集。世界についてまだ何も知らない子供が次々と発見する様子が楽しいように、大人になっても見つけてしまう感じが楽しい。というか、世界にはまだまだ発見できることがあるんだって勇気づけられる。いっきに読むのがもったいないから、ちびちびと。
内山哲夫『転落弁護士 私はこうして堀の中に落ちた』(講談社/一六〇〇円・のち幻冬舎)は、札束と女体の誘惑に負けて転落した弁護士の手記。悲劇的な内容なのに、無邪気にも思える文章が子供の作文みたいで、たくまざるユーモアになっていて、変におかしい。
四コマ漫画を二冊。ちまきing『あふがにすタン』(三才ブックス/一五〇〇円)は、あふがにすタン、ぱきすタン、うずべきすタンなどの美少女キャラが活躍する世界情勢を四コマ漫画化した異色作。施川ユウキ『サナギさん』(秋田書店/三九〇円)、”「帝王切開」を「切開帝王」に変えるとスゴ味が一気に増す!”とか”「晴れがましい」は「がましい」の部分があんまり晴れがましくない!!”と愚にもつかないことを考えるサナギさんが素敵な子供ふしぎ発見ねじれ四コマ。言葉好きな人はぜひ。
【この読書日記が収録されている書籍】
付け焼き刃で名作の知識を仕入れてもしょうがない、課題となった作品だけをきちんと読むのだというスタイルで挑む。手抜きじゃなくて、文学無垢な俺がどう感じたか、素直に喋ったほうがおもしろいだろう、近代文学に詳しい人には「こいつ馬鹿だなぁー」と笑っていただこうという戦略だ。
夏目漱石の『こころ』も、この鼎談のために初めて読んだ。『三四郎』も、柔道やってる小説だと思ってたぐらいである。
理想の教室シリーズで石原千秋『「こころ」大人になれなかった先生』(みすず書房/一三〇〇円・のち朝日文庫)なんて本が出てると、無知暴言を吐いた身としては気になる。ので、読んでみた。
がーーーーーーーーーーーん。
文学よ、ごめん!
漱石、すまんかった。
俺は本当に無知であった。
すごいな、文学って。
いまさら、こんなことを言うのは恥ずかしい限りだが、小説を読むということはなんと深い営みであることよ、業の深いものであるか。
『こころ』に登場する「先生」が、ほうれんそう(報告・連絡・相談)できないタイプで、ぼくはとても苛立った。ほうれんそうができないとこんな悲惨なことになるという具体例としてフレッシュビジネスマンに読ませるべきだと思った。そんなダメ男を先生と呼び尊敬する青年もダメだと思った。漱石も、漱石だ。青年を成長させるわけでもなく、そのまんま中途半端に終わらせちゃって!
読みが足りぬ!
足りんかった!
「余所々々しい頭文字などはとても使う気にならない」という理由で青年は「先生」と記す。しかし、その先生は親友のことをKと「余所々々しい頭文字」で書いているのだ。ここから、青年が”敬愛の情の表明の形を借りた隠微な批判”を先生にしているのだ、と石原千秋は、指摘する。
その他にも、衝撃の指摘が連続する。何故、先生はあんなに「ほうれんそう」しないのか。未亡人と娘のところに下宿しているというラブコメな状況にわざわざ親友Kを呼び寄せて混乱させる意図はなんなのか。青年が先生をそんなに慕っていたのは何故か。
謎が解けていく快楽。テキストを探る文学的想像力の冒険に興奮しながら読み進めていくと、最後の衝撃的な解釈。どーーーーーーーーーーーん!
その解釈を知った瞬間に、読んだと思っていた作品がまったく違った世界に変貌する驚き。
“ほころびは、実はほころびではなく解釈の重要な手がかりになるかもしれません。そういう可能性を信じない限り、小説の解釈などできはしないのです”
まず夏目漱石の『こころ』を読むことをオススメする。昔、読んだって人も、再読。できれば、三人以上の友達に勧めて、全員で読んで、みんなで『こころ』について話し合って、それから本書を読むと良い。『こころ』が、超絶ミステリィ問題編で、本書がひとつの解決編、そういう読み方をしてみると、すげぇぇぇおもしろい。保証する。
自閉症関連の本を二冊。ニキ・リンコ『俺ルール!』(花風社/一六〇〇円)の著者はアスペルガー症候群。”俺ルール”をキーワードに、自閉特有のこだわりや、編集力の障害を、日常のできごとから具体例をあげて説明するライトエッセイ。四コマ漫画つき。前著の『自閉っ子、こういう風にできてます!』から読むとわかりやすい。朴美景『走れ、ヒョンジン!』(ランダムハウス講談社/一四〇〇円)は、自閉症と診断された息子を持つ母親の手記。「マラソン」というタイトルで映画化(自閉について基礎知識があると滅法泣ける映画)。
長谷川啓三『ソリューション・バンク ブリーフセラピーの哲学と新展開』(金子書房/一八〇〇円)。ブリーフセラピーというのは、小さく・受け入れやすく・ユーモアを持って、介入するカウンセリングの方法。「原因の除去=解決」と考えないのが新鮮。靴箱に「死ね」などという手紙を入れられいじめられてた子には、先生と靴箱を変えてもらうという介入を行って解決した、というような事例がたくさん載っている。
心はファンタジックな性質を持っているもので、精神分析とはこのファンタジーの分析であり、分析結果もまたファンタジーだという認識がこの本で述べられているが、だとすると高橋準『ファンタジーとジェンダー』(青弓社/一六〇〇円)は、ファンタジー小説であつかわれるジェンダーを分析することで、現実のジェンダーの問題をリフレーミングする試みだとも言えるだろう。「男装する女性」「戦う女性」「家族」といったテーマを軸に「十二国記」「ハリー・ポッター」「グイン・サーガ」「指輪物語」と取り上げる作品の幅の広さが嬉しい。
長嶋有『いろんな気持ちが本当の気持ち』(筑摩書房/一三〇〇円)はエッセイ集。世界についてまだ何も知らない子供が次々と発見する様子が楽しいように、大人になっても見つけてしまう感じが楽しい。というか、世界にはまだまだ発見できることがあるんだって勇気づけられる。いっきに読むのがもったいないから、ちびちびと。
内山哲夫『転落弁護士 私はこうして堀の中に落ちた』(講談社/一六〇〇円・のち幻冬舎)は、札束と女体の誘惑に負けて転落した弁護士の手記。悲劇的な内容なのに、無邪気にも思える文章が子供の作文みたいで、たくまざるユーモアになっていて、変におかしい。
四コマ漫画を二冊。ちまきing『あふがにすタン』(三才ブックス/一五〇〇円)は、あふがにすタン、ぱきすタン、うずべきすタンなどの美少女キャラが活躍する世界情勢を四コマ漫画化した異色作。施川ユウキ『サナギさん』(秋田書店/三九〇円)、”「帝王切開」を「切開帝王」に変えるとスゴ味が一気に増す!”とか”「晴れがましい」は「がましい」の部分があんまり晴れがましくない!!”と愚にもつかないことを考えるサナギさんが素敵な子供ふしぎ発見ねじれ四コマ。言葉好きな人はぜひ。
【この読書日記が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする