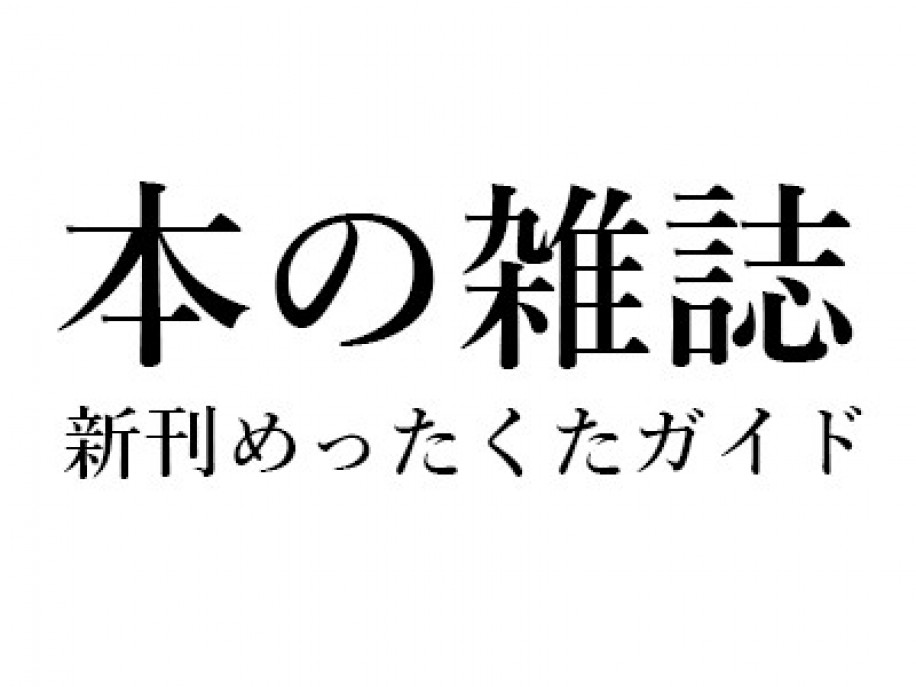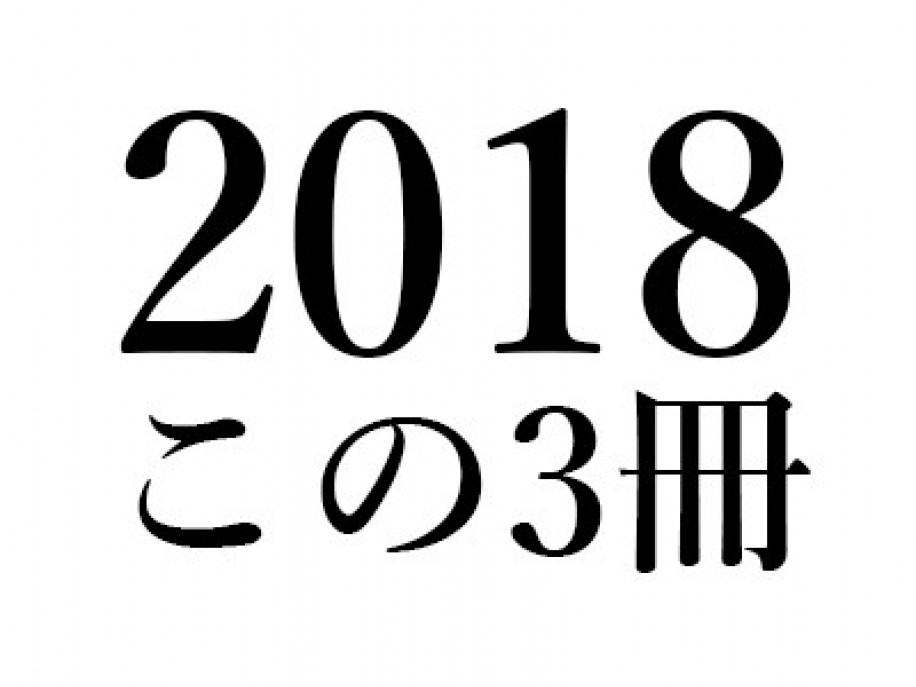読書日記
木村敏『関係としての自己』(みすず書房)/『異常の構造』(講談社)/『時間と自己』(中央公論新社)、呉連鎬『オーマイニュースの挑戦』(太田出版)ほか
出た。木村敏『関係としての自己』(みすず書房/二六〇〇円)。新しい木村敏の本を読めることが、今月はとにかく嬉しくて、Nintendogsと一緒に常に持ち歩いていた。らっこ(デジタルな犬)よりも、よほど愛して、読み耽った(ALL REVIEWS事務局注:本書評執筆時期は2005年。木村敏『関係としての自己』は新装版が2018年7月に発売)。
木村敏は、精神病理学の第一人者であり、「私とは何か」について、深い思索をつづったテキストを発表している。初めて読んだのは、高校生のときだったと思う。
世界が一変した。「わっ」と思った。脳の中の回路がカチカチと音をたてて変わっていくような興奮にのみこまれ、もう一度読んだ。
そんなぼくにとって、この新刊は至福の一冊だ。一節読んでは、またもどって読み返し、以前の本を引っ張り出して関連箇所を読みなおし、目を閉じテキストが意味することを考え、想像を巡らせる。
「あっという間に読めてしまった」という楽しみもあるが、それとは違った楽しみ。これも読書ならではの醍醐味。
とはいっても、ぼくは木村敏作品のよい読者とはいえない。引用されるハイデガー作品も、ヴァイツゼッカー作品も、ブランケンブルク作品も、未だ読んでいない。どちらかというと深い思索には向かないタイプの人間だ。それなのに木村敏の本を読んでいる間だけは、哲学者や現象学者が、なぜあんなにあれこれいつまでも考え続けられるのか理解できるような気がする。おもしろいのだ。
あぁ、じれったい。おもしろいという言葉が細分化されていない日本語を恨む、もしくはぼくの無知を。これは、ぼくが普段使う「おもしろい」とは違う。違うおもしろさだ。雪の多い地方に行くと、雪の状態によってさまざまな名称があるように「おもしろい」にも、もっといろいろな名称があればいいのに。今、勝手に作るけど「ふかおもしろい」のだ。
たとえば、たびたび引用されるキルケゴールの「自己とは関係が関係それ自身と関係するという関係である」という言葉。暗号か早口言葉にしか思えないこの言葉が、木村敏のテキストを読んでいくと、魔法の絨毯に封印されていた世界が恐ろしい勢いで実体化していくような興奮とともに理解できたような気になる。新たな光が言葉に当てられて! わぁぁっ!(輝く奇跡がまぶしくて手をあげ顔を守りながらたじろぐ)そんな気持ち。
と、自分だけ興奮したり、形容詞がいっぱいだったり、印象や喩えだらけだったり、そんな具体性の低い文章は書くまいと心に決めていたのに、「はいはい、読んで興奮してるのね、どうどう」と読者にたしなめられそうなテキストで、原稿の半分近くまで到達してしまった。
許してくれ(これでも、推敲してそうとう削ったんだ)。本当にまだ興奮しているのだから。こうやって紹介テキストを書いているうちにまた興奮してきているのだから。どうどう。
本書がわかりにくかったら、『異常の構造』(講談社現代新書)、『時間と自己』(中公新書)を読んでから、読むこと。身悶えするほどオススメ。
呉連鎬『オーマイニュースの挑戦 韓国「インターネット新聞事始め」』(大畑龍次+大畑正姫訳 太田出版/一八〇〇円)は、「市民参加型インターネット新聞」の成功例として知られるサイト創設者が自ら記した本。新しいメディアを作るこの戦いは、古いメディアの構造を解体/再構築することに通じる。表現者、メディア・出版関係者にとって、考えるためのヒントがうなるほど潜んでいる。
横田増生『アマゾン・ドット・コムの光と影』(情報センター出版局/一六〇〇円)は、秘密主義アマゾンの仕組みを暴くっちゅーよりも、アルバイト哀歌みたいなアマゾン物流センター潜入ルポ。著者が労働者としてはアマゾンを嫌うけど、ユーザーとしてはどんどん気にいっていくところは笑う。
元主任分析官の国策捜査暴露本、佐藤優『国家の罠 外務省のラスプーチンと呼ばれて』(新潮社/一六八〇円)は、ヒロイックな語り口で、「信用できない語り手」スタイルっぽく読めるけど、報道とは真反対の視点を与えてくれるハードボイルドストーリーとしてしびれる。
古東哲明『他界からのまなざし 臨生の思想』(講談社選書メチエ/一五〇〇円)は、生のまぎわに臨む死の視点「臨生」から世界を見すえる哲学論考。「臨生」をはじめとして「冥顕同体」「他界の近傍性」「地上即銀河」「二重人」「無辺円のエチカ」など、用語・造語がギミックのように頻出。ギミック好きには興奮の書。
高橋一郎/荻原美代子/谷口雅子/掛水通子/角田聡美『ブルマーの社会史 女子体育へのまなざし』(青弓社/一六〇〇円)は、純粋に社会学的な問題意識からブルマーに迫る本。他国では特定種目の競技ユニフォームに限られるのが通例なのに、日本では、なぜ、全国ほとんどの学校体育でブルマー着用が強制されたのか? そして、一九九〇年以後、急速に駆逐された経緯は? ニッポンにおけるブルマーの興亡と衰退を研究し、女性の身体とセクシャリティをめぐる物語を示す歴史社会学的探求。〝軽めの風俗史的読み物を欲するブルマー愛好家諸氏には、あるいは期待はずれの向きもあるかも〟とエクスキューズがあるが、ブルマーの思い出一覧、戦後ブルマー変遷、詳細な分類など、真摯にブルマー萌えな人も必読。
五月号で紹介した佐藤幹夫『自閉症裁判』(洋泉社/二二〇〇円)に衝撃を受けて以来、自閉症についての本を読んでいる。『発達障害かもしれない 見た目は普通の、ちょっと変わった子』(磯部潮/光文社新書七〇〇円)は、理解の難しいこれらの障害についての最新かつ基礎的なガイドブック。繊細な問題なのに記述が荒っぽいかなと思える部分もたくさんあるんだけど、これは現場の人だから書ける乱暴さなのかもしれない。理解をひろめることが大切なので、新書という手に取りやすい形でこういう本が出ることに意義があると思う。
五月二十八日に最新刊が出る漫画『光とともに…自閉症児を抱えて』(戸部けいこ/秋田書店)は、自閉症の子供を授かった家族の物語。自閉症についての入門書としても最適だと思うし、素晴らしい作品なので(何回泣いたかッ)、ぜひ。
【この読書日記が収録されている書籍】
木村敏は、精神病理学の第一人者であり、「私とは何か」について、深い思索をつづったテキストを発表している。初めて読んだのは、高校生のときだったと思う。
世界が一変した。「わっ」と思った。脳の中の回路がカチカチと音をたてて変わっていくような興奮にのみこまれ、もう一度読んだ。
そんなぼくにとって、この新刊は至福の一冊だ。一節読んでは、またもどって読み返し、以前の本を引っ張り出して関連箇所を読みなおし、目を閉じテキストが意味することを考え、想像を巡らせる。
「あっという間に読めてしまった」という楽しみもあるが、それとは違った楽しみ。これも読書ならではの醍醐味。
とはいっても、ぼくは木村敏作品のよい読者とはいえない。引用されるハイデガー作品も、ヴァイツゼッカー作品も、ブランケンブルク作品も、未だ読んでいない。どちらかというと深い思索には向かないタイプの人間だ。それなのに木村敏の本を読んでいる間だけは、哲学者や現象学者が、なぜあんなにあれこれいつまでも考え続けられるのか理解できるような気がする。おもしろいのだ。
あぁ、じれったい。おもしろいという言葉が細分化されていない日本語を恨む、もしくはぼくの無知を。これは、ぼくが普段使う「おもしろい」とは違う。違うおもしろさだ。雪の多い地方に行くと、雪の状態によってさまざまな名称があるように「おもしろい」にも、もっといろいろな名称があればいいのに。今、勝手に作るけど「ふかおもしろい」のだ。
たとえば、たびたび引用されるキルケゴールの「自己とは関係が関係それ自身と関係するという関係である」という言葉。暗号か早口言葉にしか思えないこの言葉が、木村敏のテキストを読んでいくと、魔法の絨毯に封印されていた世界が恐ろしい勢いで実体化していくような興奮とともに理解できたような気になる。新たな光が言葉に当てられて! わぁぁっ!(輝く奇跡がまぶしくて手をあげ顔を守りながらたじろぐ)そんな気持ち。
と、自分だけ興奮したり、形容詞がいっぱいだったり、印象や喩えだらけだったり、そんな具体性の低い文章は書くまいと心に決めていたのに、「はいはい、読んで興奮してるのね、どうどう」と読者にたしなめられそうなテキストで、原稿の半分近くまで到達してしまった。
許してくれ(これでも、推敲してそうとう削ったんだ)。本当にまだ興奮しているのだから。こうやって紹介テキストを書いているうちにまた興奮してきているのだから。どうどう。
本書がわかりにくかったら、『異常の構造』(講談社現代新書)、『時間と自己』(中公新書)を読んでから、読むこと。身悶えするほどオススメ。
呉連鎬『オーマイニュースの挑戦 韓国「インターネット新聞事始め」』(大畑龍次+大畑正姫訳 太田出版/一八〇〇円)は、「市民参加型インターネット新聞」の成功例として知られるサイト創設者が自ら記した本。新しいメディアを作るこの戦いは、古いメディアの構造を解体/再構築することに通じる。表現者、メディア・出版関係者にとって、考えるためのヒントがうなるほど潜んでいる。
横田増生『アマゾン・ドット・コムの光と影』(情報センター出版局/一六〇〇円)は、秘密主義アマゾンの仕組みを暴くっちゅーよりも、アルバイト哀歌みたいなアマゾン物流センター潜入ルポ。著者が労働者としてはアマゾンを嫌うけど、ユーザーとしてはどんどん気にいっていくところは笑う。
元主任分析官の国策捜査暴露本、佐藤優『国家の罠 外務省のラスプーチンと呼ばれて』(新潮社/一六八〇円)は、ヒロイックな語り口で、「信用できない語り手」スタイルっぽく読めるけど、報道とは真反対の視点を与えてくれるハードボイルドストーリーとしてしびれる。
古東哲明『他界からのまなざし 臨生の思想』(講談社選書メチエ/一五〇〇円)は、生のまぎわに臨む死の視点「臨生」から世界を見すえる哲学論考。「臨生」をはじめとして「冥顕同体」「他界の近傍性」「地上即銀河」「二重人」「無辺円のエチカ」など、用語・造語がギミックのように頻出。ギミック好きには興奮の書。
高橋一郎/荻原美代子/谷口雅子/掛水通子/角田聡美『ブルマーの社会史 女子体育へのまなざし』(青弓社/一六〇〇円)は、純粋に社会学的な問題意識からブルマーに迫る本。他国では特定種目の競技ユニフォームに限られるのが通例なのに、日本では、なぜ、全国ほとんどの学校体育でブルマー着用が強制されたのか? そして、一九九〇年以後、急速に駆逐された経緯は? ニッポンにおけるブルマーの興亡と衰退を研究し、女性の身体とセクシャリティをめぐる物語を示す歴史社会学的探求。〝軽めの風俗史的読み物を欲するブルマー愛好家諸氏には、あるいは期待はずれの向きもあるかも〟とエクスキューズがあるが、ブルマーの思い出一覧、戦後ブルマー変遷、詳細な分類など、真摯にブルマー萌えな人も必読。
五月号で紹介した佐藤幹夫『自閉症裁判』(洋泉社/二二〇〇円)に衝撃を受けて以来、自閉症についての本を読んでいる。『発達障害かもしれない 見た目は普通の、ちょっと変わった子』(磯部潮/光文社新書七〇〇円)は、理解の難しいこれらの障害についての最新かつ基礎的なガイドブック。繊細な問題なのに記述が荒っぽいかなと思える部分もたくさんあるんだけど、これは現場の人だから書ける乱暴さなのかもしれない。理解をひろめることが大切なので、新書という手に取りやすい形でこういう本が出ることに意義があると思う。
五月二十八日に最新刊が出る漫画『光とともに…自閉症児を抱えて』(戸部けいこ/秋田書店)は、自閉症の子供を授かった家族の物語。自閉症についての入門書としても最適だと思うし、素晴らしい作品なので(何回泣いたかッ)、ぜひ。
【この読書日記が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする