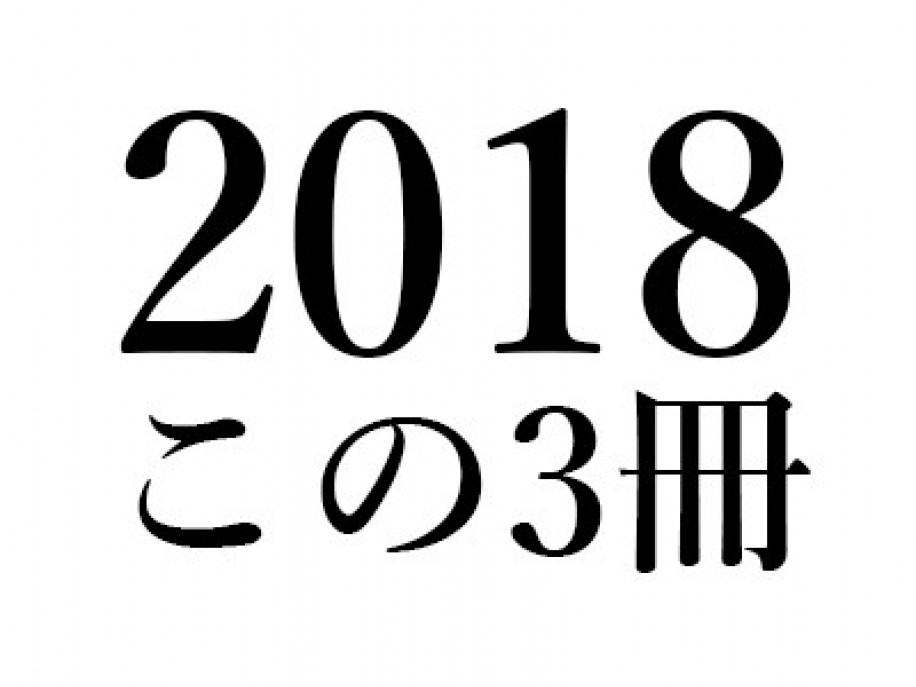書評
『近代神学の誕生: シュライアマハー『宗教について』を読む』(春秋社)
知の覚醒願う叱咤激励の書
大学院で神学を専攻した佐藤優氏とプロテスタント神学が専門の深井智朗氏が、シュライアマハーをめぐり対論した。シュライアマハーは、バルトを遡(さかのぼ)ることおよそ一世紀、近代神学の草分けの思想家。深井氏が彼の『宗教について』(春秋社)を翻訳したことが、本書の対論のきっかけとなった。キリスト教はカトリックとプロテスタントに分裂した。ドイツではプロテスタントの、ルター派が主流となった。ニュートン力学など自然科学が発展すると、神が「天にいる」と素朴に考えるわけには行かなくなった。自然科学とキリスト教の信仰をどう両立させるか。それを考えるのが近代神学である。
シュライアマハーは一七六八年の生まれ。一九世紀前半に活躍した。当時は学校制度が出来かけだ。貴族の子は家庭教師につき、学校に行かない。貧乏な子は学校に行けない。裕福な市民か牧師の子が学校に通った。牧師の子は教育を受けると、信仰に疑問をもつ。ニーチェがそう。シュライアマハーも牧師の子で、批判的になった。
ドイツのルター派は政府と結び、体制べったりだ。その現状(実定宗教)は正しくない。シュライアマハーはルター派でなかったので、主張は先鋭だ。知識人として有名になり、プロイセン国王夫妻が宗派が違ってもめていたのを調停もした。
当時は、自然科学が興隆した理性の時代である。啓蒙(けいもう)思想はもう常識だ。理性は信仰と折り合いが悪い。信仰を時代に合わせて立て直そうと、神学は苦労する。理神論、汎神(はんしん)論、神秘主義、敬虔(けいけん)主義などさまざまな思潮がつぎつぎ現れた。
例えば、理神論。神は自然を創造したあと、放置した。自然は自然法則に従っている。神から理性を与えられた人間は、自然法則を理解できる。自然科学は、神の計画を明らかにする。当初は信仰に支えられた活動だったが、やがて世俗化した。
また、汎神論。神は姿を変えて、世界のそこここに宿っている。神は人びとと共にいる。これに対しキリスト教の主流は、神は天にはいない、めいめいの心にあると思うようになった。自然科学と両立できる。だがそれなら、教会や神学はなぜ存在するのか。模索が続く。
本書がすぐれているのは、シュライアマハーを素材に、キリスト教が近代的に姿を整えていく精神のドラマを追体験できるところである。啓蒙思想やロマン主義を乗り継いで、やがてナショナリズムの母胎となる。深井氏、佐藤氏の素養と洞察がそれを明らかにする。
神学を学ぶ意味は、なんだろう。神学は、信仰(この世界を生きるあり方へのコミットメント)に接続している。単なる知識でなく、価値や道徳と連動している。江戸時代、日本人が儒学を学び精神を磨いたように、キリスト教圏の人びとは、神学と信仰を通じて近代を生み出した。その出来事の根底を衝(つ)き当てることができる。
さらに神学は、領域横断的である。いまの専門的知識は分断されていて、世界の全体を捉えるのを諦めている。神学は、神と世界全体に向かう。政治や経済や社会と共に生きる現代人にとって、時空を超えた世界の全体を考える神学の能力は大切である。それを体系的に学べるのが、シュライアマハーだ。
神学の訓練を受けた著者両氏の、憂慮は深い。困難な課題に立ち向かう知力の根幹が、日本語でものを考える人びとに欠けているのではないか。遅まきながら神学は、その欠落を補うことができないか。知の覚醒を願う、叱咤(しった)激励の書物である。
ALL REVIEWSをフォローする