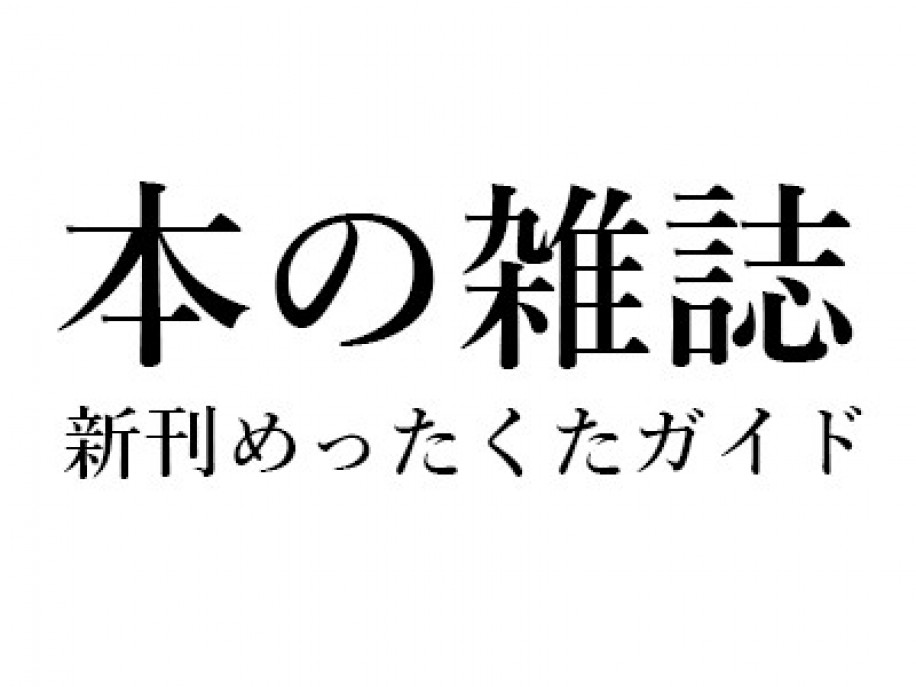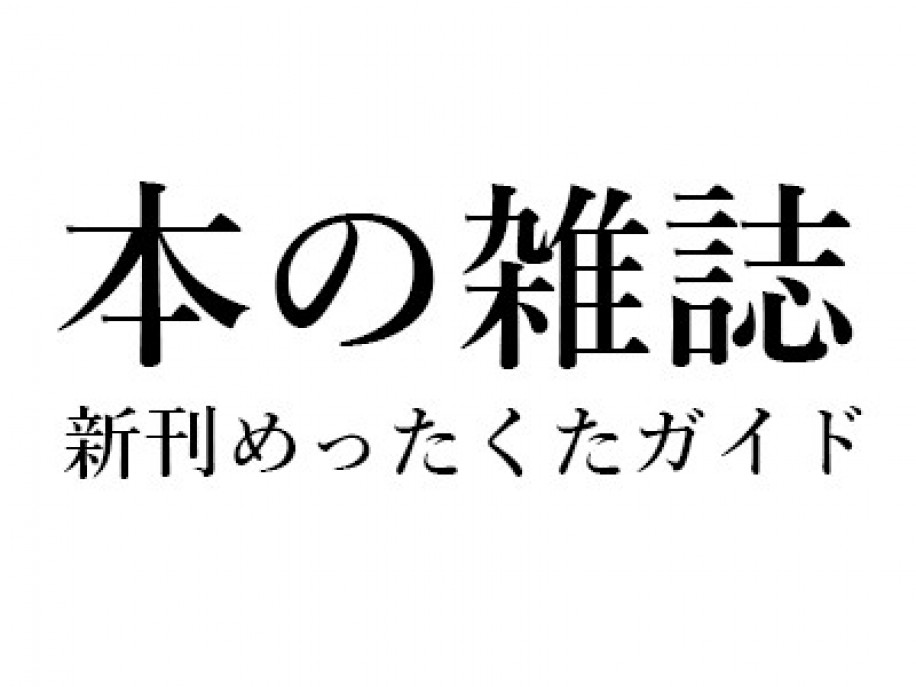読書日記
ジム・ドワイヤー,ケィン・フリン『9・11生死を分けた102分』(文藝春秋)、唐 十郎,室井 尚『教室を路地に! 横浜国大VS紅テント 2739日』(岩波書店)ほか
ジム・ドワイヤー&ケィン・フリン『9・11生死を分けた102分 崩壊する超高層ビル内部からの驚くべき証言』(三河基好訳 文藝春秋/一八〇〇円)を紹介する。
二〇〇一年九月十一日、航空機が激突して、ツインタワーが崩壊するまでの百二分間、視点を超高層ビルの内部にほぼ限定し、同時進行で起こる猛烈な混沌を、本書は分刻みに克明に冷徹に具体的に描いていく。
航空機激突の瞬間、誰が何をしていたのか。その後、いつ激突したことを知り、誰がどう行動したのか。崩壊の危機があるという連絡はどのようにして伝わったのか(というより、どのように伝わらなかったのか)。誰が閉じこめられ、誰が迅速に脱出し、誰が誰を救助し、誰が何も知らないまま死んでいったのか。並列で一気に起こっている出来事が、”二百回以上におよぶ生存者やその家族・知人へのインタビュー、警察や消防の交信記録(はじめ当局は記録の公開をしぶったという)、電話の会話の記録などに基づいて”描かれていくのを読んでいると、いいしれない焦燥感に襲われる。
南タワーの〈みずほ・富士銀行〉の社員は、非常事態にすばやく対応して、ゲートまでやってきたにも関わらず、警備員に「こちらは大丈夫です。オフィスに戻っていいですよ。この建物は安全ですから」と言われ、また迅速にオフィスに戻っていく。ぼくは、ここの部分を読んだとき、思わず本に向かって本当に声を出して「いやいや、もどっちゃダメだ、おいおい!」と言っていた。それぐらい焦燥。
センチメンタルな描写や大仰な言葉を使わず、人々の行動や高層ビルの構造を、事実を積み重ねるという手法で描写する本書は、読む人によって、多様に受け止めることができるだろう。それほどのパワーを持っている。著者が繰りかえし強調する”緊急事態に果敢に対応しようとしたにもかかわらず、通信の障害や、協力態勢の不備、命令系統の混乱などに大きく行動をはばまれていたようす”から、人災としての教訓を得るだけでなく、もっと多くのことを語りかけてくる。
ぶんぶんゲンコツふりまわして絶賛したくなるのを抑えて、なるべく冷静に紹介した。
唐十郎/室井尚『教室を路地に! 横浜国大VS紅テント 2739日』(岩波書店/一七〇〇円)は、「横浜国立大学の教授になった唐十郎の授業とはどんなものだったのか?」を、唐を呼んだ室井尚による文章、唐と室井の対談、講義メモ、唐ゼミの生徒たちの座談などから構成された本だ。「黒板をぶち破って登場した初講義、赤い木馬に乗って窓の外に消える最終講義」なんて聞くと、エキセントリックな授業を想像するが、実際はただエキセントリックなだけじゃない。最初の授業では、携帯を見たり、抜けだそうとする生徒たちに苦戦する唐だが、唐ゼミが誕生し、生徒たちと劇団を作りはじめると、”両者が血を吸い合う”ような体験になっていく。
“けっして反復されることはない一回限りの人との出会いの中で隠されているものに耳を澄まし、それを引き出していくような個人の「生き方」や「構え」の中からしかそうした「教育」が生み出されることはない”と断言する室井の文章は熱く、唐へのラブレターのようにも読める(ちょっと照れる、なんで俺が照れるか、馬鹿)。
野口悠紀雄『ゴールドラッシュの「超」ビジネスモデル』(新潮社/一七〇〇円)の内容は、帯の文句が適切に内容を説明しているので引用します。
で、「成功の法則」が検証され、日本経済の未来を切り開くためのヒントが提示される。もちろんそれらの提言にも、ふむふむははぁーんなのだけど、なんといっても、ゴールドラッシュに関するエピソードがおもしろい。
マーク・トウェインや、トロイの遺跡を発掘したシュリーマン、怪盗ブラック・バート、アメリカ合衆国初代皇帝、ジョン万次郎まで登場する。とても読みやすい文章で(いや、教授とか学者で、読みにくくて読めない文章書く人って多いよねぇ)、イッキに読めてしまいます。
十月号で紹介した『「こころ」大人になれなかった先生』を読んで以来、ディナーショーあれば駆けつけますよレベルの石原千秋ファンになったぼくなので『国語教科書の思想』(ちくま新書/六八〇円)も当然読みます。国語教科書のテクストを、教科書編集者や執筆者の意図から切り離して読み解き、そこに隠されたイデオロギーを炙り出し、いかに怖ろしい洗脳が行われているかを暴いた本書は、スリリング&エキサイティング。
吉本ばななの「みどりのゆび」ばかりが選ばれる理由は? 父親が不在の作品が多いのは何故なのか? 小学国語、中学国語の現状はどうなのか? 具体例をあげながらそこに含まれる欺瞞を指摘していきます。
その具体例で、そこまで断言しちゃいますかッ! ってぐらいのテキスト論者っぷりにしびれて、ますますファンになりました。
枡野浩一選『ドラえもん短歌』(小学館/一三六五円)。”自転車で君を家まで送ってたどこでもドアがなくてよかった”ドラえもんをモチーフにした短歌を九十三首収録。なんだかマジックなリアリズムを感じさせる。
漫画。よしながふみ『大奥』(白泉社/六〇〇円)、伝染病で、男が激減。男は子種を持つ宝として育てられ、女が労働し全ての家業を継ぐという世になった日本。もちろん将軍職も、女が継ぐのでして、そうすると、大奥には美男が三千人!? 男女逆転大奥という物凄い設定の中で展開される大河漫画。ぜひ、こっちの設定でテレビドラマ化希望であります。
漫画もう一冊。久世番子『暴れん坊本屋さん』(新書館六四〇円)は、書店員兼漫画家が描く本屋さんの裏話。間違ったタイトルでたずねる客(ハリー・ポッターの書いた『ピーターラビット』はどこにあるの!? に爆笑)やら、万引き話やら、ボーイズラブ小説のはずかしい口絵隠し秘技やら、本屋好きは必笑。
二〇〇一年九月十一日、航空機が激突して、ツインタワーが崩壊するまでの百二分間、視点を超高層ビルの内部にほぼ限定し、同時進行で起こる猛烈な混沌を、本書は分刻みに克明に冷徹に具体的に描いていく。
航空機激突の瞬間、誰が何をしていたのか。その後、いつ激突したことを知り、誰がどう行動したのか。崩壊の危機があるという連絡はどのようにして伝わったのか(というより、どのように伝わらなかったのか)。誰が閉じこめられ、誰が迅速に脱出し、誰が誰を救助し、誰が何も知らないまま死んでいったのか。並列で一気に起こっている出来事が、”二百回以上におよぶ生存者やその家族・知人へのインタビュー、警察や消防の交信記録(はじめ当局は記録の公開をしぶったという)、電話の会話の記録などに基づいて”描かれていくのを読んでいると、いいしれない焦燥感に襲われる。
南タワーの〈みずほ・富士銀行〉の社員は、非常事態にすばやく対応して、ゲートまでやってきたにも関わらず、警備員に「こちらは大丈夫です。オフィスに戻っていいですよ。この建物は安全ですから」と言われ、また迅速にオフィスに戻っていく。ぼくは、ここの部分を読んだとき、思わず本に向かって本当に声を出して「いやいや、もどっちゃダメだ、おいおい!」と言っていた。それぐらい焦燥。
センチメンタルな描写や大仰な言葉を使わず、人々の行動や高層ビルの構造を、事実を積み重ねるという手法で描写する本書は、読む人によって、多様に受け止めることができるだろう。それほどのパワーを持っている。著者が繰りかえし強調する”緊急事態に果敢に対応しようとしたにもかかわらず、通信の障害や、協力態勢の不備、命令系統の混乱などに大きく行動をはばまれていたようす”から、人災としての教訓を得るだけでなく、もっと多くのことを語りかけてくる。
ぶんぶんゲンコツふりまわして絶賛したくなるのを抑えて、なるべく冷静に紹介した。
唐十郎/室井尚『教室を路地に! 横浜国大VS紅テント 2739日』(岩波書店/一七〇〇円)は、「横浜国立大学の教授になった唐十郎の授業とはどんなものだったのか?」を、唐を呼んだ室井尚による文章、唐と室井の対談、講義メモ、唐ゼミの生徒たちの座談などから構成された本だ。「黒板をぶち破って登場した初講義、赤い木馬に乗って窓の外に消える最終講義」なんて聞くと、エキセントリックな授業を想像するが、実際はただエキセントリックなだけじゃない。最初の授業では、携帯を見たり、抜けだそうとする生徒たちに苦戦する唐だが、唐ゼミが誕生し、生徒たちと劇団を作りはじめると、”両者が血を吸い合う”ような体験になっていく。
“けっして反復されることはない一回限りの人との出会いの中で隠されているものに耳を澄まし、それを引き出していくような個人の「生き方」や「構え」の中からしかそうした「教育」が生み出されることはない”と断言する室井の文章は熱く、唐へのラブレターのようにも読める(ちょっと照れる、なんで俺が照れるか、馬鹿)。
野口悠紀雄『ゴールドラッシュの「超」ビジネスモデル』(新潮社/一七〇〇円)の内容は、帯の文句が適切に内容を説明しているので引用します。
ゴールドラッシュの成功者は金を掘らなかった。では、どうやって儲けたのか? シリコンバレーで進行中のIT革命と共通する点はなにか? なぜ多くのベンチャー企業がスタンフォードから輩出したのか?
で、「成功の法則」が検証され、日本経済の未来を切り開くためのヒントが提示される。もちろんそれらの提言にも、ふむふむははぁーんなのだけど、なんといっても、ゴールドラッシュに関するエピソードがおもしろい。
マーク・トウェインや、トロイの遺跡を発掘したシュリーマン、怪盗ブラック・バート、アメリカ合衆国初代皇帝、ジョン万次郎まで登場する。とても読みやすい文章で(いや、教授とか学者で、読みにくくて読めない文章書く人って多いよねぇ)、イッキに読めてしまいます。
十月号で紹介した『「こころ」大人になれなかった先生』を読んで以来、ディナーショーあれば駆けつけますよレベルの石原千秋ファンになったぼくなので『国語教科書の思想』(ちくま新書/六八〇円)も当然読みます。国語教科書のテクストを、教科書編集者や執筆者の意図から切り離して読み解き、そこに隠されたイデオロギーを炙り出し、いかに怖ろしい洗脳が行われているかを暴いた本書は、スリリング&エキサイティング。
吉本ばななの「みどりのゆび」ばかりが選ばれる理由は? 父親が不在の作品が多いのは何故なのか? 小学国語、中学国語の現状はどうなのか? 具体例をあげながらそこに含まれる欺瞞を指摘していきます。
その具体例で、そこまで断言しちゃいますかッ! ってぐらいのテキスト論者っぷりにしびれて、ますますファンになりました。
枡野浩一選『ドラえもん短歌』(小学館/一三六五円)。”自転車で君を家まで送ってたどこでもドアがなくてよかった”ドラえもんをモチーフにした短歌を九十三首収録。なんだかマジックなリアリズムを感じさせる。
漫画。よしながふみ『大奥』(白泉社/六〇〇円)、伝染病で、男が激減。男は子種を持つ宝として育てられ、女が労働し全ての家業を継ぐという世になった日本。もちろん将軍職も、女が継ぐのでして、そうすると、大奥には美男が三千人!? 男女逆転大奥という物凄い設定の中で展開される大河漫画。ぜひ、こっちの設定でテレビドラマ化希望であります。
漫画もう一冊。久世番子『暴れん坊本屋さん』(新書館六四〇円)は、書店員兼漫画家が描く本屋さんの裏話。間違ったタイトルでたずねる客(ハリー・ポッターの書いた『ピーターラビット』はどこにあるの!? に爆笑)やら、万引き話やら、ボーイズラブ小説のはずかしい口絵隠し秘技やら、本屋好きは必笑。
ALL REVIEWSをフォローする