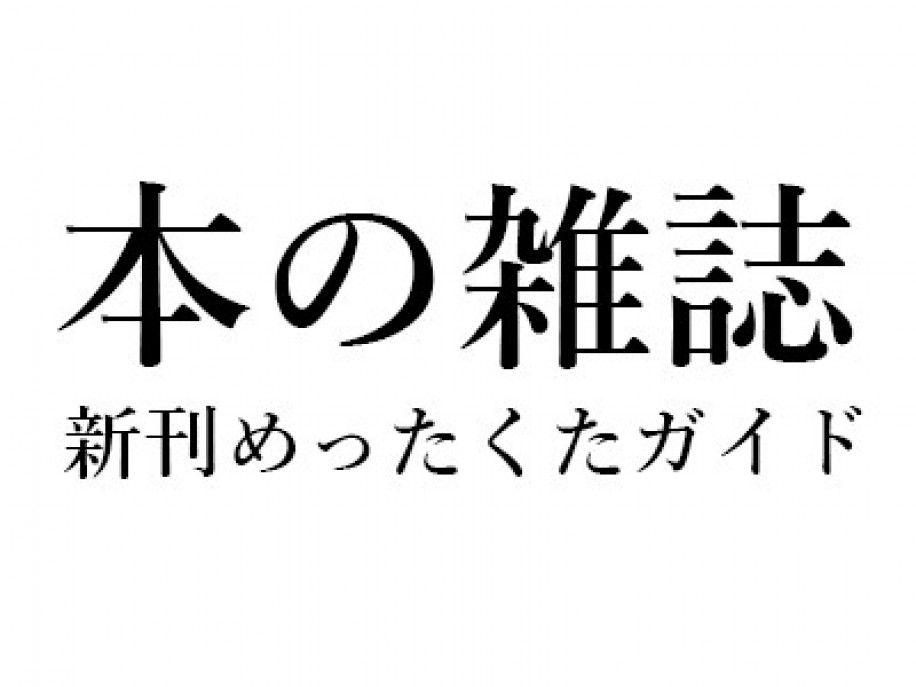読書日記
枡野浩一『あるきかたがただしくない』(朝日新聞社)、マーク・サルツマン『プリズン・ボーイズ』(筑地書館)、森達也悪役レスラーは笑う 「卑劣なジャップ」グレート東郷』(岩波書店)ほか
夏目漱石、太宰治、宮沢賢治、村上春樹、村上龍といった文豪たちに『ゲーム化してくれないか』とゲームデザイナー三人が頼まれた!」というずうずうしい設定の新感覚文芸座談会『日本文学ふいんき語り』が今月のイチオシなのだが、自分が関わった本を紹介するのはなんなので、涙を呑んであきらめる。
歌人、枡野浩一のエッセイ集『あるきかたがただしくない』(朝日新聞社/一五〇〇円)を読みはじめて、あぁ、こういった文章が、ぼくにとって、ひとつの目標であり、理想であるなぁ、と思った。
とはいっても、「枡野浩一のような文章が書きたい」という意味ではない、ということも、すぐにわかった。では、どうして、理想なんだろう。
この本は、「週刊朝日」で連載された「あるきかたがただしくない」を中心に、関連コラム、短歌、対談、河井克夫の漫画と、バラエティあふれる構成の一冊。なのだが、離婚後、息子に会えなくて辛いということが、繰り返し繰り返し出てくる。離婚話が出てこないエッセイがあると、「あ、出なかった」と軽く驚くほどに離婚話が頻出する。
江角マキコの年金CMの話題からはじまっても、お洒落の話からはじまっても、最後は、元妻と息子の話題に行きついてしまう。名古屋に行っても、鬼怒川に旅しても、離婚話がついてまわる。
「お笑い芸人は、直前に母親の死を知っても、ステージに立って、客を笑わせる」的な魂だけがプロだと考えるならば、いくら頭から離れないにしても、離婚話をくよくよ書くのはどうよ、と考える人もいるだろう。巻末に収録されている長嶋有との対談で、〝連載中も「離婚話ばっかりで辟易」とかって読者に言われて腹が立ったりしてたけど、これは辟易しますよね(笑)。〟と、本人が言ってるぐらいなのだ。
でも、だからこそ、ぼくは、ここに綴られている文章が、力強いと感じ、目標にすべき何かがあると感じた。それを無理矢理、言葉にすると。
書いている文章が、「自分」という視点から、遊離しない、確かさ。が、あること。
オレオレ詐欺のこと、初DJのこと、生まれて初めてやったパチンコのことなど、離婚話につなげなくても、そのまま「プロ」の原稿になりえたはずだ。が、離婚の話にシフトしてしまう。自分がいま感じていることを、辟易とされるかもしれなくても、書かざるをえない、その書きようが、ぼくには、力強く感じられたのだ。
〝ただひとつ悲しいことがあるだけで私の中のすべてが黒い〟のだとしたら、本書はすべてが黒い本だろうけど、黒にもいろいろな色があるように感じられるし、黒いだけじゃないようにも思える。
マーク・サルツマン『プリズン・ボーイズ 奇跡の作文教室』(三輪妙子訳 筑地書館/二二〇〇円)は、小説のために少年犯罪について調べていたことがきっかけで、少年院で作文を教えることになった著者によるノンフィクション。少年たちの作文をまじえながら、重罪少年院作文クラスの様子が描かれていく。「書きたいことなら、なにを書いてもいいんですか?」という質問に、著者は「いいです。自分の裁判について以外なら」と答える。裁判について書くと、少年達の不利な材料にされてしまう危険性があるからだ。「ののしる言葉を使ってもいいんですか?」という質問にも、「そういう言葉を使う必要があるなら、使ってもかまわないよ」と答える。訳された日本語がモッサリしていて読みにくいのだが、すぐに、あまり気にならなくなる。わかってほしいと切望する気持ちや、過酷な日常から抜け出したいという祈りが、伝わってくるからだ。
『悪役レスラーは笑う 「卑劣なジャップ」グレート東郷』(岩波新書/七八〇円)は、最近、対談本はやたら出てたけど、ノンフィクション本はひさしぶりの森達也著。第二次大戦直後のアメリカ・プロレス界で「卑劣なジャップ」を演じ、日本でも「世紀の悪役」と呼ばれ、リングを降りても「守銭奴」などと呼ばれた伝説の悪役レスラー、グレート東郷。
それらの謎の周りを彷徨うように取材を続ける。ぼくは、プロレスに興味はないのだけれど、いつもの森達也節は健在で、楽しめた。
豊田正義『消された一家 北九州・連続監禁殺人事件』(新潮社/一四〇〇円)は、二〇〇二年三月、少女が警察に保護されたことで発覚した「北九州・連続監禁殺人事件」のノンフィクション。社会から隔絶された部屋で、家族が家族を殺害し、死体を解体する。そんな状況に追い込むために、男は、自由を奪い、虐待の限りをつくし、思考停止に追い込み、家族同士を疑心暗鬼に陥れ、支配と服従の構造を作り上げる。以前、同じ事件を扱った佐木隆三『なぜ家族は殺し合ったのか』(青春出版社/七三〇円)を紹介したときに、〝語る言葉を失う、とかって、本の紹介をしている時に言うべきことじゃないけど、本当に、失うどころか、語ることにすごく抵抗があって、もうこうやって喋ってても気持ちが沈んでくる〟と書いたが、本書は、もっと実録風というか、視点が事件に寄っていて、淡々と描かれているが、あまりにも陰惨な事件で、気分が沈む沈む沈む。引きずり込まれるように読んだ。
大泉実成『人格障害をめぐる冒険』(草思社/一七〇〇円)は、「人格障害」という言葉の使われ方についてのルポルタージュとしてはじまるが、逸脱を繰り返し、人格障害である人に共振し、さらに著者本人やその周辺の出来事について書くことが多くなってくる。専門外の人による乱暴な書きっぷりだが、乱暴だから書けることもある。
漫画。山岸凉子『舞姫 テレプシコーラ』八巻(メディアファクトリー/六三七円)が出た。長編バレエ漫画。省略の仕方が実に巧い。何度も読んでしまう。この巻では、舞台であがらないための対処法が出てくるので、本番になるとあがっちゃうんだよなーって人も、ぜひ。
【この読書日記が収録されている書籍】
歌人、枡野浩一のエッセイ集『あるきかたがただしくない』(朝日新聞社/一五〇〇円)を読みはじめて、あぁ、こういった文章が、ぼくにとって、ひとつの目標であり、理想であるなぁ、と思った。
とはいっても、「枡野浩一のような文章が書きたい」という意味ではない、ということも、すぐにわかった。では、どうして、理想なんだろう。
この本は、「週刊朝日」で連載された「あるきかたがただしくない」を中心に、関連コラム、短歌、対談、河井克夫の漫画と、バラエティあふれる構成の一冊。なのだが、離婚後、息子に会えなくて辛いということが、繰り返し繰り返し出てくる。離婚話が出てこないエッセイがあると、「あ、出なかった」と軽く驚くほどに離婚話が頻出する。
江角マキコの年金CMの話題からはじまっても、お洒落の話からはじまっても、最後は、元妻と息子の話題に行きついてしまう。名古屋に行っても、鬼怒川に旅しても、離婚話がついてまわる。
「お笑い芸人は、直前に母親の死を知っても、ステージに立って、客を笑わせる」的な魂だけがプロだと考えるならば、いくら頭から離れないにしても、離婚話をくよくよ書くのはどうよ、と考える人もいるだろう。巻末に収録されている長嶋有との対談で、〝連載中も「離婚話ばっかりで辟易」とかって読者に言われて腹が立ったりしてたけど、これは辟易しますよね(笑)。〟と、本人が言ってるぐらいなのだ。
でも、だからこそ、ぼくは、ここに綴られている文章が、力強いと感じ、目標にすべき何かがあると感じた。それを無理矢理、言葉にすると。
書いている文章が、「自分」という視点から、遊離しない、確かさ。が、あること。
離婚後ずっと子供に会えていない父親ってものすごく多いんですよね。その苦しみを表立って表現しないことが「男らしさ」だというなら、私は男をおりてもいいと思っています。
オレオレ詐欺のこと、初DJのこと、生まれて初めてやったパチンコのことなど、離婚話につなげなくても、そのまま「プロ」の原稿になりえたはずだ。が、離婚の話にシフトしてしまう。自分がいま感じていることを、辟易とされるかもしれなくても、書かざるをえない、その書きようが、ぼくには、力強く感じられたのだ。
〝ただひとつ悲しいことがあるだけで私の中のすべてが黒い〟のだとしたら、本書はすべてが黒い本だろうけど、黒にもいろいろな色があるように感じられるし、黒いだけじゃないようにも思える。
マーク・サルツマン『プリズン・ボーイズ 奇跡の作文教室』(三輪妙子訳 筑地書館/二二〇〇円)は、小説のために少年犯罪について調べていたことがきっかけで、少年院で作文を教えることになった著者によるノンフィクション。少年たちの作文をまじえながら、重罪少年院作文クラスの様子が描かれていく。「書きたいことなら、なにを書いてもいいんですか?」という質問に、著者は「いいです。自分の裁判について以外なら」と答える。裁判について書くと、少年達の不利な材料にされてしまう危険性があるからだ。「ののしる言葉を使ってもいいんですか?」という質問にも、「そういう言葉を使う必要があるなら、使ってもかまわないよ」と答える。訳された日本語がモッサリしていて読みにくいのだが、すぐに、あまり気にならなくなる。わかってほしいと切望する気持ちや、過酷な日常から抜け出したいという祈りが、伝わってくるからだ。
『悪役レスラーは笑う 「卑劣なジャップ」グレート東郷』(岩波新書/七八〇円)は、最近、対談本はやたら出てたけど、ノンフィクション本はひさしぶりの森達也著。第二次大戦直後のアメリカ・プロレス界で「卑劣なジャップ」を演じ、日本でも「世紀の悪役」と呼ばれ、リングを降りても「守銭奴」などと呼ばれた伝説の悪役レスラー、グレート東郷。
なぜ東郷は、祖国である日本と母国であるアメリカで、あれほどに観客の憎悪を掻き立てるようなファイトに終始したのか。なぜ力道山は、誰からも嫌われた東郷を、あれほどに重用し、そして敬慕したのか。
それらの謎の周りを彷徨うように取材を続ける。ぼくは、プロレスに興味はないのだけれど、いつもの森達也節は健在で、楽しめた。
豊田正義『消された一家 北九州・連続監禁殺人事件』(新潮社/一四〇〇円)は、二〇〇二年三月、少女が警察に保護されたことで発覚した「北九州・連続監禁殺人事件」のノンフィクション。社会から隔絶された部屋で、家族が家族を殺害し、死体を解体する。そんな状況に追い込むために、男は、自由を奪い、虐待の限りをつくし、思考停止に追い込み、家族同士を疑心暗鬼に陥れ、支配と服従の構造を作り上げる。以前、同じ事件を扱った佐木隆三『なぜ家族は殺し合ったのか』(青春出版社/七三〇円)を紹介したときに、〝語る言葉を失う、とかって、本の紹介をしている時に言うべきことじゃないけど、本当に、失うどころか、語ることにすごく抵抗があって、もうこうやって喋ってても気持ちが沈んでくる〟と書いたが、本書は、もっと実録風というか、視点が事件に寄っていて、淡々と描かれているが、あまりにも陰惨な事件で、気分が沈む沈む沈む。引きずり込まれるように読んだ。
大泉実成『人格障害をめぐる冒険』(草思社/一七〇〇円)は、「人格障害」という言葉の使われ方についてのルポルタージュとしてはじまるが、逸脱を繰り返し、人格障害である人に共振し、さらに著者本人やその周辺の出来事について書くことが多くなってくる。専門外の人による乱暴な書きっぷりだが、乱暴だから書けることもある。
漫画。山岸凉子『舞姫 テレプシコーラ』八巻(メディアファクトリー/六三七円)が出た。長編バレエ漫画。省略の仕方が実に巧い。何度も読んでしまう。この巻では、舞台であがらないための対処法が出てくるので、本番になるとあがっちゃうんだよなーって人も、ぜひ。
【この読書日記が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする