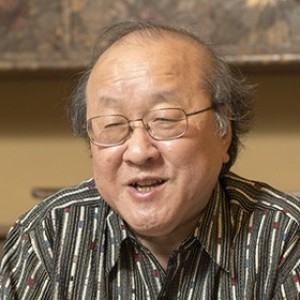書評
阿部公彦『史上最悪の英語政策―ウソだらけの「4技能」看板』(ひつじ書房)、鳥飼玖美子『英語教育の危機』(筑摩書房)
「ペラペラ信仰」そろそろ捨てよう
国難である。原発のことでもなければ、北朝鮮のことでもない。英語教育の問題だ。ある国の繁栄も強さも、長い目で見ればその土台となるのは、次の世代の教育である。それがいま大変なことになっている。現在、文部科学省が強力に推し進めている改革によって、小学校ではすでに英語教育が始まり、今後本格化する。また大学入試の際には、二〇二〇年度から民間業者による英語の資格・検定試験が導入される予定になった。その背後にあるのは、「中高で六年もやったのに全然しゃべれない」「それは今の学校教育が悪いからだ」という世論の声であり、また「グローバル人材育成」を高らかに謳(うた)う政府や産業界の要請である。しかし、事はそれほど単純ではない。
まず阿部公彦(まさひこ)氏の『史上最悪の英語政策』は、大学入試の改革に焦点を合わせた緊急提言である。著者の明快な説明を追うと、入試改革ではコミュニケーション能力を重視するために、「スピーキング」(話す能力)もテストする――つまり「読む・書く・聞く・話す」の4技能をすべて測ることになった。ところがスピーキングは従来の試験では扱いにくいので、外部委託=民営化して、TOEICなどの民間の試験を使うことになった。しかし4技能と言っても特に新しい話ではなく、今提唱されている「4技能」主義はほとんど「カルト教団の教え」(!)のような意味不明さだと阿部氏は言う。
外部試験を導入したら、受験生は点を取るための受験テクニック習得に走るだけで、英語力の向上につながるという保証はない。また外部試験には相当な受験料も必要となるし、その対策のために多くの受験生が予備校などに通うことになる。新たに大きな負担を受験生の親に強い、裕福な家の子供が有利になって、社会的格差が拡大する。その上、スピーキングは「規格化された採点のシステムにはなじまない」ので、客観的かつ公平に採点できるとは思えない。試験の外部委託の動きは、業界の利益誘導によるものではないかとさえ思える、等々。
一方、鳥飼玖美子氏の『英語教育の危機』は、もっと広く小学校から大学まで視野にいれ、過去三十年にわたる英語教育改革の歴史を振り返り、新学習指導要領を仔細(しさい)に検討しながら、全体にわたって何が問題なのか、論じている。鳥飼氏の本を読んでよく分かるのは、文部科学省が手をこまねいてきたわけではなく、じつはこの三十年ほど、「慢性改革病」と呼べるほど頻繁に改革を重ねてきたということだ。その結果、現在の中高の英語教育は文法・訳読偏重をやめ、オーラル・コミュニケーション(というとカッコいいが、実態は英会話)に向けて断固として舵(かじ)を切っている。すでに高校で、そして近い将来は中学校でも、英語の授業は日本人の先生であっても「英語で行うことを基本とする」となっているのだ。信じられますか、そんなこと? 評者に言わせれば、日本の現実を無視した突拍子もない政策である。
いずれにせよ、「文法や訳読ばかりで、話せるようにならない」という巷(ちまた)に根強い批判はじつは的外れなのであって、むしろこれだけ会話や実用性を重視しながら、その成果がいっこうに上がっていないのはなぜか、分析すべきだ、というのが鳥飼氏のきわめてまっとうな指摘である。言語環境も教える人材も整っておらず、限られた授業時間数で無理に「対症療法」として会話重視に踏み切ったため、肝心の基礎がおろそかになってしまって、かえって本当の意味での英語力が落ちつつあるのが、現状のようだ。
最後に一言、評者の個人的な考えを付け加えておくと、「ペラペラ信仰」などそろそろ捨てるべきではないか。英語教育改革の議論で乱発される「コミュニケーション」という言葉もあまりに空疎。人間どうし、特に立場が異なる人の間や異文化間のコミュニケーションというのは、英語で「買い物ごっこ」ができる、といった次元のことではない。
そもそも、どうしてスピーキングを大学入試でテストしなければならないのか? 高校までに学ぶべきもっと大事なことはないのだろうか? 英語ばかりに力を注げば、当然、他の教科が手薄になるだろう。日本語できちんと他者と話し合い、理解し合う能力と、そのために必要な人間としての教養を身につけさせるのが先ではないか? いまの政治家たちを見ているとつくづくそう思う。このままでは、英語がペラペラになる前に、日本語が滅びますよ! それに、どうして英語だけなのか? 中国語や韓国語やロシア語ができる人材の養成にも少しは力を入れないと、国益を損なうのではないか?
と、まあ、じつに色々な疑問を呼び起こす二冊だった。
ALL REVIEWSをフォローする