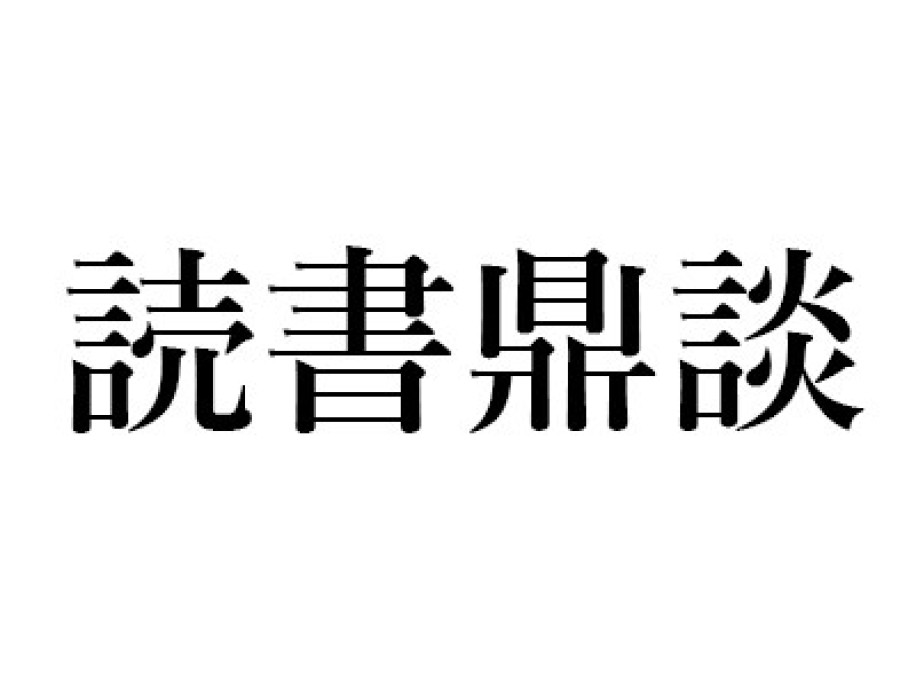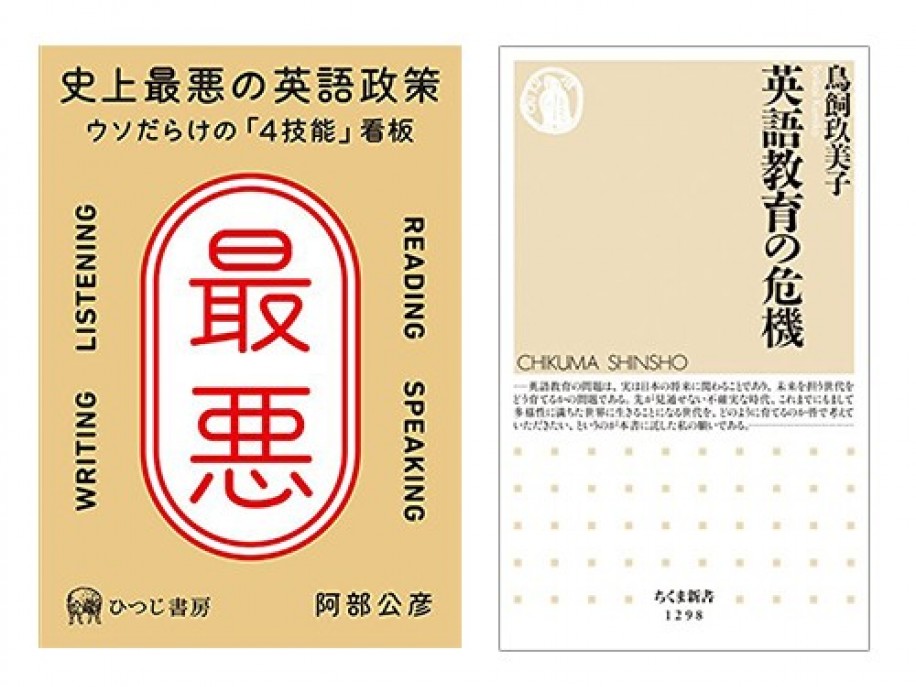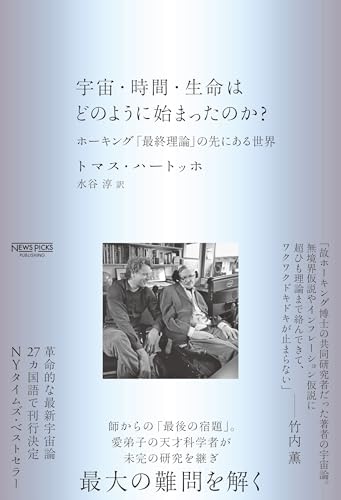書評
『手で見るいのち: ある不思議な授業の力』(岩波書店)
ここにある学びの原点
東京にある筑波大学附属視覚特別支援学校の生物教室での授業が始まろうとしている。担当の武井洋子先生が、「今日から骨を使います」と生徒たちの前に一人一個ずつ骨を置いていく。名づけて「動物A」だ。初めての授業に中学一年生七人は「えっマジで」と驚きながら、おそるおそる触り始める。最初は全身かと思いながら。「牙みたいなものがある」「奥歯みたいなものがある」……頭蓋骨(ずがいこつ)らしい。わからないものを少しずつ解いていく過程は何によらず面白い。二時間目。「穴」と「空間」に注目しての探索はますます面白くなる。鼻や目が見つかり、目の穴の中の後ろの方に見つかった穴は神経の通るところに違いないとわかってくる。歯の様子から肉食とわかった動物Aが、獲物であるシマウマをしとめる姿を想像することになり、一人が「いやなパターンだな」とつぶやく。現実味がある。
このようにして二時間ずつ三週間の観察、ではなく触察で耳の部屋が大きいので聴覚がよいなどの特徴が見えた動物Aは、イヌとわかる。その後動物B、C、D、つまりウサギ、ネコ、サルへと進み、一つ一つにかかる時間はどんどん短くなっていく。この様子を観察していた著者は自分でも触りたくなってくる(当然だ)。ある日先生がそっと骨を置いてくれた。しかしすぐに、指先が生徒のようにははたらかないことに気づかされ、傍観者に徹してこの授業の意味を読みとることにする。
このユニークな授業が実は四十年も続いていると知って驚いた。始めたのは青柳昌宏先生。子どもの頃から昆虫愛好家の中では有名で、生物教師になってからは南極でのペンギン観察でも名を馳(は)せた。生徒中心の授業をする名物教師としても知られていた。当時、視覚障害のある生徒の理科教育のうち、物理、化学は実験も含めてかなり進んでいたが、生物は置き去りにされていた。そこで白羽の矢が立ったのが青柳先生だった。
とにかく実物に触れることだ。校庭に縦五十センチ、横一メートルの木枠を置き、中の植物に触って葉の形、生え方、硬さなどを調べるところから始めた。「背の高い植物の葉は軟らかく元気なのに日の当たらない下の葉っぱは硬い」。生徒たちの発見だ。毎日葉っぱを見ているけれどこんなふうに理解してはいないぞ。多くの方がそう思われるのではないだろうか。このわかり方いいなと思う。ペンギンの標本に触りながら聞く南極の話にも目が輝く。
動物は骨で行こう。葉っぱと骨に触れる授業を考え、視覚障害の生徒の進路を広げたいと強く思っていた鳥山由子先生と共に体系化していった。後継者が武井先生。その結果、大学で理系(物理)に進学する生徒が誕生したのである。もちろん、大学側もある種革命を必要としたが、先生たち三人の力だ。
先生たちは言う。「骨は語る」と。毛皮や筋肉のない「骨には穴にも突起にも空間にも生きていたときの姿を考えるヒントが詰まっている」のである。はく製や模型ではこうはならない。骨に触って何かを発見した生徒はうれしく、その発見をなんとか言葉にしていく。そして点字で書きとめる。ウサギは後ろ足の裏が全部地面についているからジャンプができる。「コツコツコツコツ」。著者が聞いた点字を打つ音である。
「自分のうれしい気持ちを伝えるために自分の頭で考えた言葉が生まれてくる。発する言葉はすべて、自分の手で触った体験に基づいている」。このような体験を今どれだけの子どもたちがしているだろうか。学びの原点がここにある。
ALL REVIEWSをフォローする