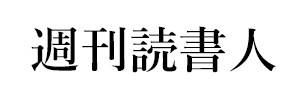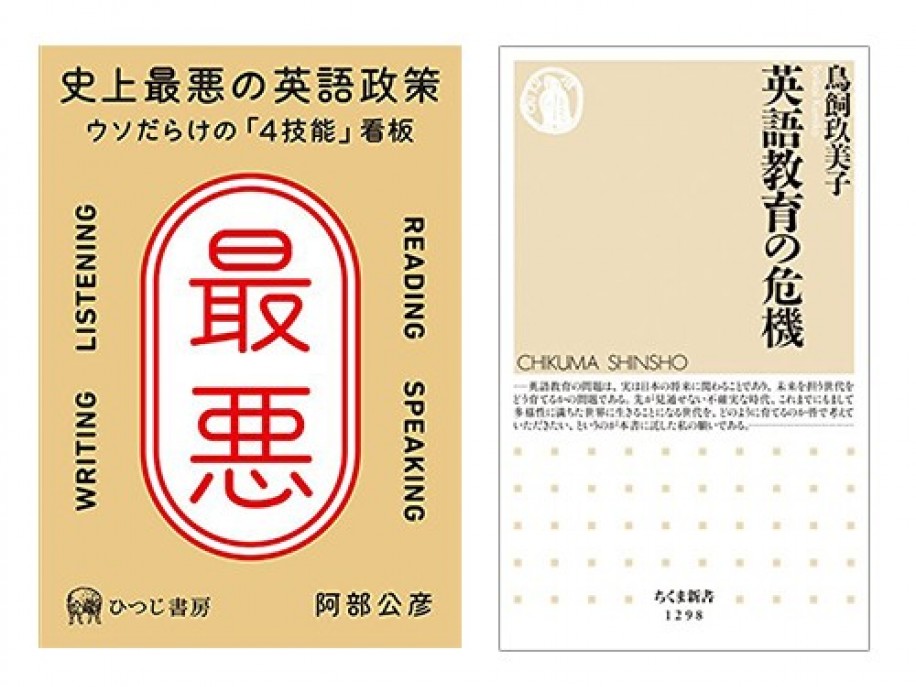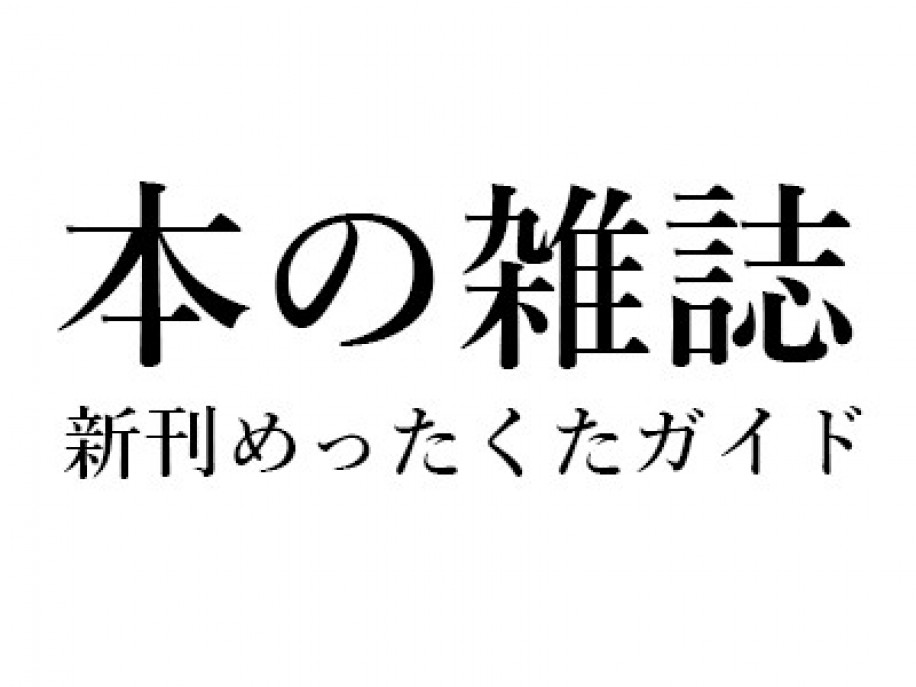書評
『私学的、あまりに私学的な 陽気で利発な若者へおくる小説・批評・思想ガイド』(ひつじ書房)
まだまだ役に立つスパルタ 特筆もののスタンスのブレのなさ
渡部直己の本を読むのは久し振りだなと書誌をあらためると、二〇〇六年の『メルトダウンする文学への九通の手紙』(早美出版社)以来、約四年半ぶりである。四年半――長いような短いような歳月だ。本書は、大学一年生から大学院生までの文学・思想を学ぶ学生へ向けた教科書ないし副読本の体裁を採っているのだが、3・4年次「テクスト読解・批評ゼミ」でデビュー作を称揚された川上未映子はもはや大作家の風情だし、また同じゼミで無理解からの救出と正統への接続を企まれた中原昌也は、宇野常寛程度を祭り上げる文芸業界のダサさに嫌気が差したと言って小説の筆を折った(『Trash-Up!!』Vol.2)。
四年半。短いようで、状況がそこそこ変化するくらいには長い。その微妙な時間を隔てて渡部の書いたものに接して思わず呟いた。
「変わらねえな」
収録されているテキストがすべてこの四年半に書かれたわけではなく、それどころか一九八五年の文章が収録されていたりもするので四半世紀に及ぶことになるが、渡部のスタンスのブレのなさは特筆ものである。
先ほど触れたように本書は、学生向けの教材という体裁に編まれている。日本ジャーナリスト専門学校から現在の早稲田大学まで、著者は二十五年にわたり学生の指導にあたっており、実際に「積年の厳選「ネタ帖」」のように使っている文章が集められているそうだが、編集の妙でそれらしく装われてはいるものの、雑文+批評集というのが正確なところだろう。雑文とはいえ、『朝日新聞』連載スポーツ時評に対して読者から届いた苦情を晒し上げるとか、読むこと/書くことからは離れておらず「批評」の枠内にある。
タイトルに掲げられた「私学」には、こうした猥雑さを含意した面もあるのだろう。渡部は言う。
「「私学」の反義語は、必ずしも「官学」ではない。(…)それはむしろ、たとえばマックス・ウェーバーのいう意味での「学問」」なのだ。ウェーバーは「学問」を職業とするものは断じて「予言者」や「扇動家」になってはならんと言ったが、本書はむしろ積極的に予言し扇動するだろう、「そのほうが、いまやずっと学生たちのためになる!」からだと。
この「ためになる」が、文学・思想を学ぶと教養がついて心が豊かになるとかそんな話ではなく、実社会において実践的に「役に立つ」であるところがポイントである。渡部はこうも予言し煽る。「ベケットやニーチェを相手に出来るなら、一般企業のエントリーシートや人事部長などはなから目じゃない、簡単に口説き落とせるはずだ」と。
渡部の十八番であるテクスト論に就いた技術を中心とした「読み方」「書き方」のトレーニングはたしかに、自己を含めたものごとに対するクールな判断力を養いうる点で「読むこと」「書くこと」に留まらず有用だろう。だが「現代思想はここが出る」と題した章で、ソシュールをはじめとするフランス現代思想が「人生に出る」と言い出す段になると首肯しづらくなってくる。つか出ねえよ。
巻末にある「主要自著自解」で、『新・それでも作家になりたい人のブックガイド』(二〇〇四年)について渡部は「十年間で潮目が変わったことに絓氏も私もKYだったことを痛感するにたる売上減」と書いている。しかしKYというよりも、ブレのなさが徒となり、ニューアカ以降の紋切型で言う「アクチュアル」さを失ったのだ。もはや反動的な趣きさえ漂う渡部のスパルタは、しかしそれでもまだまだ役に立つ。
ALL REVIEWSをフォローする